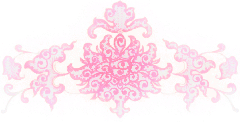
「‥‥天童くんの言った通りだったね。‥‥あんな人がチヤホヤされてるなんて馬鹿みたい、天童くんの方がよっぽどいい人なのに。」
ようやく泣き止んだ私は、自嘲気味に笑いながら言うと、軽くため息を吐いた。
「名前ちゃんがそう思ってくれるなら、他の人にどう思われてもいいよ。」
隣で佇む天童くんが、穏やかな口調で呟くように言った。
どうしてこんなにも‥‥天童くんは優しいんだろう。
「俺ね、昔から『妖怪』って悪口よく言われてたの。優しく接する人もいたけど、裏ではその人に陰口叩かれたりしてさ。誰かが悪口言い始めたら大体は便乗するのに、名前ちゃんはしなかった。名前ちゃんは覚えてないかもしれないけど、俺あの時聞いてたんだよね。」
天童くんの悪口を振られたことは覚えているが、私がその時なんて返したのかは覚えていない。
肝心のことは覚えていないものの『優しい天童くんの悪口に便乗しなくて本当に良かった』と心から思った。
私が黙っていると、それはそれで間が悪いと感じたのか、天童くんは続けて言った。
「その日から気になった。他人の評価とは無関係に、俺を肯定してくれた名前ちゃんのことが。
名前ちゃん、ホントに警戒心無さすぎるから、いつか他人に傷つけられたりしないか心配だった。」
そういや天童くんが私にちょっかい出すようになったのも、あの日以来だったような気がしてきた。
よく天童くんは私に、多くのことをからかいながら指摘したり忠告したりしてきたが、今考えれば私の為の教訓だったのだろう。
今思えば、天童くんのセクハラには性的な脅威は無く、愛しさと優しさしか含まれていなかった。
セクハラされて本気で嫌がっていた私を思い返せば思い返すほど、自分の愚かさを思い知る。
天童くんを見つめながら話を聞いていると、天童くんが私の方に向き直った。
赤色の瞳が私を捕らえていて、その瞳の熱っぽさに胸が高鳴る。
「気がついたらずっと見てて、誰にも取られなくないって思った。
俺さ‥‥名前ちゃんが好きなんだ。」
天童くんの言葉に止まっていた涙がまた溢れて、視界がにじむ。
涙が溢れると同時に、温かな波のようなものが体中に広がっていくのを感じた。
天童くんからの言葉を、私はこんなにも待ち望んでいたのだ。
「えっ、ごめん名前ちゃん!泣くほど嫌だった?!ごめん、ほんとごめんね!」
また泣き出した私を見て、慌てふためくこの瞬間でさえ愛おしい。
今、目の前のこの人が、こんなにも好きなんだ。
「そうじゃないの。嫌じゃなくて、幸せなの。」
涙を拭いながら言う私の言葉に、天童くんが拍子抜けしたような顔をする。
私は一呼吸おくと、また話を続けた。
「さっき私‥‥『好きな人がいるから』って言って告白断ったの。ある人を思い浮かべながら。」
そしてまた涙を一筋流しながら、ニコッと笑った。
「ごめんね‥‥私も天童くんのことが好きだよ。」
すると、不意に天童くんに引っ張られた。
引き寄せられ、天童くんの胸に頬があたった。
「天童くん‥‥?」
突然のことに驚いた私が、天童くんを見上げながら問う。
すると天童くんの腕が背中に回り、優しく抱きしめた。
「‥‥ズルいよ名前ちゃん。幸せ過ぎて俺死んじゃいそう。」
白いYシャツを通して私の頬に天童くんの体温と鼓動が伝わる。
伝わる天童くんの鼓動が早過ぎて、本当に死んじゃうんじゃないかと思った。
私も人のこと言えないけど。
好きな人にギュッと抱きしめられるのは、こんなにも安心感が溢れるものなのか。
すごくホッとするし、さっきあった嫌なことさえも忘れてしまいそうだった。
*
「名前ちゃんの目すっごく腫れてるね〜!誰に泣かされちゃったのカナ〜?」
翌日、教室に入ると、隣の席の天童くんが面白いものを見つけたかのように纏わりついてきた。
昨日は泣き過ぎたあまり目が腫れてしまったのだ、ちゃんと保冷剤で冷やしたのに。
黙って天童くんを睨みつけると『更に怖い顔になってるよ?』と、更に茶化される始末だ。
「そんなに意地悪だと嫌いになるからね。」
天童くんに対抗しようと、席につきながらぶっきらぼうに言い放った。
「‥‥それはダメ。」
静かな声で嬉しそうに言った天童くんが、こっそり私の手を握った。
他の人達に見られたらどうしようかと思ったが、最前列しか生徒がいないことに気づいた私は、『ま、いっか』と呆れたように少し笑みを返したのだった。