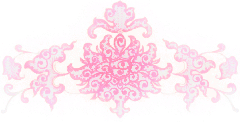
放課後、断りの返事をしようと秋月くんのもとへ立ち寄ると、空き教室で話をしようと連行された。
「私‥‥好きな人がいるんです。本当にごめんなさい。」
『申し訳ない』と気持ちを込め、深々と頭を下げて謝罪する。
秋月くんからの告白を振るなんて勿体ないと、クラスメイトの女の子たちは言っていたが、私は正直言って彼が苦手だった。
演技的な部分を感じさせる動作や喋り方や、いつもニコニコしていて何を考えているのかさっぱり分からない彼が、私は少し怖かった。
それに、『好きな人がいる』ってのも断り文句で吐いた嘘ではない。
『好き』というより、『気になる』といった方が正しいかもしれないが。
さっきから何も言わない秋月くんを不思議に思った私は、頭をゆっくり上げる。
すると秋月くんは、無表情で私を見下ろしていた。
「わ、私はこれで。」
居たたまれなくなってしまった私は、早くこの場から離れようと振り返る。
すると秋月くんが、ガシッと私の手首を掴み、私の行く手を阻んだのだ。
「そんな嘘で、俺が納得するとでも思った?」
表情は穏やかだが、声色が怒りを含んだものに変わっている。
「秋月くん‥‥?」
秋月くんの態度に戸惑っていると、背の高い彼が私の目線まで腰を折り曲げ、顔を近づけた。
「俺が名前さんに告白した理由、知りたい?」
秋月くんと私は同じクラスになったことがなく、関わりもそんなにない。
だからこそ、何故私を好きになったのだろうか、見当もつかなかった。
「調教し甲斐がありそうだなぁって思って。‥‥俺好みにね。」
耳元で囁かれた言葉に、身体からサッと血の気が引いていくのがわかった。
ニコッと笑みを浮かべると、関節が砕けそうなぐらいに私の手首を強く握り締めた。
「いっ‥‥たぁ‥‥!」
あまりの痛さに顔をしかめ、悲痛な叫びを上げる。
「その痛がる表情とか色っぽくて、嗜虐心を誘われるんだよね。名前さんにあんな事したら名前さんはどんな反応するのだろうかってずーっと考えて、ずーっと目をつけてたんだ。」
恍惚の表情を浮かべる彼に、身の毛がよだった。
私の目の前に立つ男は、人間の皮を着た悪魔だ。
その悪魔が、獲物に好奇心を持つように、執念深く迫って来る。
「俺に気があるくせに振るなんて、ほんと素直じゃないね。どうせ好きな人がいるってのも嘘なんでしょ?」
全てが自分の思い通りになるという不遜な考え方に、ますますゾッとする。
「嘘じゃない、本当なの!だからもう離して!」
「ん?‥‥嫌だね。」
この状況から逃れようと叫ぶように宥めるも、笑顔であっさり断られてしまった。
秋月くんがニヤリと怪しい笑みを浮かべ、口を開いた。
「これから名前さんは、俺とイイコトするんだよ?」
秋月くんの言葉に、悪寒のような小刻みな身ぶるいが、頭の方から足先へと波動のように絶えず伝わる。
私はこの場から逃れるようと後ずさりをしたが、その分だけ秋月くんが躙り寄る。
背中に伝わる壁の冷たさが、もう私に逃げ場がないことを教える。
そして次の瞬間、秋月くんが私の身体を壁に押さえつけた。
「は、離して!」
「どうせ、こうされるのを期待してたんでしょ?のこのこと俺に付いてきちゃってさ。」
必死に腕をバタつかせて抵抗する私を見て、秋月くんが気味の悪い笑みを浮かべる。
「や、やだ‥‥やめてよ!」
「怖がらなくて大丈夫だよ。今から気持ちいいことをするんだから。」
その言葉とともに、彼の顔がさらに近づいてくる。
誰も助けてくれないと思った私は、決死の覚悟で、彼のみぞおちに膝蹴りをかました。
「ぐっ‥‥!」
彼が呻って体勢を崩した隙に、私は身体を押し退け、逃げ出そうとした。
「おい待て!!」
しかし、恐怖で思うように身体が動かず、追いかけた秋月くんにあっさり捕まってしまった。
そして私の両手首を頭上で掴み、太腿の間に秋月くんの脚を無理矢理ねじ込んで、身動きが取れないように壁に固定する。
「優しくしてやろうと思ったけど、どうやら痛くされないと分かんねェみたいだな?」
私を見下ろす秋月くんは殴りかかりそうなほどに激昂していて、ねじ込んだ彼の脚の膝を、私のスカート中の股の間にぐりぐりと強く押しつける。
拘束から逃れようと悲鳴を上げ、蜘蛛の巣にかかったみたいにジタバタする。
しかし、身動きができないほど行動が束縛されている為、ビクともしない。
こんな遅い時間じゃ、どんなに声を上げても誰も助けに来ないだろう。
天に祈るほか、何の術もないのだ。
すると首筋をベロリと舐め、制服のボタンに指をかけた彼に、恐怖のあまりギュッと強く目をつぶった。
こんな形で初めてを奪われてしまうのだろうか、初めては好きな人に捧げたかったのに。
「はいストップー!」
すると、ガラガラと勢いよく引き戸を開かれたと共に、男の人の声が聞こえてきた。
秋月くんが私から身体を遠ざけ、振り返る。
「‥‥秋月くんさァ、何やってんの?」
虚ろな目で声の方を見遣ると、そこには天童くんがいた。
まだ腕は秋月くんに拘束されたままだったが、天童くんの姿にホッと息をつく。
「‥‥空気を読んでほしいな天童。恋人同士のすることじゃないか。」
こぼれるばかりの愛嬌を天童くんに振りまき、表の顔を演出する。
「ヘェ〜!秋月くんと名前ちゃんって恋人同士なんだ!初知り!」
事実を知った天童くんが、目を大きく見開いて驚く。
そして『お邪魔虫はとっとと退散するね〜』と踵を返した天童くんに、秋月くんがフッと笑みを溢した。
違うよ天童くん、恋人同士なんかじゃない。
誤解しないで天童くん、お願いだから行かないで。
すると、立ち去ろうとした天童くんが、くるっと振り返った。
「‥‥でもさァ〜、名前ちゃん嫌がってない?
どう見ても恋人同士の甘い雰囲気には見えないし、どう見てもこれ合意の上じゃないよね〜?
これってどう見ても強姦だよね?」
「‥‥嫌だなぁ天童、誤解だよ。」
こっちに向かって歩き進める天童くんに、秋月くんが爽やかな笑みを浮かべる。
「あの優等生の秋月くんが強姦なんてガッカリだよねェ〜〜。
加えて、影で飲酒も喫煙もしてるなんてみんなが知ったらどう思うんだろう?あ、証拠の写メ見る?」
天童くんが秋月くんに歩み寄って腕を伸ばし、スマホの画面を提示した。
「なっ‥‥!」
私の位置からはどんな画像なのかは分からなかったが、画像を見た秋月くんは驚いて目を白黒させていた。
「秋月くんってさ〜、確か難関私立の推薦貰ってなかったっけ?このことがバレたら白紙どころか、高校退学だろうねェ〜〜。
人生イージーモードからハードモードに転落なんて傑作ダネ!」
嬉しそうに笑みを浮かべた天童くんが、じりじりと秋月くんに詰め寄る。
天童くんの気迫に、今まで余裕そうな表情をしていた秋月くんが、狼狽えながらパッと私の腕を離す。
「そ、それだけは勘弁してくれっ!」
さっきまでの威圧的な秋月くんとは明らかに違い、身体中が震えていた。
「それは秋月くんの今後の行いによるでしょ。
後、やんないとは思うけど、逆恨みとかやめてね?これから一生、名前ちゃんに関わった時点でこの証拠ばら撒くから。
仮にこの先いい大学に入って、卒業して大手に就職したとしても、結婚して幸せな家庭を持ったとしても、未成年で喫煙飲酒、おまけに強姦もしていたことが知られたら、一気に信用は無くなるね。」
天童くんの言葉つきは、表面は丁寧だが、拒否を許さない強い響きを持つ。
そして言い終えると、天童くんが物凄い勢いで秋月くんの胸ぐらをつかみ、見下ろした。
「‥‥俺から逃れられると思うなよ?」
天童くんにドスの効いた声で凄まれて、秋月くんの顔が真っ青になる。
「分かったなら早く消えてくんない?」
天童くんに威圧され、秋月くんは後ろも振り返らず、そそくさと逃げるように去っていった。
誰も助けに来ないと思っていた。
恐ろしい悲劇が遠退いたことに、悪夢から目覚めたようにホッとする。
安心したと同時に、身体から力が一気に抜けてしまい、床へと座り込んだ。
「もう大丈夫だよ、名前ちゃん。」
頭上から、秋月くんに向けられた声とは違う、天童くんの優しい声が降ってきた。
「あ、ありがとう天童くん。ほんとに‥‥ほんとにありがとう。」
何度伝えても伝えきれないほどの感謝が一気に胸に込み上げてきて、必死に想いを伝えた。
すると天童くんが私の前にしゃがみこみ、強く握られた所為で赤くなった私の手首を、壊れやすい物を扱うようにそっと触った。
「ううん‥‥遅くなっちゃってごめんね。」
その大きくて温かい天童くんの手によって、自分の身体を抱くようにして震えていたのが、段々とおさまっていく。
「怖い思いをしたね‥‥。」
天童くんの言動に、湛えていた涙が頬を伝った。
最初の涙がこぼれてしまうと、あとはもうとめどなく溢れ、火がついたように泣き始めた。
子供のように泣きじゃくった私の横で、天童くんは何も言わずにただ黙って一緒にいてくれた。
誰よりも、天童くんにそばにいて欲しかった。