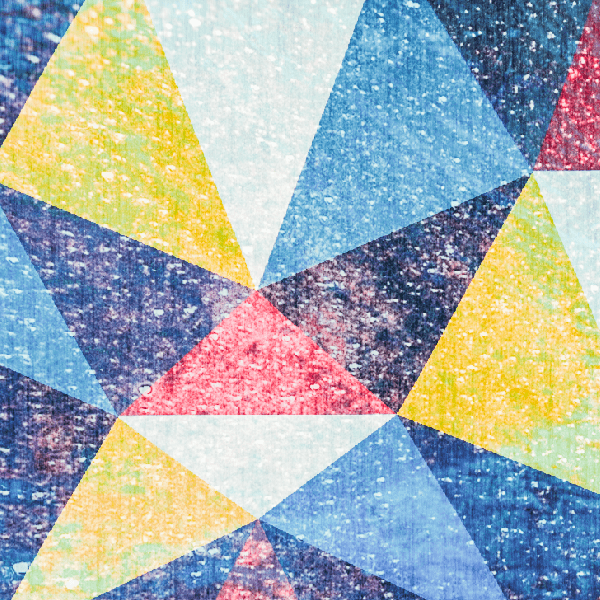
愛はあまいと知っている
「慎導さん!炯さんにオレンジジュースのこと話したでしょ」
「ん?駄目だった?」
今日の当直は私と慎導さんだ。一係と二係で配属は違くとも出社時間は一緒なためお昼は一緒にとろうと思い慎導さんの自宅を訪ねた。放っておくとまたカップラーメンで済ませてしまうのはやっぱり私としては気になるのだ。
お昼前に寝ぼけた慎導さんを起こして軽く支度をするように促した後キッチンを拝借して簡単に料理をする。オートサーバー食はいろいろ考えられているから健康面を考えたらそれでもいいのだろうけれど食べたなって気持ちになれるのはちゃんと自分の手で作った料理だと思い今日はオムライスを作った。
無意識に献立をオムライスにしたことで先日炯さんと話したことを思い出す。シャワーを浴びてきたのにまだ寝ぼけ眼の慎導さんに一言異議を申し立てるとスプーンを咥えながらきょとん、とされてしまった。
「絶対子供だなって思われました…」
「どうだろう?でも可愛い好物だな、とは言ってた」
「ううう…恥ずかしい」
「いいんじゃない。おれも好きだよ、オムライス。特に名前が作ってくれたのは絶品だ」
嬉しそうにオムライスを頬張る慎導さんを見るとやっぱり怒るに怒れない。がつんと言ってやるつもりだったのに…。でも我ながらオムライスに関しては上手くできてると自負していたからそれはそれで嬉しかった。私も同じようにオムライスを口に運ぶ。
「それよりも名前」
「んむ、なんれすか、」
「呼び方」
「…む」
慎導さんはじとりと眉間に皺を寄せて私を見る。慎導さんが何を言いたいのかすぐに思い当たった私はご飯を飲み込んだあと照れくささを紛らわすため水に口をつけた。
「炯のことは炯って呼ぶのに」
「それはそう呼んでくれって言われたから…」
「じゃあおれのことも灼で呼べるね」
「…う」
慎導さんに紹介されてから少しの間はイグナトフさん、と呼んでいたのだがファミリーネームで呼ばれるのは違和感を感じていたのか「炯でいい」とすぐに訂正されてしまった。外国の人は友人とは名前で呼び合うのが普通らしいから未だに少しくすぐったさを感じる。
そういう経緯で炯さんのことはお名前で呼んでいるだけで普段私が他の人を呼ぶ時はほとんど苗字で呼ぶことが多い。それは慎導さんも例外ではなかった。なかったのだがどうも慎導さんとしては気になるようだ。
「…どうしてもですか?」
「うん、どうしても」
「…」
「できたら特別に名前が喜ぶものをあげよう!」
慎導さんはニヤリと笑う。食べ終えた食器をキッチンへと持って行って流し台にある水の張った桶にお皿を漬けてから冷蔵庫を開けてのんびり中を物色し始めた。…私が面と向かって言うのは恥ずかしがるってわかって敢えて席を外してるな。
なんだかいいように乗せられてる感は否めないけれど喜ぶもの、っていうのもちょっと気になるのもあって私は慎導さんが見ていないことを確認してから顔を俯かせて小さく息を呑む。
「あ、灼…さん、」
「んー?」
「こ、これでいいでしょ!」
「なになに?冷蔵庫のファンの音が大きくて聞こえなくて。もう一回」
「灼さん!」
「はい、よくできました」
顔をばっとあげればにんまりと嬉しそうな灼さんが既に私の前に移動して来ていて箱を差し出していた。がっつり顔を見られてしまっていたことが恥ずかしくて顔が熱くなる。唇をきゅっと噛みながら私は灼さんが差し出してくれている箱を受け取った。よく見ると最近人気のお店のチョコレートだ。食べてみたいと思ってたやつ。
「昨日捜査で行ったところの近くにあったから帰りに買ってみました!どう?喜ぶものでしょ」
「…た、食べてみたかったんですこれ。確かに嬉しい、」
「ふふ、それなら何より」
灼さんに小さくお礼を述べれば相変わらずにこにこしてどういたしまして、と返される。テレビで特集されてて食べたいなあ、なんてぼやいてたの聞いてたんだ…。ソファーでうとうとしてたからてっきり聞いてないと思ってたのに。箱を開けて早速一粒口に入れてみた。甘さとほろ苦さが絶妙で頬が落ちるとはこのことをいうのだろう。たまらない美味しさに思わず口元が緩んだ。
「名前」
「んっ、なんですか?」
「チョコ食べるとすごいゆるゆるな顔になってる」
「…っ!?気を付けます!」
「そういう顔のが可愛いしおれはいいと思うけど」
遠慮なく食べて、と隣に座って嬉しそうに食べているところを眺めている灼さん。そんなにまじまじ見られると恥ずかしいんだけどな。でも顔が緩むとわかった以上これを外で食べるわけにはいかない。名残惜しさはあるけれどチョコは全部此処で食べていかないと。
もう一粒口に入れた後ふと横にいる灼さんに視線を向ける。「灼さんも食べますか?」そう聞けば嬉しそうに頷いて口を開けて待っているから気恥ずかしいけれど私は開いた灼さんの口にチョコをそっと押し込んだ。ぱくりと一口で食べた灼さんはもごもごとチョコを咀嚼すると確かに美味しい、とふにゃりと笑ってくれる。
「また買ってくるから一緒に食べよっか」
「…是非!」
「じゃあ名前もまた美味しいオムライス、作ってね」
灼さんにそう頼まれて大きく頷いたところで端末のアラームが鳴り響いた。出社時間が近づいていることをAIが知らせてくれる。名残惜しいけれどこうして出社前に灼さんと過ごせたことは何よりも私にとってはメンタルケアなので晴れた気持ちで片付けを済ませたあと出社できるのだった。
20191126