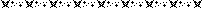

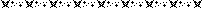
10 飼い馴らされた自由 ──承太郎が日常に戻って早2週間。 「………」 相変わらず昼夜が逆転しがちであの日、涙を見せた事以外、特に九龍に変わった所は無い…はずだった。 「ねえ、承太郎。九龍ちゃん最近、元気無いわね…」 「…んな事、わかってる」 この頃の九龍は、起きている時間でもぼーっとして、つい最近まで夢中だったはずの玩具で遊ぶ事もなくなった。 承太郎もホリィも一度は原因を考えて九龍本人にそれとなく訊ねたが、ホームシックという訳でもなさそうだ。 「一度、病院に連れて行った方がいいのかしら…」 何かの病気に罹っていたら大変だ。 しかし、承太郎はホリィの提案に頷けないでいた。 起きている間も寝ている間もスタンドが発動しっぱなしの、理性でスタンドを扱えるとは思えない子供を、普通の病院に行かせるのは不安だった。 事情を知るSPW財団と連絡を取った方が良いかも知れない。 「…承太郎」 その夜、話題の人物が承太郎の部屋を訪れた。 「どうした、九龍。また本でも読んでほしいのか?」 ベッドの上で音楽を聴いていた承太郎は上体だけ起こして訊ねる。 「ううん、違う」 否定の言葉通り、九龍の手は頭部を模したスタンド以外、何も持っていない。 部屋の中に入って来た九龍の瞳に、承太郎は微かな違和感を覚える。 だが、それも束の間──… 「…ちょうだい」 何を、と問う前に九龍は身を乗り出す。 「!」 チュッと押し当てられた唇から小さな舌が承太郎の咥内に割り込もうとして、ようやく承太郎は九龍を引き剥がす。 「…何やってんだ」 溜息混じりのその問いは、九龍ではなく、未だ九龍の中に巣くうDIOへと向けられていた。 しかし、既に死んでいるDIOは、息子の育て方を責める承太郎の疑問に、永遠に答えはしない。 答えは、自我すら危うく見える九龍本人から知るしかないのだ。 「ダディは…くれた。いつも、『食事』──…」 「…何?」 承太郎の脳裏に、今まで半信半疑だった可能性が現実味を増して浮上する。 「オイ、待て」 まさか… いや、まさか… 認めたくなかった最悪の可能性。 日常生活において昼夜が逆転しているとはいえ、太陽の下でも九龍は生きている。 しかし、九龍の父親は百年生きた吸血鬼のDIO。 いや、本来ディオ・ブランドーが持たない筈のジョースター一族の星型の痣を持つ時点で、九龍という存在は既に『異質』なのだ。 「!」 九龍の尖った歯が承太郎の指の皮膚を突き破る。 「………」 そこから溢れ出た液体を、恍惚とした表情で舐める九龍を見て、とうとう承太郎は確信せざるを得なかった。 ──九龍は『吸血鬼』の血を引いている。 >>これを前章最後に持ってくると、なんか不吉な感じで終わってしまうのでこっちです。 |