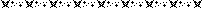

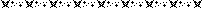
12 「うう…いい天気ィ…」 電車で杜王町に着いた九龍は早速、折り畳みの日傘を開く。 ちょうど学生の下校時刻なのか、駅前のバスターミナルには学生服姿の若者が多い。 「いいタイミングだな。寄り道してなけりゃあ、俺達が着く頃には『東方仗助』も家に帰ってるだろう」 ジョセフの隠し子、東方仗助は今月入学したばかりの高校1年。 通う学校は授業の長い進学校でもないし、まだ遅くまで学校に居残る用事も特に無いだろう。 「さて…」 タクシーの姿も無いので、歩きながら承太郎の方は日傘ではなく、予め用意していた杜王町の地図を開く。 「駅は…此処だな。俺達が行きたいのは定禅寺という所だが…」 「ちょ…承太郎、こういうの危ないって言うんだよ。どっか座ろうよー」 しかし、九龍の忠告は手遅れだった。 「うわっ!」 1人の小柄な男子学生が突如、進行方向に現れた承太郎とぶつかり、鞄の中身をぶちまけてしまった。 「え!?あっ!あっ!あれェ〜?おかしいな…今ぶつかって転んだと思ったのに…?」 すかさずスタープラチナを発動させて鞄の中身を戻し、男子学生を助け起こしたので惨事は免れたが… 何が起こったか分からない男子学生はすっかり混乱している。 「承太郎、今日2回目ー」 「よそ見しててすまなかったな…」 だが、ちょうどいい。 承太郎は地元の人間らしい男子学生に道を訊ねる事にした。 「君、この町で『東方』という姓の家を知らないか?」 「『東方』…?う〜ん、ちょっと知りません…」 「なるほど、ならば住所ではどうかな?『定禅寺1の6』」 「ああ、定禅寺なら…あそこから3番のバスに乗れば行けます。この時間、タクシーはあまり来ませんよ」 そう言って男子学生はあるバス停を指差す。 「ありがと、学生さん」 「い、いえ…」 (親子?なんか変わった組み合わせだな…) 「あ、定禅寺みっけ」 同じ方向らしい男子学生こと広瀬康一と承太郎達が3番のバス停でバスを待っていると、康一はこちらに近付いてくる学生達を見つけ、表情を強張らせる。 学生達は時代遅れだが、いかにも不良といった風体だ。 「こらっ1年坊ッ!挨拶せんかいッ!」 「さっ、さよならですッ!先輩ッ!」 康一は彼らに頭を下げ、穏便にやり過ごす。 「大丈夫ですよ…あの人達は5番のバスで違う方向へ行っちゃいますから」 「え?康一、何で分かるの?」 どうやら、この界隈で有名な不良集団らしい。 「…というか、今時、ああいう不良が本当にいたんだ…」 「はは…」 康一と不良達のやり取りをポカンと見つめていた九龍は珍しそうに呟く。 「何しとんじゃッ!」 「何のつもりだ貴様ッ!」 先程の不良達の声が聴こえる。 視線を移せば、人工池の前に座って亀と戯れる、これまた時代錯誤なリーゼント頭の男子学生が彼らに絡まれていた。 「何って、その…この池の亀が冬眠から覚めたみたいなんで見てたんです」 「ハァ?テメーもこの亀の様に…してやろうかッ、コラーッ」 すると、不良の1人が亀を近くの柱に投げつける。 「あっ…」 「さ、サイテー」 亀は甲羅が割れ、無惨にも血を流しながらピクピクと手足を動かしていた。 痛々しい光景に九龍と康一は彼らへの不快感を表情に出す。 「今日のところは勘弁してやる」 「その学ランとボンタンを脱いで置きな。それと銭もだな」 「はい!すみませんでした!」 それなのに、リーゼント頭は不良達にあっさり頭を下げる。 意外にも、尖った見掛けの割に肝が小さいのだろうか。 「オイ!腰抜け!貴様の名前を聞いとくか!」 「はい。1年B組…」 次の瞬間、リーゼント頭から発せられた名前に、承太郎と九龍は一斉に彼に視線を向けた。 「東方…仗助です」 捜し人と同姓同名で同年代。 間違いない、彼が承太郎達が会いに来た『東方仗助』だ。 「コラ!バスが来ちょったろがッ!チンタラしてっとそのアトムみてーな頭刈り上げっど!」 「おい…先輩。アンタ…今、オレの、この頭の事、なんつった?」 その時、東方仗助の纏う空気が変わった。 「!」 何が起きたか、承太郎と九龍以外の人間には分からない。 『見えない』からだ。 だが、2人には確かに見えた。 仗助の背後からスタンドの腕が飛び出し、不良の歯を折り、鼻が変形する程の威力で殴った光景を… 「ホゲェーッ」 「うわーッ」 殴られて吹っ飛ばされた不良に他の仲間達も巻き添えになる。 「オレの頭にケチつけてムカつかせたヤツぁ、何モンだろうと許さねえ!」 不良に制裁を加え、気が済んだのか平静を取り戻した仗助は先程の亀を拾い、池に帰す。 しかし、そこでまた異変が起こる。 今度はスタンドの見えない人間の目にも見える変化だ。 「あ…あれ?お、おかしいぞ、亀の傷が治ってる!甲羅が割れていたのに!」 更に──… 「今殴られた顔の傷がどんどん治っていく!鼻が裂けて血がドボドボ出てたのに!」 「で…でも何か変な感じに治ってないか?」 仗助や仗助のスタンドが触れた対象の傷が、『治る』。 その特性に気付いた九龍は確証を求め、同じスタンド使いである承太郎に訊ねる。 「じょ、承太郎っ、これって…」 「ああ」 間違いない、スタンド能力だ。 「やれやれ、コイツが俺の探していた、ジジイの身内だとは…」 捜し人が目の前に居る。 承太郎は早速、彼に接触を図った。 「東方仗助。1983年生まれ。母の名は朋子。母親はその時、21歳。東京の大学へ通っていた」 突然現れた大男に自分の名前と母の経歴を言い当てられ、仗助は不思議そうに承太郎を見つめる。 どう反応したらいいか分からない、といった表情だ。 「生まれた時より、この町に住んでいる。4歳の時、原因不明の発熱により50日間、生死の境を彷徨った経験あり。父親の名前は──…『ジョセフ・ジョースター』」 私生児である為に自分の家族しか存在を知らない、会った事も無い父親の名を出され、ようやく相手が只者でないと気付いた仗助は何者か訊ねる。 「アンタは…?」 しかし、承太郎は答えない。 「ジョセフ・ジョースターは79歳。まだ元気だが、遺産を分配する時の為に調査をしたら、ジジイ自身も知らなかった君という息子が日本に居る事が判った。あのクソジジイ…『ワシは生涯妻しか愛さない』などと聖人の様な台詞吐いときながら…」 「え?アンタ、もしかして…」 ジョセフ・ジョースターの存在を知る人間どころじゃない。 説明に愚痴が混ざり始め、仗助は目の前の大男が父親の非常に近しい身内である事を悟った。 「おっと、口が悪かったな。俺の名は空条承太郎、何つーか奇妙だがお前の『甥』ってやつになるのかな」 「はあ…どうも」 驚きのあまり、気の抜けた返事を返した仗助はふと、承太郎にしがみつく眠そうな子供に視線を落とす。 「こっちは俺の…『弟』の九龍だ。正確には俺達の遠い親戚に当たるがな」 「えっと…ヨロシク」 「うん、よろしく…ふあぁ」 流石に見た目小学生、実年齢14歳の子供を『お前の父親(79)の血縁上の叔父』とは説明出来ず、承太郎は詳細をぼかして曖昧な紹介をした。 >>もし主人公との血縁関係を説明すると、傍から見たら一体どんな一族という関係に… 康一君の頭がパンクしそうです。 |