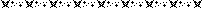

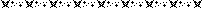
27 カチ、カチ 「………」 カチカチカチカチカチカチ 「…?」 「どうした?」 「シャープペンの芯、もう無い。朝になったら買いに行かないと…」 †††††††† ある週末──… 土曜の授業が終わり、一度家に帰ってきたばかりの仗助の元に、承太郎から電話が掛かってきた。 「はい、もしもし〜?何だ、承太郎さんスか」 『すまないが、そっちに九龍は来ていないか?』 「え、おチビ?来てないっスけど…」 普段通り冷静な声だが、どこか焦っている様に聴こえるのは恐らく仗助の気のせいではない。 「どうかしたんですか?」 「朝に九龍が出掛けたきり、戻ってこない」 チラリ、と仗助は横目で時計を見る。 「戻って来ないって…まだ昼前っスよ?寄り道でもしてんじゃねーの?」 「『もう』昼前だ。アイツはこんな時間にわざわざ寄り道出来る体質じゃあない。それに携帯も通じない」 承太郎の言葉に、そういやそうだった…と仗助は納得した。 億泰の父親に肉の目を植え付けた吸血鬼の血を引く息子。 父親の様に死ぬとまではいかないが、調子が出ないらしくて太陽は苦手だ。 そんな九龍が昼という最高に明るい時間帯が近付くまで望んで出歩くとは考えにくい。 「ま、まさか、誘拐ッ!」 ふと過ぎった嫌な可能性に仗助も慌てるが… 「仮にも九龍はスタンド使いだ。もしそういう輩に狙われたとして、大人しく捕まると思うか?」 「ですよね。普通の人間じゃ…」 無理、と言い掛けた所で、ようやく仗助は承太郎が言わんとしている事に気付く。 「まさか承太郎さん、スタンド使いの仕業っつーんじゃあないでしょーね!?」 この町には虹村形兆、音石明が弓と矢を使って目覚めさせたスタンド使いが『まだ』存在するかも知れないのだ。 「確証は無いが、九龍の身に何かが起きた事は間違いない」 とりあえず承太郎達は一度どこかで落ち合い、九龍捜索を話し合う事に決めた。 「どうだ、ジジイ。何か撮れたか?」 「ふぅ…さっきからやっとるんじゃがのう、さっぱりなーんも撮れんのじゃ」 杜王駅、噴水前──… 抱いていた赤ん坊を承太郎に預け、インスタントカメラを持ったジョセフは印画された写真を手に取り、お手上げといった風に手を振った。 ひらひら動く写真は真っ黒だ。 「何も撮れてないか、もしくは何も見えないくらい暗い所に捕まっちゃってるって事なのかな…」 手掛かりが無い以上、虱潰しに探すしか無い。 「俺とジジイはホテル周辺で情報を集める。土地勘がある仗助達には、文房具が売っている店を回ってもらいたい」 「文房具があるトコ…ん?つーかよぉ〜、シャーペンの芯くらいホテルの売店とかに置いてる気がするんスけど、何で九龍は外行ったんスかぁ?」 「あ、そうだ!もしかしてホテルの売店に買いに行ったんじゃあ…」 億泰と康一の言葉に、承太郎は首を横に振って否定した。 「今朝、売店までは俺も同行した。だが、九龍が使っていた0.3のBは置いてなくてな…本当は俺も付いてくつもりだったが、急ぎの仕事があってアイツ1人で行かせた」 「付いてくって…チビ、アイツあれでも14なんでしょーよ?ちっと過保…」 「仗助君!」 「…むぐ!」 咄嗟に康一が仗助の口を塞ぐ。 仮にも弟の身に何かあったかも知れないと後悔している人の前で過保護と言うべき状況ではない。 「…あと、聞き込みが不便だろうから、これを貸しておく」 そう言って承太郎は愛用のメモ帳を開き、何かを取り出した。 「少し前の物になるが、あまり変わらないからな」 「………」 承太郎から渡された物を受け取り、無言で見つめる仗助達3人は──… 「ブラ…」 「何か言ったか?」 「い、いえッ!何でもありませんッ!」 承太郎が普段持ち歩いていた九龍の写真を渡された仗助達3人は、もう何も言えなかった。 「すみません、この子を見掛けませんでしたか?」 「…うーん。いや、見てないねぇ」 「これでカメユーの文房具コーナーと町中の文房具屋は全部回った事になるけど…」 手掛かりは無し。 九龍は行きに何かに巻き込まれたという事か。 近くのコンビニでジュースを買いながら、3人は話し合う。 「康一よぉ、本当に文房具屋はあれで全部なのか?」 杜王町に引っ越してきて、この中で1番土地勘の浅い億泰が訊ねる。 「うん。間違いないよ…って、仗助君、何してるの!」 康一の視線の先、そこには仗助が雑誌コーナーをじっと見つめていた。 「いや、ワリィ。なあ康一、文房具売ってるトコは全部回ったんだよな?オレらが普段、何かのついでにシャー芯とか買いに行くトコも、チビが行きそうなトコも」 「そうだけど……あ!」 何かに気付き、康一は大きな声を上げる。 「ど、どうしたんだよ?」 都会育ちで学校に通った事の無い九龍に、学校の目の前にある様な小さな文房具店を使う習慣は恐らく無い。 何故、それに気付かなかったのだろう… 「そうだ!本屋だよッ!大きい本屋ならコンビニにも置いてない種類の芯だって置いてある!」 ちょうど、ホテルのギリギリ徒歩圏内には大きな書店が存在する。 承太郎達はまだこの可能性に気付いていないかも知れない。 3人は、すぐさま書店へと向かった。 「それにしても仗助君、よく気付いたね!」 「アンジェロ捕まえる為に承太郎さん達とウチで張ってた時によぉ、アイツ、オレにしつこいくらい訊いてきたんだよ。学校の事とか」 仗助にとっては当たり前の日常生活を、まるで冒険譚を訊く様に、キラキラした瞳を仗助に向けて。 「…それ思い出した時、チビとオレらの行動範囲って、ちっとばかし違うんじゃねーかって思ったんだ」 「あの、すみません!今日、この子が来ませんでしたか?」 「…!ああ、来たよ!」 ようやく掴めた手掛かりに、3人はホッと胸を撫で下ろす。 「よーく覚えてる。外人の子供なんて珍しいし、店を開けたと同時に来たからね。それに…」 「それに?何だよ」 「いやね、ウチの常連の有名人がわざわざ店の外まで追い掛けて、この子に話し掛けてたんだよ。ほら、此処に色紙が飾ってあるだろ?あの人さ」 そう言って店員はどこか誇らしげにレジの奥の壁を指差す。 ○○書店様へ、と書かれた色紙は直筆でキャラクターのイラストまで描いてある、ちょっとしたお宝だ。 何せ相手が全国区クラスの有名人なのだから。 だが、店員の意図とは別の方向に、康一は驚愕する。 「あ…あ…そんな…ま、まさか!」 ハットを被ったキャラクターの絵を、康一はよく知っていた。 大好きなのに、先日の1件のせいで現在ちょっとしたトラウマになりかけているそのキャラクターは──… 「『ピンク・ダークの少年』!岸辺露伴ッ!?」 >>承太郎氏が写真持ってたのは、本来なら今はもう一緒に住んでないからです。 決して疚しい感情はありません(汗) |