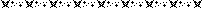

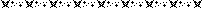
30 何も、スタンド使いが『人間』とは限らない。 DIOの側近にはスタンド使いの鳥が居たし、九龍は直接会った事が無いが、DIOを倒す為に承太郎と共に戦った仲間には犬が居た。 「厄介な事になったな…」 現在、杜王町で弓と矢を使用した人間で生存しているのは、SPW財団によって拘束されている音石明のみ。 その音石が射った対象を白状させ、承太郎が生存=スタンドに目覚めたか、相手がどんな人物かを調査しているのだが… 「どうしたの、承太郎?」 SPW財団からの報告を受けた承太郎は、これまでの反応とは違う。 †††††††† 「仗助…これから『狩り』に行く。一緒に来てくれ」 「はあ〜〜っ?」 突然呼び出されたと思ったら、これまた唐突な事を言われて仗助は困惑する。 しかも、相変わらず九龍も一緒だ。 この人どんだけ弟大好きなんだよ… 「ちょっ…ちょっと待って下さい、承太郎さん!」 何も言わず歩きだした承太郎を、仗助は慌てて呼び止める。 「いきなり言うもんだから金縛りに遭っちまいましたよ。今『狩り』って言ったんスか?『ハンティング』って、まさか…それって…」 仗助は急に乗り気になり、デレデレしながら続ける。 「ナイスバディのお姉ちゃん捕まえるハンティングっスか?」 何を勘違いしたのか、満更でもなさそうに語り出した。 「俺、結構純愛タイプだからなあ。そーゆー事やった事ねーっスよ。出来るのかなあ〜〜」 「仗助、そういうの『鼻の下が伸びてる』って言う。サイテー…」 「なぬっ!?おい、チビ!オメー何怒ってんだよ?」 不機嫌そうにむくれる九龍に訳が分からず、仗助が現実に引き戻されると… 「『レッド・ホット・チリ・ペッパー』の音石明が昨日、自白した」 「音石?」 何故、今更になって承太郎の口からその名が出てくるのか。 「『音石明』は俺達に正体がバレる前…例の『弓と矢』を使って、この町のある場所で1匹の『鼠』を射っていた」 「ネズミぃ!?」 なんつーモンを射って遊んでたんだよ… 仗助が呆れていると、承太郎は手持ちの地図を広げ、場所を指した。 「その『鼠』は射られても死なず、藻掻きながら突き刺さった『矢』から自力で脱出し…逃げ去ったと言う」 「『矢』で射られながら死んでない!?つまり…」 矢の特性を知る仗助はすぐさま状況を理解する。 「『鼠』だが、そいつは確実に『スタンド能力』を身につけている事になる。どんなスタンドかは分からんが、何かが起こる前に、その鼠を狩らないといけない」 人間ならば、強大な力を手に入れた時に取る行動、騒動の規模を大方予測する事が出来るが、原始的な欲求だけで動く生物はそうもいかない。 本能だけで動く存在の厄介さは、承太郎も目の前の弟が幼い時に経験済みだ。 「『狩り』っていうのは、その…鼠を、『捕まえる』つー事ではなくて『殺す』…ンスか?」 「仗助?」 鼠とはいえ、血が通った動物の命を奪う事に抵抗があるのだろう。 人間の偽善じみた価値観だが、九龍は仗助のその優しさが嫌いではない。 「なるべく捕まえたいが…人間ではないからな、相手次第だ。どうなるかは分からない」 「分かりました、いいっスよ…一緒に、行きます」 音石明が鼠を射ったと証言した目的地周辺に到着した3人は、早速手掛かりになる痕跡を発見した。 「足跡を見つけたぜ。この辺りにどのくらいの数かは分からんが、鼠がいる」 その足跡を辿ると、承太郎達が目指していた排水路に到着する。 「間違いなく、この排水口の奥に『巣』がある。ここにとりあえず何個か『罠』を仕掛けておこう。九龍」 「うん」 九龍が鞄から出した罠に使用する道具やカメラを、承太郎は手早く仕掛けていく。 すると、その最中、九龍は不快そうな表情を見せる。 どうしたのかと仗助は声を掛けようとするが、仗助自身もある異変に気付いた。 やけにハエの数が多い… その中でも特にハエが群がっている草むらを仗助が掻き分けると、そこには──… 「じょ、承太郎さんッ!」 ハエが群がる物の正体を見た仗助は、一瞬の判断で承太郎だけを呼ぶ。 だが、敢えて仗助が見せたくなかった九龍は承太郎の後を付いてきてしまったのだ。 「おい馬鹿!オメーが見るもんじゃねーっての!」 「うげ…」 茂みの奥にあった物、それは──… 「鼠の…死体か…」 ただの死体では無い。 何匹ものネズミの死骸が1ヶ所に集められ、まるでゼラチンを固めた食べ物の様に固められていた。 とても自然に出来た物ではない。 専門は海洋生物だが学者である承太郎としては、この奇妙な物体を調べないと気が済まない。 「ギャー!承太郎何してんの!」 「ゲッ、突っつくなんてやめて下さいよ…」 若者2名の非難の声を無視し、そこら辺に落ちていた枯れ枝で物体を突き刺すと、煮凝りの中身が吹き出す。 更に枝で内部を切り開くと承太郎が気付いた事だが、枝の先についた粘性のある液体は腐敗だけが原因という訳では無さそうだ。 「この鼠らの肉が一度溶けて固まっているって感じだな。しかも、皮膚の内側から溶かされて死んでいる…コイツは俺達の追っている『鼠』の仕業と見ていいぞ」 仗助の背に隠れてグロテスクな光景から目を背け、承太郎の言葉に耳を傾けながら、九龍は呟く。 「全部グチャグチャって、なんか勿体無い事してるんだね。その鼠」 「奴らは雑食の生き物だからな。お前の感覚じゃ食えないから勿体無いだろうが、何でも食う鼠にとっちゃ合理的だ」 だが…と、九龍に鼠の生態を説明しながら、承太郎は今回の本題について結論を下す。 「どうやら、この『狩り』は、殺す事を前提に追跡した方が良さそうだな。…やれやれ」 「グレート…やっぱりおぞましくなってきた」 生け捕りか殺処分か。 まだ詳細な能力は分からないが、危険性のあるスタンド能力である事は明白。 殺す、という承太郎の判断を、危険性を目の当たりにした仗助も最早頷くしか無かった。 「『何か事が起こる前に鼠を狩る』と言ったが…まずいな、この排水路…」 望遠鏡を使って付近の様子を探っていた承太郎が呟く。 「あ」 続いて、九龍も小さく声を上げる。 2人の視線の先には、田園に囲まれたとある1軒家が存在した。 「あの農家の下水に続いている。既に遅かったかも知れん…」 承太郎の中には、既に最悪の可能性が生まれていた。 「どうすか?何か分かりますか?」 発見した民家の様子を引き続き望遠鏡で探る承太郎に仗助は訊ねる。 「かなりヤバいな。鶏小屋があるが鶏が1羽もいない、餌箱も空だ。家には住人の気配が全く無いが、ドアが少し開いているから外出していない事は確かだ」 「…と、言う事は?」 「『鼠』は、いるな。そして不安通り、住人は既に殺されてる可能性が高い」 >>もったいない=血(食糧)と食べられない物を混ぜるなんてとんでもない! |