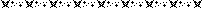

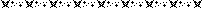
35 空条九龍は漫画家、岸辺露伴が苦手だ。 先日、彼には酷い目に遭わされた。 嫌悪の対象とまでは行かないが(本気で恨んでたら誘拐された件の詳細を仗助達に口止めして承太郎に隠したりしない)、出来ればあまり近付きたくない相手だ。 そんな岸辺露伴が、康一と偶然再会して2人は不思議な存在に出会ったらしい。 「オーソンの前に居る女の子の幽霊、かあ…」 夕暮れの公園でブランコを漕ぎながら、九龍は3人から聞いた存在を呟く。 「本当なんだよ、九龍君!」 「…で、やっぱスタンド使いじゃねーと承太郎さん達やSPW財団は動かねーんだろ?」 「そりゃ、ただの殺人事件だからね…吸血鬼とか石で出来た仮面とかならやってるってジョセフが言ってた」 元々、SPW財団は超常現象について調べる為の組織だ。 百年前、石仮面という吸血鬼を生み出す道具をきっかけに吸血鬼との戦いやジョセフも使える波紋に関わって死んでいった親友を持つ創設者の方針らしい。 『この肉体は、私とお前…親子の絆の様なモノでジョナサンの子孫と通じているらしい』 その亡き親友というのが、ジョセフの祖父で九龍の父DIOが身体を奪い取った男なのだから… 血液を提供して貰っている九龍は全く、財団に足を向けて眠れない。 「さて、と」 九龍がブランコから降りると、視線の先には承太郎が居た。 「一応、話してみれば?」 †††††††† 少女は、泣きながら青空を見上げる。 「なんて事…!また…だわ、また『アイツ』だわ!アイツにやられた魂が飛んでいく!」 ──少女が空を見上げた次の日、オーソンの前には10人以上の人間が仗助達の招集で集まっていた。 学生達にコック、老人に子供、はたまた人間離れした容貌の者など、一見すると何の集まりか分からない集団だ。 だが、彼らの共通点はそのほとんどが特異な能力の持ち主、スタンド使いである、という事だ。 仗助達がこれまでに出会った者の中で、友好的な関係のスタンド使い全員がこの場に呼ばれている。 その中の例外、スタンド使いでは無い少女は輪の中心で仗助から渡された写真を真剣な表情で見つめていた。 少女は一瞬、悲しげに目を伏せ、再び顔を上げると同時に重い口を開く。 「間違いないわ……この子は、死んでるわ」 写真に写る少年、重ちーもまた、スタンド使いであり、仗助と億泰の友人であった。 「重清君はアイツに出会って、そして殺されたのよ。あたしには分かるの…何故アイツに出会って、どんな方法で殺されたのか、それは分からない。でも、アイツの仕業よ…あたしを殺したアイツの仕業って事は分かるの」 少女の名は鈴美。 康一と露伴が先日出会ったという、例の殺人鬼に殺された幽霊の少女だ。 同じ殺人鬼に殺された者の魂が天に昇る姿が見える為、昨日見た同類の存在を彼女は気に掛けていた。 友人が奇妙な痕跡を残して消えた仗助は康一から先日聞いた鈴美の存在を思い出し、重ちーが最期に残した痕跡から事態を大きさを感じ取って承太郎達だけでなく他のスタンド使いもこの場に呼んだ。 「みんなは重ちーの事、あんまり知らねーだろーがよ、重ちーのハーヴェストに勝てる奴ってのは考えらんねーぜ。しかも重ちーをオレ達と別れた後、たった5分の間に殺して学校の中から死体をどーにかして隠しちまったんだ」 昨日の昼休み、仗助達は重ちーと会っていた。 しかし、仗助達より年下の中学生で校舎の違う重ちーと別れて5分後、仗助の元に傷だらけになった重ちーのスタンド、ハーヴェストが訪れた。 スタンドが受けたダメージは本体に跳ね返る。 だが、スタンドにダメージを与えられるのはスタンドのみ。 「つ…つまり、その…犯人はスタンド使いって事?」 ましてや、ハーヴェストは小さいながらも無数の数を持つ群れのスタンドで、その内の1体がダメージを受ける程度では本体に跳ね返るダメージなど、たかが知れているのだ。 故に仗助は、ハーヴェストに…重ちーに勝てる相手は滅多にいないと考えていた。 傷だらけのハーヴェストが自身の元に来なければ、仗助も彼の失踪の原因に辿り着けなかったかも知れない。 重ちーは仗助達に、己の身に起こった非常事態をなんとかして伝えようとしたのだ。 「仗助、ボタンを拾ったらしいな」 「ああ…これっス。重ちーのハーヴェストの1匹が持って来たんスよ」 そしてスタンドはバラバラになって消滅した。 「変な模様…」 「これは重ちーの遺言だな。ひょっとすると犯人が着ている物から引き千切ってきたのかも知れん」 仗助からボタンを受け取った承太郎はじっくり観察しながら呟く。 (遺言…) 状況は分からないが、ボタンをもぎ取るなんて、犯人の本体に相当近付かないと不可能な芸当だ。 死を覚悟し、犯人を激昂させるかも知れないリスクをわざわざ冒してまで仗助達に『自身をこれから殺す犯人の存在』を伝えようとしたというのか。 その予測に辿り着いた時、九龍は戦慄し、鳥肌が立った。 「そ、そんなどこにでもあるよーなボタンから追跡できるもんスか?」 「…可能性はある。くっついてた服のブランドやメーカーくらいは分かるかも知れん。このボタンは預からせてくれ」 もし流通ルートが限定的な物だったら、犯人の特定に大きく繋がるかも知れない。 ──重ちーが、望んだ通りに。 「は、話が済んだらよ…オ、オレは帰るぜ。な、なんか妙な気分だぜ…イラついてよ。帰るぜ、親父」 皆に背を向け、父親を連れて億泰は歩き出す。 「億泰君、なんか変だよ?」 康一の言う通りだ。 いつもの調子の億泰ならば、こんな時に1番怒り、悲しむ姿を見せるのに。 顔と声を強張らせるだけで、静かなままだった。 「こういうの、億泰らしくない。何でだろ?」 「…重ちーってよ、すげえ欲深でムカつく奴なんだが、ほっとけねーってタイプの奴でよ。死んだってのが信じられねーんだ」 ポンと九龍の頭に仗助の手が乗せられる。 「それに…今のこの気分、怒ったらいいのか悲しんだらいいのか、それさえも分からねーイラつきがあんだよ。今のオレ達…億泰は特にだろーな」 背中を見送っていると、億泰の歩みが止まる。 「く……くそ〜…」 背を向けたまま、肩を震わせる億泰はきっと泣いているのだろう。 兄を喪った時の記憶を友の死に重ね、相手への怒りと自分の無力さに対する憤り、大切な人を喪った悲しみが心の中でぐちゃぐちゃになっているのだと、仗助は語る。 「仗助──…」 でもそれは、仗助も同じでしょ? 『そんなハズは…オレのスタンドは傷を治せる!じいちゃんのこの傷は完全に治った!コラじいちゃん、ふざけると怒るよ!』 大切な人を悪意あるスタンド使いに殺された経験を持つのは、億泰を気に掛ける仗助自身もだ。 いつも、もう立ち直った様に振る舞っているけれど、喪失感はそう簡単に埋められるモノでは無い。 死んだ相手が親しければ親しい程、日常のほんの些細な出来事で故人との記憶が蘇り、現実を改めて突き付けられる。 仗助が祖父を喪ってから、まだ2ヶ月しか経っていないのだ。 「………」 九龍は強がる仗助の顔を不安そうに見上げる。 未熟な自分では、悲しみを内に抱え込む仗助の支えになれない… 己の無力さがやるせなかった。 「あたしが知らない間にとんでもない事が起こってたのね」 「ワタシハオ店ニ来ルオ客様ヲ注意シマショウ」 「スタンド使いとスタンド使いは惹かれ合う、か。ボクは会いたくないけどね…」 「これで皆、動き出すって訳か」 集められたスタンド使い達は皆、それぞれの日常に戻っていく。 ただ1つ、この町に潜む殺人鬼の存在を胸に留めながら。 >>吉良との戦いはこの話的に最後までやらなくてもいいかなーと思ったり… |