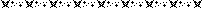

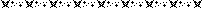
37 「最近、日が出てる時間帯にこき使われてる気がする…」 そう呟き、手前を歩く九龍の表情は日傘に隠れ、承太郎からは見る事が出来ない。 「わざわざ着いて来なくてもいいんだぜ。辛いだろう?」 「やだ!置いてかれるのは、もっと嫌!」 立ち止まり、日傘ごと身体を反転させた九龍は、不機嫌そうに頬を膨らませて承太郎を見上げていた。 今日の2人は、重ちーが仗助に託したボタンについて調べていた。 聞き込みの結果は…全滅。 「…承太郎、この前は僕を囮にしようとしてたくせに」 忘れもしない、アンジェロとの戦いで聞かされた話──… 「やれやれ…あれはまだお前を守れる自信があったからだ。正体も分からない敵との戦いにお前を巻き込みたく無いってのが本音だ」 「それって徐倫達みたいに?」 「………」 (ふーん、図星なんだ…) 妻と娘を引き合いに出されると途端に黙り込んだ承太郎に、九龍はやるせない感情を抱く。 承太郎は妻達にDIOとの戦い、スタンドやそれに関わる事は一切話していない。 今回だって、実家の問題と仕事が重なったと半分嘘をついて杜王町の滞在を続けている。 そんな彼女らと、九龍は承太郎の中では『同じ』なのだ… 九龍はスタンドの事だって、承太郎が妻達に何を隠しているのか、ちゃんと知っているのに。 ──役立たずだと言われたみたいで、悲しい。 いっそ、直接はっきり言われた方がすっきりするのに… どうして承太郎はいつも、言葉でないと伝わらない事を言ってくれないのだろう。 (言ってくれないと、分からないのに!) 駅前の商店街を2人で歩いていると、聴き慣れた声がぎこちなく呼び止めた。 「あ…こ、こんにちは。承太郎さん、九龍君」 「康一!」 学生鞄を持った康一だった。 「康一も帰り?」 「も?」 「あーもー、すっごい疲れた!今日さぁ…ぶふっ!」 急に足を止めた承太郎にぶつかり、九龍はコートに顔を埋めた。 一方の承太郎は傘が当たっても気にした様子も無く、眼前の店をじっと見つめながら康一に問う。 「康一君。この店…見たところ『靴屋』の様だが…」 「えっ?ええ、靴屋さんですよ。どうかしましたか?」 靴のムカデ屋──… 店名もガラス窓から商品をアピールする外観も、何処からどう見ても靴屋だ。 しかし、そのガラス窓に貼られた1枚の貼り紙を承太郎は無言で指差す。 貼り紙の文字を読み、あ〜と康一が承太郎の質問の意図に納得の声を小さく上げる。 「靴屋ですけど、スカートのウエストやズボンの裾とか、服の軽い直しもやってるんですよ」 カメユーとかあるからたまにしか行かない靴屋だけじゃ、最近はやってけないですからね…と、康一は地元民から見た町の現状を語る。 副業を行う事で常連客を掴む。 便利な大型ショッピングセンターに客を取られてしまう個人経営の店なら、近年どの地方でも珍しくない戦略だ。 「あっ!」 康一の説明を聴き、九龍は弾かれた様に、埋もれていた白い巨体から顔を上げる。 ここ数年、日本から離れて暮らしていた承太郎とあまり外を出歩かなかった九龍は、今まで気付きもしなかったのだ。 「…なるほどな。杜王町近くの洋服屋は今日全て訊いたが、こういった所への聞き込みは見落としていたぜ」 承太郎の言葉と、コートのポケットから取り出された小さなビニール袋…いや、その中身に、今度驚くのは康一の番だった。 「あっ!そ、そのボタンの…犯人の証拠品の聞き込みなんですか!?」 ──早速、目の前の靴屋に入り、3人は店主にボタンを見せた。 「ふーむ、このボタンがどうかしたの?」 ホットコーヒーを飲みながら、店主は不思議そうに訊ねる。 確かに靴ならともかく、こんな服にしか使いそうに無いボタンについて訊きにわざわざ靴屋に来る客など、滅多にいないだろう。 「いや、見覚えが無いならいいんだ。どんな服についてたボタンか思い出せなくてね…」 「そ、そうそう!承太郎って割と忘れっぽいよね!」 理由を作るのにも一苦労だ。 「ふ〜ん…でも、見覚えが無いも何もさ」 おかしな客にそれ以上詰問する事も無く、店主は承太郎達にとっての希望を口にした。 この人は、このボタンを知っている… しかも──… 「そのボタンの服なら…」 店主は、背後のハンガーに掛かった1着の服を指差す。 男物のスーツの上着、その正面に縦に3つ並ぶボタン。 「…ほら、そこに直したばっかのヤツがあるよ。昨日、全く同じボタンを取れて紛失したから付け直してくれってお客さんあってさ」 恐らくスーツに付いている予備のボタンを使ったのだろう。 ボタンを紛失したというのに、全て同じ物が付いている。 「ほら、同じボタンでしょう?」 失くしたボタンは、承太郎の手の中にあるのに──… 「あー!変な模様のボタン!」 「承太郎さんッ!!」 「やれやれだ…とうとう見つけたぞ」 同じ町に同じタイミングで服から同じボタンを失った人間が2人も存在するとは考えにくい。 予想外の収穫に、3人は驚愕と歓喜の入り混じった反応を見せる。 「見つけた?」 「い…いえ、そ…それよりどんな客でしたか?名前、分かります?」 脱獄犯故にこそこそ人目を隠れて生活していたアンジェロと違い、こんな場所に服の直しを頼む様な人間だ。 名前さえ分かれば、ほぼチェックメイト。 「そりゃあ分かりますとも」 「本当か…」 康一の質問に、店主はさも当然の様に頷き、得意気な表情を浮かべる。 「え〜と、あの名字は…何て読むのかな、確か…」 暫く考え込んだ後、読み方が思い出せないからタグを直接見せた方が早い、と言って店主は椅子から立ち上がり、ハンガーラックの方へ向かった。 そして、湯気が出ているコーヒーカップを片手に持ったまま、ハンガーに掛けられた上着の裏を捲る。 3人が固唾を呑んで見守る中──… 事件は、起こった。 ボゴォォッ 「え……?」 それは、あまりに突然の出来事だった。 コーヒーカップを持っていた店主の手が、カップごとまるで爆発した様に吹き飛んだのだ。 床にカップの破片と、店主の指や血が飛び散る。 承太郎と康一は唖然とし、九龍は新鮮な『餌』に目を奪われた。 一体何が起こったのか、事態を飲み込めないのは3人だけでなく、手を吹き飛ばされた本人も同様だった。 「え?え?」 人とは不思議な生き物だ。 傷を負った瞬間よりも、傷を知覚してしまった後の方がずっと、感じる痛みが強いのだから。 ぽっかり空いた穴、そこから剥き出しになった骨、身体から失った指… やがて、現実を理解すると同時に、痛覚が店主を襲う。 「なあんだぁ──ッ!?私の手がぁッ!」 今までに経験した事の無い激しい痛みと恐ろしい状況に叫ぶ店主の肩を、3人は警戒しながら見つめていた。 『コッチヲ見ロ』 いつの間にか現れた、玩具の車の様な『何か』が店主の背中を這い上がり、肩の上へ辿り着いていたのだ。 その不気味な『何か』は大口を開けて叫ぶ店主の口の中へと飛び込んでいく。 咄嗟に承太郎は長い戦いの経験で得た勘で危険を察知し、巨体で小柄な2人を背中で庇う。 「うわあああああっ!」 再び、店主の身体が今度は咥内を中心に爆発した。 間違いない、この『何か』が元凶だ。 そして、その正体は──… 「犯人のスタンドか…!?」 承太郎と九龍はガラス窓の向こう、外の様子を見る。 こんな口封じと取れるタイミングでスタンドが動くのなら、今この瞬間まで本体は何処かから店主を見張っていたはずだ。 だが、スタンド使いらしき人物は何処にもいない。 「じょ、承太郎さんッ!九龍君!」 承太郎のコートの裾を引き、康一は店主の家に直接繋がる店内の方のドアを指差す。 するとその先では、何とドアの隙間から男の腕が伸び、ハンガーに掛けられた上着を今にも奪おうとしているではないか。 隙間から片腕だけを使ってハンガーラックに掛かった上着を取るのは難しいのか、男はハンガーに掛かった上着を焦れったくガチャガチャと引くだけだ。 何故、そんな手間の掛かる事をしているのかと言えば、答えは簡単だ。 迂闊に身を乗り出せば、承太郎達3人に顔が知られてしまう。 彼らの目の前で店主を殺すリスクを冒す程、男はジャケットの持ち主の『名前』を知られる事を恐れているのだから。 それも直接手を下さずスタンドを使って、だ。 当然、自身の面が割れるのも避けたい筈だ。 こんな危ない橋を渡り、スタンドの力を悪用する男の正体は、間違いなく──… 「やれやれ、『犯人』が直接服を取りに来るとは…」 >>主人公の心の傷を抉るお話の始まり。 |