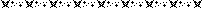

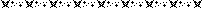
42 エステシンデレラのエステティシャン、辻彩はスタンド使いである。 「吉良吉影は僕の名前も知っていた…由花子さんの名前も、辻彩さんの事も知っていた。でも何故、彩さんの所に?」 一行の中で唯一、彩と面識がある康一は首を傾げる。 しかし今は、理由などよりも、殺人鬼のスタンド使いがこの建物に入ったという事実だけが重要なのだ。 彼女の身が危険だ。 「彩さんッ!いるんですかッ!?」 恐ろしく、静か過ぎる店内──… 「あっ、この変なネクタイ!それに、こっちの血がついたジャケットも!見た事ある!」 エステらしく清潔感のあるリノリウムの床には、吉良吉影が先程まで身に着けていた物が不似合いにも散乱していた。 そして、店の奥では──… 「彩さん!」 裸の男と白衣を着た女性が血を流して倒れていた。 男の方は背丈が似ていた為、最初は吉良吉影と身間違えたが、彼には吉良吉影には無い『左手』が存在している。 無関係の男…だが、男の顔を見て一行は戦慄する。 「コイツ、顔がねーぞッ!」 「手の指紋もだ!」 よく見れば、散乱している男物の荷物は全て吉良吉影の物だけだ。 身に着けていたはずの衣服も、男の物は何も残されていない。 吉良吉影の物は身分を示す免許証まであるというのに… 「この人、誰なの…?」 「うっ…」 ──沈黙を破る呻き声。 「男…が……」 承太郎達がその声に視線を向けると、相手は一行の中に顔見知りである康一の姿を見つけ、苦しそうに話し始める。 「背丈、格好が同じ男…を連れて来た…アタシの前で、殺して見せた…『シンデレラ』で、その男の顔や指紋を変換させられた…」 「顔を変換!?別人になったって事か!?」 此処で死んでいる男の物が無い理由、吉良の物が残されている理由。 承太郎達に顔も名前も知られてしまった今… 吉良は追跡を逃れる為に、見ず知らずの男を殺して、その男に成り代わるつもりなのだ。 その後、口封じに彩は吉良のスタンド能力で爆破させられた。 爆破に気を取られている間に、唯一の手掛かりだった左手は吉良に戻り、見失ってしまった。 †††††††† 「──で、他にスタンドに異常は?」 吉良の行方ともう1つ、九龍には解決しなければならない問題が残されていた。 「無い、と思う。多分」 承太郎の質問に答えながら、九龍は徐ろに無垢なる皇子の頭を揺らす。 …九龍自身の頭がグラグラするだけだった。 「今はさ、普通に今まで通り使えるもん」 そう言って、九龍は机からシャープペンを落とし、スタンド能力を使う。 スロー再生の様に緩やかに落ちていくシャープペンを承太郎が受け止める。 「その様だな」 「でしょ?」 重傷を負った承太郎の時間の流れを操作した時、確かに承太郎の時が巻き戻ったのだ。 だが、今は巻き戻る事なく、これまでと同じだ。 「…九龍。さっきはスタンド能力をどう使おうとした?」 「え?」 承太郎は宙でシャープペンを掴んだまま、九龍に問う。 「『時が戻る』事を想像して、もう一度やってみろ」 シャープペンが承太郎の手を離れる瞬間、九龍は指示通りに時を戻す事を願いながら無垢なる皇子のスタンド能力を発動させた。 「!」 「…やはりな。確かにスタンドは成長している」 シャープペンが重力に逆らい、机の上に戻っていく… 九龍がスタンド能力を止めると、シャープペンはカーペットが敷かれた床の上へと落ちた。 「後は、お前が成長した能力に慣れて制御出来る様になるだけだ。…俺としては、必要以上にスタンドを使ってほしくないんだがな」 †††††††† 翌日、承太郎達はある場所を訪れていた。 古いが立派な日本家屋… 表の表札には『吉良』と書かれている。 そう、此処は吉良吉影の自宅だ。 …正確には、元・自宅と呼ぶべきかも知れない。 無人となった家の中で、承太郎達は顔を別人に変えた吉良吉影に繋がる手掛かりを探していた。 承太郎、仗助、九龍が調べる吉良吉影の自室は子供の頃や学生時代に取った様々な3位のトロフィーや賞状が飾ってあり、手の届きやすい机の上には健康に関する本が置いてある、殺人鬼とは思えない普通の部屋だった。 承太郎は、親が作ったと思われる吉良の成長アルバムを開く。 「奴のアルバムっスか?これが子供の時?面影ある風っスねー。思い出も過去も捨て去って『別の人生』を歩むって訳か…」 確かに、大変な話だ。 家も地位も人間関係も、何もかも捨てるのだ。 成り代わった相手にも同じく、その人物が歩んできた長い人生と築いてきたモノがある。 「『吉良吉影』1966年1月30日、杜王町生まれ。集めた奴の人物像は身長175cm、体重65kg、血液型A型。両親が歳を取ってからの子供で、父親は奴が21歳の時に病死…死因は癌。母親もその後老け込んで死んだそうだ。特に両親の死に不審な点は無い。近所の人の証言によると、とても仲の良い家族だったそうだ」 「仲の良い家族、スか…」 「………」 家族に曰くのある少年2人は承太郎が語る吉良の家族の話に何とも言えない感情を抱く。 2人に構う事なく、承太郎は吉良の略歴を説明する。 「…前科や手術経験は無い。結婚歴も無し。『左手』は奴に戻ったが、指紋や歯型、手術跡から奴を見つけるのは不可能だ」 吉良は殺人において、徹底的に証拠を消す男だった。 自分の身体の記録を残し、そこから足がつく可能性も警戒しながら生きていたのかも知れない。 現に、今こうして吉良の情報を集める存在がいるのだから。 「特徴の無い特徴っスね〜、何か奴を見分ける目印みてーなモノは無いんスか?」 「この男は『目立たない様に』人生を送って来ている。見ろ、このトロフィーや賞状。全て『3位』、決して学校のヒーローにはなっていない。しかも、何か特技なのかよく分からん。スポーツ?音楽?作文?」 部屋に入った時から承太郎がトロフィーや賞状を眺めていたのは気付いていたが、そんな事まで見ていたのか。 九龍は呆気に取られる。 「そこまで見てる承太郎も凄いけど、そんなに色々なモノで賞が取れるって逆に凄いよね…」 ぽつりと漏らした九龍の感想に、承太郎は「そういう事だ」と頷く。 「大学も2流、会社でも目立たない…だが、落ちこぼれでも無い。コイツは自分の長所や短所を人前に出さない男なんだ。勿論、ワザとだ。高い知能と能力を隠す、それが最もトラブルに出くわさない事だと知っている」 ──パシャッ… 部屋を物色している最中に聴こえた音に、3人は机の方を振り返る。 音の正体はすぐに判明した。 机の上にあったポラロイドカメラが勝手に動き、写真が出てきたのだ。 「コイツはよぉ──っ、今のはよ──っ、この家の中に…他に誰か居るって事っスか〜?」 「らしいな。だが仗助、油断するな」 九龍を抱き寄せ、承太郎が忠告する。 「吉良に『仲間』がいるって事っスか?」 「いや…それは絶対に無い」 「何で?」 きっぱり断言する承太郎の顔を九龍は見上げる。 「吉良は1匹狼だ。犯罪は人間関係から足がつく。仲間がチクるってヤツだ。奴の最も信用しない事だ。しかし、家の中に何者かが潜んでいる。億泰達にも知らせろ」 出てきた写真が徐々に鮮明になっていく。 ポラロイドカメラで撮った写真は画が出てくるまで意外と時間が掛かるのだ。 仗助が写真を手に取り、パタパタ振る。 「仗助、実はそれ逆効果なんだって。現像ムラ出来ちゃうよ」 「げ、マジかよ!」 九龍からの指摘に、仗助は慌てて写真を見た。 だが、そこに写るとんでもないモノを見つけ、顔色が変わる。 「これは…承太郎さん、今のインスタントカメラを見て下さい。オ、オレ達の背後に…背後に…」 プリントされた写真に写るモノ、先程の承太郎達とその背後… 部屋の片隅に1人の老人が座り込んで承太郎達を恨めしげに見つめている。 知らない老人では無い、この家にあったアルバムの写真で見たばかりだからだ。 「吉良の、父親がッ…写ってる!!」 >>延長戦。 ポラロイドカメラの写真をパタパタ振るの、昔ずっとやってたんですけどね… これ書く為に調べて真実を知った時の衝撃ッ! |