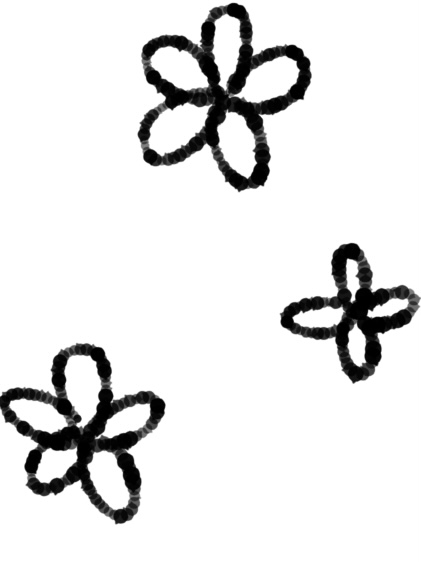 Day3
Day3
なんでこうなった…!
何度目かわからない悲鳴を、わたしは心の中でそっと上げた。
うちとほぼ同じ間取りにも関わらず、住む人が違えばこんなにも雰囲気が変わるのかと思わず見回してしまったお隣さんのうち。お腹の虫が大きな音で鳴いたわたしは、彼の提案にのって晩ご飯をご馳走になることになっていた。
だから先の答えは、わたしの食い意地のせいが正しい。
でも店からいい魚介もらってきたから一緒にパスタでも、なんて言われて断る理由があるだろうか。いや、わたしにはない。
「サンジさんって、飲食業なんですか?」
「ん?ああ、言ってなかったっけ」
わざわざ出してくれた紅茶に口をつけてそう聞くと、冷蔵庫を開けていた彼はさらりととんでもないことを口にした。
「バラティエって知ってるかい?」
「ばら…って、あの海上レストランの…?」
「そ。そこの副料理長」
「ふ…っっっ!!?」
バラティエと言えば、料理のおいしさとともに戦うコックさんが有名な、知らない人はいないおかしらつきの海上レストランだ。
そこの副料理長だなんて、有名人も真っ青じゃないか。
「さ、どうぞ」
わたしが1人で慌てている間に、目の前においしそうなペスカトーレが置かれた。サラダとスープもついて、どこのレストランだ。いや、バラティエなんだけど。
「い、いただきます」
その出来栄えに気圧されながら手を合わせるのを、自分の前にも同じものを並べた彼が眺めている。
お世辞にも上手いとは言えない手つきでパスタをフォークに巻きつけ、エビをぶさりと突き刺す。それを口へ運ぶと、魚介の旨味を閉じ込めたトマトソースが口いっぱいに広がった。
「お、いし…!」
「ふ、そりゃよかった」
確実に今までの人生で1番おいしいその味に目を丸くしたわたしに、彼は嬉しそうに笑った。
あっと言う間に空っぽになったお皿を眺めながら、バラティエ副料理長の手料理ってことは、お店で食べるのと変わらないわけで、ただごちそうさまでしたで終わらせていいものだろうかと考える。
「くく…」
「え、な、なんですか?」
「いや、すっげェうまそうに食ってくれるから嬉しくて」
そう言われてしまえば、お代はなんて無粋なことが言える雰囲気ではない。
今度絶対なにかでお返ししよう。
「デザートもあるけど食うかい?」
「いただきます!」
少々食い気味で答えたわたしに、彼は満足そうに頷いた。
more & more