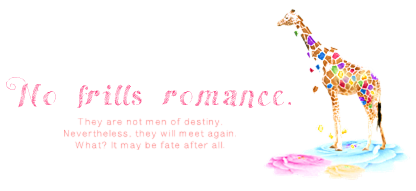
03
実は最近、陶芸教室に通い始めた。もともと趣味でちょくちょく通っていてて、仕事がしんどくなって転職したと同時にやめてしまっていたのを再開したのだ。今の仕事も相変わらず忙しいし土日は1日中眠っていたい気持ちはあるけど、なんとなく、本当になんとなく思い立って再開した。
陶芸は楽しい。ろくろが回るのをじーっと眺めながら集中するのも、粘土のなまぬるさと独特の柔らかい感触も好きだ。昔、家族におそろいで作った湯呑みをプレゼントしたこともある。お母さんと弟が使ってるのは見たことがないけど、お父さんはよく使ってくれている。あ、そういえばサイタマにもプレゼントしたことあったな。なんだっけ?湯呑みだっけ?お皿だっけ?まあいっか。遠い日のことは置いといて、目の前のろくろと粘土に集中した。
今日は、この前作ったわたしと彼氏用のおそろいの湯呑みができあがる日だ。
「なまえさん、とっても綺麗に焼けましたよ」
「わあ〜!ホントだ、今までで1番うまくできたかもしれません!」
「喜んでもらえるといいですね」
「あはは、どうかなあ…」
「ふふ、よかった」
「え?なにがですか?」
「最後にいらっしゃったとき、なまえさん元気なかったから心配してたんです」
「えっ…そ、そうでしたっけ…?」
「今日は少し元気そうで安心しました」
少し、という言い方が気になったけれど、あまり心当たりがないので気にするのはよした。手渡された湯呑みを持って彼のことを思い浮かべる。正直、こんなものには絶対に興味を持たないと思う。いや、持たない。絶対に。そういう人だ。でもこれは自己満足というか、たまには彼氏彼女っぽいことしたいなとか、それくらい適当な気持ちで作っただけのことなのでとくに問題はない。割れないように丁寧に包んでもらった湯呑みを持って、陶芸教室をあとにした。
★
『ああ、ごめんねなまえ。やっぱり今日、会いたいなって思ってさ』
「え?うん大丈夫だよ。どうしたの急に」
『可愛い彼女に会いたくなっただけだよ』
「えー、あはは、めずらしいね。今日はひとりで過ごしたいって言ってた日なのに」
『気が変わったんだ。ほら、この前デートできなかったし。車で行くから、いつもの公園で待っててくれる?』
「えっ、でもあそこはちょっと、」
『あの公園の前、車とめやすいんだ。じゃああとでね』
「あっ…」
優しい声色、優しい言葉遣い。別になにも引っかかることなんてないのに、彼と話すとわたしはいつもモヤモヤしている。
(怪人に襲われたところで、一人で待つのは怖いんだけどな…)
はあ、と短く溜息をつきながら、それでもおとなしく公園へ向かう。なんてしおらしくて聞き分けのいい女なんだろう。わたしは彼女の鏡だな。高身長・高学歴・高収入、なんだからやたら高い車を持ってるハイスペック。毎週ちゃんと会う時間を作ってくれるし、デートはいつも高そうなレストランに連れてってくれる。誕生日とか記念日も、まるでマニュアルのように色々なプレゼントを用意して祝ってくれるし、連絡もマメだし。彼の好きなところをたくさん頭の中に羅列して、一歩一歩歩く。モヤモヤを吐き出そうと、今度は思いっきり溜息をついた。
「…しまった。陶芸教室帰りだから、服適当なやつだったんだ」
彼はひらひらのスカートにさらさらのブラウスみたいな服装が好きだ。今日の格好は完全に失敗している。ちょっと急いで帰って着替えてこようかな?そしたら化粧とか、髪とか、やり直さなくちゃ。でも時間に間に合わなかったら色々言われそうだし、でも、と、ゴチャゴチャ考え始めたところで急に思考がとまった。
(めんどくさ………)
せっかくこれから彼氏に会うというのに、みるみる下がっていく気持ちに自分でも追いつけない。気が変わってやっぱり会わないとか言ってくれないかなあ。一縷ののぞみをかけてみたが、携帯が鳴ることはなかった。
約束の公園の入口まできて、わたしは足をとめる。また怪人が現れたらどうしよう。そう思ってしまったら、なんとなく中に入るのはためらわれた。公園の前に車とめるって言ってたから、ここらへんで待ってよう。でもここらへん、治安が悪いってニュースでも言ってたな。ちょっと周りを確認しようと、公園の奥に目を凝らした。
「あれ?なまえか?」
「ゲッ、出た…」
公園をウロウロするサイタマと目が合ってしまった。
「よう。なにしてんだこんなとこで」
「なにって…サイタマこそなんでまたここにいるの?」
「パトロールに決まってんだろ。この公園、怪人がよく通るってニュースで言ってたってジェノスが言ってたし」
「ええ〜、サイタマがニュース見てたんじゃないんかい」
「見てたよ。聞いてなかっただけだ」
「ドヤ顔で言うな」
「ていうかホントになにしてんだこんなとこで。お前めちゃくちゃ怖がってたじゃねーか、怪人」
「こっ怖がってません!」
「いや泣いてたじゃん。普通わざわざ遊びに来るか?忘れもんか?」
「ちがうわ!サイタマ、ホントそういうとこ!だからモテないんだよ!」
「なっ…!」
モテないという指摘がよっぽど傷ついたのか、サイタマはそれからしばらく打ちひしがれていた。昔と比べて色々な意味で落ち着いた雰囲気はあるものの、サイタマ自身の中身はそれほど大きく変わってはないように感じる。「俺はヒーローなんだぞ…モテないとかじゃなくてだな…」と言い訳をする姿が面白かったので、わたしはちょっと笑った。さっきまでのモヤモヤが少しなくなったような気がして、そういえば彼はまだなのだろうかと後ろを振り返った。
「なまえ」
「ギャーッ!!!」
するとなんと真後ろに、彼が立っていた。サイタマも彼に気づいたのか、それとももともと気づいていたのか、「あ、この前の彼氏だったのか」とのんきに思い出している。おかしいな、エンジンの音しなかったのに。いきなりのことに悲鳴というか雄たけびをあげてしまった恥ずかしさをなんとか誤魔化しながら、彼に向きなおった。
「き、来てたんだね。気づかなかった…あはは…」
「うん。さっきついてね。また怪人が現れたら危険だと思って、しばらく車の中で様子を見てたんだ」
「(だからなんで1人だけ安全な場所に…)」
「その人、この前のヒーローの人だよね」
「うん」
少し様子がおかしいと思ったのに、気にしないようにつとめてしまった。彼は相変わらず優しい声色で、優しい言葉遣いで話しているが、目が笑っていない。サイタマを指さしながらわたしに確認をとる顔は、むしろ怖いくらいだった。あ、嫌な予感がする。そう思った時だ。
パァンッ!
なかなか鋭い音がして、その瞬間目の前がチカチカして、気づいたら砂ぼこりのなかでサイタマに庇われるようにして抱きしめられていた。
「え……え!?ええっ!?どういう状況!?」
「オイオイオイオイ、マジかお前」
砂ぼこりが晴れてきたのでもう一度状況を確認する。まず、サイタマに抱きしめられていたというのは少々語弊がある。さっき、様子のおかしかった彼はなんと急に大きく手を振りかぶったのだ。つまりわたしを引っぱたこうとした。しかしそれから守るかのように、サイタマは片腕で彼からの攻撃をガードし、もう片腕でわたしの肩を軽くつかみ自分の方へしっかり抱き寄せている。砂ぼこりは多分、ちょっと距離のあるところから一瞬でこっちに駆け付けた反動のせいではないかと、なまえは予測しました。(パニック)
「なにしてるんだ?」
「いやいやお前がなにしてんだよ。え?てか今、コイツ殴ろうとしてなかったか?」
「そういうことか…」
「どういうことだよ。この前も思ったけど、お前ホント会話できねえのな。なんかS級の奴ら思い出すわ」
サイタマは依然、わたしを抱き寄せたまま彼と会話をする。彼はかなりイラついているように見えたが、サイタマの方は冷静、というか、ドン引きしている様子だった。
「なまえ!浮気したんだろ!そのハゲと!」
「オイ!ハゲとか言うな!」
「ちょっと待ってよ!わたしそんなことしてないよ!」
「どうせなまえを送ってそのまま家に上がり込んだんだろ…ヒーローのくせに…!」
「んなことするワケねーだろ。だいたいお前が送れって言ったんだろーが。落ち着けよ」
どうどう、と興奮してまた殴りかかってきそうな彼と、なだめているのか煽っているのかわからないサイタマにハラハラしっぱなしだった。それになぜか浮気を疑われているのも心外だ。一体なにをどう見たらそうなるのだろう。確かに偶然会って話していたけど、なにも2人寄り添ってとかコソコソ隠れていたわけじゃない。なんなら公園の内側と外側で、散歩中のご近所さんに挨拶していたぐらいの距離感とテンションだ。それは傍目からも明白なはずなのに、彼には伝わらないらしい。
「あのね、この人とはホントに今そこで偶然会っただけなの!」
「偶然会っただけの奴に抱きしめられて楽しそうだな!」
「そ、それはそっちが殴ってこようとしたから…」
「この前だってなんで家に帰ったんだ!」
「だって…そっちが帰ろうって言ったから…」
「俺のことが好きならイヤだって言えよ!今日だって普通お前から俺に会いにくるとこだろうが!」
「なっ…」
「俺がするならともかく、なんでお前がしてんだよ…!バカにしやがって…バカにしやがって!!」
初めて見る剣幕と怒涛のような言葉に、すっかり言葉を失ってしまった。怒りに震えた彼の目は怖い。何よりも、彼が何に怒っているのかが分からなくて怖かった。さっきからずっと何を言ってるんだろうと妙に冷静なわたしと、現状を理解しきれていなくて思考停止しているわたしがいる。サイタマが抱き寄せていてくれなかったらもう向き合ってもいられなかっただろう。
「お前みたいなバカ女が俺と付き合いたいなら、もっと好かれるように努力しぐふぅっ!?!」
「いい大人が公園でギャーギャー騒ぐんじゃねーよ」
「サイタマ…!」
さっき彼の攻撃を受けていた片腕でサイタマは彼の顔を掴み、ぎりぎりと音がしそうなくらいの強さで、しかしそのまま悠々と宙に持ち上げるようにしていた。ピリッ、とまた緊張した空気がわたしの肌をさす。サイタマの顔を覗き込もうとしたけれど、いつのまにか、今度こそ強く抱きしめられてしまい動くことは叶わなかった。
「ぐっ…ひ、ヒーローが…一般人を攻撃するなんて…!」
「るっせーバーカ!俺は正義の味方なんだよ!」
「いっ、やめ…っ」
「急に人殴ろうとしたり、怒鳴りつけて泣かせてるような危ない奴、ぶっ飛ばすに決まってんだろ」
ぐきっと変な音がして、どしゃりと人が地面に倒れこむ音を最後に、怒鳴り声はおさまった。静かな声が、うるさくてしょうがなかった男を黙らせた。サイタマはまるでなにごともなかったかのようにわたしを開放して「大丈夫か?」と、ヒーローのように声をかけてくる。まだすべて状況を整理しきれていないせいで、またうまく言葉が出てこない。最近、こんなんばっかりだ。
「なまえ」
「…さい、たま、」
「なんか…災難だったな。ドンマイ…」
「うっ、うるさいなあ!そうじゃないでしょ!だからモテないんだよ!」
「だから別にモテなくていーっつーの俺は!」
変に茶化されて緊張が解けたのか、思ったよりもすんなり言葉が出た。それからゆっくり深呼吸をして、地面でのびている彼を見る。さっきのことがフラッシュバックするとやっぱりショックだったけれど、ずっとモヤモヤしていたものがすべて体から抜けていくような感覚があった。もしかしたらどこかで、こうなることを予想していたのかもしれない。まさかサイタマにコテンパンにされるとは思っていなかったけど。
心の中で彼にさよならと告げて、サイタマの方に向き直る。もう2度も助けてもらってしまった。今回は前回ほど動揺していないので、しっかりお礼が言えるはずだ。
「あれ?」
「サイタマ、」と呼ぼうとしたところで、先に言葉を遮られた。
「その持ってるやつ、もしかして陶芸の袋か?」
「え…?そうだけど、なんで…」
「だってお前好きだったじゃん。俺にもくれただろ、変な皿」
「…!」
「まだやってたんだな。ホント好きだなー、それ」
そうだ。お皿だ。初めて人に渡そうと思って頑張って作ったのに、全然うまくいかなかったお皿。ちょっとでも誤魔化そうとして無理やり模様を入れたら、人の顔みたいなヘンテコなできあがりになってしまったやつ。
「…なにそれ。覚えてない」
「マジかよ。なんかアレ人の顔みたいで捨てづらくてとってあんだぞ」
「知らなーい。わたしそんなへたっぴじゃないもん」
「オイオイとぼけんなよ。わかった、今度見せてやる」
「わかった。じゃあ、写メでも撮って送って」
「おう。…………ん?どうやって?」
わたしは自分の携帯を取り出して、久しぶりににっかりと笑った。