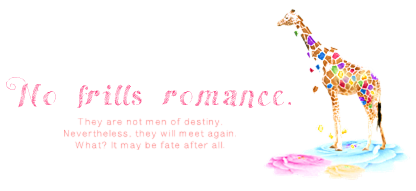
04
サイタマ先生は最近、機嫌がいい。
「先生、携帯が鳴ってます」
「おう」
とくに携帯が鳴ると機嫌がよくなる。表情筋、声音、体温、どれもさして変化はなく数値も正常なので一見すると「機嫌がいい」とは分からない。しかし俺には敵の身体情報がわかる機能があるので見えている。携帯が鳴るとほんの一瞬、先生の心拍数が上がるのだ。そしてそのあと、ひどく穏やかになる。しかしこの一連の流れは本当に一瞬で、微々たるもので、俺のように常に先生の動向を観察していなければ気づくことなどできないささいな機微だ。
テーブルに頬杖をつきながら携帯をいじる先生を見て俺は感嘆していた。さすが先生だ。決して動揺を悟らせず、常に冷静。それは敵の前ではプレッシャーになる。日頃からどんなにささいなことにも微動だにしないよう訓練なさっているのだろう。いや、それもまた歴戦の戦いで身に刻まみこまれたからこそ成せているのかもしれない。俺も早くそんな強者になりたい。先生、あなたという人は…!
「…ジェノス、鍋、鍋」
「はっ!」
先生の強さを目の当たりすると誰でも釘付けになってしまう。それは日頃行動を共にしているはずの俺でさえいまだに例外ではない。いつのまにか料理をしている腕がとまっていたようで、味噌汁がすっかり沸騰してしまっていた。しくじった。沸騰させると味噌の旨味が飛んでしまう。こんな栄養価の低いものを先生に差し上げて筋肉繊維に影響が出たら一大事だ。これは俺が飲むことにしよう。先生用の新しい味噌汁を作り始めようとした時、先生に呼ばれた。すぐさま料理を中断し、エプロンで洗った手を拭きながら先生の隣に膝をつく。
「なあジェノス、この湯呑みどう思う?」
「はい?」
先生が携帯の画面を見せてきた。そこには1枚の写真があり、うつっていたのは不恰好な形に、変な…人の顔に見えなくもないような…とにかく不気味な模様の入った2つの湯呑みだった。なんだこれは…呪物か…?
「なんですかこの……ダサ………独特な湯呑みは。先生、これがほしいんですか?」
「(今一瞬ダサいって言おうとしたな)いや、俺の……知り合い?が趣味で作った湯呑みらしいんだけど、なんか2つ作ったから俺とジェノスにどうだって」
「こんなセンスのセの字も感じない湯呑みを先生に!?許されない!侮辱している!俺はいりません!」
「お、おう……そっか……お前焼き物に厳しかったんだな……」
「だいたいなんなんだこの人の顔を模した模様は…。先生、もしや呪いの類では…?危険です。嫌な予感がします」
「いや、うん、そんな言ってやんなよ…。じゃあまあ俺の分だけもらうって言っとくわ」
「俺もほしいです」
「……え?いや、今いらないって言っ、」
「いえ、ほしいです」
「すげえボロクソに、」
「生涯大切にします」
先生が必要とするものならそれはきっと強さに繋がっている。間違いない。言われてみれば呪いのような模様も前衛的なアートに見えなくもない。これを棚に飾ればきっとアーティスティックな部屋を演出でき、先生もモテ始めるはずだ。そんなわけでメールに返信しはじめた先生を尻目に俺はキッチンに戻った。料理をしたらあの呪いの湯呑みを飾る棚をDIYでもするか。今日は任務もなさそうだからな。再び料理にとりかかろうとした時、またも先生に呼ばれた。
「ジェノス悪い、俺ちょっと迎え行ってくる」
「……迎え?」
「さっきの湯呑み作った奴がさ、今から持ってくって言うから」
「……」
「どうした?」
「先生を出向かせるだと?!一体何様のつもりだ!!!」(バキィッ)
「ジェノス?ジェノス?オタマ壊れたぞ?ジェノス?」
「偉そうな奴め…俺が行きます!先生は味噌汁が沸騰しないよう見ててください!」
「いやいいって俺が行くから。だいたい顔知らねーだろ」
「ダメです!先生はお前を迎えに行くほど暇じゃないんだと教えてやります!」
「だーっ、マジでいいから!別に頼まれたんじゃねえし、俺が勝手に行くだけだから!」
「な……っ!?」
先生が自ら……!?一体…一体何者なんだ!?さっきの湯呑みのことといい、迎えに行くことといい、そもそも携帯が鳴ると嬉しそうなことといい、先生がこんなに好意的にしている人間なんてまったく心当たりがない。納得のいかない怒りで、思わず持っていたオタマをギリ、と強く握ってしまった。勢いあまって壊してしまったが今そんなことはどうでもいい。
玄関でいそいそと靴を履く先生を、キッチンから顔を覗かせて眺める。そこでハッとした。まさか、先生の…先生か…!?そうだ。先生は強さの秘密を頑なに秘密にしているが、人が成長するにはすべからく師匠やその後押しとなった存在がいるはず。なるほど、そういうことだったのか。だからこんな丁重とも思える扱いを…。
それなら携帯が鳴るたびに嬉しそうだった様子も納得がいく。最近、自ら率先して部屋の掃除をするようになったのも、いつか先生の先生をここにお招きするためだったからに違いない。それならば俺も料理の腕を奮うしかない。俺の先生は先生だけだが先生の先生ならば先生のメンツのためにも先生の先生にはそれなりのリスペクトが必要だ。少しくらいもてなしてやろう。
「パスタでも作るか。………!! この皿は―――」
・
・
・
・
「もー、迎えとか別にいいって言ったのに」
「まあ気にすんなって。ちょうどジャンプ買いにコンビニ言ってたからな」
「ジャンプのついでですか」
「……今週のジャンプ、ワンピ休載かー」
「なんで無視するの。あ、この部屋?サイタマんち。なんか人気ないね」
「ああ、なんかな。ジェノスー、戻ったぞー」
「お帰りなさい先生!そして先生の先生!」
「えっ」
「ん?」
帰ってきた先生が連れてきたのはただの女だった。いや、先生の先生の性別はなんだっていいのだが、俺は2つの熱反応を確認してから瞬時に身体能力の数値を分析した。違和感を抱いたのは、先生の先生と思われる個体の筋肉量が戦う人間のそれではなかったことだ。しかし先生の先生ならば侮ることはできない。タツマキのように秘められた異能力を持っているかもしれない。いや待てよ、異能力だとすると…。
「チッ…。やはり呪物だな…?」
「え?呪物?なにが?」
「あの呪いの湯呑みを作ったのはお前だろうと言っている」
「呪いの…湯呑み…?」
「わーっ!やめろジェノス!なまえ、なんでもねえから!」
「呪詛師というやつか?最近ジャンプで流行りの…」
「わ、わかんないけど流行ってるのは呪術師のほうだと思うよ…」
「やめろ!微妙にジャンプ談義を始めんな!」
菜箸でビッ、と女の方を差し示しながら悪行を暴くが、さすが先生の先生と言ったところか。まるで動揺しない。それどころかまったく心当たりがないかのような顔をしている。しかし女は身の危険を感じたのか、あろうことかやんわりサイタマ先生の後ろにそっと隠れた。先生の肩からひょっこり顔をのぞかせて不安そうにこちらを見ている。
まさかこの女、先生を盾にすれば俺が攻撃できないと見抜いたのか?いや、たとえ攻撃をしたところで先生には届かないことは分かっている。まさかこの女(2回目)、それさえも見抜いて先生の後ろに!?やはり只者ではないかもしれない…。
「ちょちょちょ、ジェノス落ち着け。とりあえず部屋入るから、」
「いいえ先生。その女は気づいています。俺の戦闘力がまだ先生に遠く及ばないことに……」
「いやいや今そういうのいいから。とにかく紹介するから部屋に入れてくれ」
「……先生がそうおっしゃるなら…」
「ね、ねえねえサイタマ。大丈夫かな…?やっぱりわたし帰ろうか…?」
「ん?大丈夫だろ。ジェノスたまにこうなるんだわ」
女は先生の服の裾をくいくいっと掴みながらコソコソ言っているがすべて丸聞こえだ。しかし帰るというのは賢明な判断だ。部屋そのものに呪いをつけられたらたまったものではない。しかし先生の「あ、ジェノス麦茶くれ」という言葉もあり、仕方なく部屋へ招き入れることにした。先生に言われては成す術がない。俺が気合を入れて用意したランチが並んだテーブルの前に3人で座る。
「お、今日はやけに美味そうな昼飯だな」
「すごい…カフェみたい…」
「先生」
「ああそれでな、コイツはなまえ。なまえ、コイツはジェノス」
「先生の弟子をやっているS級ヒーロー、ジェノスだ。ヒーロー名は鬼サイボーグ」
「えっと、なまえです、OLです。ていうか弟子?サイタマ、弟子とるほど強かったの?」
「いや弟子ってのは成り行きというかなんというか」
「成り行き?まさか…!適当に言いくるめてこんな家事とかさせて…!?」
「は?ち、ちげーってこれはジェノスが勝手に…」
「えっ勝手に!?ジェノスくんのお父さんとお母さんは知ってるの!?」
「いやだからこれにはワケがあったりなかったり…」
「もー!だめだよこういうのはちゃんとしなきゃ!サイタマのほうが大人なんだから!」
「あー…実はジェノスはかくかくしかじかで…」
俺をそっちのけでなにやら言い合いを始める先生と女。いやしかし女のほうが先生に強めにしかけている。おかしい。たとえ女に異能力があったとしても先生の力があれば物理的に黙らせることなどたやすいはずだ。しかし先生は女にやいのやいのと言われるたびにむしろ少し嬉しそうだ。身体データの数値に変化はなく何も読み取れない。それなのに、なぜかそんな風に見えた。
「そうだ。湯呑み。アレで茶でも飲もうぜ」
「あ、ごまかした!」
「ああ、あとあの皿も」
「え!あのお皿はいいよ!へたくそで恥ずかしいから…」
「今さら恥ずかしがるなよ。この湯呑みもなかなかだぞ」
「うっ、うるさいなあ!」
ぽか、としょうもない音を立てて女は先生の肩にパンチする。条件反射でエネルギー砲を発射しそうになったが、サイタマ先生は女の攻撃を意にも介していなかったのでやめておいた。というよりは、ここで俺がなにかを言うのはよくないのではないかと、なんとなくそう思ったのだ。さっきからなんの根拠もないその思考が我ながら理解し難かったが、理屈はなしに不思議と腑には落ちていた。
ああそうだ。思い出した。あの湯呑みと似た模様の、さっき見つけたあの皿。それは少し前まで、棚の奥の奥のほうにしまってあったものだ。新聞紙で何重にも包まれていて、割れないようにというよりはまるで封印するかのように保管されていた。ある日それを引っ張り出してきて、静かに眺めていた先生を見たのはそう遠くない最近のこと。
その時と同じような目をして先生は女を見ているんだ。携帯を見る時も、さっき家を出る時も、女にうるさく言われていた時も、肩にパンチをされた時も、今だってずっと、いつもと同じようで少し違う穏やかな目をしている。
「…先生、オタマを壊してしまったので買ってきます」
「え?いやいいよ。なまえ送る時についでに買ってくるから」
「いえ、いいんです。他にも新調したいものがあるので」
「そうか。んじゃまあ、よろしく」
「はい」
女は俺が買い物に行くことになぜかまた文句を言っていたが、とくに興味なかったので聞かなかった。行ってきますと控えめな挨拶を残し、先生の部屋をあとにする。閉まる扉の隙間から見えた2人は、まるでドラマで見かける幸せな恋人同士のようだった。