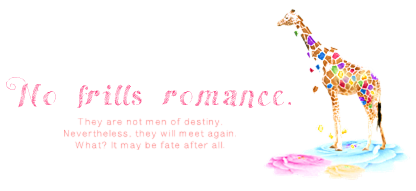
05
「なんか久しぶりに楽しかったなー」
「そっか」
サイタマの家でジェノスくんと一緒に過ごした。ゲームをしたり漫画を読んだり、最近のヒーロー事情を話したり。わたしには分かるようで分からないことばかりだったけれど、不思議と気持ちはずっと穏やかで、最近ではなかった確かな充足感があった。
夕方も迫ってきたのでそろそろ帰ろうとしたところ、サイタマが「送る」と言ってきた。その時のジェノスくんの表情は、無だった。無だったのだけれど、なにか複雑な想いを抱えているのであろうことはすぐに分かった。そもそも3人で過ごしているときのジェノスくんのサイタマへの陶酔っぷりはハンパじゃなかった。恐怖すら感じた。なんかごめんね、と思いつつ、サイタマの家をあとにする。
「サイタマもさ、よかったね」
「なにが?」
「ジェノスくんがいるなら毎日楽しいでしょ」
「いや…楽しいとかじゃねーよ…あれはもう…」
「寂しくないじゃん。家事も掃除もできるし、かっこいいし、サイタマに対してはすごくいい子だし。うらやましい」
「(かっこいい…)」
空はもう半分夕暮れになっていた。オレンジ色の夕日とかすかにまだ青い空が中途半端に混ざり合って、なんとも言えない色味になっている。並んで歩くわたしとサイタマの影はおんなじくらいの高さに伸びていて、少し懐かしくなった。
元々会話の多いわたし達ではなかった。それでも自然と頭に浮かんだことをぽろりとこぼせば、くだらない会話が適当に続くような、そんな2人だ。それは今も変わらない。変わったのはサイタマの頭がつんつるてんになったことくらいだ、と言ったらサイタマはきっと怒るので言わないけれど。てくてく歩く2人はお互いに前を見ている。
「あのさ、サイタマ」
「…お、おう」
「わたしずっと言いたいことがあったんだけど」
「…」
「サイタマ?」
「エッ。あ、な、なんだよ」
ぼーっとしているサイタマを不審に思いつつ、わたしは今日までずっと言いそびれていたことをやっと口にした。
「助けてくれてありがとう、サイタマ」
横にいる彼の顔を見ながら笑って伝えると、サイタマはいつもの間の抜けた顔をしたまましばらく沈黙する。え、いやいや、おい。おかしいだろ沈黙って。「サイタマ?」ともう1度呼びかけると、「あー…いや、あー…」と言葉を探しているようだった。それからまた「あー…」と唸って片手で額を抑えながら困っていた。
そのままなんとなく立ち止まって、この微妙な雰囲気を正そうとお互いに言葉を探し始める。最初にセリフを見つけたのはサイタマのほうだった。
「どういたしまして」
「…いえいえ」
「まあヒーローだからな、俺は。当然のことだけどな」
「あはは、そうだね。でもありがとう」
「まあ、当然なんだけどな、なまえ」
「うん?」
サイタマの瞳に、わたしが映っているのが見えた。
「ヒーローじゃなかったとしても、俺はなまえを助けたよ」
え、という短い言葉ですらすぐに返せなくて固まってしまった。タイミングよくふいた心地のいい風がわたしの髪をゆらす。サイタマは髪の代わりにシャツの裾がゆれていた。
まるで見つめるみたいに目をそらさないサイタマに、さっきの言葉がふざけているわけじゃないということが分かってしまった。わたしが元カノだからとか、サイタマが優しいからとか、そういうんじゃなくて、多分。そう気付いた瞬間、確かに心臓がどくんと鳴った。いやいや、待て待て。鳴ってどうする。どうするの。
「…じゃ、気を付けて帰れよ」
「エッ」
「また連絡すっから」
気付けばもう自宅の近くまで来ていた。サイタマはすぐに背を向けて、片手をひらひらさせながらとことこと立ち去っていく。うそ、やっぱりそういうこと?わたしがそう思ったのは、夕日のせいというにはあまりに不自然に染まった、サイタマの赤い耳を見てしまったからだった。
「ど、どうしよう…」
みるみる熱くなる自分のほっぺを両手で覆ってごまかしてみる。困ったふりをしてみたものの、心はウソがつけないようだ。だってその証拠に、まだ見えるサイタマの後姿に、駆け寄りたくってしょうがない。ねえ今、どんな顔してるの?
They are not men of destiny.
Nevertheless, they will meet again.
What?
It may be fate after all.
2人は運命の相手同士ではありません。
それなのに、2人は再び出会います。
あれ?
ということはやっぱり、運命かもしれません。