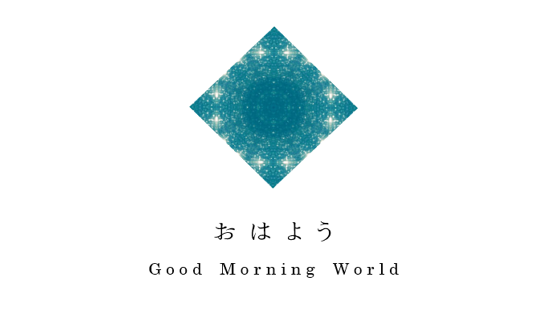
千空に嫌われたかもしれない、と思ったことが一度だけあった。何度目かのロケット打ち上げ実験の日、いつものようにみんなで山を登っていた。その日のわたしはどうしても体調が悪くて、でも実験を見ていたくて、大丈夫だと自分に言い聞かせてついていった。しかし自己暗示の甲斐なく、打ち上げポイントに辿り着く前に体調は悪化することになる。
途中、とうとう体力の限界が来てがくりとその場に座り込んで歩けなくなった。体がだるい。熱もあったらしい。杠と大樹の心配そうな顔と、千空の驚きと焦りの混ざったような顔を今でもよく覚えている。
「今日は帰るぞ」
数分も悩みもせずに千空が静かに言ったのを聞いて反対の声をあげたのはわたしだけだった。元々ロケットの実験をやりたいのは千空だったから杠と大樹は本人が言うなら、ということだったんだろう。なにをどう言っても決定は変わらず、その日は結局下山した。大樹におんぶをしてもらい、みんなに家まで送ってもらった。
わたしがいなければ、今日はロケットを打ち上げられたのに。「打ち上げ実験はいつでもできる」となんでもなさそうに笑った千空を見て、そうだよね、と納得できるほどその頃のわたしは無知ではなくなっていた。いろんな好条件が揃う日を、千空が毎日考えているのをちゃんと知っている。ロケットが飛び立つ日を楽しみに待つ横顔が好きだったのに、台無しにしたのだ。道中、座り込んで足を引っ張ったわたしを見た千空の顔に、失望が含まれていた、気がする。
家に帰ってだるい体に鞭を打って着替える。制服を乱雑にイスの背に引っ掛けて、適当にスウェットを着てベッドにもぐりこんだ。嫌われた、今度こそ絶対に嫌われた。大樹や杠みたいになにかできるわけでもないのに、なんの役にも立っていないのに、足だけ引っ張った。自分の無能っぷりに自己嫌悪で消えてしまいたくなった。布団をかぶって、あの時わたしを見た千空の顔を思い出すと、罪悪感に耐えられなくなって涙がぽろりと流れる。謝ってもきっと「気にすんな」としか言われない。ううん、もしかしたら「もうついてくんな」って言われるかもしれない。千空、千空。やだよ、お願い、嫌わないで。頭の中には、千空しかいない。ああきっとこんなんだからダメなんだ。わたしだけ、千空のこと以外、なんにも考えていないから。そう思ったら余計に涙がとまらなくなった。
それからしばらく泣いていると、布団の向こうから変な音がしていることに気づく。なんの音だろうと耳をすませると、携帯のバイブレーションが途切れることなく響いていた。布団から出て、お母さんかお父さんの「今から帰るね」コールかなと思って画面を見ると"石神千空"と表示されている。
「千空!?」
思わず声に出してびっくりする。千空から電話なんて珍しいにもほどがあった。十中八九今日のことについて悪い方向性のフィードバックをされるに違いないと思うけれど、それでも確信はできなくて、びくびくしながら電話に出る。手も声も震えて、わたしは自分が思っているよりもずっと情けない小さい声で「もしもし、」と言った。
『あ"ー、寝てたか?』
「う、ううん…起きてたよ」
『いやそこは寝とけよ。熱あったんだろうが』
「うん、そう、だよね…」
そこからしばらく沈黙が起きる。電話で起きる沈黙の気まずさといったらない。わたしは今日のことをどうやって謝ろうか、千空はやっぱり怒っているんだろうか、もしかして本当にもう実験に来るなと言われるのだろうか、と、いろんなことをぐるぐる考え出してどんどん言葉が出てこなくなる。そうしていたらおさまっていたはずの涙がまた流れそうになって、思わず鼻をすする。
『…悪ィ』
小さい声で、その言葉はよく聞こえなかった。
「なに?千空?」
『…俺と大樹はともかく、杠も気づいてなかったぞ』
「あ、今日のこと…」
『強がってぶっ倒れてんなら世話ねー。ちゃんと言いやがれ、そういうのは』
「うん、ごめん」
『なんでテメーが謝ってんだ』
「だって…」
『ったく、いつもアホほどどうでもいいことは話すくせによー。隣んちの犬の名前がメスなのに万次郎だったとか』
「違うよ、万太郎」
『どうっっでもいいわ!』
少しだけ緊張したものの、いつもと変わらない千空の顔が電話の向こうに浮かんだ。電話で聞く声はいつもより少し低くて穏やかだ。普段たくさんのことを説明するための早口も今はどこかゆっくりで、まるでひとつひとつ言葉を探しているように感じた。さっきまですっかり悲しみに包まれていたのに、千空の声を聞いただけでこんなにも簡単に気持ちが落ち着いてしまった。
それからまた少しだけ沈黙が流れる。わたしはまだほんの少し緊張している心臓を抑え込んで、千空、と呼んだ。
「今日、本当にごめんね」
『なにが』
「わたしのせいで、実験の邪魔しちゃった」
『…』
「ごめんね、千空」
返事はすぐは返ってこなかった。きっと、言葉を探しているんだろう。
千空は、もともとずっと優しい。わたしにだけじゃなくて、大樹にも杠にもちゃんと優しい。口が悪くて合理的で最初は怖気づいちゃうけど、この人はちゃんと大切なものの大切の仕方を知っている。だからわたしも千空の大切なものを大切にしたいと思った。科学とか、夢とか、そういうものを全部。千空のやりたいことの邪魔をしないというのは誓いにも似たわたしなりの愛の形だった。愛、なんて子供が言うとたちまちチープに感じてしまうけれど、それ以外にこの気持ちに近い表現がないのもまた事実だ。
今、わたしたちはどんな顔をしているんだろう。きっと千空はふいに見せるあのあたたかい目をしながら、優しくわたしを拒絶する言葉を探している。
『テメーどうせまたくだらねえこと考えてんだろ』
「別にわたしはなにも、」
『邪魔だなんて思ったことねえ』
しんとした空気のなかで、ただひとつだけ響くその声が、いつもわたしの心の深いところに刺さる。愛おしいその痛みはじんわりとした余韻を残してだんだんと消えていく。本当はずっと消えないでいてほしいけれど、消えるころにはまた新しい痛みを千空がくれることを、わたしは知っている。
千空はもともとずっと優しい。わたしが追いつけなくても、なんにもできなくてぐずぐずしていても、少し先でいつも待っていてくれる。時折立ち止まってこちらを振り向いてくれることこそが、きみの愛の形であればいい。
・
・
・
最初に視界に入ったのは、高い空と緑だった。緑より少し高いところに大きな鳥が飛んでいるのも見えたので、自分は今仰向けに寝転んでいるのだろうことがわかった。しばらくしてから、ざわざわと人の声が聞こえる。それでも状況がよく飲み込めない。動いていいのかだめなのかが分からなくて、わたしはただただ、もうずっと久しぶりに見たような気がする澄んだ遠い青に見惚れていた。
「よう。お目覚めか、なまえ」
すぐそばで声がした。そっちのほうを向くと光を背負った誰かがいる。晴れていく影を待たなくたってすぐに分かった。ぶっきらぼうな言葉にはとうてい似合わない、優しい目をした千空がいる。確かめるようにその頬に手を伸ばして触れると、そこに千空の手が重なった。
強く握りしめられた温度とやんわりと細められた少し泣きそうな目元を眺めていたら、わたしのほうが先に視界が霞んで、けれどすぐに鮮明になった。千空のもう片方の手が流れていく涙をまるでとりこぼさないようひとつひとつ拭ってくれる。
「おはよう、千空」
話したらきっと呆れられるくらい、ずっとずっと、きみのことばかり考えていたよ。
(宇宙の中心にいて)