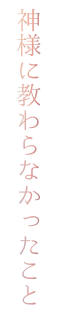
今日の任務は最悪だった。
たいしたことのないはずの低級呪霊たちが群れを作っていた。"奴ら"はなけなしの知能を使って数人の人質を餌に、より強い呪力を持つ呪術師を喰うためにわたし達を取り囲んだ。一体一体はひとりでも祓えるくらいだったのにその群れの数というのが想像を絶した。まともに相手をしていたらキリがなく、気を取られているあいだに人質の半分は呪霊に喰われたりぐちゃぐちゃにされたりして死んだ。たくさんの人間を助けることができなかった。今日のバディの猪野くんとやっとすべての呪霊を祓った頃にはもうふたりともボロボロで呪力もほとんど残っていない。補助監督の待つ帳の外までの道のりもやけに長く感じた。
呪霊に喰われかけてところどころ皮膚を持っていかれた手足が痛い、血も止まらない。ぎしぎしと身体が悲鳴をあげているのでおそらくどこかの骨が折れている。痛い、痛い。生き残った人質たちは周りの人間が無惨に死んだ光景を見て錯乱してしまい、落ち着くまでに何度か殴られたり引っ掻かれたりした。いたい、いたい。血を流しすぎたのかフラフラして、とにかく気持ちが悪い。
今日の任務は最悪だ。何よりも、助けられなかった人質たちの、わたしに縋る断末魔が耳から離れない。
帳の端で車の横に立つ人影が見えた。やっと帰ることができる。補助監督の彼がわたしに気づいた瞬間、がくっと体から力が抜ける。立てない。限界だったみたいだ。帰ることのできる安堵から気を抜いたせいで、おそらくもう二度と立てない気がする。いきなりしゃがみこんだわたしに驚いた猪野くんが慌てていた。
「みょうじさん大丈夫ッスか?」
「ごめんね、大丈夫だよ。今立つから、」
「無理しないでください、なまえさん」
猪野くんに言ったつもりが返ってきた声はさっきまで車のところにいたはずの伊地知だった。へたりこむわたしの視線に合わせてひざまずく伊地知は、いつもの気弱な顔ではなく少し怒ったような顔をしていたので、なぜかこちらが悪いことをしたような気持ちにさせられた。「大丈夫だから」と立ち上がろうとする前に、体がふわりと浮かぶ。急に視界が見慣れない高さになって、浮遊感に動揺する。すぐ上を見ると真顔の伊地知がいて、抱っこされているのだと分かった。「きゃっ!」とからかうような猪野くんのリアクションを尻目に、わたしはそのまま車まで運ばれる。意外と悪くない抱かれ心地に、やっぱり伊地知も男の人なんだなあとのんきに考えていた。
車の前まで来ると、ひとひとり抱えているというのに伊地知は慣れた手つきでドアを開いた。そのままそっと後部座席に座らされる。まるでたやすく割れてしまう風船みたいに優しく置かれるからなんだか恥ずかしくなった。
「そんな、お姫様みたいに置かなくていいよ」
「そうはいかないですよ。こんなに満身創痍の人」
「お姫様ってところはツッコんでほしかったな…」
「…私には似たようなものですが」
「えっ」
「わがままなところとか無茶振りしてくるところとかこうして世話が焼けるところとか」
珍しくキザなことを言うと思ったらそういうことだった。なんというやつ。なかなか失礼なことを言ってくるので逆にツッコんでやりたかったのだけど、身体中が痛くて気持ち悪くてそんな元気はさすがにない。伊地知も察しているのかそれ以上は何も言ってこなかった。
猪野くんの所在を聞くと、このあと別の任務があるらしくバディの七海さんを拾うために別の補助監督の車に乗ったらしい。家入さんに診てもらわなくていいのかなと少し心配になったけれど、七海さんもいるから大丈夫だろう。おそらくわたしのほうが重症なのだ。だってこんなにも伊地知が怒っているような顔をしている。
「車、すぐに出して大丈夫ですか?」
「…ごめん、ちょっと気持ち悪くて、少し待ってほしい」
「どこかほかに辛いところは?」
「ぜんぶ、いたい」
「背中、さすりましょうか?」
「うん…。でも肩のほうは食われたから、触らないでね」
こともなげに言った。もっと大袈裟に騒いでもいいくらい本当はひどい怪我であるのは知っていたけれど、もう慣れてしまった。そんなわたしのまるで自嘲するかのような言葉を聞いて、伊地知は悲しい顔をした。真顔になったり怒ったり悲しんだり、忙しいやつだなあと思う。お願いだからわたしのためにそんな顔をしないでよ。とは言うことはできず、食われたところを刺激しないようにゆっくりゆっくり背中をさする手に、静かに身を委ねていた。
座席のすぐ外側で、車のドアに隠れるようにして中途半端に屈んでいるスーツには、ところどころに血や泥みたいな汚れがついていた。どれもこれもわたしの汚れだ。それに気づいて少し胸が痛むけれど、謝ったりはしない。大丈夫だって言ったのに、戦い終わってぐちゃぐちゃの人間なんて抱き上げるからそういうことになるんだよ。これに懲りたらきっともう伊地知はわたしが大怪我をしても抱き上げたりしないだろう。気づいてもらえるように「スーツ、汚れちゃったね」と言ってみたけれど返事はなにも返ってこなかった。
伊地知も隣に座ればいいのにと思ったけれど、きっとこの人のことだからその時間すら惜しいんだろう。優しい手は、ぼろぼろのわたしの体をいっそう優しく撫でる。
「ありがとう、ちょっと落ち着いた」
「本当ですか?」
「ほんとにほんとう」
「…少し止血しましょうね」
「うん」
戦いの中であちこち破れたり穴が空いたりしてほとんど上着の役目を果たしていないアウターを脱ぐ。こうして任務で怪我をして服がボロボロになるので、アウターの下は基本的にタンクトップを着るようにしている。素肌に触る夜の空気は思っていたよりも冷たくて肩が震えた。車のドアを開けたまま血だらけの女に止血作業をするのは憚られたのか、伊地知はぱたんと静かにわたしの隣のドアを閉めてやっと反対側の席に乗り込んできた。ぎし、と狭い後部座席がかすかに揺れる。
お互いに正面で向き合う形になって、怪我が酷いほうの腕を差し出す。酷いほうと言っても、わたしの体はほとんど傷だらけだから酷さで言えばどこもおんなじだ。細かな傷は家入さんが治してくれるけど、たとえば思いっきり横っ腹を切られた傷とか、腕を刺されて穴のようになった傷とか、そういう大きいのは残っている。酷い体だと思った。この前五条さんに貸してもらった週刊誌に載っていた巨乳の女の子とは大違いだ。
伊地知は応急処置のための救急箱を取り出してわたしの処置を始める。まるで壊れ物でも触るような手つきはもたもたしていて、なかなか手当てが進まない。昔から、そう、一緒に教室で授業を受けていたときから伊地知はわたしの手当てだけがほんとうにへたくそだ。これ以上壊れないようにと、恐る恐る触れる手。こんなになっても結局生きているのだから、いまさら簡単に壊れたりなんかしないのに。むしろそんなに綺麗な手でわたしに触るほうが、いつか伊地知に傷をつけてしまいそうで怖い。そう言いたかったけれど、わたしの身体を滑る指先の体温を拒絶するようなことはどうしてもできなかった。
「また傷作っちゃった。ごめんね、この前約束したのに」
「…仕方ないですよ。任務なんだから」
「やっぱり悲惨かな。こんなに体に傷があるのって」
綺麗な手が羨ましい、と笑って見せた。皮肉めいた、けれどほんとうに思っている言葉に伊地知はどんな顔をするだろう。また悲しそうな顔をするのかな。気になってじっと見つめていると少ししてからゆっくりこちらのほうを向いた。その表情は優しくて、微笑んでいた。けれどあまり目を合わせてくれなかった。予想外の反応をするからわたしもどうしていいか分からなくなる。なんとなく気まずさを感じて黙っていたら、止血がすんだのかお手本のようにきちんと包帯が巻かれた腕を伊地知がさすってくれた。
このまま痛みも傷も汚れもぜんぶ吸い取って消してくれたらいいのに。伊地知ならきっとできてしまう気がする。弱くて優しい、いつでも綺麗なままの彼ならば。
「怪我をしないでほしいと言ったのは、私がただ、なまえさんに痛い思いをしてほしくないからですよ」
静かに言い残して伊地知はわたしの隣からいなくなる。すぐに運転席のドアが開いて、「行きましょうか」という声とともに車が走り出した。車内は驚くほど静かで、心臓の音でも聞こえそうなくらいだった。
窓の外を流れていく景色はひとつも頭に残らない。醜い呪霊と、死ぬ人間と、叫び声と、自分の血肉を奪われる感触が頭のなかでずっと繰り返されている。疲れて朦朧としているはずなのに目を閉じたらそのまま深い黒のなかに引きずり込まれそうで、恐ろしくて眠りにつくことはできなかった。ぼうっとするわたしを確認するように眺める伊地知とミラー越しに目が合う。ふっとむりやり笑ってみせて口を開いた。
「伊地知。なんか、話そうよ。五条さんの愚痴でもいいから」
「嫌ですよ…ぜんぶ五条さんに告げ口するじゃないですか」
「今度は言わない。ほんとだよ」
「なまえさんのほんとは信用できません。昔から」
「お願い。伊地知の声を聞くと、安心するの」
昔から、と同じようにつけくわえる。伊地知がわたしのお願いに弱いのは、昔からそうだった。呪いを祓ったあとは、どうしてか自分の心のようなものがどこかに置き去りにされそうになる。必死に引き戻そうとすればするほど時間がかかる。帳の向こう、朝を知っている伊地知に手を引いてもらわなければわたしはこっちに戻ってこれないのだ。
渋々という雰囲気を出しながら伊地知はいつものように話し始めた。さっきまで血まみれの泥まみれだったのがうそみたいな、なんでもない毎日の話。五条さんの愚痴は止まりそうにない。時折、ちょっぴり七海さんが怖いみたいな話があったから今度は七海さんにバラしてしまおう。困った顔をしてわたしを恨めしそうに見る顔が目に浮かんだ。
そんなことを考えていたら自分の顔が綻ぶのを感じた。ふと視線をあげたら、またミラー越しに伊地知と目が合った。安心したような顔をして微笑まれるからなんだか泣きそうになった。
ゆっくり、静かに、日常に戻っていく。耳の奥で響く名前も知らない人たちの悲鳴を、少しずつかき消しながら。
「私のお願いも言っていいですか」
「えー、だめ」
「……死なないでください」
だめって言ったのに。また車内が静かになる。流れていく景色と呪いの記憶が、頭の中でゆらゆら混ざって過去になろうとしている。
早く、早く、色褪せてほしい。
そっと目を閉じて、車の音に耳を澄ませた。誰か、ひとの、生きている心臓の音が聞きたい。
「ちゃんと着替えて綺麗にしたら、ちょっとだけ伊地知にくっついてもいい…?」
「えっ!?…なっ、また急にそんなことを…」
「うそだよ。照れ屋さんだなあ、伊地知は。昔から」
消え入りそうな声で言ったのにちゃんと届いてしまったので誤魔化すために茶化して言った。からかわないでくださいよ、という声が聞こえる。わたしは目を閉じていたから、彼が赤い顔をしてずれてもいない眼鏡を直しているのには気づかなかった。
このままどこかに行ってしまえばもっと静かに眠れるかもしれないと考えたことがある。けれどどんなに考えてもそれは無理だった。呪術師として生きた時間のほうが長すぎて、いまさらこの身体に刻まれたたくさんのものをなかったことにはできない。足元に広がる沼のような暗闇から黒い手が伸びてきて、ずっとこの身体を離さない。呪霊や人間の血の匂いが消えない。わたしはきっと、穢い。
「…そんなこと気にしなくたって」
車の揺れはゆりかごのようだった。心を覆っていた影がほのかに薄らいでいつの間にか眠りに落ちていた。夢現に浮かぶ闇のなかでぼんやりと考える。誰にも教わらなかった、清らかな生き方について。
「あなたはずっと綺麗ですよ。昔から」
わたしは呪術師として死ぬのが怖い。どこもかしこも痛くてもうとっくにここに立ち続けてなんていられなかった。いつかきっと跡形もなく消えてなくなって、優しい彼の心に仄暗い穢れを残してしまう。きみに悲しい顔をさせたくないのに、それでもわたしは。