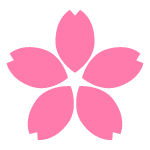私は昔考えた事がある。弟も考えたことがあるらしい。
正しい歴史とは、今守っている歴史で正しいはず。
でも、本当にそうなのだろうかと。
バカバカしくなって、考えることを辞めたけれど。
何か、ずっと喉に魚の小骨が刺さったような、異様な違和感を感じている。それがなんなのか、全くわからないのだけれど。
ただ、その違和感の先は刀剣男士を連れていない庭梅に感じているものだということだけは確かだ。
「まずは傷口だね」
「正面からひと突き…背に到達していることから刃物より長く、傷口の大きさはナイフのような形状だとは思いますが…」
「んなもんあるのか?長さがそれなりにある刃物ならすぐに見つかりそうなもんだが」
探偵たちの推理をBGMに周囲を見渡しながら集中する。だが残念なことに私の勘に引っかかるものもなく、腕を組んで堂々としていることにした。
そこに、スザクと名乗っていた少年が話しかけてくる。見たところまだ成人前のようだ。
「あんた、堂々としすぎじゃね?」
「いくら犯行時刻あの探偵たちと本邸にいたとしても、担当を殺す理由となり得るものは十分にあるからね。変に動いて自分の首絞める趣味はないからこうしてるのさ」
「…あんたたちは、殺してないんだよな」
「社会的に殺したいだけで、物理的に殺したいわけじゃないからね」
「あんた、さっき言ってたよな。「犯人がこの中にいれば」って」
「凶器の気配がどこにもないんだもん。十中八九やつらの仕業だろう」
「…侵入を許したってか」
ため息をついて、彼は至極真面目な顔でこちらの言葉を待っている。
「何故我らじゃなく奴を狙ったかは謎だけど。何より気になるのは、庭梅だ」
「は?」
ちらりと庭梅を見れば心配そうに親子を宥めている姿が視界に映った。
「梅花派は本人が戦闘狂である場合が多いが、誰しも戦闘系ではないから彼女みたいに戦いからは遠そうな子もいるにはいる。…だけど、甘っちょろ過ぎるんだよ、梅花派にしては」
「…確かに。演練で会う奴らとはちょっと違う気がする」
そう、それだ。短い口論の中で感じたのはまさにそれ。
梅花派の効率と戦績優先はほぼ審神者の意志と実力により他の派閥から引き抜かれる又は、そういう新人を採用する場合が多い。そういう奴らの集まりと言っても過言では無いのだ。
それにしては、彼女は妙に甘い気がする。
ああいうタイプは互いのためにすぐに桜花派へ流されるのだが…ああ、そういえばそういう話を友人から………と思い出してしまった。なるほど、考えや憶測が大変飛躍するが…。
急に黙り込み考え出す私にスザクは首をかしげている。
「どうしたんだよ」
「いや、思い出しただけだ」
話は終わりだ、と私は黙った。
調査は難航している。警察が来るのも時間の問題で、桜花派の担当の顔にも焦りの色が見えてきた。
歴史的大事件とは言えないが、後々のことを考えるとほんの少しだけ歴史が変わるかもしれない。なおかつ、この探偵たちが関わったのなら尚更である。
こっそりと近づいて、私は小さく声をかけた。
「桜花派担当、ひとつ確認したいことがある」
「…なんでしょうか」
「庭梅の所属国はわかるか」
「相模国と名乗っておりました」
「…そうか。担当、少しだけ席を外して騒ぎを起こして探偵たちの気を引いてくる。このままでは不味い。やつの処理を頼んだ」
「わかりました、お願いします。どこでも繋げられますが、1度政府のゲートにお越し下さい。お気をつけて」
「了解した。そちらもな」
会話を終わらせて、庭梅を見る。コナンくんが話しかけているのに対して、やや緊張気味であるように見えていた。すっと近づいていくと、微かに会話が聞こえてくる。
「ねえ、お姉さん。前にあのおじさんが在らざる者って…」
「庭梅、少しいいか」
あっぶねぇぇえええ!!!いや、遅かったぁぁああああ!!!!
内心のテンションがおかしいがこれは仕方ないことだ!なんてこった、ここでそれを聞くか!
庭梅は目を見開き驚いている中、コナンくんとの会話を邪魔して話しかけた。
「凶器の気配を探っているが何かに妨害されている。少し手伝って欲しい」
「……わかりました。ごめんね、坊や。お姉さんちょっと行ってくるから」
「は、ちょっ…待て!」
「村正!相手をしていろ!貞宗はついてこい!」
私は庭梅の手を取り走り出す。追いかけようとするコナンくんを村正が襟元を掴んで妨害し、驚きの表情を浮かべている毛利小五郎と安室透、蘭ちゃんその他の面々を横目に、木々を縫って撒くことにした。
ただし体力のない私は早々にバテて亀甲に抱えられ、まだ余裕のあった庭梅もついでに運んでもらったことは言えまい。
ろくに鍛えてない半引きこもり生活を送っていた20代後半なんてこんなものだチクショウめ。