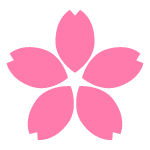人生はRPGではなく自分育成ゲームである。
私自身が人生というものは自分育成ゲームだと気づいた頃には、所謂ゲーム中盤の分岐点で、それぞれのルートを選ばねばならないところであった。
今更ステータスを上げようにもどう足掻いても中途半端にしか伸びずこれといったものがない上で就職という難題に躓いた。
そんな詰んでいるまま人生はクソゲーだとやさぐれ、何となくで生きていた私という存在が世界から、歴史から、記憶から消え、弟の本丸に保護されたばかりな頃の話をしよう。
本丸生活の初期はイケメンに囲まれガチガチに怯えていた私だが、刀を顕現するところを見てから不思議と平気になったのを覚えている。だって人みたいな物なのだろう?生身の人間のイケメンは怖いが、物がイケメンなだけなら別に怖くない。どちらかと言うと驚くべきは刀を顕現してイケメンになることらしいのだが、理解の方が大きく反応するのを忘れていた。
弟からは「その反応はおかしい」とツッコミを受けたが、弟も刀を顕現し従える事に慣れたのだから、そういうものなのだろう。
天災を除き、物は人を傷つけない。
人を傷つけるのはいつだって人だ。人が意思を持って人に向けなければ物はそこに有るだけだ。
落下事故もあるが、それだって人が物をそうしただけなのだから物に罪はない。
生身の人間とは違い相手が意思を持った物であるなら弟が仕向けない限り私を傷つけることはない。相手が意思を持った物なら怖くない。
理解してしまえば私は借りてきた猫のような生活から勝手知ったる家が如く普通に暮らし始めていたのだ。
デイリー任務で弟が部隊の指揮を取っている間に鍛刀のため弟に指示された量の資材を鍛刀妖精に渡し、妖精が資材を火に投げ入れるところを見届ければ板に鍛刀にかかる時間を確認する。
板の数字も見なれたもので、ある程度の回数をこなすと全審神者からグロ画像と呼ばれている1:30:00と表示された板に納得したものだ。
それを見届ければ弟に報告をして、結果に項垂れている弟を尻目に畑仕事へ向かう。
畑当番の鳴狐と薬研藤四郎に合流すれば、芋虫に怯えた可愛い私も最早いなくて、葉だけでなく実まで食い尽くさん勢いの芋虫共を駆逐する。ただし未だに毛虫は触れない。ヤツのせいで肌がかぶれて悲惨な目にあったのだ!つまりは軽いトラウマ。そんな毛虫をひょいと掴んでひょいと捨てる薬研ニキまじニキ。
畑当番に別れを告げて井戸で手と顔を洗い、軽く汗を拭く。
次に向かうのは厨である。キッチンと呼ぶより厨と呼んだ方が正しいほど時代を感じる古い作りだ。唯一、場違い感を醸し出す業務用冷蔵庫に技術の時代を感じる。
厨組のママ…もとい燭台切光忠、私の教育係を兼任してる歌仙兼定、蜻蛉切とある意味カオスなメンバーに混じり握り飯を作る。これは手合わせをしている薬研と鳴狐を除く粟田口短刀たちと日曜大工に勤しんでいる打刀と太刀、槍連中用にだ。
山のように積まれた握り飯の乗った皿を両手で持ち、利き手の肘にはお茶の入ったポットと大量の紙コップを入れた袋を下げ、道場に向かうべく声をかけた。
「んじゃ、粟田口短刀たちに届けてくるね」
「足元には気をつけるんだよ」
「転ばないようにね」
「はは…いってらっしゃいませ」
歌仙と、それに続いて注意する燭台切に私がどう思われているのかわかるだろう。私は子供か。純粋に存在してきた年月を考えれば私は子供なのだろうけど。
蜻蛉切のパパみを感じる心配そうな眼差しにグッとくるが、私がこの本丸で盛大に転んだのは慣れない下駄で外に出た時と、弟が着任当初に鍛刀した唯一のレア太刀である鶴丸国永のイタズラでワックスのかけられたツルツルな廊下に滑った時だけだぞ、納得いかない。
なお後者は思いっきりケツを打ちしばらく座ることすら苦痛であった…。自分の尻を鏡で見るほど情けないこともないと思っているせいで確認はしなかったが青アザくらいにはなっていたかもしれない。あれは本当に痛かった。
「お昼だよー」
「あ!あるじさんのお姉さん!ありがと!」
「ごはんですね!」
「いろんな味のがあるから好きなの取ってね」
「あ、あの…ありがとうございます…!」
「いえいえ、こちらこそ何時も姉弟揃ってお世話になってます」
短刀たちに握り飯を届け、軽く言葉を交わしてからワイワイと皿に集まって小さな口いっぱいに頬張る姿は本当に癒し以外のなにものでもない。
二十代の折り返し年齢もすぐそこで、こういう子達の姿を見ていると結婚からの子供が欲しい願望が膨れるが、かと言って恋愛願望がある訳でもないのでややこしいところだ。まあ、擬似家族も悪くは無いのだし自分の身の立場を考えると子孫を残す気にもなれないし…このままで良いかと結論付ける。
ひとりひとりの頭を撫でさせてもらい、米粒ひとつ残っていない空の皿を回収して厨へと戻る。余りの握り飯をひとつ貰って私の昼食は終わりだ。彼ら基準で握られた握り飯は大きくておなかいっぱい、余は満足じゃ。
燭台切にはもっと食べてなんたら〜と怒られるのだが、ほら…胃の容量は個人差があるから…沢山盛られても食べきれないのだ。彼らの一食分が私の二食、もしかしたら1日分の食事量に近い。太刀大太刀、槍や薙刀の量なぞ一日かけて食べ切れるかも怪しい。
それを知った燭台切と歌仙の二人は常々私の食トレを狙っている。ついでに私に比べたらまだ食べる方の弟を含めてだ。勘弁して、身体は正直だから容量以上食べたら食べたもの全部出ちゃうのぉ…!
そこまで考えてから……淫夢ネタはNG、いいね?
その辺で完成した刀を取りにいく弟に続いて付いていく。
けして歌仙のスパルタ淑女教育から逃げた訳ではない。あの歌仙の扇子の、ハリセンの痛みから逃げたのでもないのだ。
ハリセンって音だけ派手でそこまで痛くないように出来ているはずなのに首が折れるかと思うほどの威力を秘めた一撃を繰り出す歌仙はゴリラだ。ちくしょう、ゴリラめ…手加減してくれよ。こちらは生存数値低いんじゃ。
楽器の時はこちらも比較的楽しめるのだが舞踊と言葉遣い、仕草の授業は心が死ぬ。
舞踊は慣れない動きとリズムが取れずにグダグダになるし、言葉遣いと仕草はもう染み込んで取れない。汗ジミみたいなものだ。汗はとっても湧いてくるからね。
話を戻し、完成した刀を見れば見なれたものだ。弟の初期刀、加州清光と同じ刀がそこにある。
弟はそれを手に取り倉庫にしまうとふと、私を見た。
「なんだよ弟」
「姉、鍛刀してみない?」
「?今日もしたじゃん?追加?」
「いや、お前が資材量決めて」
「上限は?」
「1回につきオール999まで許す」
「つまりどのレシピ回しても構わんのだな。おっけー。」
そんなやりとりをして、少し考える。
レア太刀を狙うなら鼻紙と呼ばれる紙を使うかとも思うのだが、まあ勿体無いのでこれは却下。適当に太刀レシピを回すかとALL550で回した。
2:30:00と表示された板を見て弟とグロ画像回避したことに安心しつつ予想を立てる。
「大太刀かな」
「太郎次郎のどっちか希望」
「石切丸はいるもんね」
「ただなぁ…この数字、もう1人いるんだよなあ…はい、姉。手伝い札」
受け取った手伝い札を妖精に渡せば、それをまた火に投げ入れる。
キンッと音を立てて完成した刀を二人で見れば…大太刀ではなかった。
赤い柄に黄色…金色?もしかしたらカラシ色か。そんないろの鞘。赤い紐が絡まっているそれを手に取り、弟へ渡せば「こっちかぁ」と思っているだろう弟の表情が見て取れた。
そして、この本丸では見たことのない刀を顕現した姿を、私は忘れることはないだろう。
「今日もまだ生きてたのか」
「今日もまだ折れてなかったんかワレェ」
「本当に、主ではなくお前に鍛刀された事実がなさけない」
「その程度だったってことだろ、ざまあみろ」
「…」
「…」
後日、この私が決めたレシピでという意味での初鍛刀したへし切長谷部と何か決定的な事件があった訳でもないが、絶望的なまでにウマが合わないせいで埋まらない溝を作り毎日戦争する日々を送ることになる。