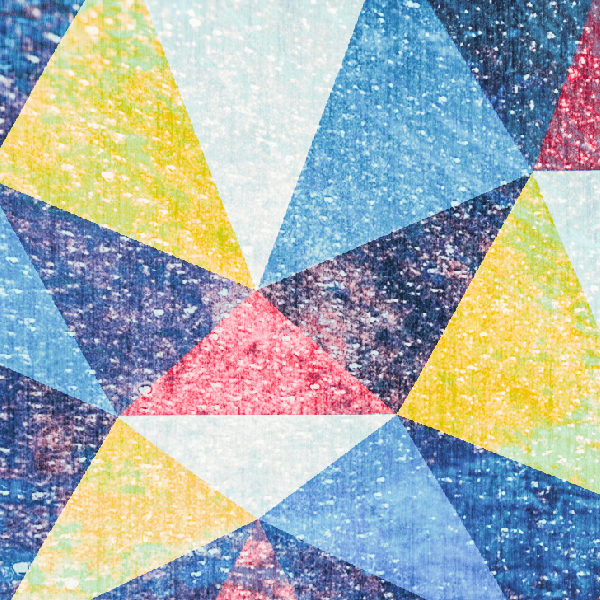
ゆっくり純情に溺れて
私は思うのだ。
「赤葦くんって意外と変な人だよね」
「え、赤葦って、あの赤葦?」
赤葦なんて珍しい苗字、他に出会ったことないんだからきっとその赤葦だよ。私は「うん」と頷いた。
「そうかなあ?」
残念ながら友人からの同意は貰えなかった。それでも思うのだ。
赤葦くん、ちょっと変わってるって。
「変なのはアンタでしょ?」
「...それはそうかも」
「否定しないんかい!」
アイテ、なんでこの子はすぐチョップするんだろ。芸人目指してんのかな。
◇◆
「うわあ、かっこいい」
__今日も木兎さんはかっこいい。
へいへいへーい、体育館に響く木兎さんの声にどっと観戦していたみんなの笑い声が響く。木兎さんはこの体育館の中でも1番輝いていた。
今日は他校と梟谷の練習試合の日だ。
放課後に梟谷の体育館であって、観戦OKだからそれなりの人が体育館に訪れている。なんたって梟谷のバレーボール部は全国レベルだ。この学校に在籍しているだけで、気後れすることなく応援できるのだからある意味ラッキーだろう。
「アンタ、まじで木兎先輩オタクよね」
「そりゃもうファン歴5年と1ヶ月よ」
「はいはい、ファン(本人承認済み)第1号さん。分かったからコートに顔向けろ」
「いてて、ほっぺ押さないで」
木兎さんとは中学校が一緒だった。
私は女バレで、木兎さんが男バレで。木兎さんはいつも熱量の凄い人だったけれど、周りはあまりついていけてないようだった。それでも木兎さんは走り抜けていく。
私はというと本当はもっともっとバレーに熱を入れたかったが、周りのみんなはそうでもないらしいので、それに合わせてプレーをしていた。
私にとって木兎さんは憧れだ。
私もあんな風になりたいな、なんて思っていた。「私をファン1号にしてください!!」と頭を下げたら変な目で見ることなんてなくて「おう!いいぞ!名前は?」だ。神だ。アイドルに自分のことを知ってもらうみたいなもんだ。大袈裟だと笑われたが、私にとって木兎さんはそれくらいかっこいい存在だった。
その翌日に貰った「俺のファン1号!! 木兎!!」という、何故か名前の後ろにも「!!」が付いている友人からすれば何とも間抜けな缶バッジを私は未だに大事にしている。友人だって推しのアイドルの名前や名台詞??みたいなのが書いてある缶バッジをしてるんだから変わりないのにね。
本人作成だし、油性ペンで書かれたものなのである意味これはサインである。多分いつかプレミア付く。いや、家宝にするから一生売る気はないけどね!
ことあるごとに「壊れてないか?ほい」とバッジを作ってくれるせいで、「俺のファン1号!! 木兎!!」バッジ、そして「へいへいへーい!!」バッチ、「おれ!エース!」バッチは家にもうそれぞれ10個近くある。全て表面保護専用の缶バッジカバーで保護している。一番最初にもらったやつなんかは特に気を使って保護し、そして大事に棚の中に保存した。
缶バッジは部屋に飾ってるものとバッグについてるものと色々だ。お守りよりもお守りらしいそれが友人に引かれようと知ったことではないのだ。
「今のスパイク、すごい...」
ふと中学時代、放課後に一緒に自主練していたあの頃が懐かしいく思えた。木兎さんは体力おばけだから振り回されてばっかりだったけど、それでもとっても楽しかったなあ。
特に下手でも上手でもなかったトスが上達したのも、チームのみんながバレーに熱を入れなくたってあまり寂しくなかったのも木兎さんのおかげだ。
今ではすっぱりバレーは辞めてしまったが、それでも木兎さんの姿を見ると少しだけバレーがしたくなる。
「...良いチームに出会ってよかった」
「??なんか言った?」
「ううん、なんでも」
へいへいへーい!!こちらに向けて手を挙げた木兎さんに歓喜する。友人に喜び過ぎだとチョップされたが気にしない。
なんたって、私の絶対的ヒーローは今日も最っ高にカッコイイのだから。
「......?」
視線をコートに向けたままにしているとふと赤葦くんが視界に入る。ぱちり、目が合った。ふっと赤葦くんが見たことないくらいに綺麗に笑うものだから私はぱちぱちと瞬きした。
◇◆
苗字名前という女の子は梟谷の男子バレー部では割と有名だった。中学は木兎さんと同じ。木兎さん曰く中学時代によく一緒に自主練していた「妹みたいな存在」らしい。
彼女が応援に来ると木兎さんの調子が良くなる。あとしょぼくれモードからの復活も早い。なんでも「俺のファン1号にいい所を見せなきゃ!」だかららしい。それで簡単に復活してくれるのならこっちとしてもありがたかった。だからまず彼女が来る練習試合や公式試合の日は何処にいるかを探すことから始まるのだ。
「いやあ、木兎幸せもんだなー」
「それな」
「ん?何がだ??」
あんなにキラキラした瞳でコートを、そして自分を見つめてくれて、点を入れたら喜び、ミスをしたら「ドンマイ!次、1本」なんて言ってくれる子はそうそういない。試合に勝った時の喜びようなんて見てて飽きないものだ。
本人だけが「んん?」と首を傾げている。そして「おう!まあ幸せだ!」と恥ずかしげもなく声を上げるのだ。きっとよく分かってはいないのだろうな。
苗字さんから誕生日に貰ったらしいタオルで汗を拭いている木兎さんを見て思う。
___羨ましい、なんて。
「赤葦!次のセットも取るぞ」
「はい」
ああダメだ。こんなこと考えては。
そんなことを考えながらふと彼女の方を見上げた。
「.....」
ぱちり、また目が合った。
◇◆
「なあ、赤葦」
「はい、なんですか?」
練習試合も終わり、自主練の時間になる。他の部員たちは既に帰ってしまい体育館には2人だけだったが、こんなことは珍しくない。
自分の中でスターである木兎さんとの自主練習は自分にとってとても大切な時間だ。
「......」
「...?木兎さん?」
「いや、ふと今思ったんだけどさ」
「はい」
一体何を言い淀んでいるのだろうか。首を傾げながら木兎さんの言葉を待つ。
「赤葦はさ。.....名前のこと、その、好きなの?」
「...は?」
思わぬそれに素で声が出た。思考が一時停止する。そして次の瞬間には急速に回転し始めた。
木兎さんは今なんて言った?
言葉を何回も咀嚼して、それから反芻して。それを繰り返していればまた木兎さんが口を開く。
「いや、なんかよく名前のこと見てるから」
「.....」
それは木兎さんがより良くプレーしてくれるならと探して、.....あれ?でも別に特に意味もなく見上げてしまうこともあるような。
色々なことが頭の中を駆け巡っていく。試合だけじゃなくて教室でのことも全部全部ぐるりと混ざって、それからストンと胸の中に落ちてきた。
___ああ、そうか。ようやく分かった。
「いや、まあ気にすんな」
「.......好きです」
「えっ!?」
「.....」
体育館に木兎さんの声が響いた。あんなに練習試合で動き回っていたのに、自主練を始めてもう大分時間が経ったのに木兎さんはまだまだ元気らしい。
「えっ、やっぱり!?」
「.....はい。...まあ、たった今気づきましたけど」
まさかこの感情を木兎さんの言葉で気づくことになるとは思わなかった。木兎さんも自分自身も驚いている。何だか少しだけ照れくさくなって、木兎さんから顔を背けた。そんな俺を見て木兎さんが笑っている。
「俺はいいと思うぞ!」
「.....痛っ」
バシッと背中を叩かれる。その力強さに思わず声が出た。少しは手加減して欲しかったな。
木兎さんも苗字さんもお互いに恋愛感情がないことはとっくに知っている。
木兎さんの「俺の妹みたいな存在!」という言葉に苗字さんは目を光らせて「妹!?そんな、嬉しい!...ああ、でも烏滸がましい。1ファンでいいですっ!」と言っていたのだ。
周りに「お似合いだぞー」と揶揄われても本人たちはそれをすぐに否定する。木兎さん曰く「俺の妹兼ファン1号!!」。苗字さん曰く「私のヒーロー、絶対的エース」なのだ。
それが変わることは今後一切ないらしい。
そんな二人を見て最初に感じたのはただの親近感だ。多分木兎さんに向ける感情が自分と苗字さんはよく似ていた。
だからだろうか。苗字さんを気にかけるようになったのは。思い返してもきっかけは分からない。でも確かに木兎さんの言うように自分は彼女が好きなのだ。
ようやく、ようやく最近のもやもやのひとつが解けたような気がした。
「.....」
「...あかーし!」
「はい」
「応援するぞ!俺は!」
「ありがとうございます」
バシバシ!また手加減なく背中を叩かれた。絶対赤くなってるだろうな。そんなことをぼんやりと考えながら手の中のボールをくるりと回す。
やっと気づけたこの思いは中々消化されることはなく、沸々と煮えるように燻っていた。
「俺、頑張りますね」
「おう!」
◇◆
「苗字さん」
「ひえ、赤葦くんか...。びっくりした」
背後から声をかけられてビクリと震える。振り返れば赤葦くんが笑みを浮かべて立っていた。
何故だか最近よく話しかけてくる赤葦くんは、コートに立っている時よりもニコニコしている。
「どうしたの?」
「苗字さんが見えたから声をかけただけだよ」
「?そうなんだ?」
あ、でもコートではさすがに真剣になるか。あれ?いやでも、クラスにいる時もこんなにニコニコしていないような気がする。みんな「赤葦ってクールだよね。ふっとは笑っても、ニコニコしてるところあんまり見たことない」と言っていたし。
なんだか二人でいる時は特に笑っているような...、いないような?勘違いか?
もしかしたら私が木兎さんを推してるから親近感があるのかもしれない。赤葦くんも木兎さんはスターだと言っていたし。
「ね、今度の試合来る?」
「もちろん!」
「そっか」
「え、うん」
それだけ聞くと赤葦くんは去っていってしまった。
え、また?
何だかこの前もこんなやり取りした気がする。どういうことだ?首を傾げるが一向に分からない。
「赤葦くんって不思議だなあ」
思わずぽつり、そう呟いた。
つい木兎さんに「赤葦くん、どうしたんですか?」と聞いてしまった。すると、木兎さんは「あー...」と言ったまま口を閉じてしまった。何か知ってるのだろうか。「ま、気にすんな!」と言われたが、気になるものは気になる。
だからつい赤葦くんに声をかけてしまった。
「あ、あの。赤葦くん」
「っ、苗字さ、ん.....?」
振り返った赤葦くんはこの前の私みたいにびっくりした表情を浮かべたあと、きょとんとしてこちらを見つめる。その表情が新鮮で思わず笑ってしまう。
何だか心がほわほわしてて、むず痒かった。
「どうしたの?木兎さんが何かした?」
「ううん。木兎さんは関係ないよ。.....ちょっと赤葦くんが居たから声をかけてみただけ」
素直にそう言って笑う。ぱちぱちと瞬きをした赤葦くんは考え込むように黙ってしまった。
「俺がいたから」
「うん。赤葦くんの後ろ姿が見えたから、あっ赤葦くんだーって思って声かけたんだけど...」
「そうなんだ」
「うん」
私の言葉を繰り返した赤葦くん。それに頷いてそう言葉を続けて、それからじっとその顔を見つめた。赤葦くんもこちらを見つめている。
目を離せないまま数秒が経つ。
何だこの時間。そんなことを考えていると、
「.....はぁーー」
「え、なに?どうしたの?赤葦くん?」
赤葦くんは何故か顔を両手で押さえてしゃがみ込んでしまった。彼に声をかけるが反応がない。何故か耳が真っ赤だ。
え?熱か?
見慣れない赤葦くんの頭を見下ろして慌てる。
遠くに木兎さんとそれから木葉さんが見えて、赤葦くんの方を指差しながら慌てていると、何故か2人は大爆笑していた。
え、助けてよ。
(赤葦ってさ、アプローチの仕方が変だよな!)
(木兎にまで言われてんぞ、赤葦.....)