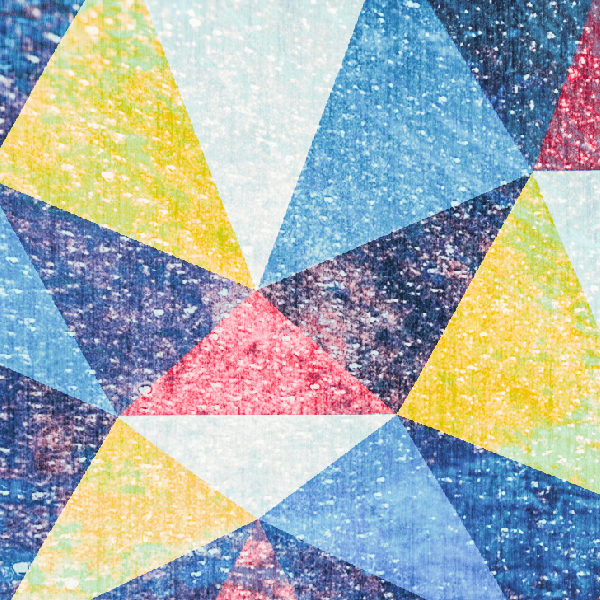
流れ星を詰め込んで
「キラキラ、してる」
佐久早は思わずそう呟いた。その言葉に名前はそのキラキラとした瞳でぱちぱちと瞬きをする。そして、そのきょとんとした顔で佐久早を見上げると、「んん?」と小さく唸って首を傾げた。そして思うのだ。
佐久早くんって難しい、と。
◇◆
佐久早は中途半端ができない男だ。バレーボールだって、掃除だって、その他だって。
綺麗好き、潔癖、気にしすぎ。
今まで彼を称する言葉はそういうものが多かった。本人は潔癖と言われるのが嫌でも、周りから見ればそのように映る。清潔なものや綺麗なものの方が好き、という感情は誰にだってあるが、彼はきっとその思いが特に大きい。
中途半端が嫌い、と言うよりできない。だからこそ高校生の中でもトップレベルのプレイヤーになれたのだろう。あとは周りに恵まれたこともあるだろうけど。
そんな性質である彼は、やはり興味関心に関しても中途半端では終われない。
「あ、あの佐久早くん?」
「何?」
「いや、えっと…」
「……」
「ナンデモアリマセン」
「うん」
その圧に気圧され、名前は片言でそう答え、口を噤んだ。
そんな彼女の瞳をじーっと見つめて、佐久早は考える。
どうしてそんなにキラキラと綺麗な瞳で彼女はこちらを見上げるのだろう。それがどうしても気になる。その理由を知りたい。
それが気になって仕方がない。と、佐久早はついその長身を彼女の背に合わせて姿勢を低くする。
「……」
「……」
周りに誰もいないから良いが、これを見られたらカツアゲされてるように映らないだろうか、とか。身長高い、何か顔も近い、とか。そもそも佐久早くんって人に近づくのも近づかれるのも嫌いじゃなかったっけ?とか。そんな考えが混乱とともに名前の頭の中に思い浮かぶ。
「……」
「えっと…」
じーっと見られるため、どうしたら良いのか分からない。せめて何か言ってくれたら有難いが、彼が口を開く様子は全く見られない。
暫くすると、更に佐久早の顔が近づいてきたので、名前は思わず目を瞑った。
「あ…」
「…?」
すると何故か悲しそうな声が降ってきて、薄目を開ければ、声と同じように少しだけ悲しさを浮かべた佐久早の瞳が見えた。
よく周りの人から「機嫌悪いの?」とか「寝不足?」とか言われていたり、「ひっ」と怯えられていたりするあの目はどこにもなく、名前には捨てられた子犬のような表情に見えたのだ。
まあ子犬にしては、ちょっと体格が大きすぎるが。
名前がしっかりと目を開けると、そんな佐久早の瞳が一瞬だけキラリと光った。彼は常日頃からマスクをしているため、先程から目だけでどうにか感情を読み取ろうとしていた。その瞳が一瞬だけではあるが、輝いたので名前は驚く。佐久早のこんな表情を見たのは初めてだったからだ。
不覚にも心臓が大きな音を立てたのが分かった。
「あの、佐久早くん…」
「……ごめん」
「エッ、何が?」
「怖がらせた」
惚けて佐久早を見つめていると、そんな言葉が降ってきた。一体何に対して謝ったのだろう。そう考えていれば、続く言葉。それだけを残して佐久早はその場を去ってしまった。
「え、え?結局何だったの…」
何にも追いついていない名前は、その後ろ姿をぼんやりと見つめることしかできなかった。
◇◆
佐久早の脳内にはいつまで経っても、あのキラキラした瞳でこちらを見上げる苗字名前の姿がチラついていた。
バレーをしている時や授業中はそうでもないが、ふとした時に頭に過ぎる。
彼女は同じクラスではあるが、席は近くないしいつも友人と談笑している。
「……」
「佐久早?聞いてる?……おーい、聖臣?」
この前のことで怖がらせたかもしれない。そう考えしまえば、そうとしか思えない。佐久早は1度ネガティブに嵌ると、そればかりを考えてしまうのだった。
そんな佐久早には、不思議そうにこちらに呼びかける古森の声など聞こえていなかった。古森は古森で、いつも通りスルーされてるのかと一瞬思ったが、わりと長年一緒に居たのだ。佐久早が上の空で聞いていないことにすぐに気づいた。
「どうかしたの?」
何に気を取られているのだろう、と古森がそう尋ねると、佐久早はハッとして古森を見た。急にこちらに意識が向いたことに、古森は少しだけ驚いた。
「どうしたら良い?」
「ん?」
主語なくそう尋ねられ、古森は思わず首を傾げた。「いや、何が?」と言えば、ようやく佐久早が事情を話してくれた。その内容に古森は衝撃を受けた。
いや、だってあの聖臣だ。
思わず自分の従兄弟を見つめると、真剣な視線が返ってきた。何事にも中途半端ができない彼は、その思いも、興味も、そして気にし過ぎも中途半端では終われない。
それがよく分かっている古森は考える。相手は苗字名前か。古森の中で彼女の印象を考える。確かに彼女は佐久早の嫌いなタイプではないだろう。清潔感はあるし、ちょっと抜けているようには見えるが、気が利くし、優しいし。
古森はちらりと彼女を見やる。友人と談笑している彼女は、口を手で覆って「ふふっ」と笑みを零していた。その光景を佐久早も見ていたことに気づいた。いや、見すぎ。古森は口の中でそう呟いた。
「試合に誘えば?それが一番お前のことが分かると思うけど」
「……」
やはり佐久早と云えば、バレーだろう。これしかない、古森はそう思いながら口を開いた。佐久早は数秒考える素振りをした。そしてコクリと頷いたのだった。
◇◆
それから数日後。移動教室からの帰り道。
佐久早と古森の前を名前が歩いていた。その傍らに友人の姿はない。彼女の友人は、教室を出る際に教科担当の先生に呼び止められたからだ。先に行くように言われた名前は、素直に頷いて教室に向かう所だった。
「苗字さん」
「?…あ、佐久早くんに古森くん」
名前を呼べば、彼女が振り向いた。「どうかしたの?」と2人を見上げる名前は、突然呼び止められたことに目をぱちくりとさせていた。
古森はわざと1歩下がる。その気配を察知しながら、佐久早は口を開いた。
「…来い」
「え?」
何を言われるのだろう、と名前は佐久早を見上げる。相変わらず感情の読み取りにくい佐久早の黒目をじっと見つめていると、降ってきた言葉に名前は思わず声を上げた。佐久早の斜め後ろで、古森が頭を押さえたのが見えた。
主語なく発せられた言葉に名前に緊張が走る。ぞわりとした恐怖が全身を駆け抜けた。
これは集団リンチの呼び出し?
集団といっても相手は2人だが。もしかしたら着いて行くと他にも誰か待ち構えているのでは?
一瞬のうちに完全に色々と勘違いした名前の脳内には変な想像が沢山思い浮かんだ。
「えっと、…こ、校舎裏に、…ですか?」
「は?」
「ブフォッ」
色々と一生懸命考えて出した名前のその言葉に、佐久早は素で声を出した。その佐久早の後ろで何故か古森が苦しそうに笑い始めた。
あれ?そういうことじゃないの?
2人のその反応に名前は首を傾げた。はあ、とため息をついた事の発端である佐久早は小さくポツリと言葉を零した。
「…試合」
「しあい?」
「見に来て欲しい」
「…試合って、バレーの?」
「うん」
あー、なるほど。ようやく理解した名前に、佐久早の斜め後ろで古森が「ご、め、ん、な」と口パクで謝った。きっと言葉足らずでごめん、ということだろう。それに小さく頷いてから、名前は佐久早を見上げる。そしてにこりと笑いかけた。
キラキラと瞳が光る。
「いいよ。佐久早くんのバレーしてるところカッコイイんでしょ?私、見てみたかったの」
「……うん」
名前の直球な言葉に佐久早は数秒固まった。そしてようやく出た声は酷く小さかったが、ちゃんと名前には聞こえていた。こくりと名前は頷いた。
「じゃあ今度試合の日教えてね」
「うん」
「ちょうど友だち来たし、じゃあね」
佐久早や古森の後方からやってきた友人の姿が目に入った名前はそう言って手を振ると、駆け出して行った。
「アンタこんな所でどうしたの?」
「んー、別に」
ふわふわと笑う彼女に視線を送ってから、佐久早と古森は廊下を歩き出す。ちらりと見えた佐久早の耳が赤く染っているのに気づいた古森はわざと指摘することもなく、「良かったな」とだけ呟いた。それに「うん」と佐久早は頷いて、小さく笑った。
(お前、あの誘い方はないって)
(…うるさい)