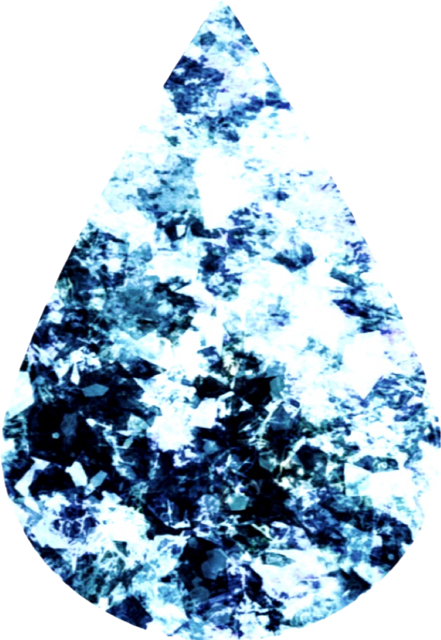「おはようございます、シエナさん」
「あぁ、おはよう、名前!」
開けっ放しの扉から店のバックヤードへ入る。出迎えてくれるのはいつも、店主の奥さんであるシエナさんと様々な果物の香り。壁にかけてあるサロンを腰に巻き、シャツの袖をまくれば出勤準備は完了だ。今日の目標は、5ケースあるオレンジを半分以下にすること。「さぁ、今日も頑張るよ!」シエナさんの一声で、背筋がぴんと伸びた。
「大丈夫かい?今日は結構あるよ?」
「大丈夫ですよ、このくらい」
よいしょ、と持ち上げた箱からは、得意先ごとに袋詰めされた商品が積み上がっている。視界が半分ほど奪われながらも歩き出す私を、シエナさんが心配そうに見つめていた。彼女のもとで働き始めておよそ8年、早くに両親を失った私にとってはもうシエナさんと、その旦那さんで店主であるダナエさんは親同然と思っている。夫妻もまた、私のことを娘のように想い育ててくれた。住み込みで6年、一人で住むことにすると伝えたときの二人の泣きっぷりは今でも忘れられない。住み慣れた町を海岸の方へ真っ直ぐ歩くと、開店前だというのに店の周りに人が集まっているカフェが見えてくる。相変わらず人気だなあと思いながら店の裏手へ回ると、ちょうど開いた扉の向こうで美人が私に手を振っていた。
「おはよう、名前ちゃん」
「おはようございます、アイリスさん」
ミルクティーみたいな色素の薄い髪を揺らして微笑むこの人はこの町一番の美女で、この町一番の紅茶とサンドイッチをだしてくれるカフェのオーナーだ。美しくて穏やかで優しくて気品に溢れ、おまけに料理上手。そんな完璧な女性が営むここは開店から閉店まで、老若男女問わずお客さんで賑わっている。私がここへ一番に配達にくるのは、この笑顔を見るためだと言っても過言ではない。幼少期より可愛がってくれた彼女はさながら姉のようで、私に1日の元気とパワーをくれるのだ。
「今日は何かある?」
「えーと、できればオレンジをお願いしたいんですけど」
「じゃあ今日のオススメはオレンジティーにしようかな。10個お願いできる?」
「ありがとうございます!朝周り終わったらすぐ持ってきますね!」
「ふふ、そしたら名前ちゃんに一番に淹れてあげるね」
今日も女神の微笑みをいただけました。神さまありがとう。柔らかな笑みをしばらく思い浮かべたあと、再び箱を持ち上げ次の配達先を目指す。この後はレストランに道場、ほかに定期配達を依頼してくれているお店や家数軒で終わり。少しだけ軽くなった箱を持ち直し、来た道を少し早歩きで進んだ。
「それじゃあ、次は明後日に伺いますね!」
「えぇ、よろしくね」
最後の家に商品を届け、頭を下げる。空っぽになった箱を片手で抱え、身軽になった身体で走る。時刻は10時を回り、町はいつもの活気に溢れていた。道行く人がおはよう、と声をかけてくれるのが気持ちいい。数日続いた雨も今日は太陽に負けたのか、姿を隠した。久しぶりの青空を見上げ、なにかいいことが起こりそうだと笑みが溢れた。
「あっ、名前ちゃん…!」
「え、わ、」
店への帰り道、角を曲がったところで八百屋のおじさんに腕を掴まれた。バランスを崩しよろめく私にすまん、と謝る彼の表情はひどく硬い。いつも大きな声と笑顔で野菜を売っている姿とは似ても似つかず、何かあったのかと聞かざるを得ない空気だ。ふと周りに目を向けると、皆歩みを止め心配そうに一点を見つめている。その視線の先には、私のお店もある。突然、心臓が嫌な音を立て始めた。
「お、おじさん、何が」
「名前ちゃん、店の奥に隠れてな」
「なんで、何があったんです?」
「ダナエの旦那から伝言があったんだよ!町のやつを使って色んな店に伝わってる。名前ちゃんを見つけたら匿っておいてくれって」
「っ、どうして?何が起きてるんですか?!」
声を荒げても、おじさんの腕をつかむ力は緩められなかった。店の奥から奥さんが出てきて、早くこっちにおいでと言ってくれている。けれど私の頭はそれをよしとしなかった。ひたすらシエナさんとダナエさんの顔が浮かび、ざわつきが胸に広がっていく。唇を噛んでぎゅ、と目を瞑る。皆んなが私のことを考えてくれているのは分かる。だけど、このまま何もしないで隠れているだけも嫌だった。両親のように知らぬ間に帰らぬ人になるなんてこと、二度と味わいたくない。ごめんなさい、とおじさんの目を見て伝えると、一瞬手の力が緩んだ。その隙をみて、私は抱えていた箱を捨て走り出す。待ちなさいとかやめなさいとか、色んな声が聞こえる。それでも私は走り続け、二人の無事を祈りながらただ走った。
「だから、いないってんだよ名前なんて子は!」
「ここにいないなら、どこにいるかだけでも」
「うちの店どころか、町にすらいないよ!」
「そんなはずはねぇ。俺の仲間たちがここへ連れてきたんだ」
「あんたがどこのモンか知らないけど、これ以上いない人間のことで商売邪魔するってんなら、容赦しないよ」
「ま、待ってくれって、争うつもりはねぇんだ!」
「あんたにはなくてもこっちにはあるんだよ!」
シエナさんの怒号が聞こえる。遠くに見える店先には長身の黒い影が立っていた。とりあえず言い合いで済んでいることで安心したが、この調子だとシエナさんが本気を出し兼ねないのである意味危ない。相手がどんな人かは分からないが、普通の成人男性ひとりなら余裕で意識不明に出来てしまう彼女のことを怒らせていけないのは暗黙のルールである。それを知らないということは恐らく外からきた人間なのだろう。海の向こうには「能力者」なるものがいて、非常に危険極まりない人種が溢れているという話もきいたことがある。シエナさんと対峙している人物がそれに該当するものだとしたら今度は彼女の命が危ない。兎に角危険な状況であるその場所へ1秒でも早くたどり着くべく、死にものぐるいで走り続けた。
「と、とりあえず落ち着いてくれ、おかみさん」
「落ち着いてられるかってんだよ、この若造!」
「…参ったな」
「覚悟はできてんだろうね…」
「げ、」
シエナさんが腕まくりをする。この姿をみたのは、町に来たばかりの頃に私を笑い者にした男の子数人を目の前にした時だった。彼らはいまとても好青年に育っているが、今でもシエナさんをみると当時のことを思い出し背筋が凍るのだとか。しかしそんな話は今やどうでもいい、とにかく場をおさめるのが私の使命だ。急げ、急げ。呼吸をも止めとにかく走り、手を伸ばす。今にも殴りかかりそうなシエナさんを前に慌てる黒いコートの男性の肩を掴み、思い切り引いた。その拍子にかぶっていたハットが転がり落ちる。反動で流れる金色の髪と、左目から頬にかけて残る大きな傷跡。青のベストと白いシャツが、今日の空みたいだと思った。
|