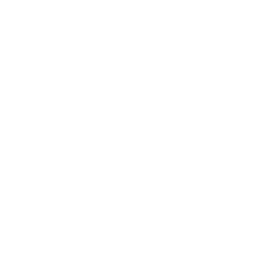パンッと掌を合わせて、2人で声を揃える。楽しそうに解斗さんが箸を手に持ち、卵焼きに手をつけた。
若干、食い込もうとする箸を卵焼きが反発したけど、無駄な抵抗もほんの僅かなことだった。箸が卵焼きの底まで沈む。解斗さんが大きく口を開いて頬張ると、蕩けそうな顔をした。丁寧に咀嚼しながら、勿体なさそうに飲み込んで、喉元に卵焼きが通っていく。
「うっめえ……!」
「ありがとうございます」
私も卵焼きを口へ運んで、その感触を確かめる。ほんのり塩味が主張しすぎず、かといって、分からないほど薄味でもなかった。噛めば、卵の層からじゅわっと味の染み込んだ汁が溶けだす。我ながら今回はいい仕上がりになったなあ、と思いつつ、舌鼓を打った。
ふと、美味しそうに食べる解斗さんの姿が目に入った。
今度はお味噌汁を啜ってる。よく噛むくせに、次はこのおかず。その次はこれ。とスムーズに選んで、箸をつけて、笑顔を綻ばせるのだ。作る側としては見てて気持ちのいい食べっぷりである。
何故、私はこの人と一緒に食卓を囲んでいるのだろう。
そんな疑問がむくり、と私の心の中に湧き出た。思えば、私と解斗さんの共通点はない。歳は一回り離れているし、出身地は地方ですら重ならない。性別も血液型も違う。
一つだけ、私と解斗さんに繋がりがあるとするのなら、それは母だ。
私が解斗さんと初めて会ったのは母がこの世から去った3日後のことだった。母は病気で死んだ。気づいた時には手遅れだったらしい。このことも解斗さんから告げられるまで、私は知らなかった。そして、解斗さんが母の遺言で決められた私の未成年後見人ということも。
母が余命を宣告されてから、時間がなかったことは理解している。頼れる親族が母にはいなかったことも分かっている。それでも事が母と解斗さんの間だけでとんとんと進められて、私が全く関わっていなかったことには戸惑いを抱かなかった訳じゃない。
いくら私が勉強のために下宿して、実家から離れていたとしても……。打ち明ける機会だっていくらでもあったのに。それなのに、血の繋がりもない、私の知らない男の人には全てを話して、全てを託していたのだ。
それがこの百田解斗という男性だった。
解斗さんは変に熱く、変に義理堅い人だった。母の葬式や身の回りの整理や、アパートの引き払いとか、全て手伝ってくれた。
それに未成年後見人は、養子縁組と違って、子供に対する扶養の義務はない。未成年とはいえ私ももう自活出来る年齢ではあったし、解斗さんと一緒に住むということはなかった。
代わりに解斗さんは私の家に通うようになった。
必ず、少なくても、月に1度は解斗さんは私の家にやって来た。最初は「元気か?」なんて言って、ただ顔を見て帰るだけだった。
いつの間に、こんな風に家にあげて、一緒に晩ごはんを食べる仲になったのだろう。解斗さんが今使ってる黒いお茶碗に、黒いお箸も最初はこの家になかったものだ。
「ごちそうさま」
解斗さんが満面の笑みを浮かべて、空の食器を手渡した。
「また料理の腕上げたんじゃねーか?」
「そうですか?」
「この前、食べたときよりも格段に美味かったぜ」
「解斗さん、お世辞が上手ですね」
「お世辞じゃねーよ。これならどこに嫁に行っても問題ないな!」
機嫌よく洗い物をしようとした手を私は止めてしまった。蛇口から水がとめどなく流れたまま、ダンダンとシンクを打ち付ける。
「そうだそうだ、名前。プレゼントがあるんだ!」
そんな私に気付いてないんだろう。解斗さんが立ち上がって、小さな山と化した荷物の中から、紙袋を一つ、私に差し出してくる。
私は洗う気にもなれなかったので、蛇口を閉めた。
紙袋の中に入ってたのは正方形の箱だった。紺地に小さな星がホップにプリントアウトされた包装紙でくるまれている。他にリボンやらシールといった装飾はない。シンプルなものだった。
「開けてみろよ」
顔にどんな反応をしてくれるのか、と期待を浮かべた解斗さんに言われて、私は無言でプレゼントの包装紙に触れた。破かないように慎重に、セロハンテープを外していく。
くしゃ、となんとか包装紙を綺麗に剥して箱を取り出した。パッケージには家で見るプラネタリウムと書いてある。中に入っていたのはプラネタリウムだった。
「どうだ!すごくねえか!?最近の技術っていうのはすごくてよ、色々種類があるんだぜ!?日周運動機能があって、光学式だとガチのプラネタリウム並に星が観れるんだぜ!すごいだろ!もちろん、これは光学式だ!」
そう、解斗さんが気合いを込めて言うけれど、私にはなんのことだかさっぱりだ。
「せっかくだからコーヒー飲みながら、見ません?」
話を一度区切るために私は解斗さんに提案した。「インスタントですけど」と、うっかり蛇足してしまったが、解斗さんは「いいねえ、これでテントがあったらまるで天体観測だな!」と、楽しそうにはしゃいでいた。
解斗さんがプラネタリウムを、私はコーヒーの準備を各々進め始めた。電気ケトルでお湯を沸かしている間に、棚から黒と白のマグカップを取り出す。
この黒地に銀のラメが入ったマグカップ、解斗さんが気にいってたんだっけ。
隣に並ぶ白いマグカップには金のラメが入っている。それも一緒に取り出して、黒い底と白い底にインスタントコーヒーの粉をスプーンで入れる。そこに沸かしたお湯を注げば、マグカップの中はコーヒーで満たされた。白いほうには角砂糖とミルクを。黒いマグカップを見て、私は手を止めた。入れてもいいんだろうか。それも一瞬のことで角砂糖を一つ、入れることにした。
マドラーでかき混ぜれば、真っ黒だった液体は白い線を帯びながら淡いブラウンへと変わっていく。
「解斗さん、はい」
「サンキュー、机の上に置いといてくれ」
もうちょいだから、待ってろ。と解斗さんが言うので、邪魔にならないように解斗さんから、距離を取って、座り込む。
解斗さんは私が予想していたよりも器用に作業を進めていった。こういうのは苦手だと思ってたんだけど、と妙に裏切られた気持ちになりながら、コーヒーを一口。
「あっつ……」
熱くて飲めなかったので、テーブルの上に置いた。冷めるまでの間、手持ち無沙汰になった私は、解斗さんがプラネタリウムを弄る様を眺めることにした。
慣れた手つきで、この部品はあっちで、これは後から必要になってくる。床に置かれた説明書を流し目で見ては、すぐにプラネタリウムのあちこちを動かしていった。
母は解斗さんのこういうところも好きだったんだろうか。
解斗さんは、母の恋人だった男性だ。
私が幼いころに母と解斗さんは付き合い始めた らしい。お付き合いが始まった当初、解斗さんが高校生で母は三十路でシングルマザー。
もし、付き合っていることが世間に露呈したら……と、母はしきりに気にしていたという。
解斗さんは「別に気にすることねーのにな……。好きなんだからよ。でも不安に思うのは仕方ねえし、オレのことを心配してくれてから、不安になってたんだよな。あの人らしいぜ」と、眉を下げて笑っていた。
誰に打ち明けるわけでもなく、母と解斗さんの間に起こったことは二人だけの秘密だ。だから、母と解斗さんが付き合っていたなんて、解斗さんから説明されるまで一切知らなかった。
知らない男性と仲睦まじく付き合っている素振りする女の姿をした母なんて私の記憶にはない。
私の母は、私の前ではいつだって微笑みを絶やさず、穏やかなままだった。
それでも、ぽつぽつと解斗さんから零れる母の面影は、私の中の母を壊さなかった。むしろ、緩やかに溶け合って、やっぱり母はこの人と付き合っていたんだな、と感じさせられてしまうのだ。
それが悲しいのか、辛いのかよく分からなかったけど、今では胸の中でストンと落ち着いている……。
解斗さんと母はどうして付き合うことになったのか。詳しくは話してくれなかったけれど、解斗さんは一目惚れだったからと言う。
母のほうは分からない。もう母には聞くことが出来ないから、書き残した日記でも無い限り永遠の謎になるのだろう。
それか解斗さんだけが知っている。
「よっしゃ、これで大丈夫だろ。名前の部屋に合わせといたから、キレイに映るはずだぜ」
「えっ、あぁ。そうですね……えっ!?」
ぼんやりとしていると、 視界が突然真っ暗になった。反射的にぎゅっとマグカップを零さないように両手で握りしめた。
「な、何!?」
「落ち着けって」
肩を掴まれて、さらに混乱した私はマグカップを落としそうになる。その寸前でコツン、とおでこに何かが当たった。解斗さんだ。解斗さんの匂いと温度が、今、目の前にある。眩みそうな熱を孕んで、微かな吐息が私の顔にかかる。
「大丈夫か?」
「……心臓に悪いです」
「悪い悪い」
一拍置いて私は返事をした。おそらく解斗さんが電気を消したんだろう。私の家の電気はリモコンがついてるから多分それだ。いつの間に回収していたのか。
「でも臨場感が出るだろ」
「臨場感って……」
なんですか。と言おうとする前に「じゃあ、点けるぞ」と遮られてしまった。そこから文句を言おうとしたけど続かなかった。天井が、部屋が、暗闇が光の粒で埋め尽されたからだ。手をかざせば、うっすらと掌中で光っていた。私の手のひらで、私の手より遥かに小さい灯りが揺れたり、瞬いたりしている。ぐっと握りしめても、空気も掴めはしなかったけど、私は笑って手を開いた。
「すごい……」
「だなぁ……」
特に天井を跨ぐ天の川は圧倒的な存在感を放っていた。名前の通り、川というよりは巨大なうねりにしか見えないそれは、よくよく見ると光の束になっているのが分かる。きっとこの天の川には何千、何万、もう数え切れないぐらいの星が集まって、ようやく目に映るんだろう。
「宇宙でもこんな風に見えるんですか?」
「そーでもねーな」
「そうなんですか?」
「オーロラも見えるし、地上からの明かりが光の洪水みてーにキラキラしてる。それが全部混じって幻想的っていうか、言葉に出来ねーロマンが宇宙にはあるんだよ」
そう語る解斗さんはいつもと違っていた。解斗さんはとても熱い人で、それをストレートに表現する。
でも、今の解斗さんは違った。熱は帯びているものの、溌剌としたものでは無い。瞳はまっすぐで、燃えているのに、ぐっと噛み締めるように零れた声が滲んで消えてしまいそうだった。
そんな解斗さんをまじまじと眺めていると、かちりと目があってしまった。私が目を逸らそうとする前に微笑みをされてしまった。いつもの解斗さんと違う、大人がするような微笑みだ。私は金縛りにあったように解斗さんに釘付けになった。
「どうしたんですか、今日」
「ん?」
「何か、あったんですか?」
おかしい。解斗さんが変に優しくて、熱い人だって言うのは分かってる。でも、こんな風に笑う人だったんだろうか。解斗さんは「いや、なんでもねーよ」と言って笑うが、その笑顔が信じられなかった。
「何かあったって言われてもよ……。名前もすっかり大人になっちまったなあ、って思っただけだぜ?」
「……なんなんですか、急に」
「名前がキレイになったと思ったんだ」
私の平静は一気に崩された。絶句どころか、思考すら一瞬吹き飛んでしまった。慌てて口元を手で覆った。バクバクとスピードを上げた心臓が口から零れそうだ。
「最初の頃は、オレのことを『百田さん』なんて呼んでよそよそしかったのになあ」
最初の頃、と言われて混乱した頭の中に浮かんだ。覚えてない訳じゃない。むしろハッキリ覚えている。珍しく怒ったときだったから。
「他人行儀みたいな呼び方はやめようぜ。堅苦しくてしょうがねー」
百田さんと初めて呼んだ時にそう言われた。
他人行儀も何も、私たちには血のつながりもない、赤の他人だ。法的にも親族ではない。父親とも、兄とも呼べる関係じゃないのに、なんと呼べばいいんだろうか。吐き出せない、モヤモヤとした気持ちが私の胸の中にあった。
(多分、そのことを話したら「血が繋がってるとか関係ねえ!大事なのは心の繋がりだろ!」と言われたに違いない。)
かといって、ムキになって「百田さん」と呼ぶのも子供じみてて嫌だった。頭の中はぐちゃぐちゃだったのに、私は、この場をどう切り抜けるか、と必死だった。
すると、ふっ、と私に何かが過ぎった。
かつて超高校級の宇宙飛行士として希望ヶ峰学園の生徒として入学、という華々しい経歴を持つ彼はよくニュースになった。初めて宇宙ステーションに行くときには異例の経歴もあって特殊も組まれたりしたからよく覚えている。
そのとき、よく決まり文句みたいに言っていた言葉があって、一時ブームにもなった。確か、宇宙に轟く百田−−。
「解斗さん」
「ん?どうした?」
ふと口から零れた声をあの日と同じように解斗さんは拾って笑ってくれた。星の光が映り込んで、銀河を押し込めたようにきらめく瞳に私は目を奪われていく。喉元から何かがせりあがって、押さえ込んでいた手の力が緩くなっていくのが分かる。
解斗さん、どうしてこんなに親切にしてくれるの?
私がお母さんの娘だから?
お母さんに頼まれたから?
もう分からないことだらけだった。
胸の中でぐちゃぐちゃした気持ちが湧き出て、消えて、残った思いを解斗さんにぶつけたくて仕方なかった。
「私っ」
「名前?」
名前を呼ばれて、私はハッとした。
「……コーヒー、いれてきてもいいですか」
返事は聞かなかった。解斗さんが何か言ったかもしれない。それでも私は解斗さんの腕から逃れて、キッチンへと足を運んだ。息を数回吸い込んで、心音を緩やかになっていくのを感じ取った。
俯いた私はマグカップの中身を見た。並々と入ったコーヒーが微かに揺れている。映し出される私の影やコーヒーの色が分からないほど、闇に溶け込んでいた。その中で、星の光がコーヒーの水面に反射している。少し飲むのをためらったけど、おそるおそるマグカップの淵を口につけた。
もう冷めてしまったそれは、苦味や酸味よりも、ミルクのまろやかさよりも、角砂糖の甘ったるさが主張し始めた。ざらり、と溶けきらずに砂糖が崩れて、マグカップの奥底で溜まってどうしようもない。
「名前」
私を呼ぶ声が聞こえる。
(2017,11.08. )