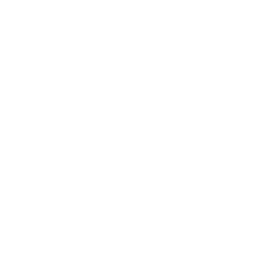もう呑まなきゃやってられない。
新しい季節の始まりということで名字には仕事が立て込んでいた。おかげ様で限界値オーバー寸前になり、息抜きでもしないとまずいと感じていた。
半ばヤケクソで名字は仕事帰りに近所のスーパーに寄った。缶ビールとチューハイとハイボール。ついでにミニワインボトル。さらにいくつかおつまみを買った。
本当に今すぐ呑まなきゃ倒れるレベルで疲れていたせいか、スーパーを出てすぐに袋から適当に缶を取り出す。
プルタブに爪を引っ掛けるとプシュと間抜けな音を立てて、穴が開いた。独特のアルコールと麦の香りが空気中に微かに広がる。それを煽れば、今度は強い香りと共にシュワシュワと弾ける液体が喉に流れ込んできた。1口、2口、と飲み込んだところで、ぷはっと息を吐く。
あぁ、生き返る。
さっきまで歩くのもやっとだった体が今では生き生きとしている。酒というのはエリクサーのように、適量であれば人に生きる力を与えてくれるものであると痛感した。名字は左手にレジ袋を、右手には缶ビールを持って、ふらふらと夜の道を歩いて帰った。
名字の家は家賃が安い分、駅から離れている。(家から駅までバスは走っているが、本数は少ない。)しかも山の上にあるのだから行きはよいよい、帰りはつらい。それでも名字がここを選んだのには理由があった。
ちょうど今が見頃かな。
名字の足取りはとある公園に向かっていた。
山あいにある公園は大型遊具があり、割とファミリー層に人気が高い。それにあちこちに桜が植えられていているのだ。難点を上げるとするならば住宅地からも離れ、駅からも遠いところだろうか。その為、知る人ぞ知る隠れ夜桜スポットでもある。
辿り着いた公園には誰もいなかった。名字は服が汚れるのを気にせず、プラスチックで出来たカラフルなお城のてっぺんを目指す。たどり着いた巨大すべり台の頂上で名字は景色を眺めた。
見渡す限りの桜。公園が桜で埋もれている。満開の桜が群れをなして入道雲のように見えた。大地には満開の桜。夜空には満ちた月。ありきたりな表現をするなら、本当にまるで夢のような幻想的な景色だった。名字の心臓が高まって気付けば口ずさむ。
「ゴメンね、素直じゃなくて。夢の中なら云える」
あれ?なんでこの曲をチョイスしたんだろう?と、どこか遠くにいる冷静な名字が不思議そうにする。それでも、まぁいっか!と思って続きを歌うのだから、また遠くの名字がだいぶ酔っ払ってるなぁと呆れている。
「月の光に導かれて、何度も巡り会う」
そこで名字の歌は止まった。その次の歌詞が思い出せない。せっかくのサビなのに。なんだかもどかしい気持ちになって、微かな記憶を頼りに言葉ですらない声を発した。
「星座の瞬き数え、じゃないの?」
「あっ、それそれ!」
わだかまりが解消して高らかに続きを歌おうとしたが、名字は不思議に思った。誰の声?と。
振り返ればそこに子供がいた。子供と思ったのは小柄な体格から。肩につきそうなくらいに長く、外巻きにはねた髪。黒々とした丸い目は幼い印象を与える。全身真っ白なコーディネートに、服と同じくらい白い肌。先ほどの声の高さから、子供が彼なのだろう。そう、彼と分かってはいるのだが、女の子顔負けの美貌を持つ彼に名字は見とれてしまった。
「あれ?歌わないの?」
「えっ、えっ、誰?」
「誰でもいいでしょ?」
まさかの返しに、名字がまた「えっ、えっ」と戸惑いの声を口に出すと彼は楽しそうに笑った。
「ちょっと、壊れたおもちゃみたいな反応しないでよ。オレが悪いみたいじゃん。オレだってさ、こんなことは言いたくないんだよ?でも学校で習わなかった?『知らない人に名前を教えちゃいけません』って」
「習ったけど……」
「じゃあしょうがないよね!オレは悪くないよ!」
間違ってはいないが腑に落ちない。しかし頭がフワフワした状態の名字はそこで考えるのをやめてしまった。
「というか、キミ、子供じゃないの……。ダメだよ?こんな夜遅くに出歩いちゃ」
「オレは何をしても許されるんだよ」
にししっと笑う姿は月明かりに照らされていて、名字は戸惑う。可愛らしいのに不気味。美しいのに、胡散臭い。笑顔一つで様々な印象を名字にもたらした。この幻のような景色もあって、彼がこの世のものでもないような気もした。もしかしたら彼のような姿を悪魔というのかもしれない。ぽつり、名字はそう思う。
「それでお姉さんは何をしてたの?」
「月を見てて、歌ってました」
悪魔だったら嫌だなあと名字は呑気なことを考えて、バカ正直に答えた。
「ふうん。嘘じゃないみたいだね」
「嘘をつく理由があるの?だって、キミ聞いてたじゃない」
「いやー!実はさ、ひどい音痴で聞いてられなかったから聞いてないんだよね!」
「あれ、聞いてなかったの?うん……?聞いてたの?どっち?」
彼に質問をすると、大きな目をくりくりさせて名字を見た。えー、とか、あー、とか困ったような声を口にする。
「……お姉さんさ。めっちゃ酔っ払ってるよね?」
「酔っ払ってないない」
絶対に嘘でしょ……。という彼の呟きは聞こえなかったのか、名字は不思議そうに彼を見つめる。
「なんでキミはここにいたの?危ないよ?」
「お姉さんに言われたくないんだけど」
「確かにそうだね!」
ケラケラと名字が笑い飛ばすと、彼はため息をついた。
「普通知らないヤツにはさ、警戒しなきゃダメじゃないの?」
「それこそキミに言われたくないよ。もし私がショタ好きの誘拐犯だったらどうするの?」
「まさか酔っ払いに説教されるとか……。え?お姉さん、ショタ好きなの?」
少年が名字から三歩ほど距離を取った。
「例え話だってば!それに私が好きなのはイケメンだよ」
「うわっ、包み隠さず暴露したね!」
再び笑顔を見せた彼に名字は泣きたい気持ちになった。イケメン好きで何が悪いのか。
「お姉さん、ここで花見しようとしてたの?」
「えっ、そうだけど」
「オレも一緒に花見していい?」
「うーん……。いいよ!」
名字が二つ返事だったのは、彼ともっとしゃべってみたいとも思ったからだ。そして何よりこの美しい景色に美少年と過ごすという格別感を味わってみたかったという邪な思いがあったことだ。
「あたりめにビーフジャーキーって……。お姉さん、オヤジ臭いよ?」
ガサガサとスーパーの袋から名字の買ってきたものを取り出してみて、彼は呆れた。
「おいしいよ?」
「おいしいけどさ!もっと、こう。女子っぽいチョイスを……おっ。これとかいいんじゃない?オレ、これにする」
「ボッシュートです」
「ええー」
彼の手から名字は慌てて回収した。名字の手にあるミニボトルにはブドウの写真とフランス語がおしゃれにデザインされているが、ラベルには『おいしい赤ワイン アルコール分4%』と書かれている。
「いくらなんでもダーメ」
「ケチ」
「うふふ、後10年ぐらいしたら飲めるわよ」
「ちょっと、オレは10年しなくても飲めるんだけど」
「またまたー。ご冗談を」
「ひっ、ひどいよ……。本当のことなのにさ……」
とうとう「うわーん」と彼は泣き出してしまった。これには名字も困ってしまう。しかし袋の中身はビールにハイボールにチューハイ。それから名字の手にある赤ワイン。彼に飲ませられるような飲み物は他にない。
「しょうがないな……。お酒はダメだけどジュースなら奢ってやろう」
「9本でいいよ!」
「わー謙虚だねー。でもお姉さんの懐には1本分のお金しかないので、1本しか買いません」
「何それ!ぬか喜びじゃんか!」
声では怒ってるように聞こえる。しかし立ち上がって「もー、炭酸飲むまで許さないからね」と言うあたり、そんなに怒ってないようにも聞こえる。
「せっかくだしワープゾーンを使おう。その方が早いよ」
「ワープゾーン?……あぁ、なるほどね」
彼は名字の言わんとすることが分かったのか、穴の中に足を突っ込んだ。落ちないように淵に腰かける。
「ほら、早く」
「あー……。失礼するね」
彼の邪魔にならないように、彼を足で挟み込んだ。彼の思った以上に細い腰に背後から腕を回した。ぎゅっと抱きしめたら彼の香りがした。ほのかに甘い、けど甘すぎないリンゴのような果実の香りだ。
「苦しくない?」
「全然!」
彼の髪の毛がくすぐったいこともたむて身動ぎをすると、離さないように組んだ名字の両手に彼が手を重ねてきた。彼が触れた瞬間ドッと強く心臓が胸を叩いた気がする。
「しゅ、出発!」
心臓の音聞こえてないかなあ。内心ドキマギしつつ、名字は体を前へ倒した。重力に身を任せて、真っ暗な穴の中へと滑り込む。うねりを上げながら、どんどん速度は加速していく。風で前髪がへばりついてうっとうしさを感じ始めた頃、視界が開ける。そう認識したときには彼と名字の体はクッションの上に投げ飛ばされた。
「うっわ!やばいやばい!早かったね!」
「アッハハハハ!お姉さんの語彙力のほうがやばくない?」
「確かにー!」
それでも頭の中にしかやばいという言葉しか浮かんでこないのだから、名字の頭は相当やばいことに間違いない。
「お姉さんさ、会ってすぐにこんな心許しちゃうなんて普通じゃないんじゃない?」
服についた砂を払いながら彼はそう言った。
「そういうキミも普通じゃないでしょう」
「あれ?そんなこと言っちゃう?」
目を細める彼に嫌悪は感じない。むしろ指摘されて楽しそうにくるり、と一回転する。
「桜もだけどさ。こんなに月夜が綺麗なんだから、普通ではいられないよ」
月光をスポットライトにして、散りゆく桜の花びらを背景にして踊るように回る彼はやはり美しい。しかも両手を広げたことで白い袖が羽のように見えた。もしかして彼は悪魔じゃなくて天使かもしれない。どこか遠くにいる名字がまた呆れてる気もしたが、本当にそう見えたのだ。
「そうだね」
「にししっ。お姉さんもなかなか風情ってものがあるんじゃない?」
「そうかなあ?」
「オレが言うからにはそうだよ」
彼が発する言葉には時折ジャイアニズムが混じる。でも何故かそんなに高圧的だと感じないのは名字の気分がいいからかもしれない。
「ねぇ、せっかくだから楽しいことしない?」
名字の自由奔放な発言に彼はニヤリと口角をさらに下げた。
「へぇ。言ってみなよ。つまらなかったら……どうなるか分かってるよね?」
彼の言うツマラナイが名字には分からなかったが、名字は言うだけ言ってみることにした。
「遊ぼう!」
名字の酔狂な発言に彼はきょとんマヌケな顔をした。もう十分に歩いて、会話もしたからアルコールを抜けてると彼は思っていたが……。名字の頬はまだ紅潮している。
「お姉さんってさぁ……。面白いよね。いや、面白いってよく言われるでしょ……!」
「そんなことないよ!今日が初めてだよ!」
「嘘はやめてよ。オレは嘘が嫌いだからさ」
「嘘じゃないよ」
「嘘だ!面白くなきゃこんなこと言わないって!」
肩を震わせながら必死で笑いを噛み殺しているが、彼の口元は歪に歪んでいる。
「だって天気もいいし、満月だよ?桜だってきれいに咲いてるし、誰もいない。もったいないよ。貸切状態なんだよ?私達だけのものなんだよ?きっとこんな日は今しかないんだから堪能しなきゃ」
名字の言葉を聞いて、彼はパチパチと目を瞬かせた。まつ毛が大きいなあと思っていたら、彼が名字に顔を近づけた。とても愉快そうな顔で。
「お姉さんがそこまで言うなら遊んであげてもいいよ?」
「えっ、いいの?やったー!じゃあ、ブランコ!ブランコしよう!」
そこから名字と彼は遊びに惚けた。ブランコでは二人乗りをしたり、シーソーを何度も漕いだ。他にも飲み干した空き缶を使って意味の無い缶蹴りをしたり、砂山で城塞を作った。途中で疲れて自販機で炭酸を買ったり、花見をしたり、また遊びを再開したり、思いつく限りの遊びをやり尽くしていった。
しかし、そんな時間も長くは続かない。星が空に溶け始めてきたのだ。
「あぁ、もうそろそろ夜が明けるね」
「じゃあ、帰ろうか」
名残惜しい気持ちはあるが、いつまでもこんな風に遊んではいられないのだ。東の空が淡い色に変われば、月が西に沈んでいく。
「付き合ってくれてありがとうね。すごく楽しかった」
「オレもそれなりに楽しめたからいいよ」
それなりに、という割にはずいぶんと満足気に笑うのだから名字もつられて笑顔になった。
「ねぇ、お姉さん。名前は?」
「……誰でもいいでしょう?」
してやったり、と名字が笑うと彼は目を丸くした。そしてすぐに不機嫌そうに唇を突き出す。
「名前が分からなきゃ次、会えないじゃん」
「ふふ、『知らない人には名前を教えちゃいけません』って学校で教わったから。」
それに今日のことを思うとお互いの素性なんて知らない方がいい。なんとなく、名字はそう思ったのだ。さすがに彼も自分で言い出したことをねじ曲げるのは癪だったのか名乗ることはしない。彼は少し考えて、名案だというように名字に言った。
「そこまで言うなら見つけてあげるよ」
うん?と名字は首を捻る。
「何それ鬼ごっこ?」
「鬼ごっこ、ね……。そうかもね!オレがお姉さんを見つけて、名前を当てれば勝ちってことで!」
自己申告した割にはずいぶんと彼にとって厳しいルールである。どうせ子供の言うことだし、まぁいっか!と名字は考えることをやめてしまった。
「いいよ。それじゃ、私逃げてあげる」
「にししっ、約束だからね」
彼が小指を差し出す。名字は彼の小指と絡めた。
「指切りげんまん、嘘ついたら……」
そこで彼の口ずさむ声が止んだ。
「どうしたの?」
「オレ、痛いのはイヤなんだよね。嘘ついたら、別のにしてもいい?」
「何にするの?」
「社会的に殺す!」
「ハイ、ダメ」
「えぇー」
不満なのかブーイングの声を荒らげる。痛くはないがつらいのもNGだ。「もう少しまともな案はないの?」と名字は彼に尋ねる。
「じゃあ、相手の家を掃除するってことで!」
「それはなかなかやりたくないね」
「だったら約束破らなきゃいいんだよ」
「それもそっか」
「じゃあいくよ。ゆーびきった!」
名字と彼の小指がほどけた。きっとこれでお別れになってしまう。
「お姉さん」
一度目は何をされているのかよく分からなかった。ようやく理解したのは二度目だ。角度を変えるようにして彼はキスをする。唇と唇をただ重ねているだけなのに、触れ合ったところから熟れた果実の味がした。
「……オレのこと忘れちゃやだよ」
「えっ、えっ、うん?」
キスなんてなかったように平然と尋ねるから名字は今のが夢ではないかとパニックになった。そんな名字に満足したのか彼は微笑んだ。そして別れの挨拶もせずに立ち去っていった。
しばらくして夜明けの光が差し込んできた。そっと唇に触れる。あの柔らかな感触と残り香が確かにある。
−−オレのこと忘れちゃやだよ。
もうここにはいないはずの彼の声が聞こえて、名前も分からない彼に囚われ始めていることに名字は気付く。その事実が分かっていても、名字の指は唇をゆっくりとなぞった。
月の光に導かれ、何度も巡り会う。
彼なら出来てしまうような、そんな予感がして。
(『ムーンライト伝説』より一部歌詞引用)
(2017,11.19. )