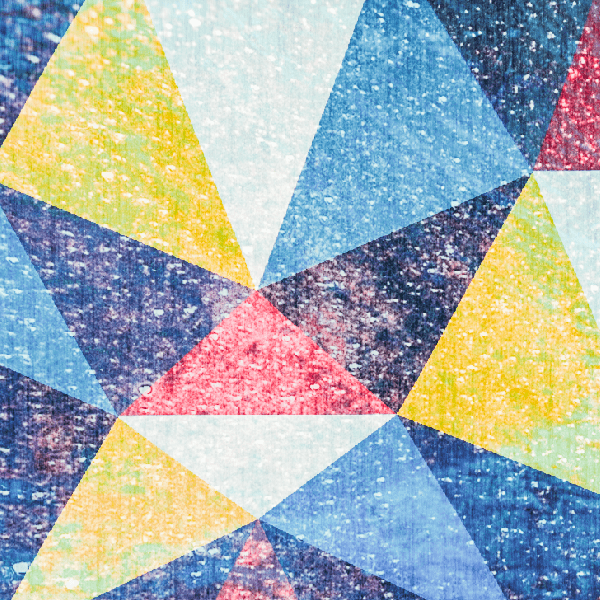
親切と愛情が分かりにくい
「あっ」
「あ〜!お前、またか!」
「あーあ。ほら、監督生上向くなって」
「ん……ごめん」
ぼたぼたと何の予兆もなく滴り始めた赤い液体に思わず声を出せば、グリムがすかさず大きな声を上げた。瞬間的に座れる場所を探すデュースと、私のポケットからティッシュを取り出し鼻を押さえるエースは、この短期間で随分と手慣れた様子である。申し訳ない。
「平気だよ。ごめんね、驚かせちゃって。……えっちょ、痛い。詰め込み、過ぎだよエース」
「わりぃわりぃ」
「何をやっているんだお前は……」
「お前、本当に病気とかじゃないのか?」
胡乱気なグリムに苦笑を零して首を振る。病気ではないのだ。ただただ、鼻血が出やすい体質なだけで。
物心ついた時から、私の記憶はたいがい鼻血とセットで存在する。
粘膜が弱いのだろう。強く鼻をかめば鼻血を出し、大きくくしゃみをすれば鼻血を出し、満員電車でのぼせては鼻血を出し、楽しい予定でちょっと興奮すれば鼻血を出し……出し過ぎではなかろうか。
そんな感じなので周囲の人間は「あぁ、またか」と気にせずにいてくれたし、その通りしょっちゅう起こる事なので私もその方が気が楽であった。しかし、ひょんな事から呼び出されたこの異世界の住人達は揃いも揃って頑丈な人達ばかりで、過剰に心配をされてしまう。嫌ではないけれど、申し訳ない。
「血を止める魔法!とか、ねーのかな?」
「血を止めたら死ぬだろう」
「なら、血が流れない魔法とかは、どーなんだ?」
「同じだろう!」
わいわいと騒ぐ二人と一匹は今日も今日とて楽しそうで、こちらまで心がぽかぽかしてしまう。一昨日始めて現場に遭遇したイデア先輩は奇声を発しながら保健室に運び込んで下さって……彼らが早めに慣れてくれて、本当によかった。
「ごめん。少し休んでるから、先に食堂行ってて」
「分かったゾ!」
「あっ、コラ待て!置いてくなよ!……先、行ってるな!」
「……名前。本当に大丈夫か?」
「ん?うん、平気。何か、軽いパン一つ保護しといてくれると嬉しいな」
「あぁ、分かった。任せておけ」
小さな青を追いかける二人を、鼻を押さえつつ見送る。さて、少し気分が悪いし中庭で休もうかなぁ。なんて呑気に考えながら振り向こうとした体が、強く引かれてたたらを踏む。
「うっ、は!?」
「うるせぇ」
顔を上げれば小麦色の肌に可愛らしい動物の耳。なんでこんな所に。というか、急に腕を引っ張らないで欲しい。驚いた拍子に廊下を汚してしまったらどうするんだ。
「ちょっと、どこ行くんですか?……あの、レオナ先輩、聞いてます!?」
「うるせぇ」
腹立たしい。よく聞こえそうな角度についたその耳は飾りなのだろうか。言ったら殺されそうだから心の中で舌を出せば、ぎろりと上から睨め付けられる。彼のユニーク魔法はサトリとかそんなアレだっただろうか。
「…………チッ」
「ひぇ……いやいやいやあの待って本当にどこに行くんですか私になんの用事ですか!?」
「黙ってその汚ぇの押さえとけ」
解放されれば全て丸く収まる筈なのに、とうとう小脇に荷物よろしく抱えられ、どうしようもなくて口を真一文字に結ぶ。180を超える巨体には勝てないのだ。
そうこうしている内に連れてこられたのは彼の寝床である温室。定位置に座り込み膝の上に私を乗せる先輩の表情は相変わらず険しくて、本当に訳が分からないが、しかし何故かこちらがやましい事をした気分になってしまって視線を逸らす。今日に限って未だ治まる気配はなく落ち続けるそれが憎い。異性の上で鼻血を押さえ続けるだなんて、かっこつかないにも程があるのに。
「……オイ」
「はぁ……。あっ、駄目です。服汚れますよ」
「構わん」
そりゃあ、どうにかするのはラギー先輩ですもんね。
ぐいと剥がされた利き手を見送りながら、肌の上を血液が流れる不快感に顔を顰める。本当に落ちてしまう。何が楽しいのか見つめる先輩に視線で抗議の意を示しながら少し上を向いた、その時。
「へ、」
べろり、と。生暖かいモノが鼻の下に触れた。
「…………まっず」
「で……………っしょうね!?あっ、ちょ、」
流れ続ける赤は、この異常事態に混乱するあまり僅かに勢いを増した。決して、興奮しているとか、そういう訳ではない。
制服の胸元を汚しかけた数滴をレオナ先輩の片手が受け止め、咄嗟に後ろへ避けようとした顔はもう片手が顎を掴んで固定する。
べろり、べろり。
かぷり。
そういえばこの人、ライオンだった。
食べられてしまいそうな恐怖感に瞳を固く閉じる。普通に汚いし、先程の通りまぁ美味しいものではない。何が、したいんだろう。
一通り治まるまでご丁寧に舐め取られ、鼻の奥の感触的にも血は止まっただろうと強張っていた身体から力が抜ける。時たま甘噛みされていたので、鼻がどんな惨状になっているのかとても見たくない。
「あ、の……せんぱ、い……っ!?」
れろぉ。
はっと視界を開けば、想像よりもずっと真剣で、力強い色を宿した緑に射抜かれた。
濡らされた唇を、伸ばされた指先が軽く撫で擦る。瞳はそのままに、汚してしまった先輩の手の平が、見せつけられるように長い舌で綺麗にされていく。
どうしよう、また、出ちゃいそう。
意味もなく漏れる熱い吐息に、彼はようやく何時もの飄々とした笑顔を浮かべた。
「妙なにおいまき散らしてんじゃねぇよ。喰われても文句言えねぇぞ」
「…………それ、は、先輩に、ですか?」
「俺以外に、なんて。許してやると思うか?」
春日狂想