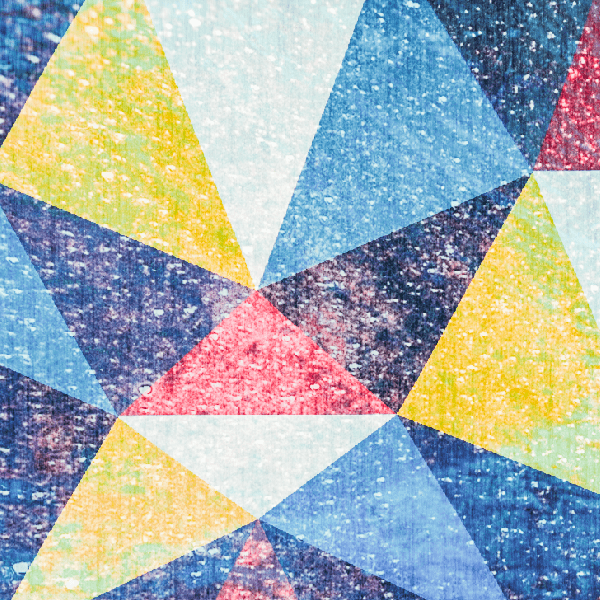
マーキングはしっかりと
「ちわーっす!お届け物でぇ…………、……あ"?」
「びぃっくりした……え、ん?ナニ……?どしたんですか、先輩」
「は?いや、え?なんスかそれ」
「どれ?」
「それ!」
みみ!
驚きのあまり、常よりやや舌ったらずな発音で告げられた部位。
耳…?と首を傾げた名前は、そうして今、掃除の為に自分の髪がポニーテールにきっちり縛っている事に気が付いた。普段は髪で隠された耳が丸見え。
つまり。
「えっ、こわ……正気と思えねーんスけど…」
趣味で開けているピアス穴もまた、丸見えなわけだ。
咄嗟に手で隠そうとする彼女だったが、目のいい彼には付けていなくとも、がっつり空いている箇所全て見えているだろう事に気が付いてがくりと項垂れる。
「すみません…その、えっと。お見苦しいものを……?」
「いや見苦しいっていうか……どういう精神状態だと、そんなバカスカ穴開けようと思えるのか、純粋に疑問っていうか……」
「精神っ…!?聞いて下さい。世界の常識が違うんです。こちらではどうか知りませんが、私の世界ではそこまで珍しいモノじゃないです!」
「特殊な趣味の人はみんな同じ事言うんスよ名前くん」
「ひどい!本当ですよ!…ここまでは、まぁ、一般的ではないかもしれませんが…。でも1つや2つならファッション感覚で男女問わず付けます!」
「えぇ……?」
未だ困惑した顔で、一先ず腕に抱えた紙袋をテーブルに置くラギー。監督生はその動作を見守りながら思考をフル回転させていた。
なんせ名前はこんな趣味なので、元々恋愛は諦めモードなタイプのオンナノコであった。ピアス開けて、パンク系の服を着て、なんならタトゥーにも興味がある。先程はちょっと盛った。彼女のちょい田舎な地元では十分すぎる程遠巻きにされてしまう。でもおんなじ趣味の男の中からまともな人を見つけるのは割と難しい。見る目がないのか運が悪いのか、8割薬をすすめてくる。1割はすぐに手を上げるし、5分5分で対面できないか部屋に連れ込まれるか。八方ふさがり出来レース。
いいんだいいんだ。恋愛しないからって死ぬわけじゃない…とやさぐれていたオンナノコだった訳だ。
が。ひょんな事から、このツイステッドワンダーランドなんて新天地にやってきてしまった。そこでとっても素敵なオトコノコに一目惚れしてしまった。恋愛経験赤ちゃんにも、早急に己の魔改造された耳を隠す必要がある事だけは理解できたという訳である。赤ちゃんなのでそれ以外は何も理解できず、一歩も踏み出せなかったが。
向こうからガンガンやってきてくれたのは本当に運が良かった。
彼女は毎日、恋した(してくれた)相手が、狙った獲物は絶対に逃さないハイエナだったことに感謝を捧げている。無神論者なので学園長を呪うついでに。
という訳なので、学園唯一の女子とかいうキラキラ補正をこんな所で無駄にはできない。
「面白くなってきたな……ちょっと見して下さいよ」
「え、これ以上引かれるのはちょっと…しんどいんですが…」
「大丈夫大丈夫。こわいなーって思っただけで、引いてはないッスよ」
「怖くないですよぉ」
「いや怖いでしょその量は。そもそも獣人はめったにピアスなんて開けないんスよ」
「あぁ……。やっぱり、敏感〜とかそういうヤツなんですか?」
「まぁね。獣耳は割と日常生活で使うし。つけてもイヤリング」
ほらほらと腕を引くラギーに素直に従う監督生は、誘導されるままオンボロソファに腰を下ろす。隣に座るラギーはそのまま前を向くよう告げて、彼女の耳に顔を近付ける。
水仕事でもしていたのか。ひんやり心地良い冷たさの指先が、監督生の耳たぶをつまんでかるく引っ張る。彼女が今唯一つけている小さな石を軽く爪先でつついて、見えないけれどきっと、視線が上へ滑って小さく主張する痕へ。
見つかってしまったショックがじわじわきている名前は何も言わずに、どうにか思考を他所へ逸らそうと必死だ。最近来客が増えたから、そろそろソファーにカバーでもつけようかなとか。先輩指けっこう華奢だなとか。グリムは陸上部へ遊びに行ったが問題を起こしてないかなとか。あの紙袋いい匂いするけど何が…あっ、掃除して汗かいてるから私今臭いかも…?
「わっ」
「ごめん。痛かった?」
「だ、いじょうぶです。びっくりしただけなんで」
「そ?いや〜、どうやって開けんのかなって気になっちゃって」
くいっと、優しく。指先が少しだけ中に入り込んで盛り上がった軟骨の部分を撫でる。
「そこは流石に、専用のお店でですね」
「わざわざぁ?ホントに好きなんスねぇ」
「はい……。お嫌い、ですか?」
「ん〜?」
答えは返ってこない。彼の指先が、続けざまに、穴をなぞっていく。
すりすりと耳たぶを擦り。
するすると耳輪をたどり。
かりかりと三角窩を掻き。
きゅぅっと耳珠を摘んで。
徐々に近づいていた口元から、はっと聞きなれない笑い声が漏れる。冷えた指先とは対象的な熱い吐息に、監督生は堪らなくなって距離を取った。
「もっ、いいですか!?」
「全然ダメっスね」
「なにがぁ!?」
シシシと響く声に、さっきまでの数十秒が夢だったかと錯覚してしまう。監督生は赤くなった頬を押さえてソファの端により、にやにや笑うラギーを睨みつけた。
「ぼーっとしてたから、つい。ごめん」
「そんな笑顔で言われても困るんですが」
「集中してくんないと」
「私が悪いんですか?」
「違うけど」
ぐっとラギーの両腕がわきの下に差し込まれて、そのまま後ろに倒れる。追うように彼の体の上にうつ伏せになった監督生は、今度こそ悲鳴を上げて目を閉じた。何もかも恥ずかしい。なんだこの仕打ちは。なにか悪いことをしてしまったのだろうか。
がっしり抱き抱える彼の腕が監督生の自由を奪う。せめてもの抵抗で肩口に顔を埋めて徹底抗戦を決意する彼女の耳に、唇が寄せられる。
温い舌が挨拶をして、鋭い歯がカチリと石を噛む。
「ぅっ……はっ、せん、ぱい」
「うんうん」
「ちょ、っと。やだ、先輩」
「やだ、はオレのセリフっスよ。ねぇ、名前」
監督生の後ろ襟が捕まれ、なんの予備動作もなく二人の位置が入れ替わる。ソファに彼女の長い髪が広がり、ラギーは目を細めて口を開く。
「なんでだろ。分かんねぇけど、アンタの体に、オレ以外が傷つけたのが気に食わねぇ」
こつり。額と額が合わさり、困惑と羞恥から浮かぶ涙が、とうとう監督生の頬を伝った。
はっと短く呼吸を整える彼女と、あはと笑う彼の熱い息が至近距離で絡まりあう。キスでもしてるみたいだ。
「ね、1回さ。穴塞いで」
「へ」
「そんで、オレがまた開けたげる。どっスか?」
とても素晴らしい事を思いついたように満足気に笑う彼は、そのまま啄むように軽いキスを監督生に浴びせる。
経験値の低すぎる監督生は突然詰め込まれたオトコの重たい感情にぐるぐる目を回しながら、とりあえず曖昧に頷いた。
春日狂想