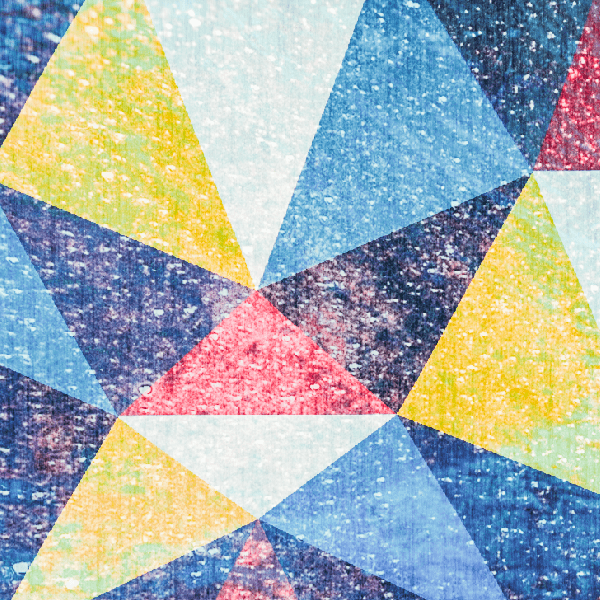
酔ってしまえば
ふらり、と。気軽な散歩でもしているかのような足取りの彼女が窓の外に写った。
風呂敷で包まれた何かを手に歩く姿はたまの気晴らしかと思えば微笑ましいが、如何せん時間がよろしくない。
ここ数日試合続きだった名前の、そのいやに揺れる背中を暫く見つめて、ジョゼフは一つ、息を吐いた。
*
「こんな時間に何をしているかと思えば……ッ!」
「おや?見られていましたか」
くふくふと笑う頬は些か血色がよくなっている。
雑に置かれた上質な布の上には、程良い砂糖とキツイ酒精の香り。目の前にそびえ立つ美しい木を見て、ようやく彼は成程と腑に落ちた。
「花見酒、ですよ。むしろ何をしていると思って着いて来られたんですか?」
「夜な夜な怪しい術でも仕掛けているのかと思ってね。ほら、日本の女性は真夜中、木に人形を縫い付けるんだろう?」
「酷い言いがかりだ。怒りましたよ。お詫びに少し付き合って下さい」
「えぇ……君、寝た方がいいんじゃないかい?夜も遅いし、疲れているだろう。悪酔いするぞ」
「疲れすぎて、眠れないんですよ。こういう時はお酒に限る。一人酒も乙なモノですが、今日はそんな気分でもないですしねぇ。……あぁ、それとも、試合終わりのハンター様はお疲れでいらっしゃる?」
隈の出来た顔でよくもまぁ言えたものだ。
ひくりと口端を引き攣らせた表情へ今の感情を全て載せたジョゼフに、再び軽やかな笑い声。
「あぁ、ごめんなさい。そうか、もうお年だから、お酒は身体に宜しくないですよね」
「いただこうか」
「……んっ、ふふ……、えぇ、えぇどうぞ!お口にあえばいいのだけれど……洋酒も持ってくればよかったな」
共用のキッチンにあるのは基本、ビールやワイン。つまりここにあるのはわざわざ名前がナイチンゲールにわざわざ注文して手に入れた代物だ。
嗜む程度にしかアルコールを口にしないジョゼフは内心理解出来ないと首を傾げたが、声に出したら最後、良く回る口でけちょんけちょんにされてしまう事は想像に難くないので口には出さなかった。
渡された小さな杯の中身を一舐めして、ジョゼフの眉が僅かに寄せられる。
「……面白い味だな」
「ちょっとクセが強かったですかね。ん〜……此方は?」
「あぁ、うん。美味しい」
「良かった。口当たりはいいけど度数は強いので、休み休みどうぞ」
「…………呑む方だと思ってはいたが、ここまでだったとはね」
「あら、お酒に強い女はお嫌い?」
「節度を弁えているなら構わないさ」
「それ、貴方の場合興味がないと同義でしょうに」
酷い人、と唄うように紡がれる。
ついと向いた名前の視線の先には、儚い薄紅。この不思議な荘園では、東の国々の四季に合わせて時が巡るというのに年中様々な植物が生息していた。見た事もない草木も多い中、この花弁は確かに一際美しい。ジョゼフも数度、相棒たるカメラにおさめている程だ。
「サクラ、と言ったかな。日本人は季節になると、この木の下で宴をするんだったか」
「えぇ、今度はおおむね正解です。大本を辿れば神事に属するのですが……まぁ細かい事はいいでしょう。本来の意図が忘れ去られたとしても、この花を想い人が集うだけで意味がある」
「奥が深いんだな……。あぁ、そういえば。君達は儚さを特に愛でていないか?このサクラも。すぐ散るが、その姿が一番だと美智子が言っていたよ」
「満開になれば最後一週間と持ちませんね。ほら、日本人は繊細ですから。終わる事に美しさを見出して安堵したいものなのですよ。そも、自然災害の多さゆえに発展した心理と言われていますから」
終焉を迎えるそれを繋ぎ止めようとは思わないのか。
美しいモノはそのまま、永遠に。
そんな疑問もお見通しなのだろう名前は、どこか困ったように微笑みながらジョゼフのグラスに酒を注いだ。
気が付けば、随分と進んでいたらしい。少しばかりぼんやりする頭を軽く振った彼は、じいと彼女の瞳を見つめる。
己の生涯をかけて達成せんとした目的とは根底から異なる思想を聞いて、沸き立つ筈の苛立ちや嫌悪は、何故か極々薄かった。あの花のせいなのか、それとも、酒のせいなのか。
「……ここから先は、主語を小さくして話さなければならないでしょうが。少なくとも私は、永遠が、怖いです」
「……怖い?」
「はい。終わりが無いのは恐ろしい。続けていかねばならないのだという圧が、怖い」
ありがたみがないだとか。
終わる姿が美しいだとか。
それが世の理だからとか。
聞き飽きた文句がどこにもない驚きを隠しもしないジョゼフに、彼女は変わらぬ笑顔を浮かべ続ける。
「臆病なだけ。終わりたいんですよ。死にたい訳でもないけど、殺したい訳でもない。終焉に美しさを見出すこれは結局、恐怖が薄らぐからこその利己的な思想です」
そっと、地に置かれていた指先がジョゼフに伸ばされる。やや乱れた白銀の髪を整えるその仕草に合わせて、甘く優しい名前の香りが広がった。社交界で培った話術で茶化してしまえるまたとない機会だというのに、どうにも声がかすれて、ジョゼフは何も言えなかった。
「諸行無常を重んじる東洋人であろうが、そうではない西洋人であろうが。口では何と言っていても永久への渇望はあって然るべきだと思います。だから、これはあくまで私の話です。臆病で、考え過ぎで、寂しがり屋で、二の足を踏んでばかりの私の話です。と、いうことですので、怒っちゃいやですよ」
静かな口調の心情は、だからこそ確かな形をもってジョゼフへ届いた。深い黒に映る風に乗った花弁が目を引いて、まるで彼女の瞳そのものが夜空の一欠片のようだ。見つめ合いそれを眺めたジョゼフは、何故だか無性に、泣きたくなった。
理解のできない言葉だ。同調できず、共感も出来なかった。
それでも、するりと耳に入り込んだそれは、酷く大切なものなのだろう事は分かった。
彼女の視線が、目の前の大樹へ。
情けなくも固まったままのジョゼフは、音にならない感情を必死に飲み込みながら彼女を見つめ続ける。何時の間にか頭から離れていた小さな指先は、そのまま冷えた彼の指先を包み込んでいた。
「…………やっぱり、理解しがたいな」
「ふふ。それはまぁ、そうでしょうとも」
「理解しがたいが、そうだな。まぁ、今は気にしないことにした」
彼女を閉じ込めてしまいたかった。永久を共にしたかった。もしそれが叶ったならば、きっと素晴らしい時で満ちてくれるだろうと思った。
これだって突き詰めれば、もしかしたらどこか片隅で寂しさを恐れていたからなのかもしれない。
だが生憎と、全部筒抜けだったのかと落ち込んだのは一瞬だ。
だって、まだ。不純な願いに彩られていた想いは、終わらせられないから。
そっと離れようとした温もりを器用に絡め取った男の手に、今度は彼女が固まった。
「まぁ、この地獄から逃れる術はまだ無い訳だからね。ひとまずこのまま駆け引きを楽しませて頂こうかな」
「あれ、おかしいな……?まさかジョゼフさん、結構酔ってらっしゃる?」
「それは君だろう?先程から語尾のイントネーションが怪しいぞ。ところでレディ。もしよろしければ、このまま私の部屋までいかがかな?二人とも明日は丁度休みだ」
「えっいえあの、そうですね。日本人は奥ゆかしいのでそういうお誘いはちょっと」
「今更何を言ってるんだか」
途端慌てだす名前へ胡乱気な眼差しを向けたジョゼフは、記憶を漁ってからにっこり子供のような笑顔を浮かべた。
「そういえば、美智子はこんなうた…?を教えてくれたよ。この状況にぴったりだ」
ころりと転がる杯は気にせず、腰を引き寄せる。
「花は口実、お酒は道具、酔ってしまえば?」
「で、できごころ……?」
そもそも、こんな薄い着物一枚で。こんな夜更けに。男と二人きり。
目的の為に手段を選ばないのは結構だが、自業自得というほかない。
「気長にすり合わせていこうか」
「お、おかしい……こんな筈じゃぁなかったんですが」
詰めの甘い彼女がうーんと首を傾げる。先程までの、心がざわつく嫌な静けさはどこかに消え去っていた。
花を口実にするなんてとんだ奥ゆかしさだ。
ジョゼフは笑って、彼女の体を抱き上げた。
春日狂想