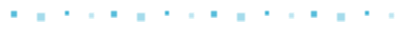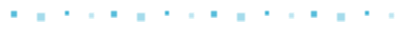
芽生えだした
ひゅうっ。
「っ……!」
吹き抜けた風の冷たさに思わず身震いする。
癖で体を温めようと腕をさするが、気休めにしかならない。
「狗縲?」
前を歩いていた唯が立ち止まって、振り返る。
こちらの様子に気づいたのか、彼は数歩分の距離をわざわざ詰めるとわたしが自身を温めようとする手を、自然な動作でとった。
「寒いのか?さっきから風が冷たいよな」
「う……うん」
何の前触れもなく唯に触れられて、急に気持ちが落ち着かなくなる。
互いの気持ちが通じあって長いというのに、未だに彼からの接触には慣れないところがある。というのも、唯はスキンシップがかなり少ない方の人だからだ。
毎晩一緒に寝てはいるが、手が触れるか、肩を寄せ合うくらいのもので、将来を誓った男女にしては本当に何もしていない。
せいぜい手を繋ぐことぐらいが肌の触れ合いだろうか。
しかも、それすら唯からのお誘いで繋ぐことはあまりない。わたしがほとんど甘えているような状態だ。
だから、いきなり唯から触れられると驚く。そしてやたら緊張してしまう。
唯は冷たいわたしの手をしばらく握ると、空いている方の手も掴んで両手で包んでくれた。
そして少しでも温めるようと手の甲を擦ったり、口許まで引き寄せてはーっと息でかけてまた握ったりする。
わたしはただ固まってそれらの一連の動作を眺めていた。
息を吐く時の懸命な表情が、
少しだけ大きい骨張った男の子の手が、
握るときの強くて優しい力加減が、
一つひとつが全部、わたしの心臓を落ち着かなくさせる。
そうしてまた自覚する。
わたしは唯が好きなんだと。
「んー……よく考えたらさっさと帰った方が温かいな!よし、ちょっと急いで帰るか」
「わっ、わっ……ぁ、うん。うん」
思い付いたように言って、ぐいと左手を引かれる。
思わず重心を崩したけど、なんとか耐えて唯の歩調を追う。
「ホント、今日は寒いな〜。なんか温かいもの食べたいなぁ」
「え……あぁ、うん。そうだ、ね……唯は何が食べたい?」
「そうだな〜……去年作ってくれた鍋とかうまかったからまた食べたい!あ!おでんっていうのも美味しかった!あれもいいなぁ」
唯は楽しそうだけど、こっちは繋がった手の温かさが気になって気が気でない。
なんとか話を理解しようと途切れ途切れになる思考で唯の言葉を拾う。
温かいもの……去年のな……な、鍋。お鍋が、美味しい?そうか、唯は喜んでくれたのか……ならまた作ろう。うん。
「じゃ、お鍋……しよう。しよう……」
「そっか、今日は鍋かぁ……すっげぇ楽しみ」
唯が首だけ振り返ってにへと笑みを見せる。
それに曖昧な笑顔を返しながら、わたしは繋がっている左手にそっと力を込めた。
+++
カチャカチャと狗縲が片付ける音を聞きながらソファの上でリラックスする。
夕飯の鍋はめちゃくちゃ美味しかった。まあ、狗縲が作るものはなんでも美味しいけど、寒いときの温かいものはいつもよりうまさが引き立ってる気がする。
食後の満足感にどっぷり浸かっていると、いつの間にか片付けを終えた狗縲が隣に座った。
隣、と言っても若干距離がある。
あと、狗縲はソファの上に正座していた。
何か変だ。
「狗縲?」
「なにかな?」
「どうかしたか?」
「……何も」
ちょっとだけ考えたような気がする間があった。
顔を覗き込んでみると、黒光する大きな眼と目があった。
じっと見つめると、じっと見つめ返される。
しばらく互いに見つめ合ってると少しだけ狗縲の瞳が柔らかくなった。
それを見るとゾワゾワとしたものが背中を上ってくる。
不思議な気持ちを逃がすように小さく息を吐くと、狗縲が微かに身じろぎした。
心なしか、頬に赤みが増したように見える。
ヒヤリとしたものが肌を伝う感触がした。オレは今、多分焦っている。
こんな感じの経験は初めてじゃない。むしろしょっちゅう起きている。
ドクドクと心臓がうるさくて、首辺りに変な汗が出て、やたら顔が熱くなる。
狗縲に触りたい。
衝動的にそう思う。
だけど触ってはいけないという気持ちが体に制止をかける。
理由はわからないけど、壊してしまう気がする。
顔を赤くした狗縲はいつもの堂々とした雰囲気がなくてなんだかふんわりとしてる。
触れたらきっと温かくて、くっついて離れられなくなるような気がする。
それは魅力的なのに、すごく怖い。
だからいつも、この気持ちになると動けなくなって、結局なにもしない。
一緒になって寝る頃には落ち着くから、これといって問題もないけれど。
だけど、今日だけは少し違った。
狗縲が静かに手を伸ばしてきたのだ。細い左手がオレの右手に近づく。
まず中指が触れた。それから薬指、人差し指も重なって、指の付け根まで指と指が重なりあう。
どっと、背中を上ったあの放流が胸の中に広がった。
ちょっと前までの自制なんて真っ白になって、気がつけば狗縲の左手に指を絡ませて握りしめていた。
「ぁ……」
狗縲の唇から小さな音が漏れる。
それに合わせて右手に少し力を込めた。触れ合った手は信じられないくらい熱い。
「なぁ、狗縲……」
「なに……?」
「これ…………イヤか?」
ぐっと手に力を込めて狗縲を見やる。いつの間にか俯いた顔は黒髪に隠れて見えない。
だけど、黒髪の隙間からのぞいた耳が真っ赤になっているのはよく分かった。
やがてか細い声が返事をする。
「……ううん」
それだけで十分だった。
繋がった手の熱さを感じながら丸まった狗縲の体を見た。
この目に写るその全てを腕の中に閉じ込めてしまえたら、もっともっと温かくて、たまらなく幸せになれるかもしれない。
そんなことを考えた。
++++++
恋人期の二人。
唯が少しずつ狗縲を恋人として意識し出したけど、狗縲からしたら積極的な唯にあわあわ困惑するみたいな頃。
狗縲は奥ゆかしさと積極性を兼ね揃えてるから唯からの求愛(?)に固まりつつ、吹っ切れたらきっとエスコートし出す気がする。
戻る
小説トップへ戻る