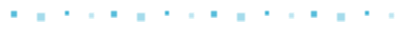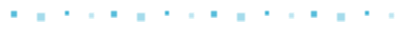
竜人2
それを見つけたのは、本当に偶然だった。
いつも通りのつまらない学校の帰り道、ふと目を向けた路地の影にキラリと光るものが見えた。
なんとなくそれが気になって、普段は絶対に近づかない路地に入った。
細かいゴミが転がる暗がりを進めば、光ったものの正体がハッキリと分かる。
銀色の細い糸の束。
地べたに散らばった美しいそれは、全てが一ヶ所に集まっている。
思わず目を疑った。
「え…ひ、と…?!」
輝く銀髪を持った、自分よりも小さな人間が汚い地面に倒れていた。
ほっそりとした手足に、汚れたスカートでその人が女であることが分かった。
うつ伏せに倒れて顔は見えないが、汚れている白い衣服は可愛らしいデザインであるのと小さな体から年は中学生くらいだろうか。
まじまじと観察をしてからそんな場合ではないことに気付き、慌てて少女に近寄る。
こんな人気のない場所で年端もいかぬ少女が倒れてる時点でただ事ではない。
白状すれば関わりたくない。
回れ右をして何もかも忘れてしまいたい。
けれど、ここまで近づいておいて見ないフリは流石に無理だった。
傍らに膝をついて(膝が汚れたのが大分不快だ)、少女の肩を掴む。
「おい、大丈夫か……」
抱き起こして、息を呑んだ。
少女の露になった顔は見たこともないほど綺麗だったからだ。
白磁のようにきめ細かい肌に、長い睫毛。
鼻は低すぎず、かといって高すぎることもない。
ふっくらとした紅色の唇は不思議と目を惹いた。
美少女という言葉は、まるで彼女のためにあるのではないかと思ってしまう。
それほどまでに愛らしい少女だ。
瞳が閉じられていることが酷く残念でならない。きっととても綺麗な目をしていることだろう。
「ん…?」
今、僕は何を考えた?
邪な気持ちを振り払うように首を左右に降る。
急いで少女を介抱するのが先決だろうと気を引き閉めて、小さな体を抱える。
「ねぇ、キミちょっといーい?」
不快な声が背後から聞こえたのはその時だった。
首だけ振り向けば、やたらシルバーアクセサリーをつけた男がこちらを見下ろしていた。
「キミの制服さぁ、宝嶺高校のでしょ?」
「……だったら何?」
「キミ金持ちだよねぇ、だから小遣いオレにちょーだいよ」
ふざけるなこの野郎、そう舌打ちしたくなった。
たまにこういうふざけた奴がいるのは聞いたことがあったが、まさか自分が標的になるとは。
腕の中の存在を少し呪った。
「ん?その子なぁに?」
少女に気づいたんだろう。男はじゃらじゃらとアクセサリーを鳴らしながらこちらを覗き込んでくる。
隠すように抱え直すが、目敏い男は汚い目をギラギラさせて笑った。
「わぉ!!めっちゃ可愛いじゃん!なぁに?お坊っちゃんったらこんな可愛い子を食べてたの?」
「……ふざけろ」
ニタニタと下品な笑顔を見せる男を睨み付ける。
すると男は笑顔のままこちらの襟首を掴んできた。
そのまま持ち上げられ、首が絞まる。
反動で声にならない咳が出て、体が震えた。
「……ん」
それに反応したのだろうか。腕の中にいる体が身動ぎをした。
自分が危ない時だというのに、視線を少女の方へ向ける。
そして、先程まで閉じられていた瞳と目があった。
血のように真っ赤な瞳。
アルビノという単語が頭を過った。
時間が止まったのではないかと錯覚するほど紅い目を見つめる。
「おっと、お目覚めかい子猫ちゃん?でも残念。今度はオレがキミの気を失くすぐらいしてやるから」
ぐっと首にかかる圧が増えた。
ヤバいと思った時に、それは起きた。
ビシッ。
鈍く、硝子のようなものが割れたような音が耳に響く。
そして、急激に周囲が寒くなる。突然の冷たさに全身に鳥肌がたった。
「あ…ぇ…?」
男のものだろう呻き声と共に絞められていた手から力が抜け、若干浮いていた体が重力にしたがって落ちる。
軽い尻餅をついたことに顔をしかめつつ、周囲を見た。
「何だよ…コレ…」
声が勝手に震える。
今目の前に広がる光景が信じられなかった。
下品な笑顔を浮かべていた男の右半身が透き通った氷に覆われていた。
その周囲にも、残滓のように真っ白な霜が地面や壁に張り付いている。
そして、最後にアルビノの少女。
彼女の背後には、その小さな体に似合わない大きな羽と尻尾が蒼碧に輝いていた。
爬虫類に似た細かな鱗に覆われたモノを持つ生き物。
「竜人…!?」
少女の紅色の瞳が、暗がりに妖しく光った気がした。
++++++
ずっと昔、竜と人間の間に子どもができた。
その子どもは人の外見に竜の鱗や羽、尾を持っており、人外の腕力と魔力を持つ。
生態系の頂点に立つ彼等は、いつからか“竜人”と呼ばれていた。
そして、人間はそんな竜人の保護下にあった。
藤夜(とうや)の父親は政治家だった。
民衆から支持されて、人々のために働く人間。
そんな彼には口癖のように息子に言い聞かせる言葉があった。
“竜人は恐ろしい。だから竜人の怒りだけはかってはいけない”と。
藤夜はそんな情けない父親が小さな頃から嫌いで、父親を情けなくさせる“竜人”という生き物を心の底から憎んでいた。
だというのに。
「…何でお前はここにいるんだっ!!」
「……ぅ?」
あの後、突然凍らされたシルバー男は早々に気絶し、少女を介抱する理由もなくなったので家に帰ってきた。
すると、何を思ったのか竜人の少女はこちらについてきて、ちゃっかり家に上がり込んでいた。
ベージュの壁紙や、橙色などで揃えられた家具が置かれたリビングは暖色の効果で明るい。
しかし、そんな部屋にこの白銀の髪の少女は異様に合わない。いや、彼女なら白以外の部屋に馴染むことはないだろう。
どうしてこうなったのか。
家に入ろうとした時にこれでも怒鳴ったし、睨みもきかせた。しかし、当の少女はどこに吹く風で表情ひとつ変えはしなかった。
というか、どうやら表情筋が仕事をしてないようで、目を覚ましてから全く表情が変わっていない。
どうしてこんなことに…。
ハァーと溜め息を吐いて部屋の隅に置かれたソファーに腰掛ける。
と、なぜかそこに少女が寄ってきてこちらの右足の近く、床の上に座った。
「なに?」
「……?」
ギロと睨みながら見下ろしてみるが、少女はこちらを見上げながらこてりと首を傾げるだけだった。
そしてそのまま赤色の不気味な瞳でこちらを見つめてくる。
蹴り飛ばしてやろうか。
そんなことを思った。
見られていることが酷く不快だ。
ましてや相手は憎くてたまらない竜人なのだ。遠慮するようなことはない。
蹴って、そのまま追い出してしまえばいい。
そう考えた。
そう考えた。
けれど、気持ちに反して足がピクリとも動かなかった。
こんなに気持ち悪いのに。
きっとこいつの見た目が弱々しい少女であるせいだ。
恐ろしい化け物だと頭で分かっていながら、理性が動きを阻んでいるんだろう。
少女はじっとこちらを見上げている。
それが忌々しくて、彼女から顔を逸らした。
沈黙が場を支配する。
「……って」
「…は?」
ポツリと少女が何かを言った。
思わず聞き返して、直ぐに後悔をする。
これじゃあこちらが彼女を気にしているみたいだ。
首を動かさないよう唇をつぐむ。
ただ、顔の側面に少女の視線を感じた。が、ガン無視だ。
「…ぅ、と……アナタ、助け、くれた?」
「……」
「ぎゅう…して、くれたの…アナタ…の?」
「……」
途切れ途切れで、どことなく頑張って声を出しているような少女からの問いかけ。
それに全て知らんぷりを決め込む。
助けようとしたのは人間だと思ってたからだ。竜人をわざわざ助けようだなんてヘドが出る。
そう、人間だから介抱しようと考えたんだ。
竜人なんて、絶対助けたりしない。
「…セネ、嬉しい」
考えることに没頭していた頭を呼び戻したのはそんな言葉だった。
気づけば自分の膝の上に乗って少女が真っ直ぐこちらを見ている。
脚に鳥肌が立った。
「何してるんだよ!降りろ……」
「セネ、アナタが好き」
…………は?
何を言われたのか分からなかった。
唖然として眼前の少女を見つめれば少しずつ視界の焦点がぶれる。
何で、と思ったのは口に熱い何かが触れた後だった。
いつの間にかぶれていた焦点は直り、ハッキリとした視界の中心で少女が真っ赤な瞳を細めて、笑っていた。
それも純粋な笑顔じゃない。
恐ろしいほど綺麗なのに、幼い外見から想像できないほど蠱惑的な笑み。
するりと首筋を少女に撫でられた。
ゾクリ、得体の知れない感覚が体を駆け巡る。
「な…に、を……」
「セネ知ってるよ。好きと、スキは惹かれるって…教えて、もらったから……だから、アナタは、セネの」
意味の分からないことを喋る竜人に頭が痛くなる。
やっぱりこんな奴は追い出した方がいい。
だけど、また体が言うことを聞かなかった。それも、全身がだ。
竜人が体を寄せて更に密着してくる。
それに合わせて、胸を中心に火照り始める身体。
銀糸の輝く頭部が首元に埋められ、スリスリと頬擦りをされた。
気持ちの悪さに鳥肌が立つ。けれど、身体は動かない。
何だか息苦しい。
寒気が背中を這いずり回るような感覚に襲われ、理解不明な現状に恐怖する。
「…セネの、セネの好き。見つけたの……見つけた、から…セネの……全部、全部セネカのものなの…ね?」
こてりと首を傾げると、再び視界で竜人の姿がぶれる。
今度はぶれの正体が、竜人の接近によるものだと分かった。
おまけに、ぶれの後にきた熱いものの正体も分かる。
きっとまた、口付けをされる。
簡単にそう予想できたというのに、それを防ぐことも、避けることもできはしなかった。
ただ、熱い唇にもたらされた接触は、僕になんの感情も抱かせなかった。
「…アナタが、好き」
遠くの方で何かを告げられた、そんな気がした。
戻る
小説トップへ戻る