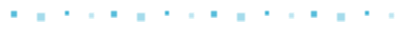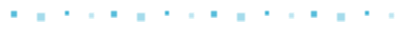
冷厳たる者2
魔法使いとは、それぞれの分野で多岐の現象に干渉、操るものをいう。
センスと努力の結晶とも呼ばれる職業ゆえ、エリートと呼べる人間は数少ない。
そもそも、人の器は小さすぎて、甚大な魔力を産み出せてもほとんどが効率的に使えないのだ。
こればかりは勉学を極め、経験を積んでも解消は難しい。
しかし、そんな使われない魔力に惹かれる生き物が多々存在した。
彼らは人の魔力を対価に人のために働き、尽くした。
何時しか、魔力を欲する生き物を従属させるのが魔法使いの通過儀礼になり、人々はそんな生き物を『使い魔』と呼んだ。
ディミルダ・トゥリスはその強さを学園中に見せつけながら、長く使い魔を持っていなかった。
いや、持てなかった。
使い魔との契約には個々に適齢期があり、周囲に比べディミルダはそれがかなり遅かった。
それに、使い魔がいなくてもディミルダは使い魔がいる人間すら凌駕していたし、大抵のことは自身の力でどうにかできた。
だから本人は使い魔を熱望していなかった。ついでを言えば周囲も彼に使い魔ができることを望んでいなかった。
だが、その時はあっさりとやってきた。
元々優秀なディミルダは難なく召喚魔法を発動させ、さっさと使い魔を呼び出した。
そして、幾つか問題を起こしながらも契約(という名の従属)に成功し、彼は使い魔を得た。
あれから二週間が経った。
その間何度も起きたディミルダの戦闘騒ぎに、しかし、件の使い魔は一回も人前に姿を現していない。
学生寮は学園と直通で、同じ背格好の建物が二つ並んでできている。
北側が女子寮で、南側が男子寮となっていて、基本は数人の相部屋だが、成績優秀者には厚待遇の一人部屋が与えられたりする。
異端な有名人ではあるがディミルダも一人部屋特権を持つ生徒だった。
15階より上に位置する自室に返ってきた彼は、リビングの北側隅にある寝室の扉へ向かう。
そして迷いなくその戸を開いた。
明らかに一人には大きすぎる寝台が中央に鎮座した室内。
かろうじてシングルサイズの寝具には、大きなシーツのまんじゅうが乗っていた。扉の開いた音に反応したのかまんじゅうはもぞりと動く。
「ラース」
ディミルダの声にまんじゅうがビクンッと跳ね上がった。そのままもぞもぞと動くと、シーツの端から静かに赤い瞳が覗く。
ギラギラと光る瞳は誰の目からも分かるほど怒りを内に湛えていた。
睨みを利かすシーツまんじゅうにディミルダは呆れの溜め息をこぼす。
そして、大きく右腕を振りかぶると、勢いよく真白のシーツを剥ぎ取った。
「あっっ!!」
細い腕が追いかけるようにシーツに縋るが、掴むことは叶わなかった。身を包むものを無くし、ベッドの上で小さな体がふるふると震える。
濃青色の短い髪に12、3歳ほどの体つきの少年が潤む目で仁王立ちのディミルダを睨んだ。彼こそ、先日『冷厳な帝』の使い魔にされた悪魔だ。
しかし、両者に流れる空気は主従というには険悪だ。主にラースがピリピリと全身で警戒を露にしている。その姿は懐かない猫のようだ。
「いつまでその姿勢でいるつもりだ?」
「……いつまでも」
「全く可愛いげのない……いい加減周りを見習え」
「五月蝿い!!誰がお前みたいな人間の言いなりになるかよ!ぜってー可愛くなんてなるもんか!バーカ!!」
鋭い犬歯の覗く口から行儀の悪い言葉を吐き出す様子に、ディミルダは頭を軽く抱える。眉間に皺も寄せて、顔に浮かべていた呆れをより濃くした。
「人に捩じ伏せられておいてよくもまあ、そこまで生意気でいられるな」
「当たり前だろ!お前なんて大っ嫌いだ!!」
「いいのか?そんなことばかり言っていて……“苦しだろう?”」
不意に強調された言葉にラースがグッと押し黙る。
小刻みに震える体。その背からフッとコウモリのものに似た羽が姿を表した。しかし、羽の翼膜は皺が寄り力なく垂れ下がっている。
悪魔が体内に内在している魔力が枯渇している証だ。
魔界に住んでいる悪魔族には二種類のタイプがある。
片方は“放出型”。魔界に満ちている魔力を常に吸収し、行使するタイプだ。こちらは総じて操れる魔力量が桁外れで、技の一つ一つが絶大な威力で放つことができる。
もう一方が“生産型”。体に魔力を生み出す機能を持っており、自分で魔力を作り出すことができる。作る分だけ吸収量を欲しないためか、総じて一度に行使できる魔力が少なくなる傾向にある。
魔界において力を振るうのは前者が多いが、人間界ではそれが異なる。
なぜなら、人間界は空気中にほとんど魔力が存在しない。大半の魔力は生き物が内に溜めているもので、それが溢れたものが漂っているのである。
魔族は魔力を失っては生きていけない。
よって、人間界で行動できるのは“生産型”であり、“放出型”はほとんど姿を見せることはない。
もしも人間界に“放出型”がいる場合、何処かで魔力の補充できる環境を持つことが必須。
ディミルダによって半強制的に召喚されたラースは“放出型”の悪魔だった。
ラースにとって幸いなのは、使い魔になったため、主人であるディミルダから魔力を補充できる“権利”があること。
しかし、この“権利”はあくまで双方が同意した場合に限る。
ラースにとって不幸なのは、主人が優秀すぎるディミルダであったことだ。
召喚されてから二週間。ラースは一度も魔力の供給を受けていない。
ふらりと、ディミルダを睨み続けるラースの頭が揺れる。
「もう喋ることすら儘ならないんだろう?観念したらどうだ?」
「……っるさい!黙れ黙れ黙れぇ!」
「そうか……なら俺は昼寝でもするかな。どうもラースは俺が嫌いのようだし、気を利かせて隣室で寝ることにしよう」
「く……うっ……っ!!」
くっくと喉を鳴らすディミルダの顔には一切の気遣いは見られない。むしろ、綺麗に弧を描いた唇は愉しそうだ。
その姿にラースは瞳を揺らす。フー、フーと浅く繰り返される呼吸はかなり苦しそうで、顔色もどんどん悪くなっていく。
「大丈夫か?」
口先だけの心配と共にラースの頬に手が伸ばされる。最早払い除ける気力もないのか、何の抵抗もなく指先が肌に触れた。
瞬間、
「……っ!?」
全身に電気でも走ったかのように小さな体がビクリと痙攣した。見開かれた瞳はただ一点に、眼前の少年に向けられる。
ディミルダの指先がラースに触れたままついと滑る。その軌跡に、仄かに光る淡い燐光が浮かんで消えた。次いで、空気中に僅かに漂う力。
膨大なディミルダの魔力が、指先から溢れているのだ。
暫し睨むことすら忘れ、体から力を抜いたラースは目を閉じていた。だが、おもむろにディミルダが指を離すと、素早く瞳を見開きその手を掴む。
「どうした?」
「は……ぅう……ハァ、フーっ」
余程力が籠っているのだろう。ラースの手の下敷きになった服の袖はくしゃりとひしゃげている。
ラースはグイと自分より幾らか大きな体を引き寄せ、先程まで触れていた指先に噛みついた。
ぴく、と手のひらが震えるが、ディミルダは顔色を変えるでもなく小さな悪魔を見下ろしていた。
ガジガジとラースは骨張った指に歯を立てる。何度も、何度も何度も何度も、何度も何度も何度も何度も何度も。
その内大きな赤い瞳の端から透明な粒が溢れ落ちた。それでもラースは指を噛み続ける。口から覗く指先は幾つも歯形がつき、痛々しい赤色に染まっていた。
ディミルダは顔色を変えない。穏やかにも見える瞳でじっとラースを観察している。
悪魔は魔力の動きに敏感だ。だからこそそこに魔力があることも、ないことも瞬時に判断ができる。
もう一粒透明な滴がラースの瞳から溢れた。
彼は理解していた。
今自分が噛みついている指先から、一片たりとも魔力が溢れていないことを。
ディミルダは恐ろしいほど魔力を操ることに長け過ぎていた。
体内から魔力を溢すことも、留めることも彼にとっては造作もないこと。
「とっくに分かっているんだろう?」
「ぅ……ぅ……」
「何も俺は死ねと言っている訳じゃない。ただ“言うことを聞く約束”を取り付けているにすぎない……そうだろ?」
「っぅ……ぅ、あああぁぁっ!!」
指を解放し、悪魔はその顔を歪めて吼える。苦しげに胸を押さえ、丸く縮こまる悪魔の背を少年は優しい手つきで撫で、笑う。
「自尊心は捨てろ。現実を認めろ。お前は、俺に負けたんだよ」
「うっ……ううっ……!」
「ラース」
俯いたラースからディミルダは静かに体を離す。
数秒の沈黙。
のろのろと濃青の髪に縁取られた顔が上を向く。
かち合う、二組の瞳。
ぽろり、一粒が落ちて瞬く間に大粒の涙が蒼白い頬を濡らしていく。
「うっ、ううううぅぅ……ううううぅぅっ!」
ポロポロ溢れる涙と、呻きに似た嗚咽が落ちていく。嫌々と頭を振りながら、引きずるように体を静観するディミルダへと寄せて、震える手で彼の胸ぐらを掴んだ。そのまま泣きながらゆっくりと目を閉じたラースは、頭をディミルダの首筋にうめる。
そして、酷くぎこちない動きで首にすり、と頬擦りをした。
「いい子だ」
止めどない涙をボロボロと落とすラースの頭をディミルダは撫でた。まるで子を慈しむ親のように優しく、優しく撫でる。
その手のひらから、先程とは比べ物にならない光が溢れた。
魔力の供給。
ラースはひっく、ひっくとしゃくりあげながら、ねだるようにディミルダの体にしがみついた。そして、どこまでも安心しきった表情でもう一度だけ彼に擦り寄る。
その耳元でディミルダは言い聞かせるように言葉を紡いだ。
「俺は諦めることを許さない。俺は、俺に負けたお前に期待しているんだよラース。もっと技を洗練しろ。そして勝利に執着しろ。俺という存在を踏み台にすることを考えるんだ。
お前は賢いからわかるだろう?期待しているぞ、ラース」
「言われなくたって、やってやるよ……!」
情けない鼻声が室内に響いた。
彼は口許に浮かんだ笑みを、より深く、深く、深くして笑った。
++++++
サディストに目覚めた。
というわけではありませんが、我が家には珍しい鬼畜っ子が生まれました。
実力主義者のディミルダさんは自分の期待に応えてくれる人には優しいよ!
ラースの方が色々と設定があって、実は年齢ウン百歳だとか、契約のルーンと顔見知りだったりします。
使い魔たちみたいな小さな子が甘えてスリスリするシチュが大好きです。や、ラースは甘えてないけども。
戻る
小説トップへ戻る