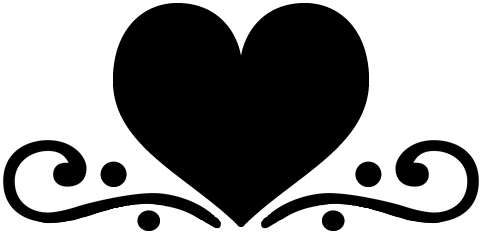
俺は幼馴染に恋してます。
まず単刀直入に言わせてもらう。俺は幼馴染の名前のことが好きだ。
家族としてじゃなく、勿論、異性として、女として好きだ。それを自覚したのは小学校に入って間もなくしてだ。
保育園に通ってた時なんて恋愛のレの字もなかったガキだったが、狭い世界からいきなり広い世界へ足を踏み入れると同時に思い知らされた。
今まで名前も顔も知らなかった奴等が名前と話す。遊ぶ。触れる時間が出来る。
俺や研磨だけじゃなく、その他大勢が名前と親しくなる。そうなるにつれて俺の中で恋というものが顔を覗かせた。
いつだってあいつの隣に居たのは俺だし、あいつが笑ってる時も、泣いてる時も、怒ってる時も、全部が一緒だった。
だが、いつしかそれは俺だけじゃなくなった。家族以外が、名前と共有するようになった。それが、きっかけだった。
自分の気持ちが最初はよく分からなかったが、高学年になった頃には幼いながらにも恋愛感情と言うものを理解してくる。
そうか。俺は名前のことが好きだから、こんなにも嫌な気持ちになるんだ。だから取られたくないって思うんだ。
そこまで自覚してからは早かった。最初は意識しすぎて変な目で見られる事もあったが、慣れが出てくれば自然と落ち着きを保てるようになるもの。
名前とは生まれた病院も一緒だし、生まれた時にはお互いの家は隣同士だったから家族も同然。
親同士も仲が良かったから必然と近い距離で過ごすのが当たり前になってた。
「それが仇になるなんて思わないだろ」
「今更仕方のない事でしょ」
音駒高校男子バレー部の部室にて、今日も部活に励む俺達はジャージに着替えるべく上着を脱ぎ捨てた。
同じ幼馴染の研磨は俺の気持ちを知っている。中学の頃に「言わなきゃ名前は気付かないと思うよ」と言われた。
そんなの俺が一番分かってた。だが、あいつに気持ちを伝えて良い方に転がるんなら良い。だがもし逆なら…そう考えたら怖くて行動に出せなかった。
長年家族も同然で育ってきた俺達は、まさに家族そのものだろう。だからこそ、その【家族】という枠を一度抜けないとあいつは俺の事を異性として意識しない。
ずっと傍に居て、どんな時も一緒に居て。それが当たり前になって、気づけば高校三年になっちまった。
「名前の鈍感っぷりはクロが一番分かってるでしょ。告白を告白と認識しないくらいなんだから」
「……まあな」
つい先日の事だ。別のクラスの奴が俺の知らないところで名前に告白した。
その場を偶然にも通りかかった研磨から話を聞いた時には焦ったが、名前は素晴らしい鈍感を発揮して相手の告白を告白と受け取らなかったのだ。
相手が「付き合ってください」と言った事に対して名前が言ったのは「どこに行くの?」だったらしい。
我が幼馴染ながら、もし告白したのが自分だったらと思うと恐ろしくてたまらない。同じ目には絶対にあいたくねぇというのが本心だ。
「梟谷の木兎と良い勝負しそうだよな」
「やめろ夜久。笑えねぇから」
あのミミズク野郎は恋愛には縁の無さそうな生活してそうだからな。ハイレベルな鈍感な名前とは確かに恐ろしい勝負しそうだ。
あいつの場合は告白されても「それって美味いのか?」とか聞いてきそうなレベルだもんな。これはこれで怖いわ。
「ねえ、そろそろ行かないと危ないと思うよ」
「何が?」
「時間からして、そろそろ名前が色々準備始める頃」
「やっべ!あいつまた転んで余計な傷増やしかねねぇもんな。おい、先行くぞ!」
「いってらっしゃーい」
「研磨はいつも見送るだけだな」
「クロはまず、保護者って立場から卒業しないと」
何もない所で転べる才能というのは誰も喜ばないだろう。けど、そんな才能を名前は生まれ持ってしまった。
昔からそれでよく転んでは色んなところに傷を作って泣いて。そんなあいつを俺が慰めて家までおぶって帰ったことも少なくない。
今は泣きはしねぇけど転ぶことは相変わらずあるから、どうしても目が離せないんだよ。
走って体育館に着くと、そこには既に名前が準備を始めていて籠に入ったボールを倉庫から出そうとしているところだった。
「走らない!」
咄嗟に注意を促すために叫んだら名前の肩がビクゥ!と跳ねた。
「てっちゃん心配しすぎっ。一日に何度も転んだりしないもん!」
「じゃあ今日何回転んだんデスカ?」
途端、あいつはスンと無表情になり俺から静かに視線を逸らした。
「はいダメー。走るの禁止ー」
「ボール籠運ぶだけで転びませんー!」
「籠に足ぶつけて転ぶに250円」
「うっ」
「更にそのまま籠ひっくり返してボールをぶちまけるに500円」
名前は完全に俯くと「…歩きます」と静かに告げた。
これは実際名前がやらかしたことがある事だ。それを覚えていてまたやりかねないと自分でも思ってるからこそ素直に従った証拠。
素直で結構。と頭を撫でてやると悔しそうに俺を見上げながら大人しく籠を押してコートの傍に設置した。
「てっちゃん、お母さんたちより心配症になっちゃったね」
「それはお前がそんだけ転んでる証拠だ。見てて危なっかしいんだよ」
「わ、私だって好きで転んでるワケじゃないもん。ただ」
「ただ?」
言わんとしてることが分かっているため敢えて意地悪く笑ってやる。
名前もそれを理解してるから俺がニヤっと笑った事に対してまた悔しそうにムッとした。
「気付いたら転んでるからぁぁ…!」
「はいはい。お前が一番悔しいのは分かってるから。背中に顔押し付けてグリグリすんの止めような。くすぐってぇから」
くすぐったいのは本当だが、別に離れる必要はない。ずっとくっついてても良い。お前が他の奴の所に行かないのなら。
誰よりもお前にとって安心できる存在でありたい。誰よりも心を許せる相手でいたい。お前だけの、特別でありたい。
何年もそう願う俺は我儘だろうか。ガキの独占欲だと笑われるだろうか。…笑われても良い。名前が、俺から離れないでいてくれるなら。
「ちゃんと足を上げるように意識してるんだよ?それでも気付けば躓いたり転んだりしてるの。…どうしたらいいんだろう」
「…なに。結構深刻な悩みの対象になってんの?」
「転んで怪我したら、てっちゃんや研磨ちゃんに心配かけちゃうから…」
こうしてこいつなりに気を付けてはいるが、どうしても上手くいかないのは、もう仕方無ぇじゃんて開き直っちまった方が良いようにも思う。
俺ならそうしちまうところだが、名前にとって俺達に心配かけるのは極力控えたいと強い想いがあるようだから止めはしない。
あんまり気を落とすなよ。そんな思いを込めてクシャクシャと頭を撫でてやったら、名前は簡単に笑顔になる。
この笑顔を見る度に元気をもらう。気持ちが楽になって、胸のところがぽかぽかするんだよな。俺は昔からこいつの笑顔が好きだ。
「私、てっちゃんのあったかい笑顔好き」
「えっ」
「今みたいにすっごく優しい眼差しをしたてっちゃんの笑顔、昔から大好きなの」
だからその笑顔見れた時、すごく嬉しくなるんだぁ。なんて、恥ずかしげもなく言うこいつは、絶対天然じごろ。
俺の気持ちを知りもしないで簡単に言ってくれる。嬉しい半面、お前にしか向けないんだからさっさと気づけよと悔しくもある。
「えへへ。今日は良い日だー」
心から嬉しそうに笑う名前はもう一度俺の背中にグリグリと頭を押し付けると、ちょうど体育館に入ってきた研磨を見つけて駆け出した。
「研磨ちゃんっ。今日も頑張ろうね!」
「名前。転ぶ前に止まってから抱きつく様にして。危ない」
「抱きつくのは止めないのな…」
続いて入ってきた夜久のツッコミもそこそこに、名前は研磨の前で転ばずに足を止めると、そのままぎゅっと抱きついた。
あいつの中で研磨は可愛い弟分という対象だから良いが、その相手がもし研磨以外だったら俺は間違いなく止めてる。
「クッソ…!研磨だけ毎日毎日羨ましいぜぇぇ!名前さんの愛の抱擁ッ、俺も受けたい…!!!」
「ははっ。山本、されたらされたで倒れないか?」
「昇天する覚悟は出来ています」
山本と海のやりとりを聞きながら相変わらず和やかな空気の中心にいる名前は、あいつ等からどれだけ慕われているか分かる。
名前が居るだけでピリピリした雰囲気も、柔らかに解されて穏やかになる。それは大事な時にも発揮されるから俺達は何度も助けられてきた。
…だからって訳じゃねぇけど。もし名前に好きな奴が出来た時は……。その時は幼馴染として協力してやれたらって―――。
「名前さーん!今日も俺にトスあげてくださーい!」
「わっ。リー君…っ、ちょっと苦しい…」
―――やっぱ思わねぇわ。
名前が優しいのを良い事に当たり前のように抱きつくリエーフの肩をガッシリ掴んだ俺は、今出来る限りの満面の笑みを浮かべて告げた。
「リエーフ。お前今日、9割レシーブ練な」
「えええええ!?」
これが独占欲だろうが、ガキっぽいと笑われ様が関係ない。名前は誰にも渡しません。