できそこないの恋
青道高校で有名な人っていったら、やっぱり御幸くんの名は挙がる。
もともと野球部が強いから、一年生の投手や三年生の前主将もそれなりに知られているみたいだけど、私たちの代では断トツで御幸くんだ。
入学したての頃はどちらかというと天乃さんのインパクトが大きかったのに、一年生にして正捕手に選ばれた頃から知名度が上がり続けて、センバツ出場を決めた今、同学年の間ではヒーローのような存在になっている。
とはいえあまりチヤホヤされるタイプの人ではないのだけど。
仮にも強豪の名を冠する青道野球部、その先頭に立つキャプテンなんて本当はものすごく偉いに違いない(そして実際、前の主将さんはけっこう雰囲気があった)のに、御幸くんは普段全然そんな素振りがない。
むしろいつも通り倉持くんとふざけ合う様子を見ていると、ちゃんと後輩の面倒見れるのかな? なんて不思議になるくらい。
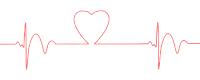
「うっ……」
「どうした?」
日直の仕事をしている友だちの横で彼女の記入する日誌を眺めていたとき、ある衝撃的な事実に気がついてしまった。
「私、来週の日直、御幸くんとだ……」
「よかったじゃん、顔のいい男と一日ペア。野球部って日直の仕事ちゃんとしてくれるしさ」
「それは……そうだけど」
けっして、他の男の子が仕事をしないというわけではない。
ただ、年に何回か回ってくる日直当番では、野球部の男の子はとりわけ信用されている。率先して黒板を消してくれたり、配布物は「俺行ってくるわ」と気づけば全部なくなっていたり。部活を理由にして仕事を押しつけてくるようなこともないし。
そういうふとしたところで、彼らは部活をしていない間にも『野球部』なのだと感じる。
「高嶺の教育がいいんでしょうよ」
というのが、私たち女子の見解。
高嶺、つまりは天乃さんだ。彼女もまた御幸くんと並んで有名な存在だった。
今年、御幸くんと天乃さんは同じクラス。
野球部的には好都合だろうけど、男女トラブルなんて起きないといいな、なんて一部私たちは考えていた。二人とも、良くも悪くも注目を集めてしまう存在だったから。
昨年わりととっつきにくい印象だった天乃さんだから最初はどうなることかと思っていたけど、彼女は存外クラスに溶けこんだ。どの生徒とも分け隔てなく喋ったし、意外とノリもよかったし、授業でわからないことを訊ねれば快く教えてくれた。
まるで年上のお姉さんみたい。
そんな彼女に引っ張られるようにして、御幸くんと倉持くんも、それなりに馴染んでいる。
野球部三人組の、いまは空席の机をぼんやり眺めていると、友だちが口の端っこでニヤリと笑う。
「これを機に仲良くなっちゃえよ」
「なっ……に言ってるの」
「御幸って将来有望じゃん。私は野球よりバスケ派だから興味ないけど。なんだかんだ言ってあの人フリーなんでしょ」
「彼女はいないみたいだけど、天乃さんがいるじゃない……」
「でも付き合ってるわけじゃないじゃん、あそこ。二年もくっつかないんだからそういう気持ちはないってことなんじゃないの?」
「うーん……どうなんだろうね……?」
もはや青道七不思議に数えられるレベルの、あの二人。
たいそうおモテになる彼らだけど、誰からの告白にもうなずいたことはない。じゃあ付き合っているのかというとそうじゃない。お互いに気を許しているのは間違いないし大切に思っているだろうけれど、彼氏彼女というよりは、一対の存在、て感じがする……。
多分、在学中に二人がおめでたい関係になることはないのだろうな。
野球をするために御幸くんが青道高校に来たように、天乃さんもまた、野球をするためにここを択んだようだから。
ついにやってきた御幸くんとの日直の日は、恙なく平和に滑りだすことができた。
ホームルーム前のちょっとした仕事だけは、御幸くんは朝練があるから私一人でやったけど、それも前日にきちんと申し入れがあってのことだった。野球部に朝練があることなんてみんな知っているのに、意外と律儀。
授業終わりに黒板を消していると、御幸くんが後ろから「上やるよ」と声をかけてくれた。
私では飛び上がっても届かなそうな上のほうにも楽々手が届く。あんまり威圧感がないから気にしたこともないけど、御幸くんはけっこう身長が高い。
「ありがとう……御幸くん身長おっきいねぇ」
「そう? 野球部だとそんなでもないけど」
「え、そうなんだ」
「うん、中間くらい」
御幸くんで中間……。私がチビなだけなのかな。
わりと雑に消し終えた御幸くんが早々に黒板前から立ち去ると、教室の後方から「御幸、上のほうもうちょっときれいに消しなよ」と苦言が飛んできた。
天乃さんだ。
教室にはしった僅かな緊張感に身を竦める。……以前、二人が大きなけんかをしたらしい時期から、たまにこういう瞬間があるのだ。みんなやっぱり、影響力のある二人には仲良くしていてほしいから。
が、御幸くんは「キビシイな……」と渋い顔になって、まったりと黒板消しを手に取る。
「手抜きするとすぐバレんだよなぁ」
「でも、次の授業、黒板キレイじゃないと文句言う先生だから……」
「あー、そういうこと」
眉を顰めて上のほうを睨む御幸くんには悪いけど、これは文句言われるかも、と私も思っていた。
「……天乃さん、厳しい?」
ふとした興味から零れた質問だった。
天乃さんも相手が御幸くんだからああやってはっきり言うのかもしれないけど、私だったらあんなこと言えないなと思ったから少し気になって。
「まあ甘くはねーよな。でも、手当たり次第に文句言ってるわけでもないから」
「どういうこと?」
「愛の鞭ってこと」
そう言って御幸くんは後ろを振り返る。
その視線を追いかけると、教科書やワークに目を落としている天乃さんがいた。勉強中の彼女の邪魔は極力しない、というのが二年B組のルールだ。
「天乃さーん、どう?」
顔を上げた彼女は両手で大きなマル印をつくる。
その様子を見てちょっと笑った御幸くんの目尻は、こっちまで照れてしまいそうなほど柔らかかった。
御幸くんって、けっこうわかりやすい。
こんなにも『大切な女の子がいます』って横顔をした人、見たことないよ。
……私が御幸くんのことばっかり見ているせいかな。
三時間目の体育はバレーボールだ。男子と女子でコート一面ずつ使用し、それぞれで試合をやっている。
運動はそんなに得意じゃないし、球技も上手にできないけど、クラスのみんなとわいわいやるのは好きだ。ミスしたからって文句を言うような人もいないし。
今日はC組と合同だ。
試合の順番でない天乃さんは、井上紅子さんと一緒に壁際に座っている。
私も天乃さんたちから少し離れたところで休憩していたけど、あの二人が一緒にいると存在感が半端ない。紅子さんのほうも、天乃さんとは少し系統が違うけど美人さんで有名だ。女子高にいたらたいそうモテそうな感じ。
ちなみに隣のコートでは、御幸くんがレシーブしようとして空振りしている。
倉持くんの「御幸テメエひっこんでろ」という怒号が響き渡り、野球部の男の子たちがどっと笑い転げた。
「御幸はあれがなければなぁ……」
傍に立っていた友だちのその言葉にちょっと笑ってしまった。
どうも彼は、球技関係の才能は全て野球に割り振られているらしい。
「でも、あれくらい弱点があったほうが人間味があっていいよ」
「まあ高嶺も球技苦手だしね。幼なじみってそういうとこも似るのかね」
天乃さんと紅子さんも男子コートに目をやって笑っている。
そうしているうちに女子のほうが一試合終わったので、私たちは交代の準備に入った。コートに入って、紅子さんが相手チームとサーブ権のじゃんけんを始める。
男子チームの白熱っぷりとは対照的に、女子のほうはゆるいムードだ。
男バレの男の子が勢いよくスパイクを決める。
ブロックのため伸ばされた両腕にぶち当たった──ところまで目撃した瞬間、後ろから肩を引かれた。ばちんっ、と痛そうな音と僅かな衝撃、それから「英!?」という悲鳴。
弾かれたボールがこっちに飛んできたのだ。
天乃さんが私を庇って、左腕で払い落としてくれた。
さ──っと血の気が引いていく。天乃さんは涼しい顔で腕を振りながら「すっごいなぁ」と感心していたけれど、白い肌は真っ赤に染まっていた。当たり前だ、ブロックされたといってもバレー部男子のスパイクが直撃したのだ。
「天乃さん……ごめんなさい、私」
「え? 平気よ、野球部で流れ弾には慣れてるから。それより怪我してない?」
しているわけがなかった。
慌てて体育の先生や前園くん、小野くんたちが駆け寄ってくる。御幸くんも顔を顰めて天乃さんの腕を掴み、「うわ痛そ」と赤くなった部分に指を這わせた。スパイクを打った男子は平謝りだ。
慣れた様子で天乃さんの腕を触る御幸くんの手つきに、場違いながらドキリとしてしまう。
「まあでもバレーボールだしな」
御幸くんはしれっと肩を竦めて、天乃さんの頭をぐしゃぐしゃと撫でた。
「そうよ、頭に当たったわけでもないのに騒ぎすぎ。硬球より全然痛くないから平気です」
「よく考えたらそれもそうだな。そっちは大丈夫かよ」
それもそう……なの?
不意に倉持くんがこちらを向いたのでびっくりしたが、慌ててこくこく頷いておく。なおも心配そうにしている小野くんたちを「はいはい、散った散った」と追い払い、天乃さんは井上さんからボールを受け取った。
試合が始まると見て、私にも平謝りだったバレー部の彼もコートから出ていく。
「高嶺ってイケメン……」
横にいた友だちがつぶやいた。私は思わず大きくうなずいていた。
御幸くんと天乃さんは、校内で二人でいるということがあんまりない。
クラスでは倉持くんを交えた三人組だし、食堂なんかでは野球部の同級生たちの輪のなかにいる。教室にいるときも喋っているのは大体倉持くんと天乃さんで、御幸くんはたまに口を挟むくらいだ。二人がお話をしているとすれば、内容は十中八九野球部のこと。
だからこの光景は非常に珍しいものだった。
昼休み、窓際の御幸くんの席に座って読書をしている天乃さんと、その前の席で窓に背を向けてスコアブックを開いている御幸くんのツーショット、なんてものは。
仲良しグループでおやつを摘まみながら横目に一瞥してみても、彼らの間には穏やかな沈黙が流れている。
「さすが。絵になる」
小さくつぶやいたのは隣のクラスの友だちだ。
彼女の言う通りだった。
一言も喋らないし別々のことをしているのに、それがごく自然なことみたい。
「そういやどうなの、御幸との日直は」
「ええ……、ふつう。御幸くんは野球部のなかで背の高さが真ん中くらいらしいよ」
「なんだその情報」
「あとは……天乃さんが御幸くんに対して厳しいのは愛の鞭だ、って」
本人たちが同じ空間にいるのにこんな話をするのも気が引けて、自然と声を潜めてしまう。
別に悪口を言っているわけじゃないのだけど悪いことをしている気分だ。
「あーでも高嶺ってスパルタらしいね。麻生とかたまにぼやいてるよ」
「そうなんだ。優しいと思うけどな、天乃さん」
「うん、多分野球部限定なんだろうね。気になるな〜今日の練習見に行こうかな」
そんな話をする彼女たちの声をやや遠くに聴きながら、わたしは窓際の聖域を見つめた。
天乃さんが長い睫毛を伏せて手元の文章を追っている。
ぱちりと瞬きをした拍子に、窓の外の何かに気づいて頬を緩めた。「御幸」って唇が動いて、御幸くんの手をトントンと指先で叩く。顔を上げた彼と一緒に階下を見下ろして手を振った。
「英せんぱーい! キャップー!」
後輩らしき男の子の声が聞こえる。どうやら彼に手を振り返しているらしい。
スコアブックを閉じた御幸くんが薄い笑みを浮かべている。いつものぼーっとした表情でも、部活のときの真剣な顔でもなく、素直な心そのまんまの顔だった。
ふと瞬きをした御幸くんは、天乃さんの腕に触れた。
こてりと首を傾げる彼女に構わず制服の袖を捲り上げる。体育の時間に私を庇った左腕だ。本人がけろっとしていた通り大したことなかったのか、もうすっかり元通りの肌の色をしていた。
なんだかいけないものを見てしまったような気分だ。
彼らの仕草に色めいた気配は微塵もないのに。
二人はそのまま何かを喋っている。
彼らだけに聴こえることばで、彼らだけに許された距離、空気で。
「──で、どうする、今日行く?」
「えっ!……えーっと、私は日直の仕事あるから、先行ってていいよ」
……うーん。
けっこう、ダメージ深いかも。
ホームルームを終えると、天乃さんと倉持くんは連れ立って教室を出ていく。日誌を開いた御幸くんの傍に近寄って、五、六時間目の内容や今日の感想を一緒に記入していった。
まだクラスメイトのざわつきの残る窓際。
「……天乃さん、腕、大丈夫だったのかな。すごい音だったけど」
御幸くんはからっと笑っていたし、本人も平気な様子でいたけど、庇われた側としてはやっぱり心配だ。
眼鏡の奥でぱちぱちと瞬いた彼は「ははっ」と笑う。
「平気だよ。やせ我慢するようなことじゃないし、本当にそこまで痛くなかったんじゃねぇの」
「だといいけど……」
「さっき見たけどもう腫れてなかったし、気にしなくていいって」
……あ。
だめ。
日誌に六限の内容を書き綴る御幸くんの硬質な字から目を逸らした。
天乃さんのことを語る彼のやさしい眼差しを、直視することができなかった。
天乃さんの苦言は愛の鞭だと微笑んだ眦。
二人だけに聴こえることば、二人だけに許された距離、空気。
当たり前のように天乃さんの腕を撫でた指先。
私、助けてもらっておいて、天乃さんに嫉妬してる。
「だいすきなんだね」
気づけばそんな言葉が唇から転び落ちていた。
御幸くんは目を丸くしている。あんまり大きな声ではなかったから、私の一言は彼以外のクラスメイトには聞こえなかったようだった。
「……天乃さんのこと」
……ああ、気づかれちゃった、かな。
決定的な台詞ではなかったはずだけど、こういう感情を向けられることは多いだろうから、妙な勘が働きそうだ。げんに彼は、うなずいたり誤魔化したりすれば済むだけの話なのに、言い辛そうに口を閉ざす。
「ごめんなさい。変なこと言って」
「や……」
なかったことにしたい。
二年間も同じ校舎で過ごして、彼が野球以外の何かに心血を注ぐことは恐らくないと知っているのに、受け入れてもらえるわけがないと最初から解っているのに。
助けてもらっておいて嫉妬して思わず口を滑らせるなんて、こんなにも恥ずかしい瞬間はない。
「……よく言われるんだけど、ちょっと違うんだよなぁ」
御幸くんは優しく苦笑した。
「色んなものを置き去りにして俺と一緒に来てくれたやつだからさ。英が、幸せになればいいなって思ってる」
なにが違うものか。
人はそれを、愛とか恋とか呼ぶんだよ。
「……ただ、それだけだ」
御幸くんは最後まで真摯だった。
真摯に私の想いを手折って、書き終えた日誌を片手に部活へと向かっていった。
在学中にあの二人が、めでたく結ばれるようなことはないのだろう。野球をするために青道高校に来た御幸くんと、野球をするためにここに来た天乃さんだから。
野球部のグラウンドが彼らのいるべき場所で、野球部の主将とマネージャーが彼らの在るべき肩書きなのだ。
彼氏とか彼女とか愛とか恋とか、そんな普遍的ななまえではなくて。
あの凛とした人たちの関係が、彼らにしか聴こえないことばで、ずっとずっと続きますように。
御幸くんの足音が遠ざかってゆくのを聴きながら、そう願った。
紗良さんのリクエストより、御幸に片想いする女子生徒視点のお話でした。第三者視点シリーズ第二弾です。
アフターダークのextraにあるお話は一年生のときのものなので、こちらは二年生冬頃にしてみました。球技の才能が全て野球に割り振られた御幸が好きなのでまた書けて嬉しかったです。
リクエストありがとうございました!
アフターダークのextraにあるお話は一年生のときのものなので、こちらは二年生冬頃にしてみました。球技の才能が全て野球に割り振られた御幸が好きなのでまた書けて嬉しかったです。
リクエストありがとうございました!
TIAM top