絶対幸福宣言
青道高校を卒業して二年が経つ。
わたしは都内の大学に入学し、あの濃密な高校生活が夢だったかのように和やかな毎日を送っていた。
雑誌の端っこに載ったことがあるせいで、青道野球部の元マネージャーということは大学入学時からすでに知られている。硬式野球部の男の子から「硬式野球部のマネをやってくれ」と誘われることもあったものの、わたしにはただひたすら、あの輝かしい三年間だけが愛しかった。
一也のいないグラウンドには心惹かれなかった。
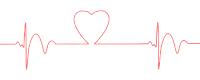
「英お願いっ!!」
「だから無理だってば」
講義終わり、目の前で手を合わせて懇願してくる友人に心苦しく思いながらもバッサリ切り捨てる。
昨日からずっと断り続けているのだ。
合コンの人数合わせ。
二週間ほど前に誘われて一度断ったのだけれど、参加予定だった女の子が風邪に倒れてしまったので、再びお誘いが回ってきたという次第。
発起人の友人──「なんで!」とわたしの胸倉を掴んでがっくんがっくんシェイクしてくる百合は、半年ほど前に彼氏と別れてからずっと落ち込んでいた。ようやく次の恋に進む気になったのが三か月前だ。わたしはそれに付き合ってもう二回も合コンに参加している。
二回とも、心を無にしてニコニコしながらご飯を食べるだけの修行の時間だった。
百合の交友関係つながりというだけあって無遠慮に触ってくるとか下心見え見えとかそういうことはなく、ひどくしつこいような男の子もいなかったのだが、もうそろそろ付き合いにも限界がある。
「今日なんにも予定ないんでしょ?」
「ないけど……なんていうか、あんまり興味ないのに参加するのも悪いじゃない」
「なにも意地でも誰か見つけないといけないってわけじゃないんだよ? 友達つくるくらいの楽な気持ちでいいんだから」
「とはいってもねぇ……」
帰り支度を整えて講義室を出た。
吹き荒ぶ十一月の寒風に身を竦ませる。そろそろマフラーを出してもいいころだ。
キャンパス内は次の講義に向かう学生や、わたしたちと同じく大学をあとにする学生でごった返している。人混みを避けるようにして一旦生協のコンビニに入り、なんとなしにスイーツのコーナーを冷やかした。
「あんた相変わらず例の幼なじみに操立てしてるわけ?」
「操立てって」
またすごい単語が出てきたものだ。
百合は野球全般に興味の薄い子だったので、わたしが青道のマネときいてもピンときていなかったし、プロ野球選手なんてバラエティに出演する人くらいしか知らない。
彼女のようなタイプの人のなかでは御幸一也もまだまだ知名度が低いほうに入るのだ。
「迎えにくるかどうかもわかんないのにさ……。やめなよもう、プロ野球選手なんてどうせそのうち女子アナとか女優とかアイドルとかつかまえていきなり結婚したりするんだよ」
「野球に興味ないわりに偏見がすごいな……」
「興味ないから偏見がすごいの」
「成る程ね」
まあ、わたしにも「一也なんてそのうちプロになって女子アナとおめでた婚する」とか言ってた時期はありましたけど。
「別に操立てってわけでもないけどね。四年間距離を置いてみて、それでもお互いがいいってなったらそのときまた考えましょうって話だから」
「でも英、結局誰に言い寄られても断るんだから。全く一体どんだけいい男だよミユキカズヤ」
呆れかえった様子の百合にちょっと苦笑を洩らす。
首に通した細いチェーンを指先でいじりながら、杏仁豆腐を掴んでレジへ向かった。高校生の頃、食堂のセットのデザートで杏仁豆腐がついたとき、先輩たちが笑いながら「やるよ」と頭の上に載せてきたことを思い出したから。
……やめよう。
もう戻らない過去をいつまでも慈しんでいたって、寂しくなるだけだ。
「連絡とってないの?」
すっかり合コンの人数合わせのことを忘れたらしい百合が腕を組む。
「うーん、たまに……。向こうも忙しいし、お互いまめなほうじゃないから」
「最後に会ったのはいつよ」
「試合やテレビを除けば、年末年始」
「ほぼ一年前じゃん!」
のんびりとコンビニを出ると、学生の流れはようやくひと段落したころだった。
それでも正門の辺りには待ち合わせか何かで混みあっている。サークルの飲み会なんかは正門待ち合わせが多いのであまり気にせず通り過ぎようとしたのだが、ふと引っかかるものを感じて立ち止まった。
女の子たちに囲まれる一人の男の子。
「ファンなんです」「いつも試合観てます」「甲子園のときから」……。黄色い歓声に周囲もなんだなんだと視線を向けているが、はっきりとはわからないみたいで首を傾げながら通り過ぎていった。
「英? どうしたの」
「いや……見なかったふりしようかどうしようか悩んでる……」
「なにが?」
長身、キャップ、眼鏡、申し訳程度のマスク。
一般人にはまだ知名度が高くないと油断したのか、変装する気はあんまり感じられない。もしかしてこれで電車に乗ってきたのかしら。よく無事に辿りつけたな……。
どれだけの群衆のなかにいても、女の子に囲まれていても、会うのが一年ぶりでも、見間違えるわけがない。
一也は苦笑いで「どうも……」なんて応対している。
昔からファンの女の子の相手をするのは苦手だったけど、プロになっても相変わらずなのか。「俺って女子の基準が英だったんだよ……」とげっそりしていたのは、センバツから帰って凄まじくキャーキャー言われだした頃だったかな。
全く、ちょっとは鳴でも見習って「ありがとー!」なんて笑えばいいのに。
……いや、似合わないからいいや。
どうしてやろうかと突っ立っていた結果、ぱっと顔を上げて動いたのは一也のほうだった。
「英。……ごめん、知り合い来たから」
「え〜」「お茶でも〜」なんて残念そうな声を上げていた彼女たちは、わたしの姿を見て目を丸くする。
幸いなことにこの『天乃英』の顔は大学に入ってからも端麗なまんま。学友会に入った友人に拝み倒されて写真掲載を許可した大学案内の冊子で、それなりに目立つ扱いをされたので顔が知られている。
あとまあ、一也のファンで甲子園から見ているような子たちなら、当然察しはつくだろう。
「……こんなとこで何してるの?」
「何ってべつに。ちょっと時間空いたから、顔見に来た」
「変装する気ある?」
「大丈夫かと思ったんだけどな〜」
「あなたいい加減に自分の顔がよくてプロ野球選手で超優良物件なこと自覚しなさい」
いつまで経っても一也は一也のままというか、野球以外のことにはとんと無頓着というか。
急に金遣いが荒くなってもそれはそれで嫌だけど、もう少しくらい変化があってもよさそうなものなのに。
そこで百合を振り返ると、彼女は両目をカッと見開いて一也を指さした。
「……ミユキカズヤ!?」
「ちょっと百合声大きい」
ざわっ、と一也に気づいていなかった学生までもがざわめく。
熱心なファンがいなかったのは幸いだった。が、名前に聞き覚えのある学生はさすがに多く、若干距離を取りつつも凝視されてしまう。
一也はすすすとわたしの傍らに身を寄せた。お話し中ですよアピールだろうか。
「……まあ、そういうことで、幼なじみの一也。一也、こっちは百合」
「あー、この子が百合さんね。いつもお話聞いてます」
「いやこちらこそ……」
まだ衝撃から立ち直れない百合が茫然と会釈するのを、一也は面白そうに眺めている。
「英このあと何かある?」
「特には。合コンに誘われてるのを頑張って断ってるとこだけど」
「へえ、合コン。行くの」
わたしの顔を覗き込んでくる、その愉快そうな眼差しに嫉妬や動揺はないようだ。
百合に付き合って参加した合コンの話、そういえば一也にはしていなかったような……。でも、一也だってこの二年の間に何かしらあっただろうけど、わたし一切聞いてないし。いちいち飲み会の報告なんてしたこともないんだから、問題ないはず。
……第一わたしたち、つきあってない。
「いちおう行かない方向だけど」
「ふーん。社会勉強くらいしとけばいいじゃん」
一也のその発言で、百合があからさまに「えっ」という顔になった。
そんな彼女など視界にも入れない様子で、一也はわたしの首筋に指を這わせる。服に隠れた細いチェーンを捜し当て、指先で引っ掛けてその先を取り出すと、細身のシルバーの指輪が顔を見せた。
高校三年生のクリスマス、一也にもらったゆびわ。
「で、精々他の男と俺と較べてみれば」
リングに人差し指を通した一也はにこりと笑みを浮かべた。
チェーンを引っ張られてよろめく。悪どいその声から遠ざかるように顔を逸らすと、ますます嬉しそうに不敵に口角を上げた。
……悪い男。
「……もう二回も社会勉強したんだからじゅうぶんよ」
「ほー。二回。聞いてませんけど」
「言ってませんから」
「で、どうだったんだよ。いい男いたの」
「少なくとも回りくどい男の子は好きじゃないわ。今日は何しにきたの」
「晩めし、一緒に食おーぜ」
にへ、とあどけない笑みを向けられて拍子抜けしてしまった。
いつまで経っても一也のままと思えば、大人の男みたいに顔を寄せて、そしたらまた力の抜けたかずくんに戻るのだからたちが悪い。振り回されるこっちの身にもなってほしいくらいだ。
なんだか悔しくなったので無言でうなずくだけにした。
「……ってことで百合さん、こいつ予約済みということで」
肩に回された一也の手は相変わらずリングをいじっている。
よっぽど、わたしがこれを身につけていたことが嬉しかったとみえる。野球選手の武骨な指先に弄ばれるシルバーリングを見下ろしながら小さくため息をついた。
「ごめん。百合」
「……いや、まあ、それはべつにいいんだけどね……」
顔の前で両手を合わせて謝ると、やや呆れた様子になった百合は一也を見上げる。
「……御幸一也は、いつまでこの子、待たせてるつもりなの?」
「待たされてるのは俺のほうだよ。俺は結婚してって言ったし」
「エッそうなの」
あ〜〜〜……。
さすがに小声で百合に耳打ちしただけとはいえ、有名人の自覚が薄いというのも考えものだ。こんな大学の正門のど真ん中でする話じゃない。
「ちょっと……。あんまりぺらぺら喋ってたら『御幸一也フラれる』みたいな見出しの間抜けな記事が出ちゃうからやめなさいよ」
「そんな記事出たら『まだフラれてません』って言うからいい。いま頑張って落としにかかってる最中です、って」
「減らず口」
「大体ちゃんと指輪つけねぇから合コンなんか誘われんだよ」
「指輪をはめるのは大学卒業して答えを出してからって言ったでしょ」
「そのくせ大事にチェーンなんか通しちゃって。とっとと折れろ」
「はいはいまた今度ね。それで今日のディナーは何の予定ですか、御幸一也選手?」
「しらじらしいな〜」と笑った一也と並んで歩きだすと、学生たちの視線も一緒についてきた。
さっきから話しかけたそうな顔つきでいた人も多かったが、一也が周囲を一顧だにしないことやわたしたちの雰囲気を見てか囲まれるようなことはない。高校生の頃、紅子に「あんたたちが二人でいると妙な威圧感があって話しかけづらい」なんてぼやかれたことをなんとなく思い出す。
……威圧感て。
いいのか悪いのかわからないなぁ。
肩に回っていた一也の手が下ろされた。
勿論こんな人通りの多いところでべたべたするのは問題だし、離れたほうがいいなとは思っていたのだけど、心なしか寒くなった肩にちらりと目を落とす。
……はなしてほしくなかったかも、なんて。
ほとんど一年ぶりなんだからもう少し触れていたかったな、とか。
「……そんなこと思ってる時点で、ねぇ……」
吐息のような声で一人ごちたつもりだったが、一也は首を傾げた。
「なんか言ったか?」
「ううん、なにも……」
「…………」
足を止めてじっと見下ろしてくる。
ここ数年はお互い忙しくてあまり顔を合わせていないとはいえ、つきあいはもう二十年にも上る。顔を覗き込めば一也の考えはなんとなくわかるつもりだし、目を見つめられれば一也に見透かされてしまうのは解っていた。
慌てて顔を逸らしたけど遅かった。
一也はニヤニヤ笑いながら再び歩きだす。
ああこの顔。沢村くんを楽しくいじめるときの顔だ。
「結婚したら堂々と手ぇつなげると思うけど?」
「……性格わる」
「はっはっは。そんな男につかまっちまって可哀想に」
そうね。ほんと、つかまっちゃったっていうのが大正解。
ほんの数年前まで『御幸一也』の人生の一部になるなんて恐れ多いと思っていたのに、いまは不思議とそれも悪くないかなって思えるの。
一也もさ、こんな女につかまっちゃってかわいそうにね。
……なんて言ったらまた「そう思うならとっとと折れろ」とか言われそうだから黙っておいた。
そのかわり、前を行く彼のコートの裾をちょこんと握った。
藍翔さんのリクエストより、高嶺の大学に御幸が迎えに来てざわざわするお話、でした。
進路の別れた二人ってどんな感じになるのかな〜という、もともとぼんやり考えていた雰囲気を形にしてみました。このお話では、高3のクリスマスに告白→保留→大学卒業後に結婚かな、という設定で書いています(本編がどうなるかはまだわかりませんが)。
とにかく御幸一也を悪い男と言いたかった!!(笑) 藍翔さん、リクエストありがとうございました。
進路の別れた二人ってどんな感じになるのかな〜という、もともとぼんやり考えていた雰囲気を形にしてみました。このお話では、高3のクリスマスに告白→保留→大学卒業後に結婚かな、という設定で書いています(本編がどうなるかはまだわかりませんが)。
とにかく御幸一也を悪い男と言いたかった!!(笑) 藍翔さん、リクエストありがとうございました。
TIAM top