掻っ攫っていって馬鹿
建物の影から顔を出した英の視線の先には、沈みゆく夕陽を浴びながらネットスローを繰り返す一人のエースが立っている。
橙色に光る汗。濡れた顎先。上下する肩、ボールを拾う指先。
スランプか何かだろうか、苦悩するように眉を顰めて悪態をつくエースの後ろ姿を見つめて、英は二度、ゆっくりと瞬きをした。
ざり、と一歩踏み出す。
背後から近づいた彼女は一本のペットボトルを差し出し、エースの首筋にぴとりと当てた。
「せーんぱいっ」
「うわっ!……なんだお前か」
驚いて振り返った彼の横で小首を傾げ、斜め下のあざとい角度から顔を覗き込むとにこりと笑う。
ぱちりとした二重瞼におさまるきらきらした瞳。すっと通った鼻梁。さくらんぼ色の唇。一つ一つのパーツを精緻に配置した人形のような、透明な存在感。
どこか作りものめいたところを感じさせる英の笑みは、それでも無邪気で、どこかやんちゃで、儚くて強い。
好き、大好き、先輩は誰よりかっこいい。力になりたい、一緒に戦いたい。そんな声が聴こえてきそうな微笑みだった。
がんばるあなたの傍に。
という字幕とナレーション、照れたようにはにかむエースが商品の蓋を開ける画面、会社名。流行のバンドのキャッチーな音楽とともに、30秒ほどの短いCMは終わった。
夕方のニュースの合間に流れたそのCMを、謎の緊張感とともに凝視していた部員たちがハアアアと息を吐く。
「……かわい〜な〜天乃英」
「俺もあれやってほしい。『せーんぱいっ』てやつ」
「梅本か夏川に頼めば?」
「それは恥ずかしいな……」
カコカコと携帯でメールを打ちながらそんな部員たちの話を右から左へ流していると、隣で興味なさげに頬杖をついていた倉持が「同い年だっけ」と話を振ってきた。
「誰が?」
「天乃英」
「あー、そうだな」
「この間クラスの女子どもが騒いでた。高校野球好きで、大会もよく観に行くんだと」
「そうだな」
今日の初戦はなんとか勝ってえーとそれで次の試合の日程は……と文章を考え込んでいたせいで相槌が適当になっていたらしい。
倉持は意外そうな顔になった。
「お前……長澤ちゃん以外の女優に興味あったのかよ……」
「あ〜〜うんまあ」
「御幸が天乃英好きなんて初耳だぜオイ」
「え〜〜うん、まあ……」
……面倒くさいからそういうことにしとこう。
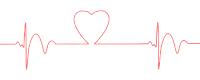
“天乃英”。
ここ二年で売り出し中の若手女優で、最近はCMやドラマ出演が増えてきている。わりと有名なのは今放送中のスポドリのCMと、水曜九時からやっている刑事ドラマの主人公の妹役。高校野球好きで大会にお忍びでよく観戦に行く。兄はプロ野球選手の天乃完吾。なお芸名は本名。
俺たちの出場したセンバツの応援キャラクターとして起用されたせいで、青道野球部はちょっとした天乃英ブームだった。
具体的には『せーんぱいっ』ごっこが流行っている。
全然先輩じゃない同級生同士でも、とにかく何か渡すときには「せーんぱいっ」と言いながら渡すという、意味のわからないブームだ。マネ陣からは「なにやってんだあいつら」という視線を受けているし、俺も「なにやってんだこいつら」と思っているが、無害なので放置している。
夏の全国高等学校野球選手権大会、西東京大会四回戦。
八弥王子高校との試合を制して一旦球場を出たところで応援組を見送ると、ぴと、と首筋に冷たいものを押しつけられた。
「せーんぱいっ」
周囲にいた部員たちの目が、カッ!!──と限界まで開く。
せーんぱいっ、と呼びかけてきたその声が、テレビで聞いているのと全く同じトーンだったからだ。
「五回戦進出おめでと!」
振り返ると、かけていた伊達メガネを悪戯っぽくずらしながら笑う、天乃英がそこにいた。
ガタガタ震えながら英を指さしている倉持やゾノに「しーっ、しー!!」と黙るよう必死に訴えると、やはりガタガタ震えながらうなずいた。よし。
こんなところで大声で名前を叫ばれたあかつきには……。想像するだに恐ろしい。
「みみみみみ御幸お前この子は一体なんなんや」
部員を代表して訊ねてきたのはゾノだった。
山口や麻生は顎が外れそうなくらいぽかんと口を開けている。白州やノリも、さすがに驚いた様子で顔を見合わせていた。
ああもう。
「なにって……。幼なじみ」
「「「幼なじみィィ!?」」」
「はじめまして、天乃英といいます。かずくんがいつもお世話になっております」
英はぺこりと会釈した。
伊達メガネに黒キャップ、パーカーのフードもかぶって、カーゴパンツに足元はブーツ。テレビで見るような清楚感を極限まで削ぎ落したボーイッシュな格好だ。芸能人になってからの英は謎にステルス性が高くなって、サングラスとかマスクとかしないで街中を堂々と歩いても滅多にばれない。
昔は町を歩けば十人中八、九人は振り返っていたのに、芸能界で気配を断つ訓練でもしたのだろうか。
はい、と手渡されたのは話題のCMのスポドリ。
有難く受け取ったものの、英の首筋に浮く汗が目についたので、お返しとばかりにぴとっと首に当ててやった。
「来てたのかよ」
「来るよ! 試合すごくよかった。相変わらずのドSリード、怪物投手の復活、1・2番の攻撃的シフト最高! 初戦に較べると気迫がすごくて、観ててゾクゾクしました」
「よく見てんなお前……」
英と俺は、江戸川の実家がはす向かい同士の幼なじみだ。
英が中三の夏にスカウトされてデビューすることになり、俺は青道を択び、なんとなく道が分かれた。とはいえ英は完吾兄ちゃんの影響もあって野球が好きだったから、俺の試合日程を細かく訊ねてはこっそり観戦にきてくれている。
「なんか用?」
「特に用という用はないけど」
「なんだそりゃ。球場で話しかけんなっつったろ、うち今天乃英ブームなんだから」
「あら、嬉しい」
あら嬉しい、じゃねーよ。追及されるのは俺だぞ。思わず片手で英の頬を掴んでぐにぐにしてしまった。
英は「痛い痛い」と笑いながら俺の腕をぺしぺし叩いている。
……ああ、いや、違うな。
特に用という用はない、のほうが嘘か。英は今まで何度も大会を観にきていたが、一度もこうして部員たちの前で話しかけてくることはなかった。
となると今日はよっぽど用があったんだ。
「はぁ……」
「そんなに怒らなくてもいいじゃないの。はいはい、帰ります」
「ちょっとこっち来い」
細い手首を掴んで、球場周辺に沿って部員から離れていく。ある程度ひと気が少なくなったところで足を止めると英を振り返った。
テレビによく出ているせいであまり久しぶりという感じはしないが、こうして顔を突き合わせて話をするのは年末年始以来だ。作りものめいたきれいな顔はいい加減見慣れているから緊張なんてしないけど、こうして衆目の前で向かい合うのはなんだかハラハラして心臓に悪い。
「……で?」
英はこちらを見上げて、へら、と笑った。
テレビを通して見るような計算された表情じゃない。力の抜けた、ただの英の柔らかい笑み。
「……えっとね」
「ああ」
「いま撮ってるドラマでね……」
そういえば何かドラマの主演が決まったとか誰かが騒いでいたっけか。情報解禁になったあとで英からメールもきたような気がする。確か純さんが愛読していた少女マンガ原作の、なんかよくわかんねぇ恋愛もの。
「キスシーンがあって」
「……はあ?」
「明日、撮影なの」
「……?」
それとこれとにどういう因果関係があるんだ、と思ったのがもろ顔に出たらしい。英は苦笑して「それだけ」と肩を竦める。
黒縁の伊達メガネが邪魔だった。
手を伸ばして、小さな顔に引っかかっているメガネを抜き去る。つるの部分が当たったのか、反射的にぎゅっと目を閉じた英は不服そうな表情になってこちらを見上げた。
フードの下に深く被っていたキャップのつばを引っ張って乱雑に脱がす。
人通りはないけど念のため、壁際でないほうの横顔をキャップで隠した。
「…………」
「…………」
互いに息を止めていた。
目を丸くした英がゆっくりと瞼を下ろす。長い睫毛が落とした翳は、距離が近すぎてぼやけていた。
ほんの少しくっついて離れただけ、なんの感慨も特にない一瞬。
「……女優なんてやるからそういうことになるんだろ」
「……反対しなかったくせに」
「英が乗り気だったから」
顔を離して、ぽすっとフードの上からキャップを乗せる。無言で俺を見つめながら、英はキャップのつばを両手で掴んでそっと顔を隠した。
「向いてるかもって思ったんだもの。せっかくお父さんとお母さんがいい感じに生んでくれた見た目だったし」
「ハイハイ」
「子どもの頃からわりと演技派だったのよ、わたし」
「まーそりゃ知ってるけど」
ビスクドールか天使みたいだと褒めそやされていた容貌とは裏腹に、英は子どもの頃から達観していた。『見た目は子ども・頭脳は大人』というフレーズがぴったりなほど。
だけどそのギャップを、『不自然なほど大人びた子ども』とは感じさせず、『少し大人しくて賢い子ども』と周囲に想わせることのできる演技力があった。
それが女優業に活きているのかどうかは、よくわかんねぇけど。
顔を隠している帽子を指先でちょこっとずらすと、真っ赤になった耳が覗く。
世間的には確か、高い演技力が評価されているとかなんとか聞いているんだが。
こんな正直に全部顔に出るような英が演技派とは芸能界って不思議だな。
……それとも俺の前だけか。
そうなんだろうな。
パーカーのフードを下ろしてキャップを被り直したときには、英はいつも通りけろりとした透明な顔つきに戻っていた。
「撮影のときも一々そんな真っ赤になる気かよ。やっぱ向いてねぇんじゃねーの」
「言ったわね……憶えてなさいよ。かずくんたちが真っ赤になるようなキスシーンにしてやるわ」
「台本守れー」
英と別れたあと、倉持たち全員から質問攻めにされたのは言うまでもない(今まで黙っていたことを詰められたが、近日発売予定の写真集をサイン入りでもらうことで手を打った)。
あゆさんのリクエストより、もし高嶺が芸能活動をしていたら、というお話でした。
リクエスト企画でifを書くたびに思うんですが、この人たち一緒に青道に行かないほうが進展が早いですね……。女優高嶺さんの目標は「長澤ちゃんと共演してサインもらってかずくんに自慢しまくる」です。かずくんにサインをもらってあげる、ではなく(笑)
リクエストありがとうございました!
リクエスト企画でifを書くたびに思うんですが、この人たち一緒に青道に行かないほうが進展が早いですね……。女優高嶺さんの目標は「長澤ちゃんと共演してサインもらってかずくんに自慢しまくる」です。かずくんにサインをもらってあげる、ではなく(笑)
リクエストありがとうございました!
TIAM top