13月に逢いましょう
「天乃先輩ってさ──……」
という声が耳に届いた瞬間、反射的に足を止めてしまった。
こういうかたちで自分の名前が誰かの話題に上がる際、内容はたいてい陰口だからだ。
もしかしたら褒めてもっているかもしれないけれど、世の中、そういう話題は本人の耳には届かないようにできているものだ。
昼休み、進路指導室を訪れたあと教室に帰る途中の廊下。
曲がり角の向こうから聞こえてきた声を迂回することも、できないことはない。
……でも階段を上り下りして遠回りするの面倒くさいな。
最上級生になって、二ヶ月前に野球部も引退した。昔は敵だらけに思えていた生徒たちも、もうすっかり御幸一也の幼なじみである天乃英のことを受け入れてくれている。陰口かどうかはもうちょっと聞いてから判断して、不穏な感じなら迂回しよう。そうじゃなければ知らん顔して通ればいい──
「どんな音楽聴くんだろうね……?」
ズッコケそうになった。
音楽?
ちょうどそこを通りがかったノリくんが「どうしたの?」と首を傾げる。慌てて人差し指を口元に添えて「しー!」と詰め寄った。
音楽、といえばわたしの周りではまず紅子。次に音楽鑑賞が趣味というノリくんに健二郎さん。アイドルファンの木島くんに東条くん……だけど。
「そもそも高嶺先輩って音楽聴くのかなぁ」
「お嬢さまっぽいしやっぱりクラシックとか聴くんじゃないの?」
「なにそのコテコテの妄想。でも洋楽とかジャズとか聴いててほしいな〜! なんかお洒落な感じするじゃん!」
「似合う〜〜森の中の洋館の窓辺でクラシックのレコード流しながら読書してる高嶺先輩見てみたい〜」
どんな妄想だ。
キャッキャウフフと盛り上がる後輩女子たちの会話に、ノリくんがぶくくと肩を震わせて笑いはじめた。
というかこの声、多分、吹奏楽部の二年生だ。野球部の応援の打ち合わせで吹奏楽部にお邪魔したときにお話した記憶があるもの。
「どうしようノリくん」
「ぶっ……ど、どうしようって、どうするつもりなの英ちゃん」
「わたしクラシックも洋楽もジャズも全然わかんない……あの子たちの夢を壊しちゃう」
「うっ、ゆ、夢って……これ以上笑わすなよ……」
「由々しき事態よ!!」
ぶは、とノリくんがお腹を抱えてしゃがみ込んだ。
けっして浅いわけじゃない笑いのツボに、珍しくはまったらしい。
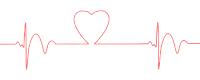
「これが英のプレイリストか……」
放課後になると、息抜きにCDショップにでも行かないか、と誘ってくれた健二郎さんとノリくんの三人で並んで学校を出た。
「英の由々しき事態だと聞いてな」と楽しそうに微笑んだ健二郎さんに音楽プレーヤーを差し出したので、彼は興味深そうにじっくりと中身を観察している。
実を言うと、あの後輩女子たちが見たらショックを受けそうな楽曲の数々である。
「なんか……オルタナが多いか?」
「だね。思ってたより、こう、なんていうか」
「どうぞハッキリ言って」
「「男臭い……」」
言われると思った。
だから『由々しき事態』なのだ。
「兄の部屋にあったCDを聴いてたから影響を受けてるのね。この辺とかは一也の好きなアーティストさんだけど」
「へー、御幸こういうの好きなんだ」
「この辺りは倉持だろ。ここだけ浮いてる」
「当たり。布教されてつい」
クラシックや洋楽やジャズをご所望の後輩女子には悪いが、わたしはごく普通に邦楽が好きだ。
せめて可愛いアイドルや女性シンガーソングライターの曲で埋め尽くされていればそこまで由々しくもないのだけれど、あんな夢たっぷりの妄想を盗み聞きしたあとでは、わたしのプレイリストは二人の感想通りあまりにも『男臭い』のだ。
「まあ見た目からはあんまりロック好きって想像つかないけど。俺は好きだな、このラインナップ」
「別にギャップがあっていいんじゃないのか」
「いや、わたしも別にそこまで思い悩んでいるわけではないけどね……ホラやっぱり可愛い後輩女子の期待には応えたくなるじゃない」
「「なるかな……?」」
首を傾げた二人と一緒に、西国駅前の商業施設のドアをくぐった。
CDショップが入っているのはビルの三階だ。エスカレーターに乗って上の階を目指す途中、後ろを振り返って、制服姿のノリくんと健二郎さんにちょっと笑ってしまった。
「どうしたの」
「なんか、制服で寄り道なんて普通の高校生みたいだなって思って」
「あー……毎日グラウンドに直行だったもんね」
夏を終え、野球部を引退して、わたしは受験勉強に打ち込むようになった。
以前ほど追われるように野球をすることもなくなった毎日は、時間も体力も気力も余裕ができたけれど、どこかぼやけていて味気ない。
引退した三年生たちもそう感じているのか、毎日誰かしらが、寮の裏手やグラウンドの隅で体を動かしているという。
お店の中には、オリコンチャート上位の女性アイドルグループの曲がかかっていた。
一年生の文化祭で踊った曲のグループだ。
「クラシックとジャズは井上に訊いたほうがいいとして、俺から勧められるのは洋楽くらいだな」
「洋楽なんて全然聴かないなぁ。なに言ってるのかわからないから」
「えっ、英ちゃんでもそうなの?」
「テストの点数とは比例しないわよ、こういうのは」
本気で驚いているノリくんにこっちが驚いてしまう。勉強の英語と、喋る英語はまた別物だ。それとも何か、ノリくんはわたしのことを何でもできる超人だとでも思っていたのか。
健二郎さんはまず「英の好きなオルタナ系はこの辺」とCDを何枚か取り出して見せてくれた。
オルタナティブロックは天乃英に生まれる前のときから比較的好んで聴いていたけれど、洋楽やジャズやクラシックなんて今も昔も完全に未知の世界だ。きっとあんな話を聞かなければ、これからも興味さえ湧かなかったに違いない。
思えば、前のわたしとはずいぶん違う女の子に育ったものだ。
中身はわたしのままなのに、前じゃちんぷんかんぷんだった数学が今やお友達。野球のことなんてサッパリだったのにこんな状態だし、前の人生で学年一位なんて取ったことなかったし、いま目指している大学の偏差値は前よりも十は上。
やっぱり一也の存在が大きかったな。
全身全霊を傾けて野球に打ち込む人がすぐ傍にいたから、わたしもがんばろう、って思えた。
気づけばわたしをほっぽって、音楽好き同士の二人はわいわい盛り上がり始めている。
なんだかこうしていると本当に普通の高校生みたいだ。
別に普通じゃなかったつもりはないけれど、特殊だったのは確かだと思うから。
「ね、健二郎さんの好きなアーティストは?」
「ん?」と首を傾げた彼はずらっとCDの並ぶ棚を眺めて、二、三枚引き出す。
さすがに、『森の中の洋館の窓辺で読書しながら聴いていそう』なジャケットではない。けれどその中から、男性四人組のバンドグループのベストアルバムを一枚選んだ。
「今日はこれにする」
「え?」
「今日は健二郎さんの好きなグループのCDを買ってみる。そういう気分になった。教えてもらったお勧めは、今度紅子と一緒にレンタルで捜してくるね」
にこっと笑うと、健二郎さんとノリくんは一瞬顔を見合わせて破顔した。
「……でも、そんな無理して趣味を広げようとしなくてもいいんじゃないか」
「無理じゃないよ。色々なものに触れるのは悪いことじゃないと思う。もしかしたらそのなかで、一生貫き通せる大事な趣味が見つかるかもしれないし」
「なんか先生みたいなこと言ってる」
「人生長いとは限らないんだから、元気なうちに色々経験しなきゃね」
前のわたしは、やってみたいことや興味のあることがたくさん残っているうちにあっさり死んだ。
今生の天乃英だって長生きするとは限らない。事故に病気に災害に、不測の事態なんていくらでもある。だからこそ、御幸一也という人の隣に生きていられるこれっきりの人生、後悔したくなかった。
そして青道高校の三年間は無事に終わろうとしている。
これから先は一也が隣にいない天乃英の人生だ。──最近よく考えることだった。
会計を終えて、今度は邦楽のコーナーで楽しそうに笑っている二人のもとに戻る。
……ロックといえば。
「大学生になったらフェスとかも行ってみたいなって思ってるんだけどね」
ずらっと並ぶロックバンドの名盤を順番に目で追っていると、ノリくんは心配そうな顔になった。
「ええ……英ちゃんが? 大丈夫? 潰れない?」
「フェスってそこまでハードなの? やだ怖い」
「最前近くまで行かなければ平気だろ。……じゃ、いつか行くか」
健二郎さんの思わぬ申し出にきょとんとしてしまう。
しかし隣のノリくんは「いいね、それ」とうなずいた。
「……でも二人とも、大学に入っても野球やるでしょ。そんな暇ある?」
「それは、まあ、うーん」
「……ないかもな」
ですよね。
一瞬、高校卒業しても一緒に遊んでくれるんだな、って嬉しくなっちゃった──
「じゃあ大人になって、時間に余裕ができて休みも合わせられるようになったら、だな」
「大人になったらかー! なんか想像できないな」
なんでもないことのように言いながら、二人はわたしの先を歩いてお店を出ていく。
三年間、一緒に過ごした後ろ姿。
入学したばかりの頃は華奢な少年の面影を残していた二人も、強豪青道野球部の背番号を背負い、色んな辛酸を舐めては立ち上がり、いま一つの区切りを終えて大人になろうとしている。
なんだか変な感じ。
みんなの未来にも、当たり前にわたしがいるんだなぁ。
「英? 聞いてたか?」
「聞いてたよ。……大人になっても友だちでいてくれる?」
すると二人は世にも奇妙なものを見るような目になった。
全く揃って同じ反応をするから思わず笑ってしまった。
「当たり前だろ。こんなキャラ濃い女子と疎遠になるほうが難しいさ」
「そうそう。きっと仕事したり野球やめたりで色んな大人になるんだろうけど、なんだかんだで誰かと誰かは繋がってて、年に一回くらいはみんなで集まってそう」
「飲み会しながら結局野球の話になるんだろうな」
「青道の練習試合とか大会とか絶対誰か観に行ってるし」
「甲子園に出場なんてなったら球場で大集合だな、先輩も後輩も」
二人はぽんぽんと掛け合いながら、ビルの中のお店をうろうろした。片手間に話してしまえるくらい、彼らにとっては当たり前の未来なんだ。
「あれっ、なんの話だったっけ?」
はっと我に返ったノリくんは、雑貨屋さんの店先に陳列してあったサングラスを掛けて遊んでいた。
あんまり似合ってなくてかわいい。
「大人になったらフェスに行こ、って話よ」
「うわ英ちゃんサングラス似合う。海外セレブみたい」
「……森の中の洋館のお嬢さまからどんどん遠ざかっていくわ」
「ていうか今更英をお嬢さま扱いする生徒がいることに驚きだけどな。いい加減色々と本性がバレてそうなものだが」
「ほら、英ちゃん後輩の前ではけっこうネコかぶってるから」
「ああ……」
「どういう意味かしら?」
「「すいません」」
むぎゅっと二人のほっぺたを抓る。
サングラスを元通りにして再び歩きだし、店舗案内の前で立ち止まった。二人は他に用事もないらしい。わたしも別に、今すぐ服がほしいとか参考書が必要とかではなかった。
「話、戻すけど」
思い出したように健二郎さんがつぶやく。
「大人になったらとは言っても何年先の話かもわからないし、英は、大学生のうちに行ける目処が立ったら行けばいいぞ」
うんうん、とノリくんもうなずいている。確かに、大学でも野球に打ち込むだろう二人は普通の大学生に較べて自由が少ないかもしれない。対してわたしは今のところ野球を続ける予定もなく、ごく一般的な大学生になる予定だ。フェスもライブも、行こうと思えばすぐに行けるだろう。
でもねぇ。
「ううん。……初めてのフェスは二人と一緒。楽しみにとっとくわ」
あんな嬉しいこと言ってもらったのに、一人だけ行くっていうのもね。
ノリくんも健二郎さんも、仕方ないな、みたいに肩を竦めて、そしてはにかんだ。
「じゃあ、未来の約束も決まったことだし──」
健二郎さんはビシ、と店舗案内の一角を指さした。
三階のはしっこのスタバだ。これまたわたしたちにはほとんど縁のなかった、寄り道の王道みたいなお店。
「お茶でも飲んで温まって帰るか」
「「賛成っ」」
ぶどーさんのリクエストより、ノリくんと健二郎さんとお出かけするお話でした。
この二人とのお出かけだったら音楽の話をしたいよな……どうせなら引退後ノンビリまったり隠居する老人たちのような雰囲気にしたいな……と思っていましたが、なにやら奇妙なテンションの三人になってしまいました(笑)
この三人トリオだと、行動の指揮をとるのは白州くんになるようですね。新たな発見でした。
ぶどーさん、リクエストありがとうございました!
この二人とのお出かけだったら音楽の話をしたいよな……どうせなら引退後ノンビリまったり隠居する老人たちのような雰囲気にしたいな……と思っていましたが、なにやら奇妙なテンションの三人になってしまいました(笑)
この三人トリオだと、行動の指揮をとるのは白州くんになるようですね。新たな発見でした。
ぶどーさん、リクエストありがとうございました!
TIAM top