変光星・後篇
わたしは中学進学と同時に、父と母の仕事の都合で江戸川を離れた。
以降ずっと、携帯電話を持たないわたしとかずくんは、月に一度の手紙のやりとりを淡々と続けている。
彼は相変わらず野球一筋らしく、手紙の内容といえば日々の練習のことばかり。成宮鳴という男の子、滝川クリス優という捕手、青道野球部の副部長先生の話題もあり、彼が順調に物語への道を歩みつつあることに、わたしは安堵していた。
このままいけば彼は青道高校に進むだろう。
超高校級捕手と称讃され、一年生にして正捕手となり、あの強豪校を引っ張ってどこまでも進んでいく。
その隣にきっと自分がいられないであろうことは、ちょっとだけ寂しいけど、でもずっと前からわかっていたことだ。
松原南朋くんと出会ったのは、中学二年のクラス替えでのこと。
担任から配られた自己紹介シートに記入した「好きなスポーツ:野球」という部分に目をつけて、彼のほうから話しかけてくれたのが最初だった。
「天乃さん、野球好きなんだ? 観るの? もしかしてやるの? 甲子園見る? そういえば天乃って苗字、青道からプロに行った選手と同じだね。親戚とか?」
といった具合。
かわいらしい顔や穏やかな喋り方をしているから女子人気は高いのだが、野球関連はやけにグイグイくるし、当時から明らかに強かな腹の底が見え隠れしていた。
なんだかんだでわたしが野球のコアな話題にもついていけるから、よく喋るようになり、気づけば勝手にコンビ扱いされ、知らない間につきあっているという設定が付与されていて慌てて二人で誤解を解いたのは中二の秋のことである。
「昨日、松原が交通事故に巻き込まれて、救急車で病院に搬送された」
──松原南朋、という名前が色味を伴って頭の中に蘇ったのは、このときだった。
「命に別状はないようだ。みんなも心配だろうけど、いつも通り過ごして、松原が帰ってくるのを待っていような」
松原南朋。足立ロケッツ。中二の事故。……車いすの、鵜久森高校のマネージャー。
「ど……して……」
ちいさく呟いたこの言葉を、隣の席の男の子は「どうして松原くんがそんな目に」だと思ったらしい。彼は涙を堪えた様子でわたしの背中を撫でてくれた。
みんな心配そうにこっちを見ていた。笑顔がかわいらしくて、朗らかで明るくて野球の上手な松原くんはみんなのお星さまだった。彼を中心にクラスがまとまることも少なくなかった。あまりの衝撃に、我慢できずに泣きだしてしまう女の子も、何人かいた。
ごめんね。ちがうんだ。
松原くんが事故に遭ったことが衝撃だったんじゃない。
どうしてこんな大事なこといままで忘れていたの、って、わたし、なによりもまずそう思ったの。
お見舞いに行けるようになったのは、事故のあと二か月が経ってからのことだ。自宅に松原くんから「なんでお見舞い来てくれないの? 暇だから来てよ」という八つ当たりのような電話がかかってきたのだ。理不尽極まりない。
混乱や不安を招かないためか、学校側は生徒に対して詳細を伏せていたけれど、母親の情報網を経由してどういう状況か少しずつ耳に入ってきていた。
そもそも二か月も戻ってこないということは、それなりの怪我だということだ。
中学生にだってそれくらいわかる。
わたしにだって、解っている。
学校が休みの土曜日に病院を訪れると、個室のベッドで身を起こしてテレビを見ていた松原くんは、いつものかわいらしい顔をこちらに向けた。
すこし、痩せたようだ。
ベッドの傍らには空席の車いすがぽつんと置いてある。
「久しぶり。そういえば私服って初めて見るかも」
「そうかもね。……これ、お見舞い。わたしのおすすめのプリン」
「ありがと。じゃあこれ持って帰って」
「はい?」テレビ台の上に置いてあった紙袋を渡される。中身を見ると、ゼリーやシュークリームが入っていた。
「チームの監督とか親戚とかがみんな持ってくるんだ。運動もしないのに一人でこんなに食べてたら太るし、そろそろ飽きたし、天乃さんにあげるよ」
「……なんかごめん」
「いいよ。来てくれて嬉しい」
拍子抜けするほどいつも通りの笑顔で、松原くんは、ぱ、と両手を伸ばした。
まるで「僕の体のこともうわかってるんだよね」とでも言いたげな仕草。こちらも応えて腕を伸ばせば、入院生活でやや握力の落ちた両手でしがみついてくる。
躊躇なく両脇の下に腕を回して体を抱え上げると、体重を預けてきた松原くんは、わたしの肩に顎を載せてちょっと笑った。
「やたら手際いいね」
「そうかな? ふつうだよ」
「うちの母さんより上手。学校でもよろしくね」
「いつ戻ってくるの?」
「さあ」
ちり、と僅かな棘のようなものを感じながら、車いすに座らせる。だらりと投げ出された下肢を整えて、跳ね上げ式のフットサポートに足を乗せてやると、「うん、完璧」とお褒めの言葉を頂いた。
「動いてもいいの?」
「いいよ。病院内ならエレベーターがあるから、車いすに乗れればどこにでも行ける。問題は、コレに乗るために誰かの手が要るってとこだよね。学校に戻ったら大変だろうな」
「学校はエレベーターないしね……」
「そう。登校時と下校時だけじゃない。移動教室のときも、トイレも。これから一生、死ぬまでずっと……嫌になるよね」
最後に浮かべた自嘲の笑みだけが彼の『ほんとう』だと解った。
何も、いえなかった。
タイヤに当ててあるブレーキを解除し、ハンドルを握って、ゆっくりと押す。初動の意外な重みとは裏腹に、滑らかに動き出した車いすを押して病室を出ると、松原くんが指さすほうへとのんびりと歩いた。
すれ違う看護師さんに「こんにちは」とあいさつする彼の横顔には、先程の自嘲の余韻は欠片も残っていない。
強い子だ。
必死に強くあろうとしているさまが、痛々しいほどに。
わたしはこの横顔を知っている。……どうしようもない痛みや悲しみを抱えて、それでも生きていくしかない人の、凄絶な覚悟と途方もない恐怖を秘めた横顔を。
段差やスピードに気をつけて院内をお散歩していると、松原くんは外を指さした。病院着一枚のまま連れ回しているので気が進まなかったけれど、自分の着ていたコートを肩に羽織らせて、渋々ドアを開ける。
二月の寒風が吹き荒ぶなか、松原くんは「うわぁ」と嬉しそうに笑った。
「さむっ」
「だから寒いって言ったのに」
「ずーっと室内にいるから、いまどのくらい寒いのかわかんなくって。寒いからって誰も外に連れてってくれないんだ」
暖かければ患者さんのお散歩コースであろう中庭にも、誰もいない。
コートを貸したこっちのほうが風邪をひきそうだ。やや松原くんが恨めしくなってきたとき、彼は寒さに強張った頬を無理やり笑わせて、背後のわたしを振り仰ぐ。
「ねぇ、僕が野球できなくなっても、友達でいてくれる?」
彼がこんな弱みを見せるとは思っていなかったから、ほんのすこし、驚いた。
「……何いってるの? びっくりした。当たり前じゃない」
「だって僕から野球取ったらなんにも残らないし。仲良くなったのも野球がきっかけだったし、それって江戸川にいる幼なじみとの共通点だからだよね」
ぱちぱちと、自分の瞬きの音が聴こえる。
確かに野球をする松原くんの姿を見て、かずくんのことを思わなかったといえば嘘になる。わたしたちはクラスメイトだけれど、野球がなければこうして話をするような仲にはならなかっただろう。
中学生なんて子どもだと思っていたけれど、子どもって意外としっかり見ている。
車いすにブレーキをかけて松原くんの正面に回ると、地面に膝をついて彼を見上げた。動かない彼の両膝に手を置いて、僅かに顔を歪めている松原くんの目をじっと見つめる。
笑っているのももう限界だったんだろう。
強張った目尻に涙が溜まっていた。
「……もし天乃さんにその気があるなら高校じゃ一緒に野球やろうよって、言おうと思ってたんだ。野球してればきっと会えるよって。けど、もう、むりだし」
「むりじゃない」つい強い口調になって、松原くんの手を握りしめてしまう。
脳裏には生前読んだ物語で、強豪校を次々追い詰めるチームの姿が鮮やかに蘇っていた。
ああ、わたし、松原くんのこと、事故のあとで思い出して本当によかった。
もしこうなるよりも先に思い出していたら、頭がおかしくなっていたかもしれない。
ごめんね。
自分のことしか考えてない愚かなわたし。
それでも友達でいてほしいと願ってくれる男の子──
「……むりじゃないよ。わたしも、松原くんにその気があるなら、高校で一緒に野球やりたいな」
「どうやって。……歩けもしないのに?」
「うん。一緒に考えよ。そして、連れてってよ」
かさついた彼の手を握る、わたしの手の甲に雫がぽたりと落ちる。
声を殺して唇を噛みしめる彼の頭を抱きすくめた。肩に溜まってゆく熱は、いつだったか、おかあさんを亡くしたあと壊れたように泣くかずくんを抱きしめたときと似ている。
きっといつか道は交わる。
甲子園を目指してただ前を向いていれば、彼と会う。
それがこの子のきっかけになるのなら。
「わたしのこと、かずくんのとこまで連れてって」
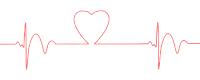
「あーっ、帰ってきた! おかえり、南朋くん英ちゃん」
「南朋くん、練習試合どうだった?」
「おかえり。代わるよ、英ちゃん」
わたしたちの姿が見えるなり子犬のように駆け寄ってくる部員たちに、ちょっと笑ってしまった。
鵜久森野球部には甲子園出場歴などなく、どちらかというと趣味や体を動かす目的で野球をしている先輩が多い。入学当初は松原くんの姿に戸惑われたり、梅宮くんが短気を起こしたりもしていたけれど、いまは一歩引いて見守ってくれているような状況にある。
アーリーに車いすを任せて先輩たちに会釈すると、手を振り返してくれた。
午後練を終えて、受験モードに片足を突っ込んでいる先輩たちは一足先に上がっていく。
足立ロケッツ組は自主練を始めたので、わたしは器具の片づけをしながら、一人ネットスローをしているリーゼント頭に近づいた。
足音を聞きつけて梅宮くんが振り返る。
「……あ? なんだよ」
「飲み物」
スクイズボトルを投げ渡すと、ふー、と息を吐いた彼はネットの前から外れて、わたしの足元に座り込んだ。
……南朋くんに駆け寄ってくるみんなはポメラニアンに見えるけど、この人だけはドーベルマンだな。
なんとなく隣に腰を下ろすと、梅宮くんはちらりとこちらを一瞥して、ボトルに口をつけた。
「どーだったんだよ、練習試合」
「ん? うんまあ、さすが強豪同士っていう感じだったかな。松原くんがしっかりノート取ってるから、あとで聞くといいよ」
「ミユキカズヤは?」
「いいキャッチャーだった。アーリーにあれを目指せとは言えないな」
「…………」
「でもピッチャーは梅宮くんのほうがいいと思った」
「…………、は?」
「なに、そのかお」
ぽかんと開いた口の端からドリンクが零れている。汚いな……。
冷たい目になったわたしに気づいて、梅宮くんは慌ててユニフォームの袖で口元を拭いた。
「天乃が俺を褒めるとか……明日は雪か……」
「失礼ねぇ」
「だってそーだろ! お前いつも俺にだけ当たりが強いだろうが!」
「お互い様でしょ? 梅宮くんだって初対面のとき『南朋この女誰だよ!』なぁんて嫌そうにしたじゃない。あといつも怒ってるのは梅宮くんがいつまで経っても下半身パンツのままだからですぅ」
「おっ、女がパンツとか言うな!」
「女の子に夢を見るのはやめなさい。大丈夫、もうパンツ姿も見慣れたわ」
中学時代、初めて松原くんから紹介されたとき、梅宮くんは金髪のヤンキーだった。
受験に際して黒髪になったはいいものの、鵜久森に入学したらしたでリーゼントにしてくるからどうしようかと思った。それでも、この見た目に反して、松原くんに対する尊敬の気持ちや野球への情熱はどこまでも真摯だ。
すぐ声を荒げたり手足が出たりするのは昔からのようだけど、わたしは殴られたことなんて一度もないし、理由もないのに他の生徒に絡むこともない。
喉を逸らしてドリンクを飲むその横顔をぼんやりと眺める。
「……南朋がよ、昨日、言ったんだ」
「うん?」
「『明日、英をミユキカズヤのところに連れていく。それが鵜久森で野球部に入るための英との約束だったから、もし英の気持ちが鵜久森から離れたらごめん』みたいなこと」
「へぇ。それ本気にしたの、梅宮くん」
「ンなわきゃねーだろ!!」
「やだもう声大きい」
「……ワリ」
しゅんっと小さくなったリーゼントについ噴き出してしまう。
女の子には「梅宮くんって怖くない?」とよく訊かれるけど、こんなに素直でいいやつなんだって、みんなもっと知ってくれたらいいのにな。
だって意外と気が利く。懐に入れた相手は大事にしてくれるタイプだ。
「梅宮くんのそばは安心するね」
「……はっ、ハアァァ?」
「今日、五年ぶりにかずくんに会って、なんだかすごく緊張しちゃった。雑誌で見るよりイケメンだったし。スポサンとかずるくない? 前はこんなにちっちゃかったのに、男の子って成長早いよね」
「……親戚のオバサンかよ」
「叩くよ」
言うが早いかわたしの手はすでにリーゼントの先っぽを叩いていた。「もう叩いてんじゃねーか」と手を伸ばしてきた梅宮くんに、ぶにっと両頬を掴まれる。
カーブを使いこなす器用な指。
長くてきれいな指に、大きな掌。野球ができて、ピアノも弾けるというかなり意外なギャップ持ちの、色っぽい手だ。
「確かにあのときは、松原くんが野球を続ける理由になるのなら、とは思ったけど」
……実際は、あれから彼が「僕はやっぱり甲子園を目指すよ」と笑顔で言えるようになるまで、さらにひと月がかかっていた。
足立ロケッツと引き合わされ、進路指導の先生が見つけてくれた鵜久森を目標に定め、オープンスクールにもみんなで行った。成績が一番やばかった梅宮くんを死ぬ気で勉強させ、どうにかこうにか全員合格、お揃いの制服を着ることができたのだった。
「心外だわ、鵜久森から離れると思われていたなんて。……なんだかわたし、それがとてもショックみたい」
言葉にしてみてようやくわかった。
ああそうか、わたし、悲しいのか。
コテンと梅宮くんの肩に額を預ける。
音を立てて固まった彼の反応が面白くて、すこし笑った。梅宮くんの両手が彷徨って、彷徨って、結局どこにも触れずに膝の上に収まる。
うーん、こういうところだよね。なんだかんだで不埒な真似はしない人だと信頼できちゃう。
「自分でも不思議だなって思うんだけどね」
「………オウ」
「わたし、御幸一也と戦うのが楽しみなのよね」
わたしが『天乃英』として生まれるよりも前の生で、読んでいた愛すべき物語。
鵜久森と青道が大会で相まみえるのは、二年生の秋だったはず。青道は秋大を制し、念願の選抜出場を果たす。鵜久森は稲実を下すけれども、青道に敗れる──
けどそれは物語のなかの話だ。
奇跡のような確率でここにいる『わたし』という存在は、この鵜久森野球部に一体どんな作用を及ぼすだろう?
自分でも悪い顔をしていると思いながら梅宮くんから離れて、悪人面のエースを見上げた。
「かずくんに与えられた野球の知識で松原くんと出会えて、こうしていまここにいる。彼を打ち負かすために全力で挑むのが、かずくんに対する最上の礼儀だと思う。……わくわくしちゃう」
お尻をぱたぱたと叩きながら立ち上がる。
五月も半ばの夕陽は汗が滲むほどの熱を帯びていた。
これから、夏がくる。
梅宮くんに向けて両手を差し向けると、彼はなんだかなぁというような表情になって、ゆるく笑いながらわたしの手を掴んだ。勢いつけて立ち上がる、おおきな彼の影が顔にかかる。
「わたしも一緒に松原くんを甲子園に連れていきたい」
梅宮くんはちょっとだけ目を丸くした。
そうしていると子どもみたいで可愛いのに、すぐにニヤリと悪そうな笑みを浮かべる。まあ、これもこの人のトレードマークといえばそうだけど。
「ったりめーだろ! 何のためにてめーらの鬼メニューこなしてると思ってんだよ」
「あー、そう、鬼ね、鬼。そう思ってたのね。言っとくわ」
「オ──イ待て待ていまそういうアレじゃなかっただろゴルァ天乃!!」
「まーつばーらくーん! あのねー梅宮くんがねー」
「ちょっと待て待て待て!!」
後ろからがばっと飛びつかれて口を塞がれたが、わちゃわちゃしている様子は見えていたらしい。離れたところでアーリーの素振りをチェックしていた松原くんがやわらかく笑った。
「梅宮、英、今日はもう終わりにしよ。部室でミーティングするよ」
わたしたちの、わたしたちだけの『理由』──
わたしたちの三年間は彼のためにある。そう誓ったあの冬の日から、どれほど成長できただろう。
「ていうか梅宮、なに英に抱き着いてんの。外周十周。ゴー」
「うっそぉ南朋サン!?」
「僕の目の黒いうちは梅宮に英はやれない。早く走ってきて」
「だって。じゃあ行ってらっしゃい」
「テメエ待て天乃!!」
茫然と立ち尽くす梅宮くんの腕のなかからするりと抜け出て、砂を蹴り、夕陽のなかに輝くみんなのお星さまのもとに駆け寄る。
くすくす笑いあいながら、握り慣れた車いすのハンドルに手をかけた。
カルさんのリクエストより、高嶺が鵜久森のマネージャーだったら、というお話でした。実はHOLAの時からやってみたかったネタなのと、ちょうどリクエスト募集する直前に鵜久森ブームがきていたこともあって、たいへん楽しくやらせて頂きました。HOLAの薬師ifよりも高嶺が健やかな感じなのは、中学で南朋くんと出会えたからでしょうね。
青道を除くと断トツで鵜久森というチームが大好きです。もっと他の子たちともお喋りしたかったけど、色々詰め込みすぎてこうなりました。梅ちゃんとは戦友みたいな関係だといいなと思っています。
カルさん、リクエストありがとうございました!
青道を除くと断トツで鵜久森というチームが大好きです。もっと他の子たちともお喋りしたかったけど、色々詰め込みすぎてこうなりました。梅ちゃんとは戦友みたいな関係だといいなと思っています。
カルさん、リクエストありがとうございました!
TIAM top