あの子の心臓窃盗罪・後篇
鳴は見事、英を口説き落としたらしい。
大学では野球しないって言ってたけど、鳴に誘われたらマネやっちゃうだろうなぁあいつ──とは思っていたので、メールで報告されたときも特に驚かなかった。
そういうわけで英は結局大学生活の三年半を鳴の野球に費やした。
あの二人なので、青道で俺といたときとは違って入部当初からバチバチ火花を散らし、先輩たちに仲裁され、毎日のように言い合い、ケンカ、罵り合い、それはもう大変な日々だったそうだ。逐一電話やメールで愚痴られた。英がこんなふうに俺に愚痴を言うようになったのは、なんだか新鮮だ。
英って、鳴と一緒にいるときだけ子どもみたいになる。
俺たち相手にはお姉さん風を吹かせていたくせに。
「キスされた」
「…………はあ?」
場所は都内のやっすい居酒屋。
プロ四年目の俺と、大学四年生の英。
英は二年生の頃に完吾兄ちゃん関連のSNSでついに世間に顔バレし、なし崩しに俺との幼なじみ関係や青道の鬼マネ時代、果ては現在の成宮の右腕っぷりまで露呈している。それに関しても逐一愚痴られた。
昨日のことだ。
珍しく英から「聞いてよ一也っ!!」と電話がかかってきた。
明日なら時間もあるし直接会って話聞くぜと俺が提案し、英ご指定の個室居酒屋(奢るっつってんだから高いとこ選べばいいのにリーズナブルなとこだ)で落ち合い、英はいい具合にほろ酔い。
カクテル一杯で顔を真っ赤にして、普段よりふにゃふにゃしている英はもう一度「キスされた」と繰り返した。
「キスって……えーっと鳴に?」
「鳴以外に誰がそんなことするのよっ」
「俺とか」
「そうですね!!」
テーブルに突っ伏して大声で認める英に、悪いと思いつつちょっと噴いてしまった。そうですね、て。
シーザーサラダを口に運びながら、英の頭をなでこなでこしてやった。
英は特別な事情さえなければ、基本的に人当たりがよく良好な人間関係を築けるタイプだ。しかしその反面、俺しか知らない複雑な生い立ちゆえ他人に対する警戒心は強く、心理的ハードルが高い。
そしてその反動であるかのように、一度懐に入れた相手には気を許しすぎてしまう。
俺。倉持。紅子さん。青道野球部の面々。そしてこの三年半で英の内側に踏み込んだ、鳴。
鳴の箍が外れたんだな、多分。
で、鳴を男として警戒するという発想のなかった英はあっさり唇を奪われたと。
……というか、「英がほしい」宣言からほぼ四年。鳴もよく我慢したほうだと思う。
とはいえ。
「無理やりだったのか」
「……え?」
「泣いたか? 傷ついたか。不愉快だったか。鳴はお前のこと力で押さえつけて最低なかたちでキスしたか?」
「一也、なに言ってるの」
「お前が鳴に泣かされたなら、今からブン殴りに行く」
「ちょちょちょっと待って」
席を立つ真似をすると英は慌てて両手で縋りついてきた。
「違う! 平気! 泣いてないし鳴がそんなひどいことするわけないでしょ!」
「じゃあ合意の上だったのか?」
「そうでもないけどとにかく落ち着いて座って! あのね、わたしだって本当に嫌だと思えば急所を蹴り上げることくらい吝かじゃないのよ。嫌じゃなかったから困ってるんだってば……!」
……だろうな。
だってこの居酒屋で合流したときから、辛いとか傷ついているとかじゃなくて、超弩級にどうしたらいいかわからなくて困ってます、って顔だった。
うちの可愛い幼なじみは、随分とあの我が儘キングに振り回されているみたいだ。
本気で慌てているらしい英にフッと笑うと、俺がからかったことに気づいたらしい。
「もう、性格わるっ!」
「はは、悪い悪い」
気を取り直して席に戻ると、英は小さく息を吐いてから呼び鈴を鳴らした。
「一也なにか頼む?」
「んー、卵焼き。お前は?」
「お冷……」
どうやら興奮した拍子に体温が上がったようだ。ぱたぱたと手で顔の辺りを仰ぎながら、「はぁ」と情けない声を零している。
「で? 嫌じゃなかった自分に戸惑ってるのはわかったけど、鳴はお前に告白したわけ?」
「告白、っていうか……。ずっと冗談だと思って流してたんだけど……」
「あー。流されまくって本気にしないから鳴がキレたんだな」
「一也はエスパーなの?」
「わかるよ。お前らのことだし」
英の話から推測するに、去年あたりから鳴は「英に触っていいのは俺だけ!」モードに入っていたらしい。
そうはいっても英からすれば、昔からいがみ合ってきた相手。同じ野球部の仲間として過ごすようになってからも毎日毎日ケンカしていたような鳴だから、「また変な独占欲を発揮してコイツは……」程度に思っていた。
さすがに昨日の事件があって思い返してみると、気づかなかった自分がただの阿呆なレベルで鳴からアタックは受けていたようだ、と。
「ふつう気づくだろ……わりとあからさまだったんじゃねぇの?」
「だって鳴だもの。金魚のフン呼ばわりしてきた人よ?」
「何年前のネタ引きずってんのお前! 言っとくけど鳴、高三の冬にはお前がほしいって俺に言いに来たからな?」
「はああっ!?」
英の声がひっくり返ると同時に、「お待たせしました〜」と店員が顔を覗かせた。
恥ずかしそうに口元を隠した英に代わって食べ物やお冷を頼む。店員が引っ込んでから、英は「うそでしょ……」と眉を下げた。
この「うそでしょ」は、本当に疑っているわけではなくてただの感嘆詞なのでスルーだ。
「英はさ、別に鳴のこと嫌いじゃないだろ」
「そりゃそうだけど」
「昔から鳴の投手としての実力は認めているし、素直に世代No.1サウスポーだっていつも言ってた。鳴のエースとしての強烈な自負とか覚悟とかそういうものも、大学に入って隣で見るようになってから前よりずっと尊敬してるって聞いた。潰れないように支えたいって思ったってのも、俺はこの三年半聞いてた」
頬杖をついて英を見つめる。
まあ、そりゃちょっとは寂しいよ。
俺だけの英でいてくれた十八年間はずっと感謝しっぱなしだった。鳴の右腕になってから自分も色々忙しかっただろうに、いつも俺のことも気にかけてくれた。都合がつく限り試合も観に来て応援してくれた。
これからもずっと、俺だけの幼なじみ。
世界で一番、幸せになってほしいと常に願っている。
「俺は、お前が一番幸せになれる道を選んでほしいし、そのためなら相手が誰だろうとお前を泣かすやつはぶっ飛ばす。──もし離れたところで生きていくようになっても、俺が一番、お前の幸せを願ってるよ」
英は目を丸くした。
酔いのせいか、別の理由か、形のいい大きな双眸は涙で潤んでいるように見えた。
「だから、怖がってないでちゃんと鳴の顔見てやれよ」
いい加減、俺たちの世界は広がった。
もう昔みたいに、別々の人生を歩むことを恐れなくてもいいくらいには。
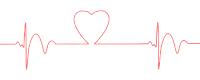
「怖がってないでちゃんと鳴の顔見てやれよ」──
そういえば一昨日は、鳴の顔を真っ直ぐ見ないで逃げだしたような気がする。
野球部の同期と晩ご飯を食べたあと家まで送ってくれた鳴に、掠めるようにキスされて、驚いて絶句するわたしに彼は小さく「ごめん」とつぶやいた。「でもいつまで経っても冗談だと思ってるから」「俺はずっと本気だったよ」と捲し立てる鳴の顔は、暗くてよく見えなくて。
……いやそもそも付き合ってないのに不意打ちで接吻する輩もどうかとは思うけどね?
「……まあ、それだけ流しまくってたのは事実だもんね……」
なんだか世界がひっくり返ったような気分だ。
だって子どものころからずっと、一也の傍にいるわたしを気に食わないと突っかかってきていたあの鳴なのに。彼とわたしは野球を通してだけ互いを認め合っていて、他の関係になんてなりようがないと思い込んでいたのに。
一也と飲んだ翌日の講義終わり、学食で野球部の同期を見つけたのでとっ捕まえる。
「どうした天乃ちゃん、この世の終わりみたいな顔して……」
「あのね、つかぬことをお聞きするんだけど、鳴の好きな人が誰か知ってる?」
「…………え?」
あ、これ「お前が言うの?」って顔だ。
「わかった。知らないのはわたしだけだったのね。ありがとう」
「イヤだってあんなわかりやすかったのに……」
「わたしは直接面と向かって『好きだ』って言われないとわからない人間なの」
「厳しいな!!」
がちゃんっ、と何かが盛大に床に落ちる音がした。
同期と顔を見合わせて音の発信源を辿ると、案の定、足元に食器をぶちまけた鳴が立ち尽くしている。
幸い食事は済ませたあとだったらしい。食器も全部プラスチックだから割れてはいない。
「……何ぼけっとしてるの。邪魔になってるわよ、鳴」
あ〜〜〜一也助けて。
顔見てやれよって言われたけど、ちゃんと見たけど、口が勝手に素っ気なくしてしまう。アワアワしている同期を「ありがとね」と遠ざけて、凍りついたままの鳴の足元の食器を拾った。
今度は彼のほうが目を合わせようとしなかった。
わたしが拾った食器やトレーを渡すと、鳴は目を逸らして受け取る。斜め下を見つめて伏せた睫毛が震えていた。
いっそ噛みついてくれたほうがよかった。
そうすれば、いつもみたいに言い合えるのに。
こう考えること自体すでに鳴とちゃんと向き合っていない証拠かもしれない。
鳴の横を抜けて食堂を出た。
……せっかく一也に背中を押してもらったのにな。
目を合わせてくれなかったくらいでこんなに落ち込んでいる。子どもの頃なんて、顔を背け合うのが当たり前だったのに。
同じチームで一緒に野球をしていたこの三年半があまりに穏やかだったから、ショックでも受けているのかしら。
「……ああもう。あんな素っ気なくしたら鳴だってさすがに気まずいわよね」
昼休みの構内は、校舎と校舎を移動する学生で溢れかえっている。
その流れを堰き止めるように立ち止まり、わたしは一人頭を抱えた。自己嫌悪。大体にして相手が鳴でさえなければ、さっきだって何事もなくにこやかにできたはずだ。
そういえば一也にも昔、お前は鳴相手のときだけ見た目相応に子どもっぽい、って笑われたっけ。
いつだって鳴だけは、本音そのままで丸ごとぶち当たってきたから。
「…………」
うん、戻ろう。
とにかく色々と複雑なことは措いておいても、目を逸らしてモヤモヤしたまま放置するのは一番よくない。
そう思って踵を返した瞬間、後ろから勢いよく走ってきた鳴と正面衝突した。
お互い完全に不意打ちをくらってコントみたいに尻餅をつく。
「いった……」
「〜〜なんで急に方向転換すんだよ! バカなの!?」
「……振り返らなきゃよかった……」
鳴の開口一番がろくなことだった試しなんてないのに、懲りずに憎まれ口を叩いてしまった。
とりあえず尻餅状態から復帰して、わたしは地面にばらまいた教科書類を拾う。その手首を全力で掴んだ鳴は「怒ってる!?」と大声で訊いてきた。
声が大きすぎて周りの学生にちょっと注目された。
「べつにそこまで怒ってるわけじゃ……いやちょっとは怒ってるけど」
「どっちだよ! そもそもあんだけ解りやすい態度とってたはずなのに一切本気にしないで流しまくった英だってちょっとくらい悪いから!」
「それは理不尽すぎ。我が儘キングが許されるのはマウンドの上だけよ」
「うっ……」
合意なき行為という意味で全面的に自分に非があることは認めているのか、鳴はそれ以上反論を重ねようとしなかった。
手首を掴まれたせいで荷物が拾えない。大学構内の隅っこといえど大勢の学生が往来するメイン通りだ、そんな場所でしゃがみ込んでいるわたしたちはだいぶ目立っていた。
「……放してよ」
「放さない。放したらまた英が逃げるから」
「だって目を合わせなかったのは鳴よ」
「それはお前がやたらと厳しい英理論を展開するからじゃん! なんなの! 俺のこれまでのアピールなんだったの!!」
「腹を割って正直に言うけど、『また鳴の意味不明な我が儘がはじまった』程度にしか思ってなかった」
「この鈍感娘ッ!!」
声を大にして罵られた。
あんまり強くは否定できないので黙って睨みつけるに留める。わたしの視線に一瞬だけたじろいだ鳴は、それでも頑なに掴んだ手首を放そうとはしない。
多分、振り払おうと思えば簡単だ。
でも鳴はわたしがそうしないことを解っている。
大事な大事な投手の体。ましてや鳴の利き腕。乱暴なことなんてできないと、この人は細胞レベルで理解しているから。
「ッああもう、天乃英!」
半ばやけになったような声音の鳴がきっとわたしを見つめた。
「〜〜〜結婚してっ!!」
一瞬、すべての音が消える。
比喩ではなく。
こんな真昼間の大学構内で、有名人の成宮鳴が急にプロポーズしはじめたから、人の流れも話し声も全て途絶えてみんながこっちに注目したのだ。
相変わらず行動の読めない鳴のびっくり発言に、わたしは盛大に頭を抱えた。
いや、──なんでそうなる。
「唐突すぎる。やり直しっ!」
「うっそお! なんで!?」
「胸に手を当てて自分で考えなさいよバカ鳴っ!!」
「バカって言ったほうがバカなんですけど!?」
「小学生レベルの反論やめてくれない!? 本当、昔っから全然成長してないわねこの我が儘キング」
「恋愛レベル小学生並みのバカ英に言われたくないんですけど!!」
いつだって鳴だけは、本音そのままで丸ごとぶち当たってきたから。
だからわたしも難しいこと全部ほっぽって、『わたし』のままぶち当たり返せる。
──とまあこんなやり取りが何度も繰り返された結果、わたしは最終的に鳴に泣き落とされた。
本当に泣かれた。
数年後になんとか開催された結婚式では、御幸一也を新郎側で招待するか新婦側で招待するか揉めに揉めて、第一次離婚危機に陥ったのだけれど──これはまたいつか、別のお話で。
ぺみ子さんより「成宮と高嶺が付き合うことになった場合の御幸視点」、桃栗子さんより「アフターダーク成宮くんルート」というリクエストでした。
アフターダーク成宮ルート時々御幸視点のつもりで書き始めたのですが、色々詰め込みすぎてリクエストからちょっとずつ離れていってしまった気がしなくもないです。力不足で申し訳ありません……。個人的にはとても楽しかったです。
(ちなみに成宮夫妻は結局御幸一也宛てにそれぞれ招待状を送付しました。招待状を二通もらっちゃった御幸は鳴宛てを『欠席』高嶺宛てを『出席』で返送して新婦側ゲストで参列。一回目のお色直しエスコート新婦側で呼ばれ、二回目のお色直しエスコート新郎側でまた呼ばれる忙しい披露宴になりました──という後日談)
ぺみ子さん、桃栗子さん、リクエストありがとうございました!
アフターダーク成宮ルート時々御幸視点のつもりで書き始めたのですが、色々詰め込みすぎてリクエストからちょっとずつ離れていってしまった気がしなくもないです。力不足で申し訳ありません……。個人的にはとても楽しかったです。
(ちなみに成宮夫妻は結局御幸一也宛てにそれぞれ招待状を送付しました。招待状を二通もらっちゃった御幸は鳴宛てを『欠席』高嶺宛てを『出席』で返送して新婦側ゲストで参列。一回目のお色直しエスコート新婦側で呼ばれ、二回目のお色直しエスコート新郎側でまた呼ばれる忙しい披露宴になりました──という後日談)
ぺみ子さん、桃栗子さん、リクエストありがとうございました!
TIAM top