星空のコンポート
「英〜〜」
午後練の始まる直前、着替えてドリンクなどの準備をしていると、これから部活だというのになぜかすでに疲れた顔をしている一也がひょこっと顔を出した。
「どうしたの?」
「なんかお前のばあちゃんから俺宛てに荷物届いてんだけど……」
「はい?」
『天乃英』の祖母は、父方はすでに他界している。
母方は健在で、現役で農業に勤しんでおり、わたしたちが子どもの頃はよく運動会や学芸会を見るために遥々東京まで来てくれていたパワフルな人だ。その関係で一也も面識があるし、長期休暇に遊びに行くと大抵「一也くんは元気にしてるのかい」なんて訊かれるほどだった。
けれど、さすがに一也宛てに荷物というのは心当たりがない。
なんだなんだと管理人室に二人で向かってみると、確かに存在感のある段ボール箱がでんと置いてあった。
試しに持ち上げようとしてみたけれどかなり重い。
《東京都国分寺市……
青道高校野球部青心寮
御幸一也 様》
「……荷物送るなんて聞いてないけどなぁ」
「怖いから一緒に開けてくんね?」
「そんな爆発物じゃあるまいし」
とはいえ怪しいのは確かだ。差出人は確かに田舎の祖母の名前になっていたが心当たりもない。管理人室でカッターナイフを借りてガムテープを切った。
中にはぎっしり野菜が入っていた。
白菜。大根。トマト。玉葱。じゃがいも。祖母が畑で作っている野菜ばかりだ。
「……あ、手紙入ってるよ」
一番上に乗っていた便箋を開くと、祖母の字で《一也くんへ》と書いてあった。
《前略 先日、完吾くんと電話をした際に一也くんがけがをしたという話を聞きました。たくさん食べて早くよくなってください。英ちゃんにでも言えば夜食を作ってくれるでしょう。ふたりとも野球がんばってね。英ちゃんのばばより》
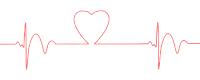
英ちゃんにでも言えば夜食を作ってくれるでしょう。
というなんとも投げやりなフリを受け、わたしと一也で一晩考えた結果こういうことになった。
送られてきた野菜で何か料理を作ろう。
二人じゃ食べきれないから寮生も巻き込もう。
となると材料を買い足す必要があるので、何人か出資者を集めてお金を出し合い、夜食を作ってみんなで食べよう。
翌朝から寮内で呼びかけた結果それなりの人数が集まった。
監督たちの許可、メニュー考案、必要な材料のリストアップ、厨房の使用申請、調理手順の確認、買い出し──
「ということで第一回、おばあちゃんの野菜ファンドを始めます」
そして諸々の準備と当日の午後練・夕食を終えて厨房に立つと、出資者の面々がなんとなく場の空気に流されてパチパチと拍手した。何か始まるらしいぞと食堂に残っていた一年生はキョトンとしている。
ちなみに、金銭トラブルがあってはいけないので今回の出資者は二年生のみに絞っていた。
どうせみんな同室の後輩や受験勉強中の先輩たちに分けてあげるんだろうけど。
「なんか手伝うことあるか!?」
ソワソワしながらわたしたちの準備を眺めていたゾノくんが声をかけてくれる。
健二郎さんやノリくんもこっちを見ていたので、「よくぞ聞いてくれましたっ」と手を合わせた。
「これから作るのはチキンのトマト煮、鶏と大根の照り煮、豚バラ白菜、ポテトキッシュ、じゃがいもおもちの五品ですが……」
「オウ! なんや野菜切ればええんか!」
「いやそんな怖いことしなくていいから厨房に近づかないで」
「英ちゃん、本音出てるよ!」
「おっと、失礼しました。──あのね、みんなはたくさん体を動かして、お腹ぺこぺこにしてきてほしいの!」
にっこり笑って語尾にハートマークを飛ばすと、二年生はぶはっと噴き出した。
「そうか! それなら俺ら誰でもできるな!! よっしゃ行くで小湊っ」
「あ、はいっ」
気合い充分のゾノくんは迷うことなく食堂を飛び出していった。小湊くんはニコッと笑ってあと追いかける。
倉持が沢村くんを、小野くんが降谷くんをといった具合で同室の二年生が一年生を連行していった。ノリくんとナベくんは「二人で大丈夫?」「手伝おうか」と声をかけてくれたけど、慣れない料理で怪我をさせるのも心配だからと自主練に行ってもらった。
しんと静まり返った食堂で、さて、と顔を見合わせる。
「なんか久々だな、料理らしい料理」
「頼りにしてますよ一也さん」
「お手柔らかに」
ごろごろと並べた野菜たちを一也と手分けして解体にかかった。
「そういや、監督たちも出資リストに入ってるって?」
「ああ、そう。厨房のこともあるから相談に行ったら、礼ちゃんと太田監督がノリノリで参加してくれて、片岡監督も笑いながら。あとで出来立て持って行こうね」
お喋りしながら一也が大根の、わたしはじゃがいもの皮を剥いていく。
寮生活をしていると特に披露する機会はないけれど、一也は料理が上手だ。
凝ったものを作るわけではないが手際がいい。冷蔵庫の中のものでその日の晩ご飯を作れる主夫スキルが高いのだ。
エプロンをつけた一也がとんとんと大根をいちょう切りにしていく様子を見つめていると、視線に気づいた彼が「なんだよ」と眉を寄せた。
「いいえ。料理のできる男って色っぽくていいわよね」
「そーか? 別に普通だろ」
「昔は一也が包丁を握るのが危なっかしくてハラハラしてたけど、今はすごく素敵よ」
「……あっそ」
照れたな。
「料理のできる男はモテるわよ?」
「はいはい」
皮を剥いて水にさらしたじゃがいもは電子レンジに突っ込んだ。
見やすいよう壁に貼ったレシピを確認しながら作業を進めていく。ポテトキッシュとじゃがいもおもちで必要になる卵や牛乳などを準備している横で、一也が「野菜終わったけど」とこちらを見た。
さすが、早い。
「じゃあ、じゃがいも出してフォークで潰して。キッシュのほうだから粗めに」
「はーい。こっちのじゃがいももチンすんの?」
「うん、そう」
本当は手際がいい一也に調理もお任せしてしまいたいくらいだけれど、一応おばあちゃんからの手紙には《英が夜食を作れ》と書いてあった。オフで試合もないとはいえ料理で怪我なんてことになっても困るので、軽めの作業を回すことにしている。
わたしのほうは、さいころ大に切ったトマトを鍋に突っ込んで調味料を投入。
ことことと煮込む傍ら、室温に戻した鶏肉にフォークを突き刺していく。
「ポテトサラダがよかったな」
じゃがいもを潰しながら一也がつぶやいた。
「……夜食には向かないなーって思って」
「こんだけじゃがいもあったら普通ポテトサラダだろー」
「だってお母さんの味にならないんだもん。何入れてるのって訊いても、別に普通って答えるし」
「何入れてるって?」
「じゃがいも、きゅうり、ハム、塩胡椒、マヨネーズ」
「普通どころかけっこうシンプルなほうだよな。卵とか玉葱も入ってねぇし」
天乃家の母のポテトサラダは絶品だ。
わたしの舌に合いすぎて、その他市販のポテトサラダが好きになれないくらい。
江戸川にいた頃も青道に入学してからもたまに自分で作ったけれど、教えられた通りにやってもどうしても母の味にならないのだ。人生最大の難問かもしれない。
「英の作ったのもよかったと思うけどな」
「そうー? 料理に関しては全然自信がないわ。一也のほうが上手だし」
「俺は、英の弁当好きだったよ」
鍋の中のトマトを木べらで軽く潰していく。
そっと顔を上げると、一也もこちらを見ていた。
「自分で作る晩飯より英の弁当のほうが美味かったよ」
「……そ、そう?」
「そう」
「…………」
「…………」
「……一也面白がってるでしょ」
「照れてる英が可愛くて」
ニヤリと口角を上げた一也にぎゅううと眉を顰めてやった。
「まー嘘は言ってねぇけど」
「はいはい」
「英さーん? ホントだぜ?」
「はいはい!」
「照れてら」
うるさいっっ。
ニヤニヤしている人から勢いよく顔を逸らして、トマトの横のコンロにフライパンを置く。油を敷いて鶏肉に火を通し、あとはトマトと玉葱と一緒に煮込んでいくだけだ。
一也のほうは着々とキッシュの準備を進めてくれている。
「英」
「なんですか」
「拗ねんなよ。髪、変なとこぴょこってなってるから結び直す」
「そう、……じゃあお願い」
鶏肉を鍋に移すと、トマトの水気もあってか一気に嵩が増した。寮の大きい鍋を借りられてよかったな。
手を洗ってから背後に立った一也の手が、料理前に適当に一つ結びにしていた髪をゆっくり解いた。
常に爪を短く切り揃えている指先が髪を梳く。人をからかってばかりの意地悪キャプテンのくせに、やたらと優しい手つきで。
「好きよね」
「え?」
「わたしの髪、触るの好きよね」
「……その話、前もした」
「そうね。でも今また思ったものだから」
玉葱とコンソメ、塩胡椒を適当に振って落し蓋をする。
髪の毛をゆっくりと結び直した一也は、ごつ、とわたしの後頭部に額を落とした。
「なぁに」
「……なんか色々考えた」
「なにを?」
「懐かしくて。俺が料理する横で、英は切り方が雑だの塩入れすぎだの文句つけてきたなーとか、俺には見栄えよくできたおかず入れてくれて、自分の弁当は分解したアスパラベーコンとか卵焼きの焦げた部分だったなーとか」
「それを考えれば成長したものねぇ、わたしたち」
「本当になー」
でも俺は、ばらばらになったアスパラベーコンでも焦げた卵焼きでも嬉しかったよ。
そう小さく零して、一也は離れた。
……そう。
ずっと、わたしの自己満足だと思っていたけど、あなたが嬉しいと思ってくれていたならそれでいいわ。
なんだかにやけてしまいそうな口元をぎゅっと引き締めて、フライパンを取り出す。
「ほら、動いて動いて。お腹すかせた子どもたちが帰ってきますよ」
「俺あんな子どもいらねー」
「少しは母扱いされるわたしの苦労も知りなさい」
それからも手を休めることなく料理を続けること小一時間して、ようやく予定していた五品が完成した。
まず出来立てを少しずつ取り分けて監督たちに持っていく。先生方はぽんっと大きめの額を出してくれたので、レンジでチンするタイプの白米も添えて渡した。
「これ、御幸くんと天乃さんが?」
「二人ともなんでもできるんだなぁ」
礼ちゃんと太田部長が大袈裟にびっくりしている横で、監督は「怪我しなかったか」なんて声をかけてくれた。
そこはかとない子ども扱いがくすぐったくてちょっと笑う。
「大丈夫です。……残ればジップロックで冷凍しておきますので、先生方もまた召し上がってくださいね」
「残らないだろう、これは」
「実は倉持たちに『お腹ぺこぺこにしてきて!』って言っちゃって。残らないかも」
監督はふっと笑って、「いただきます」と手を合わせた。
目の前で大人たちに賞味されるのも恥ずかしかったので、「食器あとで取りにきますから」と言い残して外に出る。階段を下りていくと、ちょうど自主練に出ていたみんながわらわらと食堂に戻ってきたところだった。
わたしの顔を見たゾノくんと倉持がさっそく絡んでくる。
「お。お母さんやん」
「オカン腹減った」
「今日ばかりはオカン呼びも文句言うまい。ちゃんと手洗ってきなさいよ!」
「「「お母さん……!」」」
嬉しそうに手洗い嗽をした子どもたちは、食堂のテーブルに大皿で用意された夜食を見て歓声を上げた。
夜食というかもはや二度目の晩ごはんだ。
それでもみんないつもより運動の量を増やしたらしく、「意外とうまそう!」「号令まだか!」とわいわい詰め寄ってくる。よく食べる、本当に。
「ふふん。なんか気分いいわね、褒めてもらえると」
「ははっ、確かにな」
おばあちゃんへ送る証拠写真を何枚か撮ったあとで、各自食器を用意する。三年生のところに差し入れする分、それから宛先的にまず食べるべき一也の分を取り分けると、一年生も含めた参加者たちはお行儀よく椅子に座った。
これは、あれかな。
わたしの号令待ちか。
横にいた一也を見ると肩を竦めていた。
「それじゃ、今日も一日お疲れさまでした。手を合わせましょう。いただきます」
「「「いただきますっ」」」
……冷凍するぶんなんて残らなさそうだ。
あっという間に減っていく大皿の中身を苦笑いで眺めていると、悠々と食べ進める一也は「うまいよ」とつぶやいた。
それが聞こえたのかなんなのか、みんな一々「これうまい」「俺これ好き」と報告にくる。褒めてもらえて気分いいってさっき言ったからかしら。
自己肯定感がめきめき上がりそう。
「あのね、わたしも一也にお弁当つくるの好きだったよ」
「……そ」
一也はなんだか微妙な顔つきになって、お箸に挟んだ豚バラ白菜をわたしの口に突っ込んできた。
照れてるなぁ。
うふふと笑って顔を覗き込むと、ほんのちょっと頬を染めた一也が続けざまにじゃがいもおもちを差し出してくる。ニヤニヤしながら口を開けたところで麻生くんが「イチャイチャしてんじゃねーよウゼェな!!」と怒鳴った。
いつもとほんのちょっとだけ違う夜食の時間は、そんな風に更けていった。
幸流さんのリクエストより、御幸と寮でお料理するお話でした。
改めて御幸と寮で料理ってどんな状況だろう……と頭を悩ませた結果、田舎のおばあちゃんが出てきました。野菜食べてれば元気になると思ってる系おばあちゃんです。二人にとっては料理とかお弁当って共通の思い出なんだなぁ、と懐かしく思いながら書きました。あと高嶺のオカン属性に拍車がかかるな、とも(笑)
マッタリと平和なお話になりました。ご査収ください。リクエストありがとうございました!
改めて御幸と寮で料理ってどんな状況だろう……と頭を悩ませた結果、田舎のおばあちゃんが出てきました。野菜食べてれば元気になると思ってる系おばあちゃんです。二人にとっては料理とかお弁当って共通の思い出なんだなぁ、と懐かしく思いながら書きました。あと高嶺のオカン属性に拍車がかかるな、とも(笑)
マッタリと平和なお話になりました。ご査収ください。リクエストありがとうございました!
TIAM top