残星を齧る日々
「ここに一枚のチラシがあります」
そう言って紅子が広げて見せたのは、都内にある私立大学で開催される大学祭のチラシだった。
きょとんとしている一也は措いておくとして、わたしは立派な受験生だし、倉持も野球推薦の大学進学を視野に入れる高校三年生。ぱっと大学名を見て、ああ、と納得の声を上げた。
「吹奏楽が強いところよね。受けるの?」
「硬式野球はそんな強くねぇよな」
「受けるかどうかは別として、兄貴がここに通ってんの。吹奏の演奏会も聴いてみたいし、兄貴の軽音ライブもあるし、気分転換と大学見学がてらどうかなと思ってさ」
進路が野球関係でほぼ決まりの男二人が途端に「俺らには関係ねーな」みたいな顔になった。
そんな男二人の机をバシッと紅子が叩く。
この二人、わたし以上になぜか紅子には逆らえないのだ。ビクッと肩を震わせながら、にっこり笑顔の彼女を見上げた。
「もちろん来るよな? 現役引退して暇なんだからさ」
……三人の名誉のために言っておくけれど、男二人だってさすがにそこまで暇ではないし、紅子もそのへんはちゃんと解っている。
解っていてなお押しが強いのが、紅子の素敵なところだ。
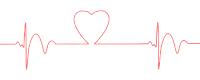
全国区に名の知れた大学とあってさすがに賑わっていた。
正門をくぐった先の受付でパンフレットを受け取り、ひとまずの目的である『吹奏楽団の演奏会』と『軽音部のライブ会場』を確かめる。吹奏楽部は構内の大きなホールで、軽音部は普通の教室にセットを組んでやるようだ。
至るところに出展された屋台数も、学部別の展示も、サークルの出し物も、何もかも高校とは規模が違った。
青道の文化祭もそれなりに立派なものだと(前の人生と比較して)感心していたものだけど、やっぱり大学は動員数も予算も桁が違うものだ。
「兄貴の出番は午後だって。どっか気になるとこある?」
「わたし、薬草研究会の健康茶」
「うわ、薬学部で酒提供してる。さすが大学」
「硬式野球部はホットドッグ屋台……まあそんなもんか」
紅子が広げた学内の地図を四人で覗き込む。
わたしの肩にかけていたカバンが通行人とぶつかって蹈鞴を踏んだ。「人多いな」とすでにげんなりしている一也の右手が背中に回って、一歩引き寄せられる。
じ、とその横顔を見上げると一也は眉を顰めた。
「……なに」
「いいえ。はぐれないよう気をつけます」
「はぐれたら置いて帰る」
「そんな!……まあ都内だから別に一人で帰れるけど」
「置いて帰れるわけねーよなこのメガネが」「血相変えて捜しまわるに決まってんのに何言ってんのこいつ」と堂々陰口を叩く倉持・紅子。まあわたしも、なんだかんだ言って捜してくれるんだろうなこの人、と思いますけれども。
すでに大学進学には縁がないからか、一也は完全に保護者気分でついてきてくれている。
多分紅子がぐいぐい押さなければ来もしなかっただろう。
「まあ御幸は過激なファンに見つからないよう大人しくしてな」
「そんなんいる?」
「いるかもしれないじゃん。いいからイケメンは目立つな」
遠慮容赦のない紅子の物言いに、顔を見合わせてちょっと笑った。
とりあえず最初に目についた薬草研究会の健康茶という展示に向かうことにした。
講義室にずらっと並んだ様々な茶葉を自分でブレンドし、お隣の講義室でいただくというかたちになるらしい。乾燥前の葉っぱの写真、効能などが添えられている。毎年恒例の展示なのか、わたしたちの前に入った家族連れは慣れた様子で茶葉をスプーンで掬っていた。
高校までとは違って、大学の教室は長机に椅子がついている。倉持たちは新鮮な気持ちで「お〜」「大学っぽい」ときょろきょろ見渡す一方、わたしはひっそりと懐かしさを感じていた。
受付でもらった紙コップにはお茶パックが入っている。そのなかに数種類の茶葉を入れて、お隣の講義室の教壇に用意されていたポットでお茶を淹れた。
空いていた席に腰掛けて、のんびりとお茶を冷ます。
「どう?」
「熱すぎてよくわかんね」
わたしの隣に一也が座って、後ろに紅子、その隣に倉持。
三年間で四人一緒のクラスになることはなかったので、なんだか変な感じだ。
みんなで大学に通ったらこんな風に授業を受けるのかな。──あり得ないと解っているけれど、なんとなく想像して笑ってしまった。
「なんだよ?」
「んーん。一也と一緒に大学生になったみたいで楽しいなって」
「…………」
ふいっと顔を逸らした一也の後ろ頭を、倉持がニヤニヤしながら小突いた。
健康茶をいただいたあと、その棟でしていた他の展示を見回ってから外に出ると、ちょうどお昼時になっていた。
屋台のラインナップを見るに、うどんや焼きそばなどのごはん系も充実しているようだ。
「あ、これいいな。チョコバナナ」
「正気かお前。昼飯だぞ、昼飯」
「いいじゃないの別にー」
チョコバナナ組とごはん組に分かれることになった。
わたしと紅子がチョコバナナ、倉持がうどんで一也が焼きそば。中庭に腰を下ろして食事している人が多かったので、そこで落ち合うことにした。
「紅子のお兄さん、何年生だったっけ」
「経営学部の二回生。高校生の時からバンド組んでたから、まあそれなりにうまいよ」
「楽しみ。こういうライブって初めてだわ」
ざわざわと、青道の文化祭の時に似た高揚感が辺りいっぱいに広がっている。
構内に設えたスピーカーから流れる放送や音楽。お客さんの騒めきと、屋台の呼び込み。すぐそばを通りかかる、お祭り特有のよくわからないコスプレの人たち。実行委員だろうか、お揃いのパーカーや腕章をつけた役員。
無事にチョコバナナを二本購入したわたしたちは、早速齧りながら地図を広げた。
大学は広い。油断すると迷子になる。
「えーっと、チョコバナナがここでしょ。校舎がこっちだから地図はこう向けて」
「来た道を戻って左に行けばいいのよね」
……とは思うのだけれど、人混みのせいでいまいち周りの景色が覚えられないから自信がない。
まあいざとなれば携帯で電話すればいいかと顔を見合わせていると、「迷子ですか?」と横から声をかけられた。
ここの大学生だろうか。ギターケースみたいなものを背負った男の人が二人。
「中庭に行きたくて」
正直に答えると、男性二人に見えない背中を紅子につねられた。
なぜ。
「あー、中庭あっちですよ。どこの大学の人?」
「いえ、高校生で……す」
またつねられる。
わかったわかった、迂闊に個人情報を洩らすなということね。
そのままごく自然に中庭方面へと付き添ってくれた男性陣は、人の好さそうな笑みで「高校生かー」とうなずいた。
「二人とも大人っぽいから大学生と思ったわ。受験生?」
「はい、大学見学と受験勉強の息抜きに。ご親切にありがとうございました」
「よかったら案内するよー」
「そうそう、うち広いし」
にっこり笑って、隣でやや呆れた表情になっていた紅子にぴたっと身を寄せる。
何をどうすると打ち合わせていたわけでもないのに、彼女は全部お見通しといった仕草でわたしの腰に手を回した。
なぜかしら、一也にされるよりドキドキするわ。
レアだからかな。
「息抜きデートなので、結構です。ご親切にどうもありがとうございました」
二人はぱちくりと瞬いてゆっくり顔を見合わせた。
わたしの言葉が嘘か本当か測りかねているのだろう。それでも二度繰り返した「ご親切に」のお礼に込めた謝意と拒絶は感じ取ったようで、「あー」「ナルホド」とうんうんうなずく。
案内してもらった中庭には、両手にうどんの器を抱えた倉持の姿が見えていた。
「じゃ、中庭そこだよ。ちなみに俺らこのあとそこの講堂でライブするからよかったら見てね〜」
「来年の入学も待ってるよ〜」
紅子の片腕に抱き着いてにこーっと満面の笑みで手を振り、離れていく二人のギターケースを見送る。
「どうだった? この間マンガで読んだ断り方なんだけど」
「向こうがしつこくなかったから通用した。三十点」
「厳しい……」
「男二人連れてきてんだからさあ。彼氏いるんで〜、くらい言えよ」
「その場合誰と誰がカップルになるのかしら」
「そりゃ……、……いややっぱナシ。英のほうがいい」
わたしと一也、紅子と倉持? それとも逆?──どちらにせよ想像力の限界を迎えたらしい、紅子はそっと首を振った。
わたしのほうがいいって、よっぽど嫌なんだな。それもそれで面白いけど。
腕組みしたまま倉持のもとへ戻ると溜め息をつかれた。
「英ってけっこう茶番好きだよな」
「なによ突然」
「懐かしいこと思い出しただけだ。お前がすげーしおらしいフリして御幸に泣いて縋った時のこと」
「もう二年も前のことじゃない。わたしたち若かったわね……」
ふっ、と憂い気にほほ笑むとお隣から「うちら現役JKだけどね」と真っ当なツッコミが入った。
倉持が紅子に、二年前の一件──秋大の決勝戦を観戦した先で大学生に絡まれ、わたしがブチ切れ、警備員さんの目の前で一也の胸に縋りついた懐かしの一件だ──を語り聞かせていると、一也が帰ってくるのが視界に入る。
薄手のジャケット、ティーシャツ、ジーンズ。やたらと人混みに馴染んでいた。
……一也と一緒に大学生なんて、なれるはずないし、なりたいわけじゃないけど。
紅子の隣を抜けだして、わたしたちを捜している一也の腕を掴む。
「うわ、びっくりした」
「遅かったね。混んでたの?」
「や、屋台の人に声かけられてた。高校生の時に野球部だったって。二年のときに練習試合もしたことあったみたいで」
「あら有名人」
「お前のことも憶えてたぞ。すげー仏頂面のすげー美人に弁当もらったって」
「『すげー仏頂面』か。それはわたしね」
「だな」
焼きそば二パックを片手に持った一也の、空いている左腕を組んでみた。
センバツに出場して、夏の大会でも活躍して、ドラフトがあって、一也の顔と名前は広く知れ渡っている。青道野球部の文字通り『顔』となるその責任から、外でひっついたり触れたりすることは最近少なくなっていた。
でも、特に文句は言われない。
ただ眼鏡の奥でにやっと笑って、「なーに」とからかいモードに入る。
「また『俺と大学生』ごっこ?」
「そう。こんな人混みなら誰も見てないだろうし別にいいかなって」
一也は薄く微笑した。
わたしと一也を見つけた倉持が呆れたように肩を落とし、紅子は嫌そうに顔を顰めた。
こんな風に四人でお出かけできるのなんて、これが最後かもしれないな。
「ちょっと御幸その腕を放して。英は今日あたしとデートだから」
「なにそれどういう状況?」
「俺に訊くな」
「ややこしい四角関係になってきたわね。とにかくお昼食べてお兄さんのライブ行かない?」
……でもなんだかんだ、大学生になってもならなくても、大人になっても相変わらず四人で一緒に旅行してたりして。
そんな感じがする。
そうだといいな。
ちなみに──
中庭まで案内してくれた親切な二人は、紅子のお兄さんが所属している軽音楽部のお仲間だったらしい。
今日JKナンパしたらふられちゃった〜、というお話から突き詰めてどうやら片割れが紅子だったと判明し、けっこうな騒ぎになったとか。
「兄貴に『おまえ超絶美人の彼女がいるって本当? 百合? 百合か?』ってしつこく問い詰められたわ……」
「お疲れさま……」
朔夜さんのリクエストより、高嶺と御幸と倉持と紅子の4人でお出かけするお話でした。
最初は大学卒業前に沖縄に卒業旅行する話を書いていたのですが、オチを見失ったので軸を高3に戻してお出かけしてみました。「ナンパされて男子に助けられるか自力で撃退する」という詳細につきましては、いつも助けてもらってるな! と思ったので今回は自力で(笑)
すごくどうでもいいことですし今後出ることはないですが、紅子には兄が3人いる設定です。
楽しくわちゃわちゃさせてもらいました。朔夜さん、リクエストありがとうございました!
最初は大学卒業前に沖縄に卒業旅行する話を書いていたのですが、オチを見失ったので軸を高3に戻してお出かけしてみました。「ナンパされて男子に助けられるか自力で撃退する」という詳細につきましては、いつも助けてもらってるな! と思ったので今回は自力で(笑)
すごくどうでもいいことですし今後出ることはないですが、紅子には兄が3人いる設定です。
楽しくわちゃわちゃさせてもらいました。朔夜さん、リクエストありがとうございました!
TIAM top