檸檬の気配・後篇
──とまあそんな昔の思い出を振り返りつつ、鏡の中の自分の顔を飾りたてていく。
日焼け止めを塗って、化粧下地、リキッドファンデ。フェイスパウダーを叩いて顔をさらさらにしたら、眉を描いて、アイカラーを載せる。『天乃英』の顔はけっこう濃い化粧もいけるけど、亮さんはあんまりゴテゴテしているのが好きじゃないみたいなので、薄く可愛らしい色合いで。
……新しく買ったアイカラーを試したその日に「なにそのハデな色」と顔を顰められたことは一生忘れない……。
服はワンピース。コーデが楽だから。
どこに出かけるとかは聞いていないけれど、特に指定がないということはまた映画だろう。大学で再会したあとから、亮さんはわたしをホラー映画のお伴に連れていくことが増えた。適度に怖がらないのが連れとして丁度良かったみたい。
でも相変わらずお化け屋敷はダメだった。やっぱり大きい音とびっくりさせられるコンボが苦手だ。
一回生の学祭で野球部の先輩に連行されたとき、順路の中で腰を抜かしてしまって、おんぶされて外に出るという大失態を犯した。
あのときの亮さん怖かったな。
お化け屋敷は毎年恒例の企画で、野球部も毎年みんなで行くらしいのだが、それを知っていた亮さんは「英はお化け屋敷ダメだから連れて行くな」と事前に言っておいてくれたらしい。
結果それがあだとなって「普段しっかりしているマネがビビるところを見てみたい」という悪戯心が湧いたようだけど。
それで、腰を抜かしたわたしは先輩におんぶされたまま、亮さんがいる野球部の屋台まで運ばれたのだ。
「連れて行くなって言ったよね」
「俺の屋台のシフト中に勝手に英で遊ぶな」
「確信犯だよねお前ら」
「どうお仕置きされたい?」
……と、エプロンに三角巾の亮さんが、焼きそば屋台で使っていたヘラを構えながら凄んだのだ。
あれは怖かった。
「えーと、それはともかく」
閑話休題。それはともかく、今なにかホラー映画が公開中だったっけ。
スマホを開いて調べようかとも思ったけれど、イヤリングをつけたところで亮さんから指定された時間になってしまった。慌てて荷物をまとめて部屋を出る。
エレベーターに乗って一階のエントランスに下り、外に出てみると、目の前の道路に一台の車が停まっていた。
運転席から降りてきたのは、感慨に耽るほど懐かしくもない一か月ぶりの亮さん。
「……えっ、車買ったんですか!?」
「まあ最初だし中古だけどね」
昔とちっとも変わらない悪戯っ子な笑みで、彼は助手席のドアを開けた。
「ちなみに助手席に乗るのは家族以外じゃ英がいちばん。どーぞ」
「ひえええ……土足可ですか……」
「……拾うの面倒くさいボケかまさないでさっさと乗って」
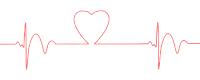
亮さんは首都高に入って東京を出た。
車を買ったのはひと月前というけれど、ハンドルを握る姿はだいぶ手慣れているように見える。助手席に座ったわたしは、流れてゆく街の景色と運転席の横顔とを交互に眺めていた。
「映画じゃないんですか?」
「今日は別。着いてからのお楽しみ」
「珍しいですね」
亮さんとホラー映画以外のおでかけなんて初めてかもしれないな。
どこに連れて行ってくれるのか楽しみになってきてこっそり笑うと、亮さんは意味ありげな沈黙とともに口元を歪めた。
「英の呑気な顔が見たくなっただけだから」
「…………」
会社で何かあったのかな。
『天乃英』に生まれるより前のわたしには社会経験がある。特に入社一年目なんて、毎日毎日失敗しては「会社行きたくないなぁ」なんてぼやいていたものだ。土日休みの会社だったから、日曜の夕方から一気に気分が重くなったりもして。
亮さんは、社会人になってからも月に一度はわたしの相手をしてくれる。
そういうときにだって愚痴を聞かせてくれたことはなかった。そういう人だと解っているからわざわざ訊きもしなかったけど、何一つ悩みがないなんてこと、さすがにないだろう。
悩みも苦難もないように見せるのが上手な人。
現役時代だって、隣で肩を並べる仲間相手ならまだしも、マネージャーたちにはそんな顔一度も見せたことがなかった。わたしにすら。
……だから、初めてだな、こういうの。
「わたしの呑気な顔でよければいくらでもどーぞ」
「どーも」
大体にしてお出かけのお誘いだって、いつも遅くとも三日前までには、予定を確認したうえで声をかけてくれていた。昨日みたいに「明日行くよ」なんてありえない。
よっぽど何かあったんだろうな、昨日。
もともと口数の多いほうの人ではないけれど、車内ではさらに寡黙だった。
流行りの洋楽だけが沈黙を埋めている。
途中でお昼休憩を挟みつつ車を走らせること一時間半程度、亮さんが連れてきてくれたのはコスモス畑だった。
川沿いにある大きな自然公園のなかに、白や薄ピンクや紅色のコスモスが見渡す限り咲き乱れる。お客さんの数も多いけれど、それよりコスモス畑のほうが広すぎてあまり気にならない。
空は秋晴れ。
遠景に聳える風車も相まって、まるで外国のような景色だった。
「すごーい。きれいですねぇ」
「展望台あっちだって」
「行きましょう!」
振り返った瞬間、カシャ、とシャッター音が響いた。
スマホを構えた亮さんが悪戯っぽく笑う。「あっ」と顔を隠す間にもう一度。「だめですマネージャー通してください」とここ数年なぜか定着してしまったネタを振る間にもう三度、容赦なく写真を撮られた。
「マネージャー俺だからいいの。オフショ、大学のほうのラインに上げとくから」
「わたしそろそろ亮さんラブの後輩ちゃんに刺されそう」
「そんなんいたっけ?」
「いましたよー。野球部じゃないですけど、亮さん紹介してほしいって言ってきた子がいます」
「聞いてないけど」
「言ってないですもの。こういう紹介する・しないはトラブルのもとですので、もう全部紹介しないことにしたんです」
ふーん、と生返事をしてスマホを操作しはじめた亮さんに近づくと、本当に写真を大学の野球部ラインに上げているところだった。ぴこぴこと既読がついて、先輩たちから色々なスタンプが返信されてくる。みなさん元気にされているようだ。
ポケットに突っ込まれていたほうの腕を掴んで引っ張ると、渋々といった感じでついてくる。
「こういうところ、来たの初めてです」
「だろうね。お前は高校も大学も結局野球漬けだったから」
「さすがにこれで終わりですかね……。寂しい気もしますけど、ようやく旅行とかできるようになるんだなぁと思うと楽しみですよ」
一通り先輩たちを煽り終えたのか、スマホをポケットに入れた亮さんは、腕を掴んでいるわたしの手をぎゅっと掴んだ。
「……大変だったね。うっかり俺と同じ大学に入っちゃったばっかりに」
「そりゃ大変じゃなかったとは言いませんけど、亮さんとの野球が三年も延長されたのは嬉しかったですよ?」
「物好きなやつ」
ふ、と微苦笑を浮かべた彼は、なんとなく繋ぐかたちになってしまったわたしの手を見つめた。
幼い頃からつなぎ慣れていた一也の手とはすこし感触が違う。大抵は愛情チョップで触れてきて、たまに頭を撫でて、それでいて極まれにわたしを混乱させる、たちの悪い男の人の手だ。
「ねえ英」
コスモス畑のさなか立ち止まる。
「最後にしようか。こうして出かけるの」
次の言葉を、頭のなかで目まぐるしく探した。
最後にしようか、こうして出かけるの。──なんて、初めて買った車の助手席に家族以外で初めて乗せてくれて、顔が見たかっただけなんて言って、花畑に連れてきてくれた挙句手をつないだ人の言うことじゃない。
本当に、たちが悪い。
どういうことですかと訊ねるよりも先に、視線を逸らした亮さんが口を開く。
「俺は社会人になったし、英ももう卒業する。じゅうぶん大人だ。今までは兄妹みたいなものって誤魔化しながら連れ出せたけど、これから先も二人で出かけたければ相応の理由は要る……俺は心が狭いからね」
彼が言葉を重ねるたびに心は凪いでいった。
腑に落ちると同時にその先が想像できたから。
「英の最優先が御幸のままなら、兄妹ごっこもおしまい」
亮さんはそれきり口を閉ざして、無理やりいつもの微笑みを浮かべていた。
秋風が吹く。
髪の毛やワンピースの裾がぱたぱたと翻るのが視界の端っこに見えた。視線は目の前の、曖昧な意味合いで手をつないだまま曖昧な言葉で煙に撒こうとしているたちの悪い人に向けている。
『天乃英』の最優先は御幸一也。
青道高校野球部でわたしたちを知る人たちの間ではもはや当たり前の事実だ。だってそうだろう。わたしはあの日、あのとき、あの瞬間、あの場所で一也の手を握るためにこの世にあった。
だけど、物語に描かれていた範疇を超えた時点でその存在理由は捨てた。
わたしはこれから先もこの世界で生きていくのだと、そう理解したから。
「……わたしが一度でも、あなたと二人でいるときに一也の話をしましたか」
亮さんはぱちりと瞬いた。
「大学にいる間も。一也の話をするのはいつも、亮さんからでしたよ。気づいてなかったんですね」
「……どういう意味?」
あ。
この人わたしから言わせるつもりだな。
そういうタイプだもの、いつだって。いたいけな後輩に意地悪して楽しそうに笑うの。そのくせ愛情チョップは手加減ばっちりで、本気で叱るときはそりゃ痛いけど、それだって本気で可愛がってくれていることの裏返しだし。
「とっくに」
小さく零すと、本当にほんとうに珍しいことに、亮さんが目を丸くした。
「……って言ったらどうしますか?」
余計な一言を付け加えてしまったけど、これだっていつも、曖昧なまま探り合ってきたわたしたちに相応しい。
亮さんは眉を下げて嘆息した。
「……とりあえず、夕飯どこで食べるか考える、かな」
どうやら亮さんは本気で、今日ここでおしまいにするつもりでいたみたいだ。
いつも映画を観たあとは亮さんチョイスで「ここが美味しいらしい」ってお店につれて行ってくれたから。
つながれた手を引っ張ると、彼はゆっくりと一歩踏み出した。
「……なに食べたい?」
「この間紅子に美味しいハンバーグ屋さんを教えてもらったのでそこがいいです! ね、その前に訊きたいことあるんですけど」
「なに」
「昨日なにかあったんです?」
亮さんは「べつに」と柔く微笑んだ。
渋るなぁ。
お見通しですよー、隠してもムダですよー、という気持ちを込めてじとりと睨む。しばらくはニヤニヤしながらわたしの睨みを受けていたけれど、やがて観念したように俯いた。
「同期が辞めた」
「……もしかして、あれですか、研修初日に友だちになってよく一緒にご飯食べてたっていう仲のいい人?」
「よく憶えてるじゃん」
「亮さんのことですからねぇ」
「あー生意気」
「……寂しいですね」
つないでいないほうの手を伸ばしてきた亮さんが、わたしの頭にゆるーくチョップを落とす。
「そうだね」静かに肯定した彼はさびしげに笑って、そのまま秋空とコスモスを遠く眺めた。器用な人だけど不器用な人。これが今のところわたしに対して見せられる精いっぱいの弱音なんだな。
わたしがいますよ、なんてなんの慰めにもならないし。
ただ無言で、展望台までの道をゆっくりと往きながら、握る手に力を込めた。
高校二年の二月、あんなにも不思議だったこの人の隣。
もうすっかり慣れてしまったし、これからはこの位置が当たり前になっていくんだろう。
なんだかこそばゆいけど、もちろん嫌じゃない。
亮さんはつないでいた手をごそごそ動かして、わたしの指のあいだに指を絡めた。
企画でリクエストを募集したタイミングでアフターダークの本編が亮さんとのお話だったこともあり、亮さんif関連のリクエストをたくさんいただいたので、三話に分けてみました。
亮さんともしくっつくとしたら、御幸最優先のうちは絶対に関係は進展しないだろうなぁ。亮さんって思ったことは全部正直に言うように見えて自分の負の部分は他人に見せなさそうだなぁ。とか、色々考えつつこんな具合のお話になりました。
やや甘やかされ足りない感じがしますかね……本当はもっとわちゃわちゃした話になってもよかったのかも……色々考えて詰め込みすぎたかな……。とにかくわたしの中の亮さんはこんなイメージ、というのを全面に出してみましたがイマイチだったら本当に申し訳ございません。
「亮さんとくっつく」というようなリクエストが多い中、具体的なシチュエーションのあった方のものを採用という形にさせていただきました。ムラサキさん、レモンさん、あやつみさん、雪音さん。リクエストありがとうございました!
亮さんともしくっつくとしたら、御幸最優先のうちは絶対に関係は進展しないだろうなぁ。亮さんって思ったことは全部正直に言うように見えて自分の負の部分は他人に見せなさそうだなぁ。とか、色々考えつつこんな具合のお話になりました。
やや甘やかされ足りない感じがしますかね……本当はもっとわちゃわちゃした話になってもよかったのかも……色々考えて詰め込みすぎたかな……。とにかくわたしの中の亮さんはこんなイメージ、というのを全面に出してみましたがイマイチだったら本当に申し訳ございません。
「亮さんとくっつく」というようなリクエストが多い中、具体的なシチュエーションのあった方のものを採用という形にさせていただきました。ムラサキさん、レモンさん、あやつみさん、雪音さん。リクエストありがとうございました!
TIAM top