青い夜のゆくえ・後篇
明け方に任務から帰ってきたばかりだった。
ここひと月はアクマの大群との小競り合いが欧州各地で起きており、教団側は窮地に立たされている。
傷を癒やす間もなく任務に飛び回り、ドイツで合流した神田とポーランドで別れ、ベルギーでマリと合流しオーストリアでリナリーと任務、スイスを通ってフランスまで戻ればまた神田との任務といった具合で欧州スタンプラリーみたいになっていた。
腕が立ち大怪我をしないせいで本部に戻る暇もありゃしない。
ようやく帰還の目処が立ったと思えば嵐で船が出ず、本部の床を踏んだのは東の空が白み始めた頃だった。
コンディションは最悪。
気が昂ぶっていたせいでベッドに倒れ込んでも眠れなかったので、ややイラついた頭をしゃきっとさせるために食堂へと向かっていた。
大勢が死んだ。
遺体を連れて帰ることができなかった団員の顔を瞼の裏に思い浮かべることができる。遺品を拾う余裕すらなかった死も、余すことなく。
悲しみに浸る時間はあまりなかった。
きっとまたすぐに次の任務が入る。
「ユーウ」
耳馴染みのない声が後ろから聞こえた。
こんな声の団員がいただろうか。本部に帰ったのも久しぶりだから、わたしの知らない団員が新しく入っていてもおかしくないけれど。
「あれれ? ユーくんてば」
それにしても『ユーくん』か。
そんな呼び名をされる団員がいただろうか。ティエドール元帥が神田を呼ぶとき以外でそんな呼称をもつ人を脳内検索してみるけれどヒットしない。
だこだこと大雑把な足音が近づいてきて、すっと肩に手を伸ばされた気配がする。
反射的に半身を翻してその手首を捩じり上げていた。──もう一度言うけれど、コンディションは最悪、気が昂ぶっていて眠れなくてお腹も空いてイライラしていたのだ。
「いでででで痛い痛い痛い! ユーくん無視したうえこの仕打ちかよヒッデェさ!」
「……は?」
寝不足のわたしがぎろりと下から睨み上げると、アンノウンのその男はキャッと口元を引き攣らせる。
右目を覆う眼帯。クロス元帥のそれよりも明るく、派手な赤髪。緑色の左目。口元にへらりと浮かんだ軽薄な笑み。
薄っぺらい心と体。
……誰だ、こいつ。
「……ん? ユーくん背縮んだ?」
「誰がユーくんだ削ぐよ」
「ヒエッッ」
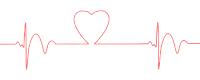
しずかな夜だ。
多くの団員が寝静まる夜、誰もいない談話室の隅で蝋燭の灯りが不規則に揺れる。
紙を捲る音だけが響いていた。
窓側を向いたソファに一人膝を抱え、乏しい光源のなか手元の文字を追う。ちらと視界に入り込んだ窓の外には夜空が青く白んで見えるほどの星々が瞬いていた。
今日は珍しく雲がない。いまにも世界へ向けて降りそそぎそうな銀河だ。
「なぁに読んでんのさっ」
──少々物騒だった出会いから二年を経て、縦ににょきっと成長した赤毛のアンノウンが後ろから覗き込んできた。
「報告書?」とぴったり頬をくっつけてわたしの手元をしげしげ見つめているラビの、形のよい耳に息をフッと吹き込む。
「キャアアア!?」
「なに女の子みたいな悲鳴上げてんの。顔が近いよ」
「それは悪かったけどさ! 姉さんズッル!」
『姉さん』。
ラビがわたしをそんな風に呼ぶようになったのはいつからだったかな、とフと思う。
耳を押さえて「あ〜ゾワゾワするさ〜」とソファの隣に腰掛けてきたラビにも見えるよう、コムイのもとから拝借してきた紙の束を開いてみせた。彼の言う通り報告書なのだ。
「方舟戦のね。……わたし結局、何が起きたのかよくわかってないし」
「お、これユウのか。リナリーにアレンに……全員分? 真面目だなぁあこやは」
指先で紙をぺろんと捲る、彼の大きな掌が目に入る。
神田のそれより武骨で男らしい指。
対アクマ武器を操る腕に残る傷跡。
「ラビに初めて会ったときのこと思い出したよ」
「なにさ、急に。そんなこと書いたっけか、オレ」
「書いてたっていうか、今のラビを見て思っただけ。……戦士の体になっちゃったね」
彼はぴくりと瞼を震わせた。
右目を覆う眼帯を外したところは一度も見たことがない。派手な赤髪は今も昔もよく目立つ。けれど、昔は硝子玉のようだった緑色の左目はすっかり感情を表に出すようになったし、処世術の一つであっただろうへらりとした笑みからは軽薄さが消えた。
ブックマンから訓練を受けたとはいっても頼りなかった体には筋肉がついた。きっと教団に来てから、消えない傷跡もできたことだろう。
「……あこやって、変なやつ。昔ッから思ってたけど」
「そうかもね。なにせ教団で生まれ育って外の世界を一切知らない箱入り戦士だから」
自虐的なニュアンスに気づいてしまったのか、ラビは悼むような表情になってわたしの手を握った。
珍しいな。
わたしが進んで一歩引いていることに気づいて、彼らもあまり深くまで踏み込んでこようとはしなかったのに。
「あこやのこと苦手な理由わかったさオレ」
「苦手だったの?」
「そー。気づいてなかったろ」
そんなことないけど、と呟くとラビは笑った。「バレてら」
「神田と同じ顔してたから、わかっただけ。最初の頃は『教団がホームで団員が家族ってマジで言ってんのかこいつ』って顔だったから、ラビにとってここは記録地でしかないんだなって、そう理解していたつもりなんだけどな」
「あ〜〜そういう物わかりのいいとこ苦手さぁ。そうやって距離取ってあんま仲良くなってくれなかったっしょ」
そうだ──なぜなら、ブックマンとその弟子にも、亜第六研究所での一件は開示しないという話を聞いたから。
ラビと初めて会った直後の任務で神田と一緒になり、宿屋の一室でその話をされた。彼のほうはブックマンの入団に際してコムイからその方針を説明されたのだという。
神田なら何を訊かれても「うるせぇ」「関係ねぇ」「削ぐぞ」「斬るぞ」で済むが、わたしのほうは万が一追及されるとどこからどう情報が洩れるか判らなかった。内部の仲間たちから興味本位に訊かれるのとはわけが違う。彼らは情報のプロなのだ。
事実、神田の尋常でない治癒能力に興味を持ったラビにさり気なく質問されたことがある。
幸い黒の教団関係者には魔術師というものも存在したので、そういう体質の者もいるのだろう、という答えで当時はお茶を濁していた。
薄く微笑み、話を逸らす。
「じゃないと神田の隣にはいられないでしょ。自分で言うのもあれだけどさ」
「ホントあれだな。……ところでユウといえばぁ〜」
ぱっ、とラビが報告書の束をわたしの手から引き抜いた。
隣でにんまりと笑っている彼を見上げると、「訊きたいことがあんだけど、あこや」とずいずい顔を近づけてくる。ソファの上に逃げ場はない。
「あこや、あの時ユウのとこまで引き返したんだろ? なんかあった?」
「そういえばラビ、そのことティエドール元帥にバラしたでしょ」
「バラすも何も自分だってキッチリ報告書に書いてたじゃねーの。本部に戻ってきたあと自分たちの態度がおかしかった自覚あんだろ? なー何があったんだよ」
「顔が近いっての」
こんな夜中に談話室を訪れる第三者がもしいるとすれば、確実にラビがわたしを襲っていると誤解する体勢だ。
幸いにも本気で組み合えばわたしのほうが強いけれども。
ラビなんてまだまだ新米だ、わたしから見れば。
「なー、あこやってユウのこと好きなん?」
「…………、は?」
「あれ、オレこれ昔ユウにも訊いた気がすんな」
「……神田はなんて?」
「なんて答えたと思う?」
ニヤリと笑ったラビになんだかむかついたので鳩尾に蹴りを一発。
「ぐほぉっ」と悶絶して倒れ込んできた彼に呆れつつ、なんてこと訊いてんだこいつは、と天井を仰いで溜め息をついた。
……どうかしている。
今わたしの上にいるのはラビで、神田とは体格も気配も香りも何もかも違うのに、神田史上最もとんでもない爆弾発言をしてくれたあの日のことを思い出すなんて。
「…………」
幸いにもわたしの心臓がちょこっとだけ煩くなったことには気づかず痛みに耐えているラビの赤毛を眺めながら、これはラビこれはラビこれはラビと心の中で唱えた。これはラビこれはラビこれはラビ。
「『興味ねぇよ』くらいじゃないの」
「おぉっと大正解……さすがさ……」
「……大丈夫? 強く蹴りすぎたかな」
「いやダイジョブ……オレがちょっと油断してただけさ……」
コツ、と足音が聞こえた。
ソファの背凭れから顔を出してみると、神田が無表情でこちらを見ている。
さすがに動揺を隠せず「かんだ」と声が上ずると、それ以上に動揺したラビが「エッユウ!? いや違うんさこれは」と慌てて飛び退き、勢い余ってひっくり返った。
「……邪魔したな」
「待ってユウ誤解!! マジで誤解!! お願い話聞いてユウ!!」
「俺のファーストネームを口にするな削ぐぞウサギ野郎」
まるで夫に浮気現場を見られて誤解を解こうと縋りつく妻のように、ラビは神田の後ろ姿を追いかける。
なんでラビのほうが慌ててるんだろう……。苦笑いで蝋燭の火を吹き消し、結局最後まで読めなかった報告書を抱えて談話室を出た。
十八歳コンビの間に割り込んで、二人の腕をとる。
「神田こんな時間に何してたの?」
「関係ねぇだろ」
「森で稽古してたんじゃないの。蝋燭の灯りが見えたから上がってきてくれた?」
黙った。
それを単なる無視と解釈したらしいラビが、半泣きでわたしの腕をぶんぶん揺らしている。
「あこやも早く誤解といて! ユウ完全にオレらが深夜の談話室で密会していかがわしいことしてたと勘違いしてるぜ!」
「誰がするか!! したとしてもウサギ野郎の強姦現行犯だ」
「だから誤解だって! オレあこやに蹴られて戦闘不能になってただけだもん」
ラビは亜第六研究所で起きた悲劇の詳細を知らない。
本部に入団したばかりの神田を知らず、彼のなかに在る破壊者としての苦しみを、痛みを、軋む心を知らない。
無知ゆえに口にできてしまう『ユウ』というその名を呼んでいいのは、今も昔もあの子だけだということを知らない。
わたしはそれがたまに羨ましい。
わたしにとっては教団がホームで団員が家族だ。永遠に神田とは交われないこの価値観を変えることはできない。彼が教団をホームと呼ぶ日など来ないように。
ラビの感覚は神田に近いのだ──いまは“近かった”とするべきなのかもしれないけれど。
だから何度『ユウ』と呼ばれたって、神田はラビを完全に突き放さない。ラビもまた、同じ価値観でいた神田のそばは気が楽だったのだろう。入団当初から暇があれば神田にダル絡みしてはキレられていた。
わたしだけ、ひとり。
とっくの昔に気づいていたことだけど。
頭上でやり取りされる男どもの他愛無い口げんかにちょっと笑っていると、盛大に顔を顰めた神田が立ち止まって、わたしの顎を片手で掴んで覗き込んできた。
「な、に」
「蝋燭の灯りを見られてる自覚があるならとっとと部屋に戻れ」
「……うい」
意訳。『心配されている自覚があるなら早く寝ろ』。
静養しているエクソシスト諸君の穴を埋めるため、そして元帥昇格を辞退することと引き換えに急を要する任務地へと日々飛び回るわたしには、おおいに『蝋燭の灯りを見られている自覚』がある。
「ちえー、なんだよ通じ合っちゃってさ。オレひとり仲間外れじゃねーの」
「気色悪い拗ね方してんじゃねぇよ」
「あこや〜〜ユウがひどい……」
「あーはいはい」
めそめそ泣きマネをしながらラビが首に両腕を回してきた。でっかい男に抱き着かれても暑苦しいだけなのだが──そして神田がひどいのはラビの自業自得だとも思うのだが──戦闘から遠ざかっているせいで手触りのいい赤毛を撫でてやる。
と、ラビの頭が急に消えた。
神田が片手で無理やり引き剥がしたのだ。えらい方向に首が曲がっているラビの喉から「いだいいだいいだい」と苦しそうな悲鳴が洩れている。
「いででででユウ首折れちゃうさ! わかった! オレがあこやに抱き着いたのが嫌だったんだ! ほらオレ昔教えてやったろそれ独占欲と嫉妬だって!」
「今すぐこの手を放すか首を折られるか選ばせてやる」
「勘弁してよ貴重なエクソシストなんだから」
「あこやさーん!?」
独占欲と嫉妬、ねぇ。
そんな簡単な想いなら、どれだけ楽だっただろうね。
「まあ落ち着いて神田。ラビが自分で墓穴を掘り進めるのなんて今に始まったことじゃないんだから」
「ぐっ……それはそれでヒドイ言い草さ……」
今度は泣きマネなどではなく本気で涙目のラビが首をさすっている。折れていなくて何よりだ。
フンと鼻を鳴らした神田はわたしの肩に腕を回すと、一刻も早くラビから離れたいというふうに足音高く廊下を歩き始めた。脚の長さが違うのだ、歩幅も当然異なる。わたしのほうは半ば小走りで神田に引きずられた。
それを見送るラビは下町の子どもみたいにべーっと舌を出す。
「あこやにとっときの話教えてやるさー! ユウはな! あこやのお父さんの墓前でジジには指一本触れさせないって決意したらしいぜ!」
任務地でアクマに殺された父は遺体が残らなかった。
火葬されたのは残された団服と靴のみだ。対アクマ武器はヘブラスカの許へ返り、髪を結っていた組み紐はわたしが持っている。遺灰もない父の『墓』というものは厳密には存在しない。
多分、歴代エクソシストの殉職者の名を刻んだ墓碑のことを指すのだろう。
「へえ。それは初耳」
「テメエこのウサギッ……」
「はいはい抜刀しない」
神のもとへ召された父の墓前で神田が厳かに何かを誓うなんて、全くこれっぽっちも想像できないのだけれど、この反応を見るに本当なのか。
……そっか。
「明日、お父さんのところ行こうか……」
格子窓の外、今にも世界へと降りそそぎそうな星空。
その眼下に広がる森の奥深くに、ひっそりと、戦士たちの名が眠る墓碑がある。
「双子が三つ子になりましたって報告しなきゃ……痛いっ」
「ふざけたこと言ってんじゃねェよ誰が行くか!!」
「そーさ! オレこんな変な双子の仲間入りはしたくねェよ!」
「変な双子て。ラビそんな風に思ってたのか」
「今も昔もお前ら二人へんなやつらだろ! なぁんも変わってないさ!」
ビシィッとこちらを指さしながら喚く彼にちょっと笑った。
なんにも変わらない、か。
「じゃ、変わったのはラビのほうだね」
右目を覆う眼帯を外したところは、相変わらず一度も見たことがない。
クロス元帥よりも明るくて派手な赤髪は今も昔もよく目立つ。
けれど、昔は硝子玉のようだった緑色の左目はすっかり感情を表に出すようになったし、処世術の一つであっただろうへらりとした笑みからは軽薄さが消えた。
わたしたちを見つめる目には親しみを帯び、その仕草の端々から慈しみを感じる。
すっかり『家族』になってしまったブックマンJr。
わたしが言外に含ませたその意に気づいたのだろう、ラビは顔を真っ赤にしてわなわなと震えた。
「…………あこやのそういうとこオレ嫌いっ!」
「ふっふっふ。まだまだ青いね、“弟”よ」
はてなを浮かべる神田の腕をとってホームの廊下を歩く。明日はジェリーの美味しい朝ご飯を食べて、軽く汗を流したら、神田とラビを連れて墓碑へ向かおう。厳密には父の墓ではないけれど、もうあの場所以外に父の存在は残っていないから。
神田の横顔を見上げてにこっと笑うと、お決まりのように舌打ちで返される。
黒の教団史上、最も暗澹たる朝を迎える前夜のことだった。
豆腐の角さんより「神田とラビとわちゃわちゃ過ごす日常」、あずささんより「あこやとラビが初めて会った時のお話」、合体させて頂き18歳トリオがわいわいしております。
出会った頃の3人がとっても微妙な距離感だったことや、間違われネタ、「ユウって呼べていいな」というエピソードを入れられたのでわたし的には大満足です。このお話を書く上でわたしも初めてこんなにラビと真剣に向き合いました……楽しかった……。ラビから見たらこんな感じなんだな、っていうのが新鮮でした。へんなやつらですよね。
リクエストありがとうございました!
出会った頃の3人がとっても微妙な距離感だったことや、間違われネタ、「ユウって呼べていいな」というエピソードを入れられたのでわたし的には大満足です。このお話を書く上でわたしも初めてこんなにラビと真剣に向き合いました……楽しかった……。ラビから見たらこんな感じなんだな、っていうのが新鮮でした。へんなやつらですよね。
リクエストありがとうございました!
TIAM top