ルビーのしもべ・後篇
「……あー、その、平気か?」
「大丈夫です。あれくらいいつものことなので」
「マジかよ。……いや、俺らも騒ぎすぎた感じはあるから悪かったな」
「いいえ、あんなものでしょう、普通」
苦笑を浮かべた彼が「メシは?」と訊ねてくれたので、バッグのなかに入れてきたコンビニのおにぎりを見せた。
倉持くんに誘導されて、OBさんや見学の生徒もいなくなり閑散とした見学席に腰かける。お昼食べに行かなくていいのかなと隣を見上げたが、彼は横に座ったまま動こうとしなかった。
あまり慣れていない男性との沈黙に耐えかねて、口を開く。
「……過保護ですよね」
「あ?……何が」
「かずくん。昔ちょこっと事件があったので、わたしが一人で出歩くのをすごく嫌がるんです。進路に口出ししたのも、制服が可愛いからなんて建前で、家から近くて電車やバスに乗らなくていいことが第一で、次に女子高だったからなんですよ。……あんなのでこの先やっていけるのかな、あの人」
「御幸も苦労すんなぁ」
くしゃっと笑ったその横顔に、ああかずくんのことよく理解してくれているんだな、と感じた。
わたしの知らないかずくんを知っている人だ。
一緒に野球ができて、対等に話ができる、わたしには寄せられない類いの信頼を寄せてもらえる人。
いいな。
「あーあ、わたし、同い年だったらよかったのになぁ」
「そしたら青道に来たか?」
「多分。その方が、目が届く場所にいてかずくんも安心だろうし。ああでも、電車通学には渋い顔しそう……」
「なんだかんだ過保護には変わりねぇだろうな」
青道高校に入学したかずくんとの電話で、最初に聞いた名前が『倉持』だったな。
足が速くて、ちょっとガラが悪くて、すぐケンカ腰になる。守備も最初はそんなに巧くなかった。けど根性があって負けん気が強くて、見る見るうちに上手になっていった。
それで、人のことよく見てる、って。
「あのね、本当にへこんでないから大丈夫ですよ、あれくらいの言い合いはたまにあるんです」
倉持くんは横目にわたしを見下ろすと、ぱちぱちと瞬きをした。
気にかけてくれるのは有難いけど、彼がお昼ご飯を食べそびれるほうが問題だ。
「もちろん、かずくんの気が散って試合に負けそうなようなら帰りますけど、多分あれはイラついてただけだし、午後も観て帰ります。あの人のことは、失礼ですけど、みなさんと同じくらい解っているつもりですから」
「べつに失礼でも何でもねぇだろ。……じゃ、昼食ってくるわ」
「はい。ありがとうございました」
ほんとに優しい子なんだな。
なんだかほっこりした気持ちで去りゆく後ろ姿を見つめていると、彼はぴたりと足を止めて振り返った。
「……あのよー、思ったんだけど」
「ハイ?」
「御幸の態度が悪かったの、アレ多分イラついてたわけじゃなくて、照れてただけだと思うぜ」
「…………はい?」
「そんだけ」
かずくんが……照れ?
十数年も一緒にいて、本当の兄よりも長い時間を一番傍で守っていてくれて、いい加減「はいはい可愛い可愛い」と褒め慣れた様子でいたあのかずくんが、今更照れ?
「ど、……どういうこと?」
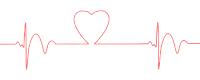
──あの子はどんどん綺麗になる
──妹なんて言えなくなる日がすぐにくるよ
「御幸。あれはないよ」
ゾノや沢村に背中を押されて弁当を受け取ったあと、わざわざ隣を陣取ってきたナベに開口一番叱られた。
「いくら制服姿が可愛くて照れたからってあれはない。普通の女の子だったら泣いて帰ってるよ」
「……ナベ。俺は一言も制服が可愛くて照れたとは言ってないんだけど」
「なに言ってるの。見れば解るよ」
「えっ、キャップ照れてたんすか? でも確かにモデルかアイドルみたいな感じのコでしたねー! 噂通り!!」
「沢村うるさい」
「なぜっ!?」
英は見学席のベンチに座って昼を食べているようだった。様子を見に残ってくれた倉持の横で、特に堪えたふうもなく笑っている。
長い付き合いだし、下手をすれば実の兄貴よりも俺のほうが、英と過ごしてきた時間は長い。多少のけんかや言い合いは初めてではないから大して気にしていないのだろう。
ノリが首を傾げた。
「ていうか、今日来るって知らなかったんだな」
「聞いてねーよ。知ってたら絶対来させない」
「頑なやなぁ」呆れたようにゾノが溜め息をつく横で、白州が「あ、倉持戻ってくるぞ」と立ち上がる。ベンチの上に残っている弁当と飲み物を取りに行ったようだ。
英はぽつんと一人、グラウンドを眺めている。
表情までは見えないが、どこかせつなげな雰囲気だった。
「おーい御幸! 心の広い美少女は特に気にしてねぇってよ! 一応、制服姿に照れただけだって伝えといてやったぜ」
「だからちげぇっつってんだろ!!」
もーやだこいつら……。
昼を食べ終わり、第二試合に向けた準備を進めたり軽く体を動かしたりしはじめても、英はベンチから動かなかった。
まあ帰る気はないだろうなと思っていたので、あー、と心の中で零した以外は文句を言わないようにしておく。言ったって無駄だ。昔から、こうと決めたら頑固なやつなのだ。
確かに「制服可愛いし家から近いし、いんじゃね」と言ったのは俺だった。
青道には追いかけてくるな、ここにいてくれとも。
別に制服なんてどうでもよかった。女子高だったのもたまたまだ。ただ、電車とバスを使うようなところに行ってほしくなかった。何かあっても守ってやれないから。
……そういえば制服、似合ってるってまだ言ってない。
完吾兄ちゃんから入学式の写真が回ってきたけど、「入学おめでとう」もまだだ。選抜から帰ってきて進級や都大会でばたばたしていて、英のことなんてとんと忘れていたのだった。
試合が終わったら、久しぶりにゆっくり話でもするか。
確かに、二時間もかけてわざわざ来てくれたんだもんな。
「おい御幸」
「……ん? なに」
白州に肩を叩かれる。
指さされたほうに視線をやると、昼食をとった位置から一歩も動いていない英の隣に、制服姿の男が二人ほど立っていた。
「あー……午前中ずっと見てたしな、あいつら……」
「よく見てるな」
「英の顔面偏差値がいいのは否定しないし。だから帰れって言ったのに」
見学を禁止しているわけでもない練習試合、ある程度の偵察が来ることは承知済みだ。午前中の試合も観ていたらしいあの二人の視線が、お嬢さま学校として有名な女子高の制服を着た英に注がれていたのも気づいている。
英は英で場数を踏んでいるからそつなくあしらっているみたいだ。
愛想笑いも浮かべず、うなずいたり首を振ったり──
膝の上で握りしめられた手が目に入った。
そうしたら、勝手に体が動いていた。
「英」
ネット越しに声をかけると英ははっと顔を上げる。
すぐ近くに俺がいたのに、一度も助けを求めるような視線は送ってこなかった。そのことが妙に腹立たしくて、でもこれが彼女なのだと納得もしてしまう。
英に話しかけていた二人はぎょっと身を引いた。
「御幸一也だ」「知り合いかよ」と戸惑っているところをじっと見据えて、三秒、しっかり視線を送る。名前と顔が売れるとこういうときに役立つようになるのか、これは悪くないかも。
「……帰り、送ってくから。片づけ終わるまで待てるな?」
「いいの? べつに、そんな気にしなくても一人で帰れるよ」
「いーよ。待ってろ」
頑なに握りこめていた膝の上の拳がゆるんだ。色をなくしていた指先が赤く染まっていく。
それと同時に、人形のように冷たい顔つきで男どもをあしらっていた頬がぱっと上気した。
「かずくん、もう怒ってない?」
「別にもともと怒ってねーけど、悪かったよ。制服もよく似合ってる」
「そっか、……うれしい」
へにゃ、と力の抜けた無防備な笑みが浮かぶ。
その横顔にぽーっと視線をやっている二人に再び視線を戻して、いち、に、さん、と見つめたところでようやく彼らは後退った。よん、ご、と心の中でカウントするうち、引き攣った笑顔で「あ、お邪魔しました……」と離れていく。
そうだそうだ。偵察は偵察らしく試合観てろ。
英は不思議そうな顔をして、去り行く彼らの背中を見ていたが、こちらに顔を戻した時にはもう忘れたらしかった。
認めざるを得ない。
この、いっそ腹が立つくらい無邪気なたった一人の女の子がこうやって笑いかけてくれるのが自分だけであることに、優越感を抱いていること。
変な奴が声をかけるのも許せないし、じろじろ見られるのも我慢ならないし、制服が可愛いと思っているならそうやって大っぴらに見せるんじゃねぇよ、なんて思っている。
俺だけに見せればいいだろ、なんて。
ガキみたいなことを思っている。
「かずくん、試合の準備始まってるよ、戻らなくていいの」
「ああ……、いいなお前また変な男に声かけられても相手すんなよ。彼氏いますとか男と来てますとか適当に言って追い払えよ」
「わかってるよ。大丈夫だってば……」
英はふと微笑んだ。
二つも年下のこの女の子は、時々、ずっと年上の女性のような仕草をすることがある。
「御幸一也と一緒に帰る予定があるので、って言ったらみんな引き下がるよ」
「よし。じゃあそこから動くなよ!」
「はぁい。動きません。ずーっと、かずくん見てます」
「なっ……」
思わず固まりかけたが、元々俺の試合を観に来たには違いないので言葉以上の意味なんてないはずだ。ただこの顔面で言われるとたちが悪い、というだけで。
勢いのまま言い返したらまた八つ当たりになりそうなので、何も言わずにきびすを返した。
すたすたと足早にベンチへ戻る。相手校の準備もほとんど整っていたので、監督に一言すみませんと謝ると、監督は英のほうをちらりと見て「完吾の妹か」と呟いた。
完吾兄ちゃんの妹と幼なじみであることは、兄ちゃんを通じて伝わっているのだ。
「大きくなったな」
「……ハイそりゃもう」
なんだか振り回されている自分が恥ずかしくなって、汗を拭うふりしてユニフォームで顔を隠す。そういや神宮大会で英に会ったあとにもナベに言われたな、あんな風に誰かに振り回される俺は初めて見た、と。
すると俺のキャップを持って駆け寄ってきた沢村がカッと両眼を見開いた。
「キャップどうしたんすか、顔真っ赤ですよ! 熱中症ですか? 体弱いんだからもう!」
「沢村うるさい」
「なぜっ!?」
レギュラー陣の生暖かい視線を感じつつ整列へ向かう。横目に見学席を見てみると、英は言われた通り一歩も動かないまま、本当に俺のことをじっと見つめているようだった。
視線が交わる。
英が笑う。なんでもお見通しです、みたいな眼差しで。
「おーいどうしたキャップ、顔が赤いぜ」
「倉持うるさい」
あーわかったよ、惚れたこっちの負けだよ。
かなわねぇなぁ、もう。
HOLAのif「ほんとうではないだろ」の続きで、柚木宮さんより「青道の試合を見に来てレギュラーと知り合う」、しいさんより「自覚してからのもだもだ」というお話でした。
書き上がってみると、年下相手にツンツンする御幸さんと安定のフォロー魔倉持センパイ、みたいな感じになってしまいましたね。一場面に大人数を登場させるのが難しくて、みんな一言喋るくらいになっちゃいました。でも多分コッソリ倉持と連絡先を交換して主に御幸の情報を横流ししてもらっていると思います。
柚木宮さん、しいさん、リクエストありがとうございました!
書き上がってみると、年下相手にツンツンする御幸さんと安定のフォロー魔倉持センパイ、みたいな感じになってしまいましたね。一場面に大人数を登場させるのが難しくて、みんな一言喋るくらいになっちゃいました。でも多分コッソリ倉持と連絡先を交換して主に御幸の情報を横流ししてもらっていると思います。
柚木宮さん、しいさん、リクエストありがとうございました!
TIAM top