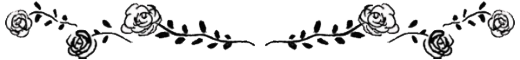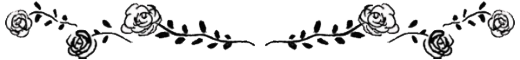
無限城の中心部近くにある一室。閉じられた障子の奥からは男の話し声が聞こえてくる。薄すらと障子に映った朦朧とした影は二つ。仄暗く幽かな灯影がさすその向こうには、端正な顔立ちの男と儚さを孕んだ優艶な女がいた。
人間を唯一鬼に変えることができる鬼舞辻無惨と、彼が以前瀕死の状態から救い上げた女、芍薬。八畳敷の立派な座敷が広がる薄暗い室内にいるのはその二人だった。
一見どちらも人間と変わりない姿形をしているように見えるが、彼らは人ではない。彼らは人ならざる者であり、人間にはない高い身体能力と不老不死性を持つ一方で陽光を弱点とする。中には異能を持つ者すらいる“鬼”、それが彼らの正体だった。
鬼である二人は肌も同じように青白い。鬼の身である以上仕方のないことだが、彼らの肌には生きている人間にあるはずの血の気が全くと言っていい程なかった。特に生まれつき雪のような白い肌を持つ芍薬は、鬼となってもその病的なまでに真白い肌を持ち続けた。
元となった体が元来そのような傾向にあった為だろう。彼女の肌はあらゆる鬼の頂点に立つ無惨よりも色が薄く、無惨のみならず他の鬼と比べても一際白かった。
しかしそれが必ずしも良いことであるとは限らず、日に当たれない肌を生まれ持った彼女はそれ故陽光にも滅法弱かった。
人間のような姿形をしていても、鬼特有の青白い肌を持っていても、二人の外見は似ているようで異なる。容姿だけではない。見た目のみならず立場まで、何から何まで二人は違っていた。
やや眦の切れ上がった怜悧な目をしている無惨と、眦の下がった物憂げで優しそうな目をしている芍薬は実に対比的であったし、互いに緩く波打った艶やかな髪を持っていても無惨の髪は鴉の羽のように黒いが、芍薬の髪は金色を帯びた白。
瞳の色も同じように紫がかっていても、無惨が血のような色を滲ませた紅梅色であるのに対して、芍薬は紫を帯びた色素の薄い淡青色と対照的だった。
片や支配する側であり、片や支配される側。当然支配する側は彼女を鬼に変えた無惨であり、その無惨に支配され付き従うのは芍薬だった。
白は何色にも染まるが、黒は全てを塗り潰し、白をも黒に染め上げる。そのことからも窺える通りの関係が二人を繋いでいて、強固な主従関係がそこにはあった。
鬼は皆例外なく無惨に支配される。これだけは絶対に避けられない定めだ。鬼となると共に鬼に変えられた者には、無惨によって強制的にかけられた呪いがその身を蝕み、死ぬまで消えることなく絡みつくこととなる。
そのような呪いに縛られた覆しようのない関係を無惨は配下の鬼に強要した。無惨は一番最初に鬼になった人物であり、唯一鬼を増やせる人物であるからそうすることもできた。
どんなに強い鬼よりも遥かに優れているのが無惨だった。臆病者であっても、いつも何かに怯えていてもその事実だけは変わらない。無惨はあらゆる鬼の生殺を握る鬼であり、自らが呪いを付与した全ての鬼を支配する、絶対的な力を持った唯一の鬼なのだ。
行燈の灯が仄暗く室内を照らす中で、無惨は芍薬の目を隠すように巻かれた包帯の結び目に指をかけて、丁寧に解いていく。
彼女が鬼となり眠りについた日に、視界を奪うように無惨自らの手で巻いたその包帯を外しながら、彼は一体何を思うのか。整ったその顔にはこれといった表情は浮かんでなく、どのような心情であるのかも悟らせない昏い瞳がただ芍薬を見つめていた。
鬼となった芍薬は鬼と化したあの日から既に弱視ではなくなった。それは無惨も把握していた。包帯を巻いてまで眠り続ける芍薬の視界を奪ったのは、彼女を側に置くのと引き換えにしたことだった。絶対的な力を持ちながら、わざわざそのような手段を取るのは無惨の臆病な性格の表れとも言える。
芍薬の目に巻かれた包帯を外していく傍らで、無惨は配下の鬼にも容赦のない言葉をかける彼にしては珍しく、酷く穏やかな口調で彼女に語りかけた。
「見えるようになった世界はどうだ」
流れるような手つきで巻かれていた包帯が全て取り払われる。伏せられた淡い金色の長い睫毛が微かに震えて、やがて閉じられていた瞼がゆっくりと開いていく。
そうすれば自然と紫がかった綺麗な淡青色の瞳があらわになり、向かいに腰を下ろして微笑を湛えながら彼女を見つめる無惨の赤い眸の中に、青い目の麗しい女の姿が映った。
その目に映る世界はもう涙が滲んだようなぼんやりとしたものではない。見えるようになった世界はこんなにも鮮明で美しいものだった。こんなにも視界は明瞭で、色彩は鮮やかで、なんて儚く綺麗なのだろう。彼女にとって当たり前ではなかった普通のことを、芍薬は今宵初めて知ることとなる。
彼女の視界はもう二度と曇らない。永遠に見えるようになった世界を変わらずに映し続ける。鬼である限りそのような有り得ないことも現実に起こり得るのだ。それは鬼となった為に得られたものであり、人間の体のままでは永遠に叶わぬことだった。
芍薬はまるで夢でも見ているかのような心地だった。見えるようになった世界はとても不思議で、ずっと諦めていたことが叶うのはまさに夢見心地だった。どうして見えるようになったのかは分からないが、確かに芍薬は心が満たされていくような幸福を感じていた。芍薬はとても幸せだった。
だけどその思いは言葉どころか声にもならなかった。無惨に問いかけられたからには答えなければならないのに、夢見心地であることを伝えなければいけないのに。頭では理解していても、どうしても目の前の男から芍薬は目を逸らすことができなかった。
そのように心の内では思っていても、鬼特有の縦長の瞳孔をした紅梅色の双眸に熟視されては萎縮するしかなかった。結局芍薬は何も言えず、ただ熱に浮かされたようにぼうっと無惨を見ることしかできなかった。
それを無惨が咎めることはなかった。機嫌を悪くすることも、何か制裁を加えることもなかった。何故なら無惨は答えが欲しくて聞いた訳ではない。
むしろ答えなど元より彼は求めていないのだ。問いかけようと、配下の鬼の思考を読める無惨にとってはそのようなことは初めから不要だった。
言葉で聞くよりも思考を読む方が何よりも正確なのだから、何も口にしなかった彼女は何も間違えていないし、うっとりと無惨を見つめる芍薬の姿は無惨にとっても、変に偽られるよりもずっと好ましいものであった。
無惨に対する、言葉には言い表せない程の深い感謝の思い、自身が呪いをかけた影響もあるのだろうが、無惨の為に尽くそうとする従順で好ましい思い。
そのようなことが読み取れた上に、芍薬の心情はどれもいじらしく無惨を敬う好意的なものばかりで、それ故に無惨は機嫌を良くすると共に益々彼女のことを気に入ったのだ。
上手く言葉に表せずにいる芍薬の思考を読み取ったからだろう。無惨はただ気を良くして伏し目がちに微笑すると、壊れ物を扱うように淡い金色を帯びた綺麗な髪を優しく撫でた。
その手を離すことなく無惨は彼女の陶器のように白い頬へと滑らせる。
慈しむようにそっと頬に片手を添えると、お前の思っていることは全て分かっているとでも言うように、この上なく優しく囁いた。
「芍薬。世界は綺麗とは限らないが、その目で色んなものを見るといい」
無惨の言葉に芍薬は恍惚とした表情で頷いた。上品に、けれどどこか心を奪われたように、うっとりと綺麗に微笑んだ芍薬は花のように美しかった。己にどこまでも従順なその様がまたいじらしく感じられて、無惨はその微笑に満足すると一層笑みを深めた。
例え夜でも無限城の中では月も星も夜空も見えないが、丁度上弦の月が昇る頃に無惨は芍薬にそのような甘い言葉をかけた。
そしてその話が終わった時にはもう、この場にいるのは部屋の外にいる者も含めて、無惨と芍薬の二人だけではなくなっていた。
障子の向こうには室内にいる二人のものとはまた異なる鬼の気配が一つ。
膝を崩して座る無惨は芍薬の華奢な体を抱き寄せたまま、自身が指示を与えた鬼の気配を障子越しに感じて人知れず目を細めた。
その気配の正体を無惨は知っていた。他でもない無惨自身が、急遽呼び出しをかけた鬼だ。近くに気配を感じて当然だった。その鬼がついにここへ到着したのだろう。
命令を下すべき相手は障子のすぐ向こう側にいる。だがそのことに気づいても尚、無惨が即座にその鬼に声をかけることはなかった。無惨にはまだ芍薬に伝えるべきことがあった。
その話を外にいる者に聞かれても構わないと無惨は思っていた。むしろ無惨はそれを呼び出した鬼にも聞かせるつもりでいた。
無惨が芍薬をどう扱っているかについては、敢えて口にする程のことではない。
しかし万が一にも間違いがあってはいけないから、無惨はこれからする話を介して、そのことを遠回しに障子の外にいる鬼にも知らしめようと思ったのだ。
己の芍薬に対する態度がどのようなものであるのか、如何に彼女に目をかけているのか。それらを知った上で、その者には芍薬を連れて共に行動してもらわなければならない。
それらを知れば呼び出した鬼もいくら弱者を極端に嫌う性分であろうと、鬼特有の同族嫌悪が顔を出そうと、芍薬を悪いようにはしないだろう。そう無惨は考えていた。
その鬼は一般的な鬼とは違い、理知的な部分をある程度持つ鬼であるから、自ずと無惨の意図を汲み取ってくれるはずなのだ。
それくらいのこともできないのなら付き人なんぞに選ばない。無惨がその鬼を芍薬に付けようと決めた理由もそこにあった。
障子の向こうに立つ男に構わず、無惨はこれからする大切な話を聞かせる為に、抱き寄せて腕に閉じ込めた芍薬に視線を戻す。
そして無惨は側に用意しておいたいくつかの髪飾りに目を遣ると、その中から青い芍薬の花が綺麗な繊細な作りの簪を手に取った。白い月の光のような淡い色をした美しい髪を撫ぜて、無惨は芍薬の頭の後ろに手を添える。
その手で頭を支えて、顔を上げさせて覗き込むように無惨は上から芍薬を見下ろした。
「芍薬、私は常にお前の側にはいられない」
その言葉は同じ男のものとは思えない程に酷く柔らかな声色で、か弱い存在を優しくいたわるように紡がれた。少なくとも、呼び出された鬼の知る無惨の声色ではなかった。
芍薬の名前に何かしら思うことがあったのか。障子の向こう側に立つ鬼に微かな動揺が走るのを無惨は感じたが、取り立てて彼がそれを気に留めることはなかった。
呼び出した鬼がそうなっても無理もないような事情に無惨は心当たりがあった。その鬼に動揺が走ったのも、人間の頃の記憶が完全に消えた訳ではなかったからだろう。
無惨は知っていたのだ。この腕に抱いた美しい女のことも、部屋の外で茫然と立ち尽くし、それでもいつ声をかけるべきかを考えながら頃合いを見計らっている男のことも。
全てとはいかないが、かつての二人の関係を知った上で再び引き合わせた。その鬼を付き人に決めた理由は一つだけではない。
いくら鬼同士嫌悪感を持とうと、虫酸が走る程に弱い者が嫌いであろうと、あの男なら間違っても芍薬を太陽の下に連れ出したりはしないと、無惨は強く確信していた。
多少なりとも人間の頃の記憶があるのなら、もう二度と同じ過ちは繰り返さないはずだ。次に手放せば今度こそそれが最後となる。そんなことはあの男にはできないだろう。
芍薬を見つめて努めて優しく微笑みながら、また一つ無惨は言葉を重ねる。
「だがお前は他の鬼と違って一人では生きていけないだろう」
それは事実だ。本来なら鬼は人間を喰らい続けなければならない。人間の血肉が鬼の体を維持する為の栄養となり、強くなる為にもそれは欠かせない行為となるからだ。
だが芍薬はその人間の血肉を口にすることができない。人が喰えない芍薬は代替として鬼の血を必要とした。それがなければ生き永らえることも、強くなることもできなくなる。
だから人の血肉を受けつけない芍薬にとって、鬼の血はどうしても欠かせないものだった。
しかし鬼は互いに嫌悪感を抱く生物であり、基本的に助け合うことは鬼の習性からして有り得ない。
また鬼の血が必要であってもそう都合良く鬼は見つからないし、仮に見つけたとしても血を分けて貰えることはまずない。
そうなるように無惨が強い闘争本能を鬼に植え付けているからだ。
だから今の状態で芍薬に一人で行動するように命じたところで、まず生き延びることから難しく、強くなろうにもその日の糧を得られなければ強くなることもかなわない。
何より鬼狩りがいる中で、回復も遅いまま一人で生きていくのはかなり厳しいだろう。
全ては人を喰らうことができない稀有な体質を持ったせいだ。目覚ましい成長をしても人間が喰えない以上、芍薬は一人では強くなることも生きていくこともできない。
「お前には強い鬼が必要だ。私もお前を失うのは惜しいと思っている」
そのことも承知の上で無惨は更に話を続けた。提案ではなく命令を、緩く波打つ白い芍薬の髪によく映える青い芍薬の花を挿しながら、無惨は諭すように優しく告げた。
「だからこれからは別の鬼と行動を共にしなさい」
灯影が揺らいだ。無惨は障子の向こう側に立つ鬼を見据えるように部屋の外に視線を向けた。
いつの間に開け放たれていたのだろうか、閉め切っていたはずの障子はとっくに開いていて、そこには芍薬と同じ年頃と思われる薄紅色の短髪の青年がいた。
顔や頚を始め、全身に刻まれた刺青のような深縹の複雑な紋様が特徴的な男だった。
その青年の姿をした鬼、猗窩座は無惨の腕の中にいる見覚えのある女の姿を見て、軽く目を瞠ったままその場に立ち尽くす。
猗窩座の視線の先には無惨と向かい合って、彼に抱き寄せられて無惨の足の間に座る女が、青い芍薬の花を髪に飾られた芍薬がいた。
2019.02.06