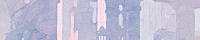 きみは裸足のクイーン・オブ・ハート - text
きみは裸足のクイーン・オブ・ハート - text
※劇団ドラマティカ カラ降るワンダフルパロディ※ネームレス
「それで? 申し開きがあるなら今のうちに聞いておこうかしら。その口がまだ回るうちに」
一人の少女の冷徹な声が謁見の間に響いた。玉座の肘掛に頬杖をついて座る少女の眼差しは吹雪よりも冷たい。スリットの深い真紅のスカートからはすらりと色の白い脚が覗き、玉肌を彩る針のような踵のピンヒールは床に膝をつく兵士の頭に乗せられている。女王の前で首を垂れる彼の顔はブルーベリーよりも真っ青で、額を伝った冷や汗がぽたぽたと床に雫を落とした。
彼の罪状は餌の与え忘れだ。女王が可愛がっているハリネズミへ餌をやるのを忘れたのだ。
「お、お許しください女王様! もう絶対に、二度といたしませんので、どうか――あぁっ!」
「頭を上げていいなんて言ってない」
兵士が女王を見上げようと僅かに首を動かした瞬間、女王は勢いよく立ち上がった。硬い床とヒールに挟まれた兵の額がゴンッと鈍い音を立てる。女王の行いそれに留まらず、さらに持っていた細い棒状の鞭で兵の背を思いきり叩いた。
額と背に走った痛みに呻いた兵はぷるぷるとその体を震わせる。もう一度同じ場所を叩くと、打ち上げられた魚のようにビクンと体を跳ねさせた。
続けてもう一度、と女王が鞭を振り上げると、その手は突如現れた別の手に覆われる。
「……何のつもり? ハートのジャック」
「ご無礼をお許しください、女王様。ですがそれ以上は、女王様がお手を痛めてしまいます」
床に這いつくばる兵と同じ軍服に身を包んだ紺色の髪の男は自身の右手を重ね、鞭の柄を握る女王の手をするりと緩めた。まるで淑女をダンスに誘う紳士のようなやわらかな手つきで、その手から鞭を奪い去る。開かれた彼女の手のひらは彼の言う通り赤くなっていた。
女王はきっと眉を吊り上げてジャックを睨んだが、彼の金色の目に見据えられて言葉を詰まらせる。邪魔をされた怒りを乗せようとしていた罵詈雑言はぐっと奥に引っ込んでしまった。一度そうなってはもう意地を張り続ける気にもなれず、女王は不機嫌そうに再び玉座に腰を下ろしす。
「……もういい。はやく連れていって」
疲れたように絞り出した女王の声を聞いたジャックが速やかに傍に控えていた兵に目配せすると、槍を携えたトランプ兵たちがわたわたとやってきては床に伏せる兵を連行していった。広い空間には女王とジャックの二人だけが残され、沈黙が場を支配する。
女王はちらりとジャックの顔を盗み見る。
彼はまるで呪い殺さんばかりの憎悪を孕んで兵たちの消えていった方向を見ていた。今まで一度たりとも自分に見せたことのない彼の顔を見てしまい、開けてはいけない箱を開けてしまったかのような気分になる。暴君とまで呼ばれる自分のはずが何となくいたたまれなくなって、すっと顔を逸らした。
するとジャックはおもむろに女王の前で膝をつき、先程消えた兵と同様に首を垂れる。
「……不躾な真似をしました。どうか罰をお与えください、女王様」
彼は床を見つめたまま女王から奪った鞭を両手に掲げて献上した。
女王は暫しそれを見下ろしたのち、鞭をつまみ上げて――ぽいっと適当に投げる。
「ああっ!」
「“ああっ”……?」
「あ、」
反射的にジャックが鞭を目で追い叫ぶと、女王の視線の温度が極端に下がった。それに気づいた彼は僅かに頬を染め、身震いをする。
女王はそんな彼の変化に目を細め、鞭を捨てた手をひらひらと振った。
「さっきの兵を叩いてもう手が疲れたの。お前へのお仕置きはなしね。帰っていいわよ」
「そんな!」
ジャックを無視してさっさと立ち上がろうとした女王の行く手を阻むように、彼はざざっと膝立ちで迫った。ひどく興奮した様子で両手を広げ、息を荒げて言う。
「鞭がお嫌でしたら、お御足で踏んでいただけるだけでも! いやむしろ踏んでください! 先程の兵への鬱憤もこめて、さあ! 思い切り!」
「気持ち悪い!!」
一国の統治者としての外聞も何もかも投げ捨てて女王は心からそう叫んだ。まるで蛇を見つけた猫のような俊敏な動きで距離をとり、玉座の後ろに隠れる。
「お前って本当に気色悪い言葉しか吐かないわね! 二度と不快な物言いをできないようにその口を縫い付けてやってもいいのよ!?」
「女王様が手ずから縫い付けてくださるのなら……」
「ちょっと嬉しそうにするなぁ!」
にやける口元を手で覆い恍惚とした表情を浮かべるジャックを前に、女王の全身を悪寒が駆け巡った。せっかくの新雪のような滑らかな腕には鳥肌が立ち、瞼はピクピクと痙攣している。国全土にまでその名が轟く悪辣の女王でも、度を越した変態が相手ではただの人だった。
「お前、昔はそうじゃなかったはずでしょう。いつ頭を打ったの?」
「いつから女王様をお慕いしているかだなんて……少々気恥ずかしいですが、女王様が話せとおっしゃるのならばお答えしましょう。あれは女王様が王位に就かれてまだ……」
「話が通じない。イライラする。……少なくとも私が女王になる前はこうじゃなかったと思ったのだけど」
女王は目を伏せ、遠い過去の記憶をなぞった。
彼女がまだ若くして王冠と錫杖を手にする前。暴君の欠片もないただの世間知らずの姫君だった頃に、ハートのジャックが護衛役として傍に仕えることになった。側近に似た役目、その上歳も近かったため言葉を交わすことも多かったが、その頃はこんなにもマゾヒズムに染まってはいなかったはずだ。
変容とは度し難いものだ。姫から女王へ、たった一つの錫杖と王冠の有無でその他の全てが変わる。姫であったころの名前なんて皆忘れてしまったかのように、ハートの女王としか口にしなくなった。真摯で忠義に厚く、庭園の隅で王位継承のプレッシャーに怯える娘の手を握ってくれた彼でさえも、彼女が女王となれば変わってしまった。
もう記憶の中の騎士はいないのだ。いっそ姿を消してくれれば、そういうものだと割り切れたものを。
「もういい。部屋に戻って休むわ。お前は他所のお茶会なり何なりどこへでも行けばいい」
「であれば、私もお部屋までご一緒し」
「動くな。お前、この私が目の前にいながら自分に自由があると思うなんて、随分偉くなったのね」
女王は鉄のような目だけをジャックに向けて、足早にその場を立ち去ろうとした。片膝をついたジャックが今度はどんな戯言を述べるのか期待していた女王だったが、不思議と彼が言葉を発することはなかった。女王は心の奥にひっそりと転がった落胆を見なかったことにして、玉座の間のカーペットを歩く。
「っ、女王様!」
ふと、ジャックが声を荒げた。何のつもりだと女王が振り返りかける。
だがその時、女王の足元からパキンと乾いた音が聞こえた。その音の正体を確かめる間もなく、彼女の体は重力に引っ張られぐらりと傾く。視界に映る床や壁が七色の軌跡を描いてぐるりと反転した。
手を伸ばして体を支えることもできないまま彼女が倒れ込む。けれどその背が、頭部が床に打ち付けられる直前で、転倒は突如終わりを迎えた。
「女王様! お怪我はありませんか!?」
目を開いた女王が最初に見たものは、豪華絢爛な装飾の天井を背景に己を覗き込むジャックの顔だ。彼の手が自身の背と膝裏に回され、女王は体のどの部分も床と接触させることなく彼によって支えられている。
自分がなぜ急にバランスを崩し倒れたのかは少し視線を動かせばすぐに理解できた。果実を刺し貫けそうなほど細く、そして高いピンヒールの踵が折れたのだ。ジャックの足元には女王のヒールの片足と、細長い踵が転がっている。
「え、ええ……お前、よく動けたわね」
「女王様のためならこの程度はなんてことありません。お怪我がないようで安心しました」
ジャックは女王の安全を確認すると、幼さの抜けた凛々しいかんばせをふわりと綻ばせた。どことなく目を合わせ続けているのが気恥ずかしくなって、ふっとそっぽを向く。
「お前は、よく人のこと見てるわね」
「女王様だからですよ。私のこの身、この心、そしてこの命は女王様のためにありますから」
彼は女王を抱える手に力を込めて、囁くように述べた。
「お慕いしております、女王様。どうかこの恋が貴方の元で朽ち果てるまで、お傍にいることをお許しください」
そうして彼は、耳を赤く染めながらも苦さを孕んだ、切なくも熱い目を女王に向けた。月光に照らされた白薔薇のような、美しい男だと思った。
女王が返す言葉を見つけられずにいると、彼は「ところで」と形容しがたい空気を自ら打ち破る。
「女王様を裸足のまま床に降ろすわけにはいきませんので、お部屋までは私がこのままお連れしようと思うのですが」
「っ、結構、よ!」
女王は衝動のままに、ジャックの頬を思い切りぶった。スパァンと景気のいい音と共に小さく呻いた彼の手から力が抜け、女王はその一瞬を見逃さずに体を捩ってぴょんと地に足をつける。直前できちんと残った方のヒールを脱ぐのも忘れずに。
「女王、様……! 今のはとても良かった……っ!」
「気持ち悪い!!」
「ぐはっ」
頬をぶたれたこととは別の要因で赤くした彼は高揚と目を輝かせたが、そのすぐ後に女王が投げたヒールを顔面に受け止めてその場に倒れ込んだ。城のメイドたちに好評の端正な顔立ちはすっかり残念なことになってしまっているが、それでも彼は立ち上がって女王の元へ縋ろうとする。
ので、女王は逃げた。裸足のまま、城の廊下を全速力で駆けた。
「おっ、お待ちください! 女王様ぁ〜〜〜!」
ハートの女王は背後から聞こえる情けない声を完全に無視しながら、つい数分前の出来事を脳内で反芻した。
『お慕いしております、女王様』
(嘘つき!)
もう私の名前を呼んでくれないくせに。