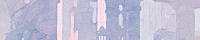 未来永劫、白き自由の君を待つ - text
未来永劫、白き自由の君を待つ - text
※ネームレス※魔神任務1章3幕、伝説任務「古聞の章」ネタバレ
旅人とパイモンが翠決坡にて九つの柱を起動させた後、その奇妙な光は弧を描いて空へと打ち上がり、真っ直ぐに璃月港の方向へと伸びていった。始終を遺跡の出入り口から見上げていた旅人とパイモンは額をサッと青く染め上げ、同時に顔を見合わせる。
片割れを探してテイワットを旅する中で、二人はこれまでに幾つもの遺跡に触れてきた。中には装置を起動させた途端に遺跡守衛や遺跡ハンターが襲ってきた例も多々あり、何度冷や汗をかいたことか分からない。大抵その奥にパイモンがお宝と目を輝かせる何かが隠されていることも多いのだが、それでもそれが全てとは限らなかった。
だから、遺跡を探索する時は十分注意しなければならない。もしかすると、お宝どころか厄災を目覚めさせてしまう可能性もあるのだから。飛んでいった光を追いかけ、旅人とパイモン全力ダッシュで璃月港へと向かった。
璃月は変革の時を迎えたばかりだった。ファデュイの使者によって復活した渦の魔神オセルを人と仙人の力だけで封印し、璃月は岩神モラクスの手を離れた。岩王帝君は今や人々の記憶の中だけに残る存在となり、本当の意味で神の時代は幕を閉じた。
だからこそ、今が最も大事で、最も警戒するべき時なのだと旅人は“天権”凝光から聞いた。岩王帝君が全権を手放し、凝光の群玉閣もオセルと共に海に沈んだ今、璃月の防衛は最大まで薄まっている状態だと言う。千岩軍も万能ではない。この璃月全域を警備しようにも、璃月の土地は広すぎた。
そして何よりも、人は未だ仙人や魔神のような人知を超えた力に到達できていない。太古の昔璃月に蔓延っていた魔神は岩神が一掃したが、中には討伐しきれずに封印された魔神もいくつか存在する。もしも今その封印が解け魔神が璃月に侵攻してきたとしたら、璃月は抵抗すらさせてもらえずにあっという間に飲み込まれるだろう。
旅人は知っている。岩神が死んだというのは嘘偽りで、今は人の世に紛れて暮らしているということを。そして、その岩神は既に神たる証を遠い北国の神へと送り、ただの凡人と成り果てたことを。
今の璃月に混乱の種を持ち込むわけにはいかない。友が守り、友が愛したあの美しき港を、戦火に塗れさせるわけにはいかなかった。
だが――璃月に辿り着いた旅人は、あまりの平凡さに言葉を失った。翠決坡から飛んできた光など皆気にもしていない様子で、いつもと変わらない賑やかさを保っている。通りも埠頭も人と商品とモラに溢れ、何ひとつ変わることのない璃月の日常がそこにあった。
おかしい。自分達の見間違いだったのだろうか。試しに付近の人物数人に話を聞いてみたが、そのような光は見ていないと言う。では、自分達が目撃したあれは一体何だったのか。道の端でそう唸っていると、ひと際明るい声が旅人の頭上に降りかかった。
「なーにしけた顔してんの? お腹すいてる?」
ごくごく平凡な少女だった。璃月の娘がよく着ている流行りの服に身を包み、髪はハーフアップにして髪留めで止めている。ゆったりとした目元から一見大人しめな印象を受けるが、口調や言葉遣いは活発そのものだった。
「ん? 確かにお腹はすいてるけど……って、お前は一体誰だ?」
「私のことはいいじゃない、ただの道行くお姉さんってことでさ。それより、時間があるなら一緒にご飯行かない? あっ、これってもしかして“逆ナン”ってやつになったりするのかな? ウケる〜!」
よく喋る人だ、と旅人は思った。公子に初めて会った時の胡散臭さにも少し似ているが、彼女からは何かを隠している様子は伺えない。本心で、旅人と一緒に食事がしたいと思っているようだった。
きっと平時であれば乗っていたであろう誘いだったが、今は渋々断る。翠決坡から放たれた光の正体が分かるまで、悠長に食事を取っている時間はないからだ。その旨を彼女に伝えると、彼女はそれならと腰に手を当てて満足そうに控えめな胸を張った。
「なら、食べながらお話しない? さっき飛んできた光のこと、聞いてくれたら何でも答えちゃう!」
「本当か!? お前、さっきの光について何か知ってるのか!?」
「翠決坡の方から飛んできた光の事でしょ? 空を見てたら偶然見えたんだよね」
これは大きな進展だ。十人中十人が知らないと答えたのに、まさかこの少女が目撃していたとは。光の落ちた場所を聞こうとするが、「だからそれは食べながらだって」と躱される。とうとう旅人の方が折れ、名も知らぬ少女との昼食が決定した。
「で、どこに行く? 璃月って、どこのお店が美味しかったりするの?」
「って、璃月の人なのに料理の店を知らないのか!?」
パイモンが驚いて彼女を見上げるが、当の彼女はあははと笑って誤魔化すばかりだった。彼女の姿は全身璃月の娘そのもので、他国からの観光客だとすると相当璃月の経済に貢献したことになる。気がかりな点が多い少女だったが、不思議と悪意は感じなかった。財布の中身と相談して、旅人は万民堂はどうかと提案する。
「万民堂は、確か香菱が働いてる店でもあったよな! 鍾離もあそこの料理は美味いって言ってたぞ!」
「鍾離……?」
聞き馴染みのない言葉だったのか、少女は首を傾げた。それもそのはず、鍾離とはとある人物の名だ。一部の界隈ではそこそこ有名だが、知らない人物も少なくはない。
「往生堂の客卿で、鍾離って名前なんだ。すっごく博識で、みんなからは鍾離先生って呼ばれてる」
「へえ、今の璃月にはそんな人がいるんだ。長い間港を離れてたから知らなかったや」
「もしかして、軽策荘から来た人?」
旅人が少女に問いを投げかける。彼女の身なりからして、そこそこ良い家の生まれなのだろう。璃月以外でそんな家が建つとすれば、軽策荘の周辺しか思いつかなかった。けれど彼女は首を横に振り、「軽策荘ほど遠くはないかな〜」と話す。
「まあ、私の話は良いじゃない。それより、万民堂? ってところに行くんでしょ? それなら早くしないと。もうすぐお昼時で混んじゃうし〜」
「おい、押すな! お前道分かるのか!?」
へらへらと陽気に笑って、彼女は、旅人とパイモンの背中を押して歩き始めた。「あはは、わかんな〜い!」とパイモンと愉し気なやりとりをする様子を見て、旅人は額を押さえる。これはあれだ、まともに取りあおうとすればするほど相手のペースに飲まれるやつだ。
とりあえず、この状態は人目を引くのでやめてほしい。そう旅人が伝えると彼女は渋々手を離し、名残惜しそうに旅人の隣に立った。
万民堂へ行く間も、彼女の口が閉ざされることはなかった。終始「あれは何?」「あの人たちは何やってるの?」と疑問が止まらず、仕方なく旅人とパイモンがガイド役を務めている。二人も璃月に来て日が長いわけではないのだが、これではどちらが璃月人なのか分からなかった。というか、いくら辺境に住んでいるからと言ってもここまで璃月の事情に詳しくない璃月人がいるのだろうか……?
時刻は正午という事もあり、万民堂の中は昼食を食べに来た人々でほぼ満席の状態だった。なんとか一番奥のテーブルを見つけ、向かい合って席に着く。労働者が腹を満たしにやってきている中、変わった服装の旅人、やけに身なりの良い少女、そして謎のマスコットという組み合わせは実に浮いているようで、ちらちらと視線が飛んで切るのを感じた。
そんな中、メニュー表を見て悩んでいると頭上から声がかかった。
「旅人、お前もここに来ていたのか」
少女よりもよほど上質な服に身を包み、この場の誰より浮いた……と言うよりも、浮世離れした青年が、テーブル席を見下ろして立っていた。旅人とパイモンは彼の姿を見るなり目を丸くし、その名を口にする。
「鍾離! お前も万民堂で食事か?」
「ああ。しかし今日は一段と人が多く、なかなか席が空かなくてな。相席しても構わないだろうか。勿論、旅人とそちらのお嬢さんさえ良ければ、だが」
鍾離の後ろを見渡すと確かに万民堂の席は既に埋まっていて、空いているのは旅人たちの座るテーブルだけだった。旅人に拒否する理由はなく、それは少女にとっても同じだった。少女は少しの間鍾離の瞳を見上げると、「私も問題ないし、どうぞ〜」と快く承諾する。鍾離は一言礼を述べ、旅人の隣の席に腰を下ろした。
食事の間、鍾離は璃月の近況を旅人と少女に聞かせた。璃月で起きた騒動からまだ時間が経ってないためか、話題はもっぱら渦の魔神に関することばかりだ。璃月七星と仙人、そして旅人によってオセルは再び海に沈んだが、それでも不安を感じる民は少なくない。漁業も盛んな璃月では埠頭を中心に“いつかまた渦の魔神に襲われるのではないか”という噂が囁かれ、事実上の統治を取ることとなった七星の手を焼かせているようだった。
好奇心旺盛な少女は鍾離の話にずっと耳を傾けっぱなしで、お前は食事をしに来たのか鍾離の話を聞きに来たのかというパイモンのツッコミでさえも耳に入っていないようだった。今なら一口くらい皿から持って行ってもバレないんじゃないかとパイモンが箸を伸ばすが、その手は少女によって払われあっけなく終わる。仕方なく、旅人が自分の分の翠玉福袋をパイモンの皿によそってあげた。
「って、お前は渦の魔神の話も知らないのか? てっきりもう璃月中に広まってると思ってたぞ」
「渦の魔神自体の話は知ってるよ。渦の魔神オセル……魔神戦争の時代に、岩神モラクスが海に封じた魔神でしょう? でもまさか、つい最近封印が解けたなんて!」
パイモン相手にそうけらけらと笑う少女の顔を、旅人は眺めた。この少女は、少し変わっている。俗世に疎いというレベルを超えていた。渦の魔神の話など今や璃月を越えてモンドにまで伝わっている話だというのに、この少女は本当に今初めて知ったようだ。
大方食事を終え、後はデザートだけというところで、旅人は「あっ」と声を上げた。
「? どうした?」
「光のこと、まだ聞いてない」
「光……? ああ、先ほど翠決坡の方角から飛んできたあれのことか」
「何!? 鍾離も見たのか!?」
旅人もパイモンも、これには驚きだった。あれだけ尋ねても光を見たという人物は目の前の少女一人だけだったというのに、まさか鍾離が目撃していたとは。これは大きな収穫だ。何せ、今の彼はただの凡人鍾離だが――6000年を生きた岩神モラクスとしての知識ならば、あの光についてより詳細な情報が得られるかもしれない。
「そっちのお兄さんが知ってるなら私いらなくない?」と少女は苦笑したが、旅人は「これも契約のうちだ」と返した。少女は旅人をパイモンを食事に誘い、共に時間を過ごす代価として情報を提供する。見ようによってはこれも立派な契約だった。
契約の神が見下ろすこの璃月の大地で契約を反故にするわけにはいかない。それは璃月に生きる者全てに通じるルールだ。少女は知らないが、旅人の隣で杏仁豆腐を食している男こそがその契約の神なのだから。尤も、今は神としての力を失っているのだが。
「でも正直、私もあれが何なのかよく分かってないんだよね。ただ、翠決坡の方から飛んできたのを見たってだけで」
「光がどこに落ちたのかは分かる?」
「うーん、璃月の上空でスッと消えちゃったから、どこに落ちたとかは分からないや……」
「そうか……鍾離はどうだ?」
「俺は……」
パイモンの問いに鍾離は答えようと一瞬口を開きかけるが、店内の様子を見て別の言葉を吐き出した。
「……少し長くなりそうだ。ひとまず、店を出よう」
万民堂の外は人の列ができかけていて、店員もせわしくなく動いている。この込み具合で長時間滞在するのはさすがに憚られたため、旅人はコップに残った水を飲み干すと鍾離の言葉通り席を立ちあがった。
「鍾離〜。何も璃月港の外に出る必要なんてあったのか……?」
万民堂を出た鍾離は、旅人とパイモン、少女を連れて璃月と黄金屋を繋ぐ道を歩いていた。ここまで来ると行き交う者もおらず、まれに千岩軍が見回りで通りがかるだけだ。それもそのはず、このまま道を進んでも黄金屋と青墟浦しか存在しない。どちらも、千岩軍でも冒険者でもない一般人が進んで来るような場所ではなかった。
歩きながら、鍾離は先程の光についての話の続きを述べる。
「璃月において、古来より“縁”とは重要なものだ。璃月に住む者たちに見ることができず、俺とお前たちだけが見ることができたのは、そこに“縁”があったからだろう」
よく分からない。旅人とパイモンは首を傾げた。
少女は鍾離の行動の理由が分からず、困惑した目で旅人に視線を送る。しかし旅人もパイモンも、何故鍾離がここまで連れて来たのか推測することはできなかった。鍾離は金銭面では突飛な行動ばかり取るが、判断能力を狂わせているわけではない。むしろ、思慮深さに至っては人間のそれをはるかに越していた。
だが、その聡明さがあれば少女をこんなところまで連れてくるという発想には普通至らないだろう。いくらこの周辺はヒルチャールが少ないと言っても、脅威が無いわけではない。戦う術を持たない一般人が外に出るには、それなりの危険があった。だからこそ、旅人は鍾離の思考をはかりかねていたのだ。
しばらく進んだところで、「この辺りでいいだろう」と先頭を歩いていた鍾離が足を止める。振り返った鍾離の瞳がすっと細められ、旅人とパイモンに緊張感が走った。
「さて――そろそろそのお嬢さんの体から出て行ったらどうだ?」
一瞬、旅人は鍾離が何を指してそう告げたのか理解できなかった。しかし鍾離の視線は真っ直ぐに旅人の隣、先ほどまで一緒に食事をしていた少女の双眸に注がれており、必然的に彼女に向けられたものなのだと物語っている。鍾離の視線は険しく、もう彼に神の心は無い筈なのに無意識に「岩神、」と呟いてしまっている自分がいた。
少女は答えない。彼女の表情は何の色も映すことはなく、ただ鍾離からの視線を見つめ返している。空気に耐えかねたパイモンが「鍾離? 一体何を言って……」とおそるおそる聞き返したが、その言葉を遮って少女は突如笑い出した。
「あっははは。もしかしたら気付かないんじゃないかって不安になるところだったよ」
「1000年……いや、1500年か。目覚めたばかりでも、お前は変わらないな」
「君は変わったね、モラクス」
少女は子供のようににっと目を細め、鍾離は仕方のない奴だと腕を組んだ。
何やら、おかしなことになってきている。鍾離は突然睨み始めたと思いきや今は何てことない普通の凡人の顔に戻っているし、少女は少女で先ほどとは少し様子が違う。旅人に初めて話しかけた時と態度が違うわけではないのだが、どこか鍾離に対してだけは気の知れた友人のような雰囲気を……友人?
鍾離と少女の顔を交互に見比べる。鍾離は元岩神。そしてその岩神と旧知の中と言えば……。
「貴女も……仙人?」
璃月を巡る騒動の中で、旅人は幾人もの仙人と出会ってきた。鍾離と少女の会話で彼女が気が遠くなりそうなほどの長寿だということは察したが、それほどまでの存在となると旅人には仙人しか思いつく心当たりがない。パイモンも同意見だったようで、少女の正体を知ろうと前のめりになって彼女の返答を待ったが……彼女は首を横に振り、「惜しいね」と答えた。
「私は……」
「彼女は“砂”の魔神。魔神戦争を生き残り、1500年前に俺が翠決坡付近に封印した魔神だ」
「魔神!?」
旅人とパイモンは目を見開き、揃ってその言葉を復唱した。対して彼女の方は腰に手を当て、「せっかく私が名乗ろうとしてたのに」と台詞を奪われたことに多少腹を立てている様子だった。しかし鍾離は全く動ずることなく、あっけらかんと腕を組んだままその場に立っている。それがまた彼女の気に障ったのか、おっとりとした瞳が少しだけ細められた。
パイモンは「そういえば、岩王帝君って言ってない!」と先ほどの少女の言葉を思い返し、仙人ではないという事実に納得した。璃月に生まれ、璃月に住む者であれば誰しも偉大なる岩神モラクスに敬意を込め、“岩王帝君”と呼ぶのが暗黙の了解だった。それは仙人も同様で、一度“モラクス”と呼べば直ぐに不敬だと糾弾されること間違いなしだろう。けれど少女は、万民堂で躊躇もせずにモラクスの名を口にした。その時点で、璃月に生きる一般人や仙人の可能性は潰えたと言っても過言ではなかったのだ。
おそらく彼女が璃月に関する常識と言っても差し支えないような情報を知らなかったのも、1500年という時間のズレがあったからだ。先日渦の魔神が復活した話も、当時は封印されていたのだから知らなくて当然だろう。
魔神という言葉を聞けば、旅人としては警戒せざるを得ない。渦の魔神オセルが璃月を飲み込もうとしてからまだ日が浅く、つい“魔神=敵”という固定概念が払拭されずに残ってしまっているからだ。
そんな旅人達を安心させるかのように、鍾離が補足として口を開く。
「心配せずとも、彼女にもう魔神としての力はほとんど残っていない。彼女がそのお嬢さんの体を借りているのがその証拠だ」
「そういうこと。そう身構えなくても、渦の魔神みたいに璃月滅ぼそうだなんてしないし、そもそもできないからさ」
「えっと、どういうことだ……?」
彼女……砂の魔神が無害であるという事は、元岩神の言葉を信じるとして。彼女が少女の体を借りている、というのは一体どういう事だろうか。そう聞き返すと、「それは私が話すよ」と少女が述べた。
「渦の魔神オセルは君たちに強烈な印象を残したみたいだけど、魔神の全員が全員凶暴な奴だったってわけじゃないのね。中にはモラクスと同盟を結んだ者もいるし……私みたいに、早々にモラクスに下って生き残った弱っちいのもいる」
砂の魔神は、魔神の中でもひと際力が弱かった。塩の魔神ヘウリアと比べればどちらもどっこいどっこいと言わざるを得ない程に弱小で、きっとモラクスに下っていなければヘウリアと同じ末路を辿っていただろう。
「なんとか魔神戦争を生き残って仙人ともそれなりに仲良くやってたのはいいんだけど……まあ、色々あってモラクスには封印されてね。1500年経った今、先日のオセル復活と近くにあった翠決坡の柱の起動が私の封印を叩いて、元々風化してた封印が解けちゃったってわけ」
「なら、翠決坡から璃月港に飛んで行ったあの光は……」
「私。正確には、私の
「魂?」
「分離したの。私の体と、魂が」
それも鍾離や仙人の使うような仙術なのかと聞けば、少女は否と答えた。体と魂の分離。それは決して、意図して起こったものではない。
「長い封印の中で、私と言う魔神は眠りについた。けれどその封印は、決して肉体の保護を保証するものではなかった」
「じゃあ、もしかしてお前の体はもう……」
「砂になって、翠決坡の大地に混ざってるだろうね」
1500年の歳月は、一人の魔神の体を朽ちさせるのに十分すぎる時間だった。渦の魔神オセルが長い封印の中でも己の姿を保てていたのは、彼自身に魔神としての強大な力があったからだ。岩神の庇護下に下らなければ生き残れなかったような魔神にそんな力があるわけもない。
「本当なら体が朽ちた時点で魂も消え失せる筈なんだけど……なぜか魂だけは厳重に守られてたんだよねぇ。一体どうしてなのかな〜?」
「………………」
鍾離は目を伏せるばかりで答えない。
本来なら、封印の中で死んでいてもおかしくないくらいだったと言うのに。それでも死だけは回避できたということは、あの封印に砂の魔神を殺させない“何か”が施されていたという事なのか。真相は隣に立つ岩神のみが知ることだ。
封印が解け魂だけの存在となった砂の魔神は、璃月港でうたた寝をしている少女と出会った。魂だけで彷徨う訳にもいかず、それならばと少女の体に入ったのが数時間前、丁度旅人とパイモンに話しかける数分前の出来事だ。
元々の体の持ち主であった少女については安心して欲しい。今も体の主導権を砂の魔神に引き渡したまま、すやすやと眠っている。この体から魔神が出て行ったとしても問題はないだろう。まあ、例え一時でも魔神の魂に触れたのだ。後遺症として妖魔の類が見えやすくなるような事はあるかもしれないが、人の世となった今の璃月で生活する分には無害だ。そう伝えると、パイモンはさらなる疑問を鍾離にぶつける。
「それなら、なんで鍾離は砂の魔神を封印したんだ? 魔神戦争が終わった後も、砂の魔神は仙人と一緒に璃月を守っていたんだろ?」
「それは……」
「若気の至りでポカやっちゃって、モラクスにコラ☆ってされたの。私にもかわいい時代があったんだよ?」
「コラ、で1500年も封印されたのか!?」
問いに答えようとする鍾離の言葉を遮って、少女――砂の魔神はいつもよりも声のトーンを数段上にしてそう述べた。かわい子ぶる、とはまさにこのことだろう。人差し指を頬の近くで立ててウインクを飛ばす彼女の姿を見て、旅人は砂の魔神が器に選んだのがこの少女で本当に良かったと考える。見てくれが少女だから許される言動だが、これが青年や中年以降の人物であればなかなかに見るに堪えない光景であった。
……というか、魔神にしてはノリが軽すぎないか、彼女。旅人比べると終始リアクションの大きいパイモンは、砂の魔神の恰好の玩具だ。
コホン、と鍾離は咳払いをすると、旅人に対して「頼みがある」と声をかけた。
「どうか、彼女の魂の器となるものを探してほしい。人……いや、この際人でなくとも問題はないだろう」
鍾離の発言に、砂の魔神は「え」と声を漏らした。
「私は別にこのままでもいいんだけど……」
「お前個人の良し悪しは関係ない。魔神の時代は終わり、そして仙人の時代も幕を引いた。俗世に紛れて暮らすのを止めるつもりはないが、それ以上そのお嬢さんに迷惑をかけるのはやめろ」
鍾離の言葉に砂の魔神は驚いたように目を見開くと、ふんと鼻を鳴らして彼とは反対方向を向いた。まるで父親に諭された後の子供のようだ。けれど、反論しないという事は彼の意見に賛同するという意味でもあった。
砂の魔神の復活がもう少し早く、まだ鍾離が神の心を手放していない頃であれば、おそらく彼女の器をつくることも容易かっただろう。岩神の死を偽装する為に偽の体を用意したように、神の権能があれば造作もないことだった。しかし岩神は消え、今は鍾離という只の凡人に成り果てた。凡人にゼロから肉体を作る手段など無い。
けれど、そんなに都合よく肉体が手に入るだろうか? 少なくとも、事情を話して“どうぞ自分の体を使ってください”と差し出してくれるような人間は存在しないだろう。人間以外の動物もそれは同じだった。
旅人は暫く熟考し、「じゃあゼロから肉体を作れる奴に頼むのはどうか」というパイモンのアイディアによって何かを閃くと、慌ててパイモンを引っ掴み「ちょっとモンドに行ってくる」と駆け出してしまった。遠ざかる旅人の背中をパイモンの叫びを見送り、鍾離と砂の魔神は頭に疑問符を浮かべつつ顔を見合わせるのだった。
九つの柱。人々が平和を願い作り上げたそこは、神殿と呼んでも相応しい場所であった。そしてそれは、あながち間違いではなくなる。神殿を神の住居を定義するのであれば、これから神を封印するこの場所も正しく神殿だ。……神と言っても、正確には魔神。魔神戦争を岩神の陰に隠れてこそこそと生き抜いた、人に誇れるような力を持つ神ではないのだが。
「見送りとは泣かせてくれるね、モラクス」
人の技術の集大成を見上げる女が、そう告げた。
この璃月の地で彼をその名で呼ぶのは、今や彼女一人だけである。人々も仙人も皆彼を“岩王帝君”と尊称し、彼の威光を仰いだ。塩の魔神も塵の魔神も逝き、渦の魔神も彼の槍の下で眠っている。残すは砂の魔神だけだったが、それももうじき潰えることを理解していた。
モラクスは彼女の横顔に、なぜ抵抗しなかったのかと尋ねた。抵抗なんてしないさと彼女は笑った。
「今ならヘウリアの気持ちが分かるよ。彼女が人を愛したように、私も璃月の平和を……お前が作った平和を愛した。ただそれだけのことさ」
砂の魔神はモラクスの次に長寿だ。璃月が生まれ、育ち、繁栄していく過程をモラクスと共に見下ろしてきた。母が子に抱く感情とはまだ違うのだろうが、確かに砂の魔神は璃月を愛していた。その気持ちだけは本物だった。
けれど、魔神と人はやはり相容れないのだろう。人を愛したヘウリアは人に殺された。海に沈んだ渦の魔神も、未だ人々から畏怖の視線を向けられている。その他の魔神戦争の最中で散っていった魔神達も、岩王帝君の武勇の数だけ人々の恨みを募らせた。そして――人々の視線は、とうとう砂の魔神へと向けられた。
砂の魔神は弱い。けれど魔神であることに変わりはない。いつか渦の魔神と同じように、璃月と岩王帝君に牙を向く時が来るかもしれない。その前に早く。早くあの魔神を封じて欲しい。
どうかお願いします、岩王帝君。お願いします。お願いします。お願いします――あの魔神を、殺してください。
その願いは、モラクスを初めて苦渋の決断へと追い込んだ。璃月の民を守るために、彼は幾度となく槍を振るった。けれど、民の肉体を守る方法はごまんとあれど、心を守る方法を彼は知らなかった。
民の不安を払拭するためには、その不安の原因となるものを排除するのが一番だ。だからモラクスは、どんな時も槍を握り続けた。魔神を討ち、妖を斃し、璃月の敵となるもの全てを滅ぼした。その信念こそ、彼が武神として祭り上げられることとなった理由の一端だった。
モラクスは考えた。考えた上で彼女を、砂の魔神を封じることを決断した。彼女は笑って、それを受け入れた。
恨んでもいい、とモラクスは言った。砂の魔神にとって、岩神の施す封印は強すぎる。身動きひとつ取れず、もしかするとそのまま亡くなってしまうかもしれない。少なくとも、今の体を捨てることになることは間違いなかった。
けれど彼女は、決して恨むことはないと首を横に振る。
「遅かれ早かれ、魔神が潰える未来が来ることは確定していた。璃月の平和の礎になれるのなら、それこそ本望だ」
砂の魔神の封印をもって、璃月に生きる魔神は全てモラクスに討ち滅ぼされたことになる。岩神の威光はより強固なものとなり、璃月は更なる繁栄の時代を迎えるだろう。“岩王帝君”はこれまで以上に信仰を集め、契約の都市が完成する。それこそが、砂の魔神が望んだ璃月の未来だった。
「魔神の時代は終わった。そして、仙人の時代もいずれ幕を引く時が来るだろう。次は君の番だ、モラクス」
呪いのように、彼女はそう言葉を吐いた。
岩神と仙人、そして人。それらは親と子の関係に限りなく近い。そして、子はいつか親の手を離れるものだ。永劫なんてものは世界に存在しない。それが100年後になるか、はたまた1000年後になるかなど想像もつかないけれど、いつの日か必ずそれはやって来る。
嗚呼、いっそ拒んでくれたら。封印されたくないと、助けてくれと一度でもその口から言ってくれれば、その通りにしたのに。仙術でも何でも使って彼女を隠し、人間や他の仙人の目の届かない場所で大事に大事に匿ってしまえたのに。
「神も仙人もいない――人の世でまた会おう」
とうとう名前を呼ぶこともできないまま。微笑む彼女の姿を、モラクスは1500年間片時も忘れることはなかった。
鍾離が往生堂に戻ると、会計係の女が伝票を持って鍾離の元へ駆け寄ってきた。その時点で先日の出費の件だと察し、どうか経費で落としてほしいとだけ伝えて通り過ぎようとする。すると、一匹の白い仔猫がどこからともなく現れ、足止めするかのように彼の足にすり寄った。
ある時から、往生堂では鍾離が仔猫を飼い始めたのだと専らの噂だった。鍾離本人は「彼女は誰かに飼われているわけではない」と否定しているが、仔猫は毎日のように鍾離の元へ現れては餌を強請り、すっかり野生を忘れてしまっている様子である。鍾離も鍾離でその仔猫に対しては甘く、雨の日の夜は冷え込むからと自宅へ連れ帰ったりもしていた。これで飼っていないと言い張るのだから驚きだった。
往生堂に現れる仔猫は職員にもよく懐き、仔猫と戯れる時間は葬儀という暗い仕事を扱う日々の癒しともなっていた。幸いにも猫アレルギーを発症している者もおらず、デスクに煮干しやねこじゃらし、またたびなんかを持ち込んでも黙認されている。
猫のいる職場、最高。往生堂は完全にお猫様の天下だった。
自身の足にぴとりとくっつく白猫の存在に気づき、鍾離がしゃがみ込む。頭のてっぺんから背中にかけてゆったりと撫でてやると、仔猫は目を細めてごろごろと喉を鳴らした。初めの頃は鍾離の手つきもぎこちなく、よく短い前足で叩かれたりしていたものだが、どうやら今日はお気に召してくれたらしい。まるで我が家であるかのように往生堂の床にでろりと転がった。
まさに自由気まま。人とモラの喧騒で溢れる璃月よりも、いっそ隣の自由の国の方が似合うのではないかと思いつつ、鍾離はこの猫と初めて会った時の事を思い出した。
旅人とパイモンが一匹の白猫を連れて璃月へと帰ってきた時は、よく捕まえられたものだと感心したものだ。しかし旅人が言うには、この猫は捕まえたのではなく
隣国のモンドの騎士団には、稀代の天才錬金術師が在籍しているらしい。植物や動物にいたるまでありとあらゆる生命を誕生させる彼であれば、きっと砂の魔神の器になり得る存在を創ってくれるかもしれない。そう考えてモンドに戻った旅人だったが、その過程はそれはもう苦難の連続だったとパイモンは話した。
良くも悪くも、その錬金術師は自分の興味のある存在しか生み出さない。何か適当に動物を創ってくれという曖昧さ極まるオーダーでは当然興が乗ることも無く、翼以外が透明な小鳥だったり妙にのっぺりとした芋虫だったり、挙句ヒルチャールが量産される始末である。旅人とパイモンが彼の興味を猫へ向けようとあれこれ画策し、なんとか仔猫が生み出されたころには一週間が経過していた。
その話を聞いていた鍾離はあまりの面白さについ笑いそうになったが、ここで笑い飛ばすのは旅人とパイモンの努力に対して失礼だろうと必死に飲み込んだ。二人への謝礼は弾ませなければならないし、今度モンドを訪れた時はその錬金術師に手土産を持って礼を言いに行かなければ。酒好きの風神に絡まれる可能性があるのは少々厄介だが、まあ許容しよう。
そんなわけで、彼女――砂の魔神は、1500年の月日を経て猫の人生、いわゆる“猫生”を十二分に謳歌していた。お腹が空けば鍾離に餌を強請り、少しかわい子ぶれば道行く人や往生堂の者が構ってくれる。砂の魔神だった頃よりも楽しんでいるのではと疑い始める鍾離だったが、まあ、それも良いだろう。
彼女は璃月の為に1500年我慢した。もしもそれすら許さずに天罰だと矢を振らせようものなら、鍾離自ら槍を振るい全ての矢をはたき落として見せる覚悟があった。それでもまだ許さないとするのであれば、凡人鍾離の全てを投げ打ってでも彼女を守ろう、と。
ごろんと寝そべった彼女のお腹を撫でる鍾離だったが、ふとあることに気づくとその手を止める。
「お前……少し太ったか?」
刹那、鍾離の手に猫パンチが炸裂する。もう彼女が人の言葉を喋ることはないが、人間の言葉はしっかりと理解していた。
レディになんて言葉を吐くんだ、このデリカシーのない男め。6000年生きているというのに紳士さの欠片もないのか。いやまあ、確かに少し、少しだけふくよかになったかもしれないけれど。それは色んな人がおやつをくれて、私はそれに応えてあげているだけなので。決して私の怠惰っぷりが極まってしまったからだとか、そういうのではないので。
クレームと弁明を必死に口から出したところで、その長ったらしい言葉は「みゃう」という鳴き声にしかならないのだ。猫の体とは時として不便である。けれど怒っているということは伝わったらしく、鍾離は「悪かった」と再度頭を撫でた。
猫と暮らす日々の中で、彼の撫でテクは格段に進化していた。それがあまりにも上手いものだから、いくら機嫌を損ねていたとしてもつい許してしまうのだ。そんな猫と鍾離のやり取りを見て、会計係の女はまるで会話をしているようだと微笑んだ。
「そういえば、以前から気になっていたのですが」
「? どうした?」
「その猫、名前はないのですか?」
会計係の女の問いに、鍾離は「あるぞ」と簡潔に答えた。それでは何と言うのかと女は再度尋ねる。
「ああ、名前は――」
鍾離は目を細め、手の中の仔猫を見下ろす。そして大層愛おしそうに、1500年前終ぞ呼ぶことのできなかった、今や誰も知ることのないその名を口にした。