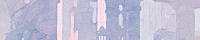 ピクラスの遠吠え - text
ピクラスの遠吠え - text
最初に手に入れられなかったのは、だった一冊の娯楽小説だ。市井でごく普通に流通している大衆文学の一つだった。何がきっかけか当時の若者の間で注目を集めた作品で、その熱は世俗と一切関わりのない私の耳にまで飛び込んでくるほどだった。
それほど流行っているのならば、さぞ面白い内容なのだろう。
すっかりその小説に興味を引かれた私は、次回の算術課題で満点を取る代わりにと本の入手を両親に打診した。同盟内屈指の貴族令嬢であり、芸術文化と言えばハイカルチャーしか与えられなかった私が
それでも宣言通り、私は家庭教師から出された課題を見事なまでに赤丸で埋めつくした。
天才的頭脳を持ってして、という訳ではない。神童だなんだと持て囃す周囲にはそのように見えてしまっていたのかもしれないが、少なくともそれはただの幻だ。机に齧りつかなければ学問は修められないし、復習しなければ知識は消えていく。
それでも同年代の庶民の子が読んでいるという文学を一度経験してみたくて、眠い目を擦って何とかペンを握っていた。その奮励がとうとう実りを迎えようとしていたのだ。
だが次の日、私の部屋の机に置かれていたのは件の小説ではなく、分厚く無機質な兵学書だった。
そのレベルの算術が解けるのならば、今から兵学を学んでも難はないだろう、と父は言っていた。
それを聞いて私は、なるほどそういうこともあるのかと自分でも奇妙なほどに納得した。
努力は報われないのだと。
約束は果たされないのだと。
貴族として生きるということは、そういうことなのだと。
その後も人形がチェスに変わっていたりティーセットが弓一式になっていたり、似たような出来事を繰り返して幾数回。
極めつけはこの家どころか、同盟諸侯全体を震撼させた事件が発端となった。
レスター諸侯同盟盟主、リーガン公爵一家が事故死したとの一報を受けた日、屋敷内はこれまでないほど慌ただしかった。
私の家は、かのリーガン公爵家の分家にあたるのだ。つまり、盟主の血が私にも僅かながら流れている。
加えて、どうやら私はリーガン家に伝わる紋章を受け継いでいるようだった。このフォドラにおいて紋章の有無は重要なもので、“紋章=当主の資格”というのが貴族社会の常識と言っても過言ではない。
そして事故によりリーガン本家の血筋が絶えてしまったため、現在本家に後継者となる人物はいない。そこまで来れば、自ずと話は一つにまとまる。
リーガンの血を引き、紋章を継いだ私が本家の養子となり、やがては次代盟主となるのだ、と。
噂どころの話ではない、自然な成り行きだった。
私の両親もリーガン家の家宰も、当時は本気でそのつもりでいたのだろう。“跡継ぎ”“盟主”という単語を聞かされる回数も格段に増え、教育は本来ならば本家嫡子にしか施されないような内容にがらりと変貌した。周辺貴族は笑顔の裏で私を見定めるようになり、その子息たちは頭の中に砂糖を詰め込まれたような甘い言葉を吐くようになった。
誰もが私を次期盟主だと思っていた。
私も少なからず、そのつもりでいた――どこからともなく煙のように現れたあの男、クロード=フォン=リーガンが現れるまでは。
「お前は将来、クロード様を補佐する立場になるのだ」
「同盟の未来のために、クロード様の助けとなりなさい」
「リーガンの血筋を絶やさないために」
「紋章を次代へ引き継ぐために」
「盟主の伴侶として、その子を宿しなさい」
私が座るはずだった次期盟主の座には、今はクロードが座っている。
私の人生はあっという間に私の手から離れ、今はクロードを中心に回っている。
――そんなの、真面目に生きる方が馬鹿らしいじゃない。
そういう経緯で、私はささやかな嫉妬と大いなる無気力を携えた歪んだ人間性を獲得してしまったのだ。
そして苦節十八年間の折、ついに私は実家から逃げるようにガルグ=マク大修道院の士官学校に入学したのである。
「そういえば、クロードくんとナマエちゃんって幼馴染なのよね?」
課題任務に向けたミーティングが終わり、先生が解散を告げてまもなくヒルダの口から話題が飛び出した。
嫌な予感がすっと胸を撫でたが、こうはっきりと名指しされては立ち止まらずにはいられない。それに勘違いは速やかに訂正すべきだ。
私は教室を出る前にヒルダの元へ行き、苦笑と共に告げる。
「まさか。クロードはリーガン家の嫡子なんですから、たかが分家の小娘が親しげにできるはずないでしょう。それにそこまで長い付き合いというわけではないので」
クロードがリーガン家の嫡子として公表されたのが一年前。彼自身はそれ以前から密かにリーガン家に出入りしていたようだが、私がはっきりと関わり合いを持つようになったのはせいぜいさらに一年前だ。長くて二年の付き合いでは幼馴染と呼ぶには不足だろう。
「そうなの? でも兄さんは実は内々で結婚の話まで出てるとか何とか……」
「そういう噂が流れているみたいですが、少なくともリーガン家との間でそんな話はありません。ただの本家と分家の関係ですし、家のことを抜きにしても私があの男と婚姻なんてあり得ませんから」
「断じて?」
「断じて」
「……そこまで否定されると妙に傷つくんだが…………」
私とヒルダの会話に割り込んできたのは、まさに今話題に出た通りの男だ。ため息まじりに眉尻を下げるクロードにほぼ反射のような形で私の肩がピクリと揺れる。
「クロード、貴方からも何か言ってください。事実でしょうに」
「貴族同士の噂なんて否定したところでキリがありゃしないだろ。言う奴には言わせておけばいいさ。どうせ数年後には嫌でも分かるんだから」
「……
「ナマエちゃん、口調口調」
ぎゅっと握りしめた拳が震え出したところでヒルダが小声で私を諌める。当のクロードはどこ吹く風と頭の後ろでて手を組んでいたので、これでは私だけが怒りっぱなしの大損だった。
ふう、と息を吐いて心を落ち着けると、私はまたいつもと同じく貴族然とした表情で腕を組む。
「……とにかく、軽はずみな言動はよしてくださいね、クロード。貴方に頼り甲斐がなきゃ、私の家も同盟全体も揺らぐんですから」
先生のところに行くと告げて、私は足早に教室を去る。クロードはまだ何か言いたそうにしていたが、あえて知らないふりをした。
そもそもクロードが取りまとめる学級で学ぶこと自体、私にとっては屈辱的でならないのだ。反対する両親を強引に説得しやっとの思いで士官学校に入学したと思ったら、蓋を開ければ毎日彼と顔を合わせなければならない地獄が待っていた。その時の心情はきっと誰にも理解できないだろう。もしも先生が
私は分家、あんたは本家。
分家は、本家の養分みたいなものなので。
本当は家も同盟も全てどうでもいいのだけれど、わたしができることと言えば、せいぜいその養分に毒を仕込むことだけだった。