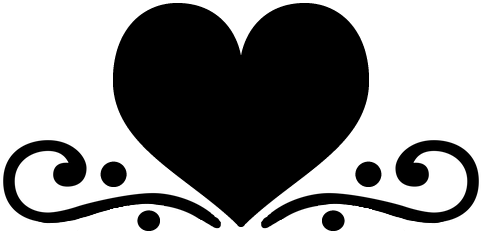
純真パパラチア
「はい、やり直し」この台詞を聞くのは一体何度目かしら。
声の主は無慈悲にも、つい今しがた出来上がったばかりの代物を目の前から退ける。
あたしのじとりとした視線に気付いた彼は、ふん、と鼻を鳴らして出来損ないを指差した。
「生クリーム立てすぎ、あんなボソボソだと舌触りが悪くなる」
「伊之助の意地悪!だったら塗る前に教えなさいよ、折角スポンジは上手く焼けたのに!!」
「あ?何言ってんだ、スポンジもきめが粗かっただろうが」
「うぅ…っそれにしてもちょっと厳しすぎでしょ!明日に間に合わないじゃない!」
そう、あたしがどうしてこんな屈辱を受けながらも厨房に立っているのかというと、全ては明日のため。
去年までは特にこれといった贈り物のなかった、執事である善逸の誕生日。きっかけは、毎夜就寝前に交わすたわいもない雑談で。
寂しいんだか贅沢なんだか、「手作りケーキを食べた事がない」とかいう話を耳にしてから、密かに思い立ってしまったのだ。
とはいえ料理はおろかキッチンに立った記憶さえないあたしは、重々自分の能力を弁えていた。
自分の力でどうにかできる気がしない、と潔く伊之助料理長の手を借りる事にしたのだけれど、手厳しい上にいちいち物言いが癇に障る。
まぁ料理の腕は本当に間違いないから、その分説得力はあるんだけど。
「妥協したくないとか言ってたのはどこのどいつだよ…それとも、一回決めた事を取り下げんのか?名前お嬢様ともあろうお方が?」
「っそんなわけないでしょ、やってやるわよ完璧にね!」
「おっしゃその意気だ、んじゃ最初っからな」
不名誉にも失敗作となったスポンジ達は、伊之助の手で次々とラスクに生まれ変わっていった。日持ちもするし、ティータイムや来客用のお茶請けで消費される事だろう。
これが一般家庭だったら…なんて考えると、今日ばかりはお屋敷育ちで助かったと思える。
そうして夕食の時間を跨いでまで格闘し、ようやく伊之助のお墨付きを貰ったのだった。
「はぁあ…つ、つかれた…!」
「出来栄えは及第点ってとこだけどな」
「分かってるわよ、でももうこれがあたしの限界!」
「まぁあいつなら、お前の手作りってだけで喜ぶだろ」
「だといいけど…ありがとう伊之助、付き合ってくれて」
なんだかんだ言いながら、ちゃんと形になるまで見放さないでいてくれたのだ。伊之助はやっぱりここぞという時頼りになる。生意気だけど。
お花については、午前中に炭治郎に相談しておいて良かった。まさかこんなに時間を取られるとは思っていなかったし。
ちなみに一瞬、宇髄さんにも相談しようかと思ったけど踏みとどまった。どうせ「自分にリボン巻いてド派手にプレゼントしろ!」とか本気で言いかねないからだ。
一応辺りを見回して、そろりと厨房を後にする。やけに勘のいい善逸の事だ、ちょっとでもおかしな動きをすればすぐに問い詰められてしまう。
普段スケジュールを握られている分、こっちだって執事の行動パターンはばっちり把握済みよ。今頃はちょうどメイド達への伝達の時間だから、確実に出歩いていないはず。
首尾は上々、と廊下を軽々スキップしていたあたしの足取りは、自室の数メートル前でぴたりと止まる。
なぜなら扉の前には、無表情の金髪が腕を組んで待ち伏せていたからだった。
「ぇ、ぜ…っ、ぜんいつ、」
「随分と楽しそうでいらっしゃいますね、名前お嬢様…何か良い事でも?」
あたしにそう問い掛ける善逸は完全に目が据わっていて、口元だけがすっと弧を描いている。
まずい、何か怒ってる。受け答えしようにも、引き攣る表情筋のせいで上手く平静が保てない。
「い、いいえ何もないわよ、」
「こんな時間まで何をなさってたんですか?」
「別に?最近体動かしてなかったし、ちょっと散歩してただけよ…あ〜疲れたし何だか眠くなってきちゃった、今日は早くベッドに…っ、!」
適当な言葉を並べ立てながらドアノブに手を掛けたところを、突然腕を掴まれて阻止された。
またいつものように眉を下げて笑ってくれるかと思っていたのに、どうも今日は様子が変だ。
「ちょ、ちょっと善逸何してるの、」
「それはこちらの台詞です」
「え…」
「厨房で、料理長と二人きりで、何をなさっていたのかと聞いてるんです」
その言葉に、思わず目を逸らしてしまった。こんなのやましい事があると自供しているようなものだ。
まさかそこまでバレてるなんて。折角あんなに頑張ったんだし、サプライズ失敗はどうにか避けたい。
しらを切ろうと意を決して彼に視線を戻した途端、口から出かけた言葉が引っ込んだ。
善逸のこんな顔、初めて見たかもしれない。
何かを堪えるようにぐっと眉を寄せて、怒ったような苦しいような、だけどどこか切なげに瞳を揺らしていて。
そんな彼の様子に困惑しながらも、何とか返事を絞り出した。
「…言えない、」
あたしの言葉を聞いた善逸は、それまで真っ直ぐにこちらを見据えていた目を伏せた。
掴んでいたあたしの腕を脱力するように離すと、淡々とした口調で話し出した。
「そうですか、ではこれ以上詮索は致しません…本日はこちらで失礼いたします」
おやすみなさいませ、と踵を返して去っていくその背中は、やっぱりいつもより寂しげで。
「あ…明日!」
咄嗟に声を上げて引き留めていた。
少しの間の後くるりと振り返った善逸に、ほっと胸を撫で下ろす。
「今は言えない、けど…明日きちんと話すから、ティータイムご一緒しましょ?」
唐突に告げた強引な誘いに、善逸は驚いた様子で少し考えるような仕草を見せる。
そしてようやく、いつもの穏やかな表情で微笑んだ。
「かしこまりました」
----------
「善逸、お誕生日おめでとう!」
翌日のティータイムに約束通り善逸を招いた。
紅茶を入れ終えたところで満を辞してバースデーケーキがお目見えすると、善逸はぽかんと口を開けたまま固まってしまった。
しばらくパチパチと瞬きしたかと思えば、何かを思案するように虚空を見つめ始める。
「な、なんとか言いなさいよ」
「は…っ!すみません、あの、お嬢様これは、」
「誕生日のお祝いと、いつもあたしのわがままに付き合ってもらってるお礼よ」
「…もしかして、お嬢様の手作りで…?」
「伊之助みたいに上手じゃなくて悪かったわね、」
こんな可愛げのない事言うつもりなんてなかったのに、照れ臭くてついついそっぽを向いてしまう。
だけど、ちらりと盗み見た善逸は穏やかに微笑んでいて。
眉を下げて泣きそうな顔でケーキを見つめるその表情に、何故だか胸の奥がきゅっとなった。
「ありがとうございます…早速、いただいてもよろしいでしょうか」
「えぇ勿論、そのために作ったんだから」
いただきます、と口に運ばれていくのを、固唾を呑んで見つめる。
自分の作ったものを他人に食される瞬間が、こんなに緊張するものだなんて初めて知った。
「お世辞はいらないから、正直な感想をお願いね」
「とっても美味しいです…!」
「本当?無理してない?」
「本当ですって!あぁ、よろしければお嬢様も是非」
そう言って、善逸は一つ分を取り分けた。
きめの細かく揃ったスポンジにクリームが滑らかに纏っていて、自分で作っておいて何だけどかなりいい線いってると思う。
一口味わえば、程よい甘さと卵の風味が口の中に広がった。
「確かに、悪くないかも」
「でしょう?生地がしっとりしていて、甘さのバランスも丁度良いです」
「…ふふ、思えばこうして一緒にお茶した事なんて、今までなかったわね」
「主人のサポートが執事の業務ですし、どうしても生活リズムは異なってきますから」
あたしが食事をする間は食べ進めるペースや飲み物の空き具合をチェックしつつ、メイドに指示を出しながら滞りなく事が運ぶように常に気を配る。
勿論それが彼の仕事なのは承知しているけど、そもそも主人と使用人が一緒に食事したって別にいいじゃない、とも思う。飲み物くらい自分で注ぐし、なんなら厨房まで上げ膳するわよ。
ずっと一族が倣ってきた昔からのしきたりってやつで、あたしがどうこう言えるものでもないんだろうけど、こういう融通の利かないところにたまに息苦しさを感じたりもしていて。
「毎日誰かの誕生日だったらいいのに…そしたらみんなでお茶できる口実になるじゃない?」
「それだとお嬢様が大変ですよ、毎日ケーキを焼かなくては」
「え?どうしてあたしが?」
「へ、」
いまいち会話が噛み合ってない感じがして思わず首を傾げると、善逸はなぜか目を丸くして固まっていた。あたしはあたしで彼の言葉に全くピンと来ていなくて、そのまましばらく膠着状態が続いた。
そして顔を赤らめた善逸が口元を押さえて目を逸らしたのを合図に、あたしはようやく自分の無自覚さに気が付いた。
使用人の誕生日。日頃お世話になってるからとか、主人として当然の事だとか、退屈な日常に少しでも華を…とか、建前なんていくらでもあったけれど。
例えば、これが伊之助だったら?炭治郎だったら?一人でまともに焼けもしないケーキなんて作ろうと思っただろうか。
喜んでくれる顔がどうしても見たい、なんて思っただろうか。
「善逸だからに決まってるじゃない」
「おじょー…さま、」
「もうっそのくらい分かるでしょばか!第一、使用人の誕生日なんて把握しきれないわよ!何人働いてると思ってるの!」
「そ、それはそうですがっ、」
「それと…昨日の夜の事だけど、どうしてあんなに怒ってたの」
その場の勢いで、気になっていた事を尋ねた。
善逸は一瞬口をつぐんでから、言い辛そうに話し出す。
「あ、あれは…お嬢様があまりに厨房に入り浸っていたので、その、少々深読みしてしまったといいますか…」
「深読み?何を?」
「…伊之助と、逢瀬をしているのかと…」
申し訳ありませんでした、と謝る善逸に、今度はあたしがぽかんと口を開けて固まった。
一瞬意味が分からず何度か善逸の言葉を頭の中で繰り返す内に、昨晩の彼の何とも言えない表情が脳裏をよぎってやっと理解した。
言葉を発する前につかつかと歩いて、パーテーションの裏に隠しておいた花束をそっと手に取る。
バツの悪そうに佇む善逸の前へそれを差し出せば、琥珀色の瞳がこちらを向いた。
「はい、これもプレゼント」
「え、」
「もし仮にあたしに逢瀬をするくらいの相手がいたとしたら、他の男性にこんな贈り物すると思う?」
「で、ですが…いいのですか?こんな立派な花束、」
「まぁ、炭治郎に手配してもらったんだけどね」
ケーキ作りに必死でこっちまで手が回らなかった訳だけど、お花の良し悪しはやっぱりプロに任せて正解ね。
白と黄色とオレンジの、善逸のイメージにぴったりな色合い。それもちゃんと誕生花で揃えるという抜け目のなさ。思い描いていた以上に素敵な花束だった。
はあぁ、と息を吐いた善逸は、感無量といった様子で胸に手を当てた。
「こんなに嬉しい誕生日は生まれて初めてです、幸せすぎて明日死んでしまうんじゃないかと」
「なにそれ大袈裟ね」
「いいえ、本当に心の底から嬉しいです…ありがとうございます、名前お嬢様」
「…どういたしまして」
にっこりと浮かべた笑みに、自然とこちらも頬が緩む。誰かに贈り物をするってなかなかいいものね、とこれから味を占めそうな予感もして。
するとしばらく花束を見つめていた善逸が、ふと何かに気付いたような表情に変わる。
「これは…マーガレットですか」
「あら、知ってるの?さすが博識ね」
「いえ、誕生花ですので知っていただけで…ところでお嬢様、マーガレットの花言葉はご存知なのですか?」
その問い掛けに待ってましたと胸を張る。
プレゼントするからには、そこはさすがに抜かりなくチェック済みよ。まぁ例によって炭治郎に聞いたんだけど。
「“信頼”でしょう?炭治郎に教えてもらったわよ、まさに主人と執事の関係性にぴったりだと思わない?」
「え…炭治郎が言っていたのは、それだけですか」
「そうだけど…他に何かあるの?」
「いっいえ!あの、お気になさらず!」
妙に言葉を濁す善逸に、これは確実に何かあると踏んだ。
他人の変化には鋭いくせして、自分の事になると色々だだ漏れなんだから。
「なによ、気になるじゃない」
「いえ本当に、大した事では…!!」
「ふーん、じゃあ炭治郎に聞いてこようかしら」
「おおおおお待ちくださいお嬢様っ!!」
踵を返したあたしの前に凄まじい勢いで回り込んだ善逸は、肩で息をしながら立ちはだかる。
一度大きく息を吐き出すと、やがて諦めたように口を開いた。
「“恋占い”…それと、“真実の愛”」
「え?」
「マーガレットの別の花言葉です、花も人と同じようにいくつか違った顔を持つものなんですよ」
顔に熱が集まるのがはっきり分かる。まさかそんな意味が他にあったなんて。
炭治郎が知らないはずないのだから、おそらく、いえ確実に、知っててわざと言わなかったんだ。人畜無害な顔して、あの庭師のしたたかさときたら…!
炭治郎への恨めしさをひっそり募らせていると、善逸は真っ直ぐこちらを見据えて、すっと目を細める。
「全て、名前お嬢様のお気持ちと受け取ってもよろしいのでしょうか」
「へ、あ、えっと、それは…」
予期せぬ事態にしどろもどろになりながら何とか言葉を返そうとしていると、善逸は小さく控えめな笑い声を漏らす。
「申し訳ございませんお嬢様、冗談が過ぎました」
「…っ何よもう、」
「ですが、どれもわたくしには勿体ないお言葉だという事に変わりはありません…たとえお嬢様にとって不本意でも、身に余る光栄です」
そう言って善逸は深々と畏まってみせた。
すると焦りが落ち着いた代わりに、今度は胸がもやもやし始める。
確かに知らずに贈ったのはもっともだけど、誰がいつ不本意だって言ったのよ。ちょっとは勘違いするくらいの度量見せなさいよ、この意気地なし!
「…決めた」
「え、何を…」
「来年も再来年もその先もずーっと贈ってあげるから、マーガレットの花束」
覚悟しときなさいよね、と捨て台詞を残して部屋を出た。
閉まりかけた扉から一瞬見えた善逸は、面食らった様子で顔を真っ赤に染め上げていて、少し気持ちがスカッとした。
高らかに宣言したその言葉が回りくどいプロポーズみたいだったと気付いて、今度はこちらが真っ赤になるのはもう少し先の話。