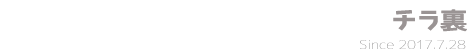二つの心臓(前編)
雄英卒業から数年後のお話。
相澤先生+オールマイト×夢主でぺろぺろラブラブします。
前編は性描写なしで、ほぼ相澤先生とオールマイトのやり取りです。
後編に性描写が入りますのでご注意ください。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
「カンパーイッッ!!!」
飯田の音頭でそれぞれがグラスを掲げてはぶつけあい、勢いよく喉に流し込んでいく。
同席しているほどんどの者からグラスの集中砲火を浴びた相澤も、普段あまり口にしないビールをグビリと喉を鳴らして一口飲み込んだ。
大人数収容可能な居酒屋の個室にずらりと揃った顔ぶれは、世間でもだいぶお馴染みとなった"あの"元A組の生徒たちだ。卒業してから数年経ち、サイドキックとして着実に力を蓄えている者、すでにヒーローとして台頭めざましい者、さすがは"あの"元A組だと言われるほどの活躍を見せてる者たちばかりだが、こうして集まり、所謂『同窓会』として相澤の前に揃うなり彼らは"ヒーロー"の顔から"生徒"の顔に戻ってわいわいと賑やかしく盛り上がっている。
「相澤先生ぇー、れぇちゃんはー?」
「いつ頃来るって?」
数人から質問が投げかけられて相澤は室内を順繰りと見渡した。
なるほど、遅れてくることになっているのか、と。
この場に西岐がいないことは足を踏み入れた時点で分かっていたが、不参加なのか遅刻なのか相澤が知る由もなかった。ここ数年、ヒーローとして応援要請があってたまたま居合わせるということがない限り、個人的に連絡を取り合ったり、ましてや会ったりということなどなかったからだ。この同窓会に来るというのなら相澤もプライベートで会うのは数年ぶりになる。
「……さあな」
適当に濁して答えると生徒たちはふうんと納得はしていない顔で納得してみせる。
西岐ことサイキッカーといえば諜報活動を主とするアングラ系ヒーロー、活動の殆どが隠密で口外出来ないことも多い。そういう意味で相澤が言えないとでも思ったのだろうか。
実際のところはそうじゃない、ただ単に知らないだけ……なのだが。
卒業して間もなく、誰よりも真っ先にプロのヒーローとして活動を始めたのは西岐だった。マスコミが騒ぐような派手なデビューではなくクラスメイトと雄英教師・一部のヒーローが知るのみというひっそりとしたデビューだったが、相澤としては非常に誇らしく彼の活躍を願っていた。
しかし、隠密な活動ということもあって連絡が取れない日々が続き、気付けば数か月……一年……と経ち、不思議なことに時間の経過と共に気持ちにも距離が開いてしまっていた。
応援要請が重なって行動を共にする機会で、それを思い知った。目が合いそうになるとスッと逃げるのだ。必要以上の言葉を交わすこともなく、以前のように笑いながら駆け寄ってくることもない。
ただ、そういう変化が自分に対してだけではなかったから、相澤はあまり深くは考えなかったし追及もしなかった。出来るだけ人と接触しないようにしているのは彼のヒーローとしてのスタイルか何かなのだろうと、そう安易に思い込んでいた。
その思い込みが砕けたのは、再び別の応援要請で活動が重なった時、西岐がオールマイトと密に話し込んでいるのを見た時だった。心底安心しきった笑顔を浮かべてオールマイトに肩を抱かれていた。あんな笑顔は随分久しぶりに見た。
ああ、そうか、と。重力に従って物が落ちるように、ストンと何かが胸に落ちた。
その時から相澤からも連絡を取ることはしなくなって、今に至る。
もう、今、西岐がどうしているのか、どんな活動をしているのかなんて、その辺のプロヒーローと同じ程度しか把握していない。
相澤のグラスが空になり次のグラスが置かれた頃、慌ただしく出入りする店員の横から恐らくクラス中が待ち望んでいた顔が現れて、数秒、室内が静まり返った。
オレンジ色の長い前髪と、へにゃっと気が抜けそうな笑みを浮かべる口元。相変わらずセンスより着心地優先なゆったりした服を纏っている。
その隣には骸骨を彷彿とさせる不健康そうなやせ型の男、我らが平和の象徴オールマイトが連れ立って足を踏み入れており、静寂を食い破る勢いで生徒たちが一斉に声を上げた。
「れぇちゃんっっっ!!!」
「オールマイトッッッ!!!」
「ひっさしぶりー!!!」
「なんだよもう全然変わんねえなあ!!!」
「仕事帰り!!?」
この煩さは苦情が来ても可笑しくないレベルだ。
「お仕事帰りだよぉ」
早速クラスメイトにもみくちゃにされては、どこに芯があるんだか分からない声でふにゃふにゃ答えては表情を綻ばせている。
それを見て、口に入れ損なった枝豆がポロッとテーブルに転がる。
相澤の頭の中にある数年分の記憶がごっそり抜き取られたかのような、昔のままの表情でクラスメイトと笑いあっている。自分が思い違いをしていたのではないのか、勝手に記憶を捏造したのではと思うほど、目の前の西岐の笑顔は自然で、しかも、それが真っ直ぐ相澤にも向けられていた。
「イレイザーさん……!」
この上なく嬉しそうに、なんなら頬を紅潮させているようにさえ見える顔で相澤の元に近寄り、隣へと腰を下ろした。
「お久しぶりです」
「……っ、……ああ」
数年ぶりに向けられる笑顔は直視するには眩しすぎる。その上、相澤は動揺の真っ只中にいて、感情をどう処理すればいいのか分からず、ビールに口をつけて濁す。
「れぇくん、何飲む?」
相澤とは反対の西岐の隣を陣取ったオールマイトがメニューを広げて意識を攫っていく。
「ん、と…………あまいの」
「イチゴミルクのカクテルがあるよ」
「ん、ん、それにする」
ピッタリと肩を寄せて一つのメニューを覗き込んでいる様子に、相澤の目がだんだんと据わる。
「……子供舌だな」
思わず皮肉気な呟きがぼそっと口をついた。
賑やかな室内に紛れそうな低く小さな声だったが西岐の優秀な耳が上手く機能したのか、正確に拾い上げたらしく、ムッとした顔をこちらに向ける。
「だってぇ……お酒飲まないもん」
「へえ、じゃあ飲み慣れたらいいんじゃないか、ほら」
こちらに意識が戻ったことに気を良しくして飲みかけのビールのグラスを差し出すと、西岐はおずおずと受け取ってほんのちょっと舐めて、ぎゅっと顔をしかめた。
「うっ……にがあ……」
グラスを突き返し、口直しになるものを探してテーブルを見渡すが、生憎ビールの苦みを拭えそうなものが周囲にはなく、口元を押さえて堪えている。その仕草が可笑しいやら可愛いやらで、相澤はふっと笑みを零した。
記憶に挟まっている数年は脳裏から消えないが、今改めてこうして西岐と接して、変わらず惹かれていることを自覚してしまう。切ないような幸福なような気持ちがじんわりと胸に広がるのだ。
ビールの苦みなど舐めて拭ってやりたいと劣情が浮かぶ程度には、何一つ薄れていない。
「はい、お口直し」
いつの間に注文を済ませたのか、店員が運んできたグラスの一つをオールマイトが西岐の前に置いた。
リキュールの濃いピンクと牛乳の白が二層に分かれた如何にも女子受けしそうなカクテルだ。西岐がそのまま口を付けようとしてオールマイトに止められ、マドラーでぐるぐると掻き混ぜて、全体が『イチゴミルク』の名に相応しい色合いになってから西岐はこくんと一口飲み込んだ。
すると、一転して笑みが戻り、聞いているこちらの力が抜けそうな声を零す。
「んっ、あまぁああ…………え……ジュース?」
「お酒だよ。ごくごく飲まないように」
オールマイトの忠告に数回頷いて西岐はもう一口と含んでからグラスを置いた。
それを待っていたかのように、賑やかしメンバーがどやどやとやってきて西岐を引っ張っていく。来て早々、教師に挟まれて座っているのを不満に思っていたのだろう。グラスもセットで西岐を持って行かれて相澤はポリッと頬を掻いた。
「さすがA組、パワフルさが違うな」
さも可笑しそうに喉を震わせて笑うオールマイトに相澤も異論はなく、同意の溜息をついた。
「また一クラス全員除籍にしたんだって?」
グラスを傾けながら問いかけてくる。カラリと氷が音を立てるそれは恐らくウーロン茶か何かなのだろう。
「見込みゼロだったんで」
「ちょうど特異点の子供たちだろ? 恐ろしいな、君は」
何のことはないと切り返して枝豆を口に放り込むと、オールマイトの手が遠慮なく伸びてきて一莢持っていく。
「……オールマイトさんは?」
「うん?」
「老後、なにやってたんですか」
わざと嫌味たらしく聞き返す相澤に笑みを深くした。
「れぇくんのサイドキックをやってたかな」
毒っ気のない微笑みを浮かべながらとんでもない反撃を見せたオールマイトに、相澤はみっともなく動揺して持ち上げかけたグラスをテーブルに滑り落としてしまう。幸い垂直に落ちたおかげで零すことはなかったが、誤魔化しようのない失態を恥じて額に手を宛がう。深々と息を吐き自分を落ち着かせる。
「こんな老兵、役に立たないだろうと言ったんだけどね、力になってほしいと頼まれれば吝かではないし……基本的には事務方で尽力させてもらってるよ」
老後と言ったことへの意趣返しなのか、あえて老兵という言葉を使って追い打ちをかけてくる『元・平和の象徴』に相澤は額を押さえたまま細めた目を向けた。
「いい性格してますよね、案外」
「相澤くんが一番手強いライバルだからね。牽制するために沢山シミュレーションしてきたのさ」
屈託ない笑みと似つかわしくない台詞が相澤の眉間の皺を深くさせる。
「牽制? 不要でしょう」
相澤の気持ちを萎えさせるというのなら西岐がオールマイトに向けるあの表情で十分だ。心を預けきっているかのような、他の者に向けるものと一線を画す微笑みが相澤に与えるダメージは、今のやり取りの比ではない。
「残念ながら、私とれぇくんの関係は相澤くんが思っているようなものじゃあないよ」
内心が顔に出すぎていたのだろうか。
オールマイトの目に気遣うような気配が漂った。
「いいですよ、そういうの。かえってヘコむ」
「いや、違うんだ」
被せ気味に言葉を発しながら蝋燭の灯を消すように静かに笑みを引っ込めて、トンと己の胸を指でついた。
「彼の抱えているものをココで識ったというだけの話なんだ」
オールマイトの指差す胸元と、クラスメイトに囲まれている西岐の後頭部を視線が往復する。
"ココ"というのは西岐が雄英一年生だった時からオールマイトと繋がっている心のバイパスのようなものの話だろう。考えていることがお互いに伝わり共鳴してしまう現象は今でも続いているらしい。
「……抱えているもの?」
怪訝に眉をしかめるとオールマイトの眉もまた意味ありげに歪む。
「さすがだ」
「……なにがです?」
「嫉妬やプライドよりまず彼の心を気遣う」
「そんな小奇麗なもんでもないです」
誉め言葉がザラッと心を撫でる。別に嫉妬やプライドの類がなかったわけじゃない。無視できないほどグルグル肚の底を渦巻いている。だがそれより西岐が抱えているものがあるという事実が無視できなかった、ただそれだけの話だ。
「で、抱えてるものってなんです?」
重ねてもう一度問いかけた相澤の声は後半が掻き消され、オールマイトがはっとして振り返った。
ガチャンッといういくつかの食器が鳴る音、硬いものと柔らかいものがぶつかる鈍い音、その後で生徒たちの心配そうな声が波のように相澤の元に押し寄せて、オールマイトと共に素早く腰を上げていた。
「先生っ、れぇちゃんが……っ」
テーブルに突っ伏した西岐を看ている数人を押しのけて、相澤はなるべく揺らさないように西岐の顔を覗き込む。真っ赤な顔でぐったりと目を閉じ、苦し気な呼吸が口から吐き出されている。能力を使いすぎて熱暴走した時のような状態だが、さっきまで何ともなかったのが急にこうなるとは考えにくい。
「酒は? どれくらい飲んだ?」
「最初に頼んだやつがまだそこにあるよ」
生徒たちではなくオールマイトがグラスを指さして答える。
たしかにピンク色の液体がなみなみと注がれたグラスが目の前に置かれている。これがお代わりじゃないならアルコールが原因でもないだろう。
「……体調不良、か?」
西岐の性格なら多少無理をしても同窓会に顔を出すかもしれない。
「仕事上がりで来たからね、疲れで酔いが回ったんだろう。大丈夫、私が家に送り届ける、安心して宴を続けてくれよ」
オールマイトが生徒たちを安心させるように持ち前の大らかな声音を振りまき、横から西岐を抱き上げようと手を伸ばしていくる。
瞬間的にムッとした。
生徒たちにも丸分かりであろう程あからさまに嫉妬がブワッと広がった。
オールマイトの手が西岐に触れるよりも先に抱えあげて、彼から西岐を遠ざける。
「じゃあタクシーを頼みます」
しれっと言い放つとオールマイトは拍子抜けしたように数回瞬きした後で、困ったように口角を緩める。
「……参ったね。君ってメンタル最強なんじゃないのかい」
ポリと頬を掻いてから背を翻し、個室を出ていく。
メンタルが最強なのならグラスを落とすような失態は晒さないだろうし、そもそも連絡をしなくなるほどダメージも受けないのではないか。今こうして西岐を抱き上げたのだって不格好な嫉妬心からで……相澤のメンタルも人並みだ。ただ、それが心に黒い影を落とすのかといえばそうではない。欝々と沈み込み立ち上がれなくなるというのがメンタルの弱さなのだとすれば確かにそういうものとは無縁だろう。
相澤は無理やり引っ張り出した教師の顔を生徒たちに向けて、大丈夫だということと、家に送り届けたら連絡を寄こすということを再三告げてから居酒屋を後にした。
繁華街の中の通りは客待ちのタクシーがビッチリと駐車していて、別にオールマイトがわざわざ捕まえに行かなくてもすぐに乗れる状態だった。
上背のある男二人とプラス西岐が少々窮屈に並んで、オールマイトが告げた住所に運ばれていく。
雄英から徒歩圏内にあるお馴染みのマンション。西岐宅。
どうやって入るつもりなのかと伺っていれば、当然のようにポケットからカードキーを取り出して慣れた動作でエントランスを通り抜け、エレベーターに乗り込み、玄関扉を開けた。
ここに訪れるのは何年ぶりだろうか。
少しも変わらない家具の配置の中にポツポツとオールマイトの私物らしきものが置かれているのが目に入った。
ひとまず西岐を寝室のベッドに運び入れて寝かせ、目蓋が動かないのを見下ろしてからオールマイトと連れ立ってリビングに移動する。小さなラグに小さなクッションがぽつんぽつんと置かれていて、そのまま座るとやけに距離が近くなるので、相澤はフローリングのところまでクッションを引っ張っていって腰を下ろした。
「……で」
オールマイトが座り切る前に疑問符を投げる。
すると、少々腰を浮かせた状態で相澤の顔を見つめ、苦笑を浮かべた。トスンとクッションに尻を落ち着かせてから、さて、と勿体ぶって口火を切る。
「どこから話そうかな」
「――恋人関係じゃないんだな」
もったりとした話口調は相変わらずだ。焦れったさに耐え切れず質問というより確認事項を放り投げた。
オールマイトの眉尻が垂れ下がり視線が斜め下の床に落ちる。
「ああ、未だに私の片思いだ」
なんだ、ひとつは確実に思い違いだったのか、と相澤は自嘲の笑みに口角を吊り上げた。
ならばと次々浮かんでくる疑問が抑えきれず口から零れていく。
「じゃあ……どういう関係なんです? 妙に親密ですよね。抱え込んでいるものとは? どうして抱え込ませている? あなたは何をしているんですか?」
「待った、相澤くん、ひとつずつ……」
「抱え込んでいるものってのは今のあの不調みたいなもんですか?」
矢継ぎ早に浴びせた言葉を拾い切れずにハンズアップしてみせるオールマイトへ、相澤は剥き出しの核心を突きつける。それが間違いなく核心だということは直後の彼の表情で一目瞭然だ。
あの不調、熱や体調不良でもなく、アルコールによるものでもない。
マンションに辿り着くまでの道中、腕の中で息を荒げていた西岐を見下ろして相澤はほぼ確信していた。
「催淫の類でしょう?」
時折うっすらと開いた目蓋の下はうるうると水分をやたら含んでいて、抱える相澤の腕がタクシーの振動で揺れるたびに小さく身じろぎしていた、あの反応は酷く性的だった。
「……凄いな。その通りだ」
オールマイトの細長い手が口元を拭う仕草をする。それが酷く疲れを漂わせる。
「なんというか……こう、感覚が鋭敏になる時期というのがあってね……適した言葉かは分からないが発情期のようになるんだ」
長々とした説明はもう要らなかった。発情期、その単語ひとつですべてに納得していた。
相澤と目を合わせなかったのも人と接触しないようにしていたのも、そうした状態にある自分を悟られたくなかったから、そして不意に触れて鋭敏になった感覚を刺激したくなかったからなのだろう。日々の中で長く一緒に過ごしていれば、変調の波というものを目の当たりにして気付けたかもしれないが、相澤が西岐と会ったのは活動を共にしたほんの少しのタイミングでしかなく、運が悪いことにその都度、発情期とやらの周期と重なってしまっていたのだろう。
気を張り詰めて活動する中で、唯一真相を知っているのがオールマイトなのなら、あのホッとした表情も頷ける。
ただし、秘密を共有できる関係だということへの嫉妬は僅かも薄れやしないし、今度はまた別の疑惑が浮上してくる。
「……で、その性欲処理をあなたがしていた、と?」
新たな疑惑、体の関係。
オールマイトが西岐を好いていることは誰の目にも明らかだし、彼も男だ。愛しい人が目の前で欲情にまみれていれば手を出さぬわけがない。
ダメージを覚悟して問いかける相澤に、オールマイトは緩く首を横に振った。
「いいや、私は触れていない」
暫く返答の意味が分からなかった。
「れぇくんがね、昂った身体をどうしていると思う? ぎゅうって身体を縮こませてひたすら耐えるんだよ。そんな子に私は触れられなかった」
やはり意味が飲み込めない。
言っている言葉自体は分かるが頭が理解を拒んでいると言った方が正しいか。
「あんたは仙人かなんか目指してんのか?」
求めてやまない愛しい人という据え膳を食わないなんてどうかしている。ましてや情欲によって苦しんでいるのだ、どうして楽にしてやろうと都合よく思考を変換できなかったのか。
「ここのところどんどん酷くなってきていてね……周期も狭くなっている。発散してないからかもしれない。同窓会という機会に君に打ち明けようかと思ったんだ。私では…………力不足だ」
彼も悩んだ末なのかもしれない。
だが相澤には到底理解出来ない思考だ。
「なら俺が解放してやっていいってことですね」
オールマイトが手を出さないと決めているのなら、据え膳を寄こすというのなら遠慮なく頂く。
返事を聞く前に立ち上がりスタスタと静かに寝室へ足を向ける。
するや、背後から激しい衣擦れの音と共に床を踏み鳴らす音が聞こえて、無遠慮な力加減で肩を掴まれた。首の捻りだけで背後を伺えば、眼下の窪みから青い光が鋭く向けられている。
「……なんだ、明確に嫌なんじゃないですか」
よもや自分とは違う次元の生き物なのではと思いかけていたが、その突き刺さるような嫉妬の光を間近に見て相澤の表情が緩んだ。
潔く諦めてくれるのは願ってもないことだが、手も出せない相手に数年寄り添い続けるなんて自虐的ともいえる愛情を抱く彼から無感情で掻っ攫えるほど、自分勝手にもなれなかった。
いろんな要因が重なり、オールマイトという人となりがあって、相澤の心の中に彼を容認するスペースが生まれ始めている。自分自身でも戸惑うような考えが、もう決定事項のように心に居座っている。
「共有してもいいですよ、俺は。隙を作ってくれたお礼に」
今度はオールマイトが相澤の言葉を理解できないと怪訝にする番だ。
相澤は彼の理解を待たず手を払いのけて、寝室の扉を開く。
「まあ……最終的に決めるのは西岐ですが」
眠っているのか、鋭敏になった感覚に支配されて周囲に気を払う余裕がないのか、身体を丸めて布団に潜り込んでいるであろうそのシルエットに目を細めた。
続く
相澤先生+オールマイト×夢主でぺろぺろラブラブします。
前編は性描写なしで、ほぼ相澤先生とオールマイトのやり取りです。
後編に性描写が入りますのでご注意ください。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
「カンパーイッッ!!!」
飯田の音頭でそれぞれがグラスを掲げてはぶつけあい、勢いよく喉に流し込んでいく。
同席しているほどんどの者からグラスの集中砲火を浴びた相澤も、普段あまり口にしないビールをグビリと喉を鳴らして一口飲み込んだ。
大人数収容可能な居酒屋の個室にずらりと揃った顔ぶれは、世間でもだいぶお馴染みとなった"あの"元A組の生徒たちだ。卒業してから数年経ち、サイドキックとして着実に力を蓄えている者、すでにヒーローとして台頭めざましい者、さすがは"あの"元A組だと言われるほどの活躍を見せてる者たちばかりだが、こうして集まり、所謂『同窓会』として相澤の前に揃うなり彼らは"ヒーロー"の顔から"生徒"の顔に戻ってわいわいと賑やかしく盛り上がっている。
「相澤先生ぇー、れぇちゃんはー?」
「いつ頃来るって?」
数人から質問が投げかけられて相澤は室内を順繰りと見渡した。
なるほど、遅れてくることになっているのか、と。
この場に西岐がいないことは足を踏み入れた時点で分かっていたが、不参加なのか遅刻なのか相澤が知る由もなかった。ここ数年、ヒーローとして応援要請があってたまたま居合わせるということがない限り、個人的に連絡を取り合ったり、ましてや会ったりということなどなかったからだ。この同窓会に来るというのなら相澤もプライベートで会うのは数年ぶりになる。
「……さあな」
適当に濁して答えると生徒たちはふうんと納得はしていない顔で納得してみせる。
西岐ことサイキッカーといえば諜報活動を主とするアングラ系ヒーロー、活動の殆どが隠密で口外出来ないことも多い。そういう意味で相澤が言えないとでも思ったのだろうか。
実際のところはそうじゃない、ただ単に知らないだけ……なのだが。
卒業して間もなく、誰よりも真っ先にプロのヒーローとして活動を始めたのは西岐だった。マスコミが騒ぐような派手なデビューではなくクラスメイトと雄英教師・一部のヒーローが知るのみというひっそりとしたデビューだったが、相澤としては非常に誇らしく彼の活躍を願っていた。
しかし、隠密な活動ということもあって連絡が取れない日々が続き、気付けば数か月……一年……と経ち、不思議なことに時間の経過と共に気持ちにも距離が開いてしまっていた。
応援要請が重なって行動を共にする機会で、それを思い知った。目が合いそうになるとスッと逃げるのだ。必要以上の言葉を交わすこともなく、以前のように笑いながら駆け寄ってくることもない。
ただ、そういう変化が自分に対してだけではなかったから、相澤はあまり深くは考えなかったし追及もしなかった。出来るだけ人と接触しないようにしているのは彼のヒーローとしてのスタイルか何かなのだろうと、そう安易に思い込んでいた。
その思い込みが砕けたのは、再び別の応援要請で活動が重なった時、西岐がオールマイトと密に話し込んでいるのを見た時だった。心底安心しきった笑顔を浮かべてオールマイトに肩を抱かれていた。あんな笑顔は随分久しぶりに見た。
ああ、そうか、と。重力に従って物が落ちるように、ストンと何かが胸に落ちた。
その時から相澤からも連絡を取ることはしなくなって、今に至る。
もう、今、西岐がどうしているのか、どんな活動をしているのかなんて、その辺のプロヒーローと同じ程度しか把握していない。
相澤のグラスが空になり次のグラスが置かれた頃、慌ただしく出入りする店員の横から恐らくクラス中が待ち望んでいた顔が現れて、数秒、室内が静まり返った。
オレンジ色の長い前髪と、へにゃっと気が抜けそうな笑みを浮かべる口元。相変わらずセンスより着心地優先なゆったりした服を纏っている。
その隣には骸骨を彷彿とさせる不健康そうなやせ型の男、我らが平和の象徴オールマイトが連れ立って足を踏み入れており、静寂を食い破る勢いで生徒たちが一斉に声を上げた。
「れぇちゃんっっっ!!!」
「オールマイトッッッ!!!」
「ひっさしぶりー!!!」
「なんだよもう全然変わんねえなあ!!!」
「仕事帰り!!?」
この煩さは苦情が来ても可笑しくないレベルだ。
「お仕事帰りだよぉ」
早速クラスメイトにもみくちゃにされては、どこに芯があるんだか分からない声でふにゃふにゃ答えては表情を綻ばせている。
それを見て、口に入れ損なった枝豆がポロッとテーブルに転がる。
相澤の頭の中にある数年分の記憶がごっそり抜き取られたかのような、昔のままの表情でクラスメイトと笑いあっている。自分が思い違いをしていたのではないのか、勝手に記憶を捏造したのではと思うほど、目の前の西岐の笑顔は自然で、しかも、それが真っ直ぐ相澤にも向けられていた。
「イレイザーさん……!」
この上なく嬉しそうに、なんなら頬を紅潮させているようにさえ見える顔で相澤の元に近寄り、隣へと腰を下ろした。
「お久しぶりです」
「……っ、……ああ」
数年ぶりに向けられる笑顔は直視するには眩しすぎる。その上、相澤は動揺の真っ只中にいて、感情をどう処理すればいいのか分からず、ビールに口をつけて濁す。
「れぇくん、何飲む?」
相澤とは反対の西岐の隣を陣取ったオールマイトがメニューを広げて意識を攫っていく。
「ん、と…………あまいの」
「イチゴミルクのカクテルがあるよ」
「ん、ん、それにする」
ピッタリと肩を寄せて一つのメニューを覗き込んでいる様子に、相澤の目がだんだんと据わる。
「……子供舌だな」
思わず皮肉気な呟きがぼそっと口をついた。
賑やかな室内に紛れそうな低く小さな声だったが西岐の優秀な耳が上手く機能したのか、正確に拾い上げたらしく、ムッとした顔をこちらに向ける。
「だってぇ……お酒飲まないもん」
「へえ、じゃあ飲み慣れたらいいんじゃないか、ほら」
こちらに意識が戻ったことに気を良しくして飲みかけのビールのグラスを差し出すと、西岐はおずおずと受け取ってほんのちょっと舐めて、ぎゅっと顔をしかめた。
「うっ……にがあ……」
グラスを突き返し、口直しになるものを探してテーブルを見渡すが、生憎ビールの苦みを拭えそうなものが周囲にはなく、口元を押さえて堪えている。その仕草が可笑しいやら可愛いやらで、相澤はふっと笑みを零した。
記憶に挟まっている数年は脳裏から消えないが、今改めてこうして西岐と接して、変わらず惹かれていることを自覚してしまう。切ないような幸福なような気持ちがじんわりと胸に広がるのだ。
ビールの苦みなど舐めて拭ってやりたいと劣情が浮かぶ程度には、何一つ薄れていない。
「はい、お口直し」
いつの間に注文を済ませたのか、店員が運んできたグラスの一つをオールマイトが西岐の前に置いた。
リキュールの濃いピンクと牛乳の白が二層に分かれた如何にも女子受けしそうなカクテルだ。西岐がそのまま口を付けようとしてオールマイトに止められ、マドラーでぐるぐると掻き混ぜて、全体が『イチゴミルク』の名に相応しい色合いになってから西岐はこくんと一口飲み込んだ。
すると、一転して笑みが戻り、聞いているこちらの力が抜けそうな声を零す。
「んっ、あまぁああ…………え……ジュース?」
「お酒だよ。ごくごく飲まないように」
オールマイトの忠告に数回頷いて西岐はもう一口と含んでからグラスを置いた。
それを待っていたかのように、賑やかしメンバーがどやどやとやってきて西岐を引っ張っていく。来て早々、教師に挟まれて座っているのを不満に思っていたのだろう。グラスもセットで西岐を持って行かれて相澤はポリッと頬を掻いた。
「さすがA組、パワフルさが違うな」
さも可笑しそうに喉を震わせて笑うオールマイトに相澤も異論はなく、同意の溜息をついた。
「また一クラス全員除籍にしたんだって?」
グラスを傾けながら問いかけてくる。カラリと氷が音を立てるそれは恐らくウーロン茶か何かなのだろう。
「見込みゼロだったんで」
「ちょうど特異点の子供たちだろ? 恐ろしいな、君は」
何のことはないと切り返して枝豆を口に放り込むと、オールマイトの手が遠慮なく伸びてきて一莢持っていく。
「……オールマイトさんは?」
「うん?」
「老後、なにやってたんですか」
わざと嫌味たらしく聞き返す相澤に笑みを深くした。
「れぇくんのサイドキックをやってたかな」
毒っ気のない微笑みを浮かべながらとんでもない反撃を見せたオールマイトに、相澤はみっともなく動揺して持ち上げかけたグラスをテーブルに滑り落としてしまう。幸い垂直に落ちたおかげで零すことはなかったが、誤魔化しようのない失態を恥じて額に手を宛がう。深々と息を吐き自分を落ち着かせる。
「こんな老兵、役に立たないだろうと言ったんだけどね、力になってほしいと頼まれれば吝かではないし……基本的には事務方で尽力させてもらってるよ」
老後と言ったことへの意趣返しなのか、あえて老兵という言葉を使って追い打ちをかけてくる『元・平和の象徴』に相澤は額を押さえたまま細めた目を向けた。
「いい性格してますよね、案外」
「相澤くんが一番手強いライバルだからね。牽制するために沢山シミュレーションしてきたのさ」
屈託ない笑みと似つかわしくない台詞が相澤の眉間の皺を深くさせる。
「牽制? 不要でしょう」
相澤の気持ちを萎えさせるというのなら西岐がオールマイトに向けるあの表情で十分だ。心を預けきっているかのような、他の者に向けるものと一線を画す微笑みが相澤に与えるダメージは、今のやり取りの比ではない。
「残念ながら、私とれぇくんの関係は相澤くんが思っているようなものじゃあないよ」
内心が顔に出すぎていたのだろうか。
オールマイトの目に気遣うような気配が漂った。
「いいですよ、そういうの。かえってヘコむ」
「いや、違うんだ」
被せ気味に言葉を発しながら蝋燭の灯を消すように静かに笑みを引っ込めて、トンと己の胸を指でついた。
「彼の抱えているものをココで識ったというだけの話なんだ」
オールマイトの指差す胸元と、クラスメイトに囲まれている西岐の後頭部を視線が往復する。
"ココ"というのは西岐が雄英一年生だった時からオールマイトと繋がっている心のバイパスのようなものの話だろう。考えていることがお互いに伝わり共鳴してしまう現象は今でも続いているらしい。
「……抱えているもの?」
怪訝に眉をしかめるとオールマイトの眉もまた意味ありげに歪む。
「さすがだ」
「……なにがです?」
「嫉妬やプライドよりまず彼の心を気遣う」
「そんな小奇麗なもんでもないです」
誉め言葉がザラッと心を撫でる。別に嫉妬やプライドの類がなかったわけじゃない。無視できないほどグルグル肚の底を渦巻いている。だがそれより西岐が抱えているものがあるという事実が無視できなかった、ただそれだけの話だ。
「で、抱えてるものってなんです?」
重ねてもう一度問いかけた相澤の声は後半が掻き消され、オールマイトがはっとして振り返った。
ガチャンッといういくつかの食器が鳴る音、硬いものと柔らかいものがぶつかる鈍い音、その後で生徒たちの心配そうな声が波のように相澤の元に押し寄せて、オールマイトと共に素早く腰を上げていた。
「先生っ、れぇちゃんが……っ」
テーブルに突っ伏した西岐を看ている数人を押しのけて、相澤はなるべく揺らさないように西岐の顔を覗き込む。真っ赤な顔でぐったりと目を閉じ、苦し気な呼吸が口から吐き出されている。能力を使いすぎて熱暴走した時のような状態だが、さっきまで何ともなかったのが急にこうなるとは考えにくい。
「酒は? どれくらい飲んだ?」
「最初に頼んだやつがまだそこにあるよ」
生徒たちではなくオールマイトがグラスを指さして答える。
たしかにピンク色の液体がなみなみと注がれたグラスが目の前に置かれている。これがお代わりじゃないならアルコールが原因でもないだろう。
「……体調不良、か?」
西岐の性格なら多少無理をしても同窓会に顔を出すかもしれない。
「仕事上がりで来たからね、疲れで酔いが回ったんだろう。大丈夫、私が家に送り届ける、安心して宴を続けてくれよ」
オールマイトが生徒たちを安心させるように持ち前の大らかな声音を振りまき、横から西岐を抱き上げようと手を伸ばしていくる。
瞬間的にムッとした。
生徒たちにも丸分かりであろう程あからさまに嫉妬がブワッと広がった。
オールマイトの手が西岐に触れるよりも先に抱えあげて、彼から西岐を遠ざける。
「じゃあタクシーを頼みます」
しれっと言い放つとオールマイトは拍子抜けしたように数回瞬きした後で、困ったように口角を緩める。
「……参ったね。君ってメンタル最強なんじゃないのかい」
ポリと頬を掻いてから背を翻し、個室を出ていく。
メンタルが最強なのならグラスを落とすような失態は晒さないだろうし、そもそも連絡をしなくなるほどダメージも受けないのではないか。今こうして西岐を抱き上げたのだって不格好な嫉妬心からで……相澤のメンタルも人並みだ。ただ、それが心に黒い影を落とすのかといえばそうではない。欝々と沈み込み立ち上がれなくなるというのがメンタルの弱さなのだとすれば確かにそういうものとは無縁だろう。
相澤は無理やり引っ張り出した教師の顔を生徒たちに向けて、大丈夫だということと、家に送り届けたら連絡を寄こすということを再三告げてから居酒屋を後にした。
繁華街の中の通りは客待ちのタクシーがビッチリと駐車していて、別にオールマイトがわざわざ捕まえに行かなくてもすぐに乗れる状態だった。
上背のある男二人とプラス西岐が少々窮屈に並んで、オールマイトが告げた住所に運ばれていく。
雄英から徒歩圏内にあるお馴染みのマンション。西岐宅。
どうやって入るつもりなのかと伺っていれば、当然のようにポケットからカードキーを取り出して慣れた動作でエントランスを通り抜け、エレベーターに乗り込み、玄関扉を開けた。
ここに訪れるのは何年ぶりだろうか。
少しも変わらない家具の配置の中にポツポツとオールマイトの私物らしきものが置かれているのが目に入った。
ひとまず西岐を寝室のベッドに運び入れて寝かせ、目蓋が動かないのを見下ろしてからオールマイトと連れ立ってリビングに移動する。小さなラグに小さなクッションがぽつんぽつんと置かれていて、そのまま座るとやけに距離が近くなるので、相澤はフローリングのところまでクッションを引っ張っていって腰を下ろした。
「……で」
オールマイトが座り切る前に疑問符を投げる。
すると、少々腰を浮かせた状態で相澤の顔を見つめ、苦笑を浮かべた。トスンとクッションに尻を落ち着かせてから、さて、と勿体ぶって口火を切る。
「どこから話そうかな」
「――恋人関係じゃないんだな」
もったりとした話口調は相変わらずだ。焦れったさに耐え切れず質問というより確認事項を放り投げた。
オールマイトの眉尻が垂れ下がり視線が斜め下の床に落ちる。
「ああ、未だに私の片思いだ」
なんだ、ひとつは確実に思い違いだったのか、と相澤は自嘲の笑みに口角を吊り上げた。
ならばと次々浮かんでくる疑問が抑えきれず口から零れていく。
「じゃあ……どういう関係なんです? 妙に親密ですよね。抱え込んでいるものとは? どうして抱え込ませている? あなたは何をしているんですか?」
「待った、相澤くん、ひとつずつ……」
「抱え込んでいるものってのは今のあの不調みたいなもんですか?」
矢継ぎ早に浴びせた言葉を拾い切れずにハンズアップしてみせるオールマイトへ、相澤は剥き出しの核心を突きつける。それが間違いなく核心だということは直後の彼の表情で一目瞭然だ。
あの不調、熱や体調不良でもなく、アルコールによるものでもない。
マンションに辿り着くまでの道中、腕の中で息を荒げていた西岐を見下ろして相澤はほぼ確信していた。
「催淫の類でしょう?」
時折うっすらと開いた目蓋の下はうるうると水分をやたら含んでいて、抱える相澤の腕がタクシーの振動で揺れるたびに小さく身じろぎしていた、あの反応は酷く性的だった。
「……凄いな。その通りだ」
オールマイトの細長い手が口元を拭う仕草をする。それが酷く疲れを漂わせる。
「なんというか……こう、感覚が鋭敏になる時期というのがあってね……適した言葉かは分からないが発情期のようになるんだ」
長々とした説明はもう要らなかった。発情期、その単語ひとつですべてに納得していた。
相澤と目を合わせなかったのも人と接触しないようにしていたのも、そうした状態にある自分を悟られたくなかったから、そして不意に触れて鋭敏になった感覚を刺激したくなかったからなのだろう。日々の中で長く一緒に過ごしていれば、変調の波というものを目の当たりにして気付けたかもしれないが、相澤が西岐と会ったのは活動を共にしたほんの少しのタイミングでしかなく、運が悪いことにその都度、発情期とやらの周期と重なってしまっていたのだろう。
気を張り詰めて活動する中で、唯一真相を知っているのがオールマイトなのなら、あのホッとした表情も頷ける。
ただし、秘密を共有できる関係だということへの嫉妬は僅かも薄れやしないし、今度はまた別の疑惑が浮上してくる。
「……で、その性欲処理をあなたがしていた、と?」
新たな疑惑、体の関係。
オールマイトが西岐を好いていることは誰の目にも明らかだし、彼も男だ。愛しい人が目の前で欲情にまみれていれば手を出さぬわけがない。
ダメージを覚悟して問いかける相澤に、オールマイトは緩く首を横に振った。
「いいや、私は触れていない」
暫く返答の意味が分からなかった。
「れぇくんがね、昂った身体をどうしていると思う? ぎゅうって身体を縮こませてひたすら耐えるんだよ。そんな子に私は触れられなかった」
やはり意味が飲み込めない。
言っている言葉自体は分かるが頭が理解を拒んでいると言った方が正しいか。
「あんたは仙人かなんか目指してんのか?」
求めてやまない愛しい人という据え膳を食わないなんてどうかしている。ましてや情欲によって苦しんでいるのだ、どうして楽にしてやろうと都合よく思考を変換できなかったのか。
「ここのところどんどん酷くなってきていてね……周期も狭くなっている。発散してないからかもしれない。同窓会という機会に君に打ち明けようかと思ったんだ。私では…………力不足だ」
彼も悩んだ末なのかもしれない。
だが相澤には到底理解出来ない思考だ。
「なら俺が解放してやっていいってことですね」
オールマイトが手を出さないと決めているのなら、据え膳を寄こすというのなら遠慮なく頂く。
返事を聞く前に立ち上がりスタスタと静かに寝室へ足を向ける。
するや、背後から激しい衣擦れの音と共に床を踏み鳴らす音が聞こえて、無遠慮な力加減で肩を掴まれた。首の捻りだけで背後を伺えば、眼下の窪みから青い光が鋭く向けられている。
「……なんだ、明確に嫌なんじゃないですか」
よもや自分とは違う次元の生き物なのではと思いかけていたが、その突き刺さるような嫉妬の光を間近に見て相澤の表情が緩んだ。
潔く諦めてくれるのは願ってもないことだが、手も出せない相手に数年寄り添い続けるなんて自虐的ともいえる愛情を抱く彼から無感情で掻っ攫えるほど、自分勝手にもなれなかった。
いろんな要因が重なり、オールマイトという人となりがあって、相澤の心の中に彼を容認するスペースが生まれ始めている。自分自身でも戸惑うような考えが、もう決定事項のように心に居座っている。
「共有してもいいですよ、俺は。隙を作ってくれたお礼に」
今度はオールマイトが相澤の言葉を理解できないと怪訝にする番だ。
相澤は彼の理解を待たず手を払いのけて、寝室の扉を開く。
「まあ……最終的に決めるのは西岐ですが」
眠っているのか、鋭敏になった感覚に支配されて周囲に気を払う余裕がないのか、身体を丸めて布団に潜り込んでいるであろうそのシルエットに目を細めた。
続く
create 2018/06/12