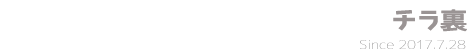相澤
飴色の想い
飴色の想い
年齢制限のある作品です。
推しえてアンケ結果により『相澤先生』で『押し倒されちゃう話』を書きました。
卒業式の後のお話。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
雄英の学校行事の中で唯一、厳粛な空気が流れる最大で最後の節目、卒業式。
受け持ち生徒21名。三年間、一人たりとも除籍者を出さず全員を送り出せるのは初めてのことだ。しみじみとした思いを胸に生徒たちを見送り、指導要録をまとめると相澤は今日ばかりは少し早めに帰らせてもらうことにした。
三月になったとはいえまだまだ外気は冷たく、コートに身を包み、長いマフラーを捕縛武器のようにぐるぐると巻いて身を縮こませながら校舎の外に出た。
遠く地平線にオレンジの光を残し濃紺の空が広がる、ちょうど夕方と夜の境目。卒業式日和ともいえるくらい天気が良かったこともあっていくつも星が瞬いている。夜空なんてものを見上げてしまうくらいには珍しく感慨にふけっているらしいが、まあ今日くらいはいいだろうと白い息を吐く。
校門に差し掛かったところで視線を前に戻し、そこに人影があることに気付いた。
風に揺れるオレンジ色の髪にまさかという思いで歩調を早める。
「あ、あいざわせんせ」
振り返ったのは間違いなく西岐だった。
卒業式は正午前には終わったはずだというのに、西岐は白い顔で暗がりの中佇んでいる。
「……は、バカ、お前ずっとそこにいたのか?」
「卒業したからもう入れなくて」
「お前は……なんで」
自分のマフラーを西岐の首にグルグルを巻きつけてやるが、そんなもので暖まりそうもないほど、手に触れた髪も頬もすっかり冷え切ってしまっている。
「一緒に帰ろうと思って、今日最後だから」
それでも嬉しそうに笑うものだから相澤は言いたいことのほとんどを飲み込んだ。
元々これから西岐の家に向かおうと思っていたわけで、冷えた手を自分のコートに招き入れて体温を与えつつ一緒に歩き始める。
雄英から徒歩圏内にあるマンション。入学当初から住み、学生寮に移った後も休暇の折に帰る場所として西岐の叔父が残してくれていたもので、相澤にとってもだいぶ慣れ親しんだ部屋だ。はじめは必要最低限しかなかった部屋に、次第に増えていった複数のクッションやカップなどの細やかなものが、たびたび訪れるのであろう友人の存在を感じさせた。
もちろん、相澤の私物も多くある。そのうちの一つ、ルームウェアに袖を通している横で、西岐がボタンのないブレザーを脱ぐ。ブレザーだけでなくシャツのボタンに至るまで一つも残っておらず、ネクタイまでもが奪われた瞬間を相澤は目撃していた。それを思い出して卒業式なのだということをしみじみと実感してしまう。
「西岐、おいで」
手招きすると西岐はシャツを脱ぎかけていた手を止めて、何も考えず相澤の膝の間に座る。
「お前さ……今日卒業したんだろ?……もう少し警戒しろよ」
少し逞しくなった体を腕に抱き、肩口に鼻先を埋める。柔らかい皮膚に触れたまま囁く唇に、くすぐったそうに肩が揺れた。
「俺はもう……"相澤先生"じゃないんだぞ」
触れているだけでは耐えられなくなって軽く吸い付く。
小さな声を上げて西岐の体が硬く強張った。
「い……イレイザーさん」
「今の俺はイレイザーヘッドでもないな」
初めて会った時の憧れが強いのか西岐はプライベートの時はヒーロー名で呼ぶ。はじめの頃は微笑ましく思ったものだが、今は強固な防御壁のように煩わしく思える。無防備に触れさせるのは相澤がヒーローで教師だから。けれどもうどれも取っ払ってしまえる。相澤ははなからそのつもりだったのだ。
シャツとタンクトップの下に忍ばせた手で腰のラインを確かめ、脇腹から上の方へとスルスルと滑らせていく。
あれほど冷えていた体が熱を持ち始めている。
「ま……待って」
「待たねぇ」
欲情にまみれた声を直接注ぎ込む。
「四年も待ったんだ、もう待てねぇ」
息がかかるだけで飛び跳ねる体に相澤は口角を上げた。以前から知っていたが西岐は耳と首が弱い。耳たぶを口に含んで軽く歯を立ててやるといよいよ余裕のない声を上げた。
「待って、待って……!」
さすがに相澤の行動の意図を理解したのだろう。唇に触れる耳たぶが熱く、頬の輪郭が真っ赤に染まっている。
シャツの上から相澤の手を掴み、離れようと体を傾ける。
「しょうたさん……ッ、待って!」
不意に下の名前で呼ばれて相澤のすべての動きがピタッと停止した。
先生でもヒーローでもないと却下されたから、消去法で選択しただけかも知れない。しかし、とてつもない威力を持って相澤に一撃を食らわせた。
西岐は緩んだ手から抜け出し距離をとってから振り返る。
「なんで?」
短い問いかけ。拒絶されているような気がして相澤は眉根を寄せた。
「お前が好きだからだ。知らなかったか?」
いや、知るはずがない。言いながら心で否定していた。
教師と生徒という立場ゆえにあまり強く出られず、曖昧に濁していたのは相澤の方だ。
立場だけが理由ではない。思いを伝えたことで西岐の抱いている憧れが壊れ、失望されてしまうのではないかと思って怖かったのだ。
けれどもう焦げ付きそうな思いを閉じ込めているのは限界だった。
「お前が好きだ」
もう一度絞り出した声に思いを乗せる。
すると、西岐の頬にボロボロと涙がこぼれた。唇を震わせて静かに泣く姿を見て相澤の勢いは完全に消え去ってしまう。
相変わらず弱い。涙を見ただけで続けられなくなってしまう。泣いて嫌がるのを無理強いはできない。
「……悪かった。もうしないから……。だから泣くな」
そう言って距離を取ろうと立ち上がりかけた相澤の手に、西岐の指が絡んだ。
「俺も、好きです」
震える声で紡がれた言葉をすぐには理解できず、ゆっくりと体を戻して西岐を覗き込む。涙で貼りついた前髪をそっと避けて、濡れた瞳を見つめる。
「俺もずっとしょうたさんが好きでした」
絡んだ指に力が込められて、相澤に実感を与える。
痺れるような喜びに目の奥が熱くなる。
「――れぇ」
ずっと呼びたかった名を呼び、その口が応える前に塞いだ。
唇で唇を挟むように啄むと、伝わる柔らかな弾力に眩暈を覚え、徐々に口づけを深くしていく。舌を差し込んで西岐のそれを引き寄せ、絡めながら舐め上げると、隙間から洩れた吐息が相澤の雄の部分を煽り育てていく。
どこで覚えたのか西岐の舌が応えようと拙く動く。
完全にのぼせ上り、冷静さが失われていく。
「そんなふうに煽ったらもうやめてやれねえぞ」
力の抜けた身体は軽く押しただけでラグの上に横たわり、潤んだ目で不安そうに相澤を見上げてくる。それすらも扇情的で相澤の頬を汗が伝う。
「いいよ」
泣き笑いのような顔で相澤へと手を伸ばす。
相澤が覆いかぶさると背中に腕を回して縋りついてきた。
愛しさが溢れて何度も名を呼び、至る所にキスを落として跡を刻んでいく。
一生手放せそうにないなと思いながら甘い恍惚に酔い、西岐の身体に溺れていくのだった。
推しえてアンケ結果により『相澤先生』で『押し倒されちゃう話』を書きました。
卒業式の後のお話。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
雄英の学校行事の中で唯一、厳粛な空気が流れる最大で最後の節目、卒業式。
受け持ち生徒21名。三年間、一人たりとも除籍者を出さず全員を送り出せるのは初めてのことだ。しみじみとした思いを胸に生徒たちを見送り、指導要録をまとめると相澤は今日ばかりは少し早めに帰らせてもらうことにした。
三月になったとはいえまだまだ外気は冷たく、コートに身を包み、長いマフラーを捕縛武器のようにぐるぐると巻いて身を縮こませながら校舎の外に出た。
遠く地平線にオレンジの光を残し濃紺の空が広がる、ちょうど夕方と夜の境目。卒業式日和ともいえるくらい天気が良かったこともあっていくつも星が瞬いている。夜空なんてものを見上げてしまうくらいには珍しく感慨にふけっているらしいが、まあ今日くらいはいいだろうと白い息を吐く。
校門に差し掛かったところで視線を前に戻し、そこに人影があることに気付いた。
風に揺れるオレンジ色の髪にまさかという思いで歩調を早める。
「あ、あいざわせんせ」
振り返ったのは間違いなく西岐だった。
卒業式は正午前には終わったはずだというのに、西岐は白い顔で暗がりの中佇んでいる。
「……は、バカ、お前ずっとそこにいたのか?」
「卒業したからもう入れなくて」
「お前は……なんで」
自分のマフラーを西岐の首にグルグルを巻きつけてやるが、そんなもので暖まりそうもないほど、手に触れた髪も頬もすっかり冷え切ってしまっている。
「一緒に帰ろうと思って、今日最後だから」
それでも嬉しそうに笑うものだから相澤は言いたいことのほとんどを飲み込んだ。
元々これから西岐の家に向かおうと思っていたわけで、冷えた手を自分のコートに招き入れて体温を与えつつ一緒に歩き始める。
雄英から徒歩圏内にあるマンション。入学当初から住み、学生寮に移った後も休暇の折に帰る場所として西岐の叔父が残してくれていたもので、相澤にとってもだいぶ慣れ親しんだ部屋だ。はじめは必要最低限しかなかった部屋に、次第に増えていった複数のクッションやカップなどの細やかなものが、たびたび訪れるのであろう友人の存在を感じさせた。
もちろん、相澤の私物も多くある。そのうちの一つ、ルームウェアに袖を通している横で、西岐がボタンのないブレザーを脱ぐ。ブレザーだけでなくシャツのボタンに至るまで一つも残っておらず、ネクタイまでもが奪われた瞬間を相澤は目撃していた。それを思い出して卒業式なのだということをしみじみと実感してしまう。
「西岐、おいで」
手招きすると西岐はシャツを脱ぎかけていた手を止めて、何も考えず相澤の膝の間に座る。
「お前さ……今日卒業したんだろ?……もう少し警戒しろよ」
少し逞しくなった体を腕に抱き、肩口に鼻先を埋める。柔らかい皮膚に触れたまま囁く唇に、くすぐったそうに肩が揺れた。
「俺はもう……"相澤先生"じゃないんだぞ」
触れているだけでは耐えられなくなって軽く吸い付く。
小さな声を上げて西岐の体が硬く強張った。
「い……イレイザーさん」
「今の俺はイレイザーヘッドでもないな」
初めて会った時の憧れが強いのか西岐はプライベートの時はヒーロー名で呼ぶ。はじめの頃は微笑ましく思ったものだが、今は強固な防御壁のように煩わしく思える。無防備に触れさせるのは相澤がヒーローで教師だから。けれどもうどれも取っ払ってしまえる。相澤ははなからそのつもりだったのだ。
シャツとタンクトップの下に忍ばせた手で腰のラインを確かめ、脇腹から上の方へとスルスルと滑らせていく。
あれほど冷えていた体が熱を持ち始めている。
「ま……待って」
「待たねぇ」
欲情にまみれた声を直接注ぎ込む。
「四年も待ったんだ、もう待てねぇ」
息がかかるだけで飛び跳ねる体に相澤は口角を上げた。以前から知っていたが西岐は耳と首が弱い。耳たぶを口に含んで軽く歯を立ててやるといよいよ余裕のない声を上げた。
「待って、待って……!」
さすがに相澤の行動の意図を理解したのだろう。唇に触れる耳たぶが熱く、頬の輪郭が真っ赤に染まっている。
シャツの上から相澤の手を掴み、離れようと体を傾ける。
「しょうたさん……ッ、待って!」
不意に下の名前で呼ばれて相澤のすべての動きがピタッと停止した。
先生でもヒーローでもないと却下されたから、消去法で選択しただけかも知れない。しかし、とてつもない威力を持って相澤に一撃を食らわせた。
西岐は緩んだ手から抜け出し距離をとってから振り返る。
「なんで?」
短い問いかけ。拒絶されているような気がして相澤は眉根を寄せた。
「お前が好きだからだ。知らなかったか?」
いや、知るはずがない。言いながら心で否定していた。
教師と生徒という立場ゆえにあまり強く出られず、曖昧に濁していたのは相澤の方だ。
立場だけが理由ではない。思いを伝えたことで西岐の抱いている憧れが壊れ、失望されてしまうのではないかと思って怖かったのだ。
けれどもう焦げ付きそうな思いを閉じ込めているのは限界だった。
「お前が好きだ」
もう一度絞り出した声に思いを乗せる。
すると、西岐の頬にボロボロと涙がこぼれた。唇を震わせて静かに泣く姿を見て相澤の勢いは完全に消え去ってしまう。
相変わらず弱い。涙を見ただけで続けられなくなってしまう。泣いて嫌がるのを無理強いはできない。
「……悪かった。もうしないから……。だから泣くな」
そう言って距離を取ろうと立ち上がりかけた相澤の手に、西岐の指が絡んだ。
「俺も、好きです」
震える声で紡がれた言葉をすぐには理解できず、ゆっくりと体を戻して西岐を覗き込む。涙で貼りついた前髪をそっと避けて、濡れた瞳を見つめる。
「俺もずっとしょうたさんが好きでした」
絡んだ指に力が込められて、相澤に実感を与える。
痺れるような喜びに目の奥が熱くなる。
「――れぇ」
ずっと呼びたかった名を呼び、その口が応える前に塞いだ。
唇で唇を挟むように啄むと、伝わる柔らかな弾力に眩暈を覚え、徐々に口づけを深くしていく。舌を差し込んで西岐のそれを引き寄せ、絡めながら舐め上げると、隙間から洩れた吐息が相澤の雄の部分を煽り育てていく。
どこで覚えたのか西岐の舌が応えようと拙く動く。
完全にのぼせ上り、冷静さが失われていく。
「そんなふうに煽ったらもうやめてやれねえぞ」
力の抜けた身体は軽く押しただけでラグの上に横たわり、潤んだ目で不安そうに相澤を見上げてくる。それすらも扇情的で相澤の頬を汗が伝う。
「いいよ」
泣き笑いのような顔で相澤へと手を伸ばす。
相澤が覆いかぶさると背中に腕を回して縋りついてきた。
愛しさが溢れて何度も名を呼び、至る所にキスを落として跡を刻んでいく。
一生手放せそうにないなと思いながら甘い恍惚に酔い、西岐の身体に溺れていくのだった。
create 2017/12/05
update 2017/12/05
update 2017/12/05