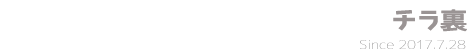障子
だから今日も読書が進まない
だから今日も読書が進まない
年齢制限のある作品です、が、ほんのりです。
1日1アンケの結果により『障子くんとラブラブ』なお話を書きました。
部屋でまったり。我慢比べ。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
身体の側面の重みがなくなって、また戻ってくる。寄り掛かっていた肩が背中に変わって本格的に体重を預けてきた。文字を追っているとは思えないぼんやりした目で手に持った本を見ている。手にしている本のタイトルは『中3から始める未来設計――まだ迷っている君に伝えたい大事なこと――』。高校一年の冬に読む本ではないことだけは確かだ。
「西岐、退屈してるのか?」
「んーん」
このやり取りも三往復目になる。
はじめは体育座りをして宙をぼんやり見ながらぐらぐら揺れ始めた時。その次は障子に寄り掛かってきた時で、三回目が今し方。
無駄どころか必要なものまで削ぎ落としたような障子の部屋には西岐の退屈を埋められるようなものはない。しかも今日の障子は読みたい本があって読書に勤しんでいたりする。西岐が退屈だというのなら別に読書などやめてしまって構わないのだが、そう言うと決まって「本を読んでて」と返ってきた。
ぺら、ぺら、とページを捲っているから読んではいるのだろう。
障子も自分の読書へと戻っていく。活字が一文字ずつ頭に吸い込まれていくに従って、本の中身へとどんどん集中力が飲み込まれていく。
微かな呼吸の音と、ページを捲る音。伝わってくる体温と、微かな鼓動。
本にのめり込んでいた意識は、しおりから何十ページと進んだあたりでバサッという音で引き戻された。
見れば、西岐が手にしていた本が床に転がっている。そしていつの間にか西岐の頭は障子の膝の上にあって、完全に閉じかけた目蓋が障子の視線を受けてギリギリで留まった。薄く開いた目が障子を見上げる。
「やっぱり、退屈させたな」
今更気を遣いあう間柄でもないしお互いが好きなように過ごしている時間をいちいち申し訳なく思うことはないが、一緒にいるのが退屈だと感じられてしまうのは不本意だった。眠ってしまほどであればなおさらに。
西岐は障子が額に手を置いて撫でると心地よさそうな表情になって手のひらに擦りついた。撫でるたびに長い前髪が揺れて鼻や頬を擽るが、構わない様子で髪の隙間から障子を見つめては口元を綻ばせている。まるで膝で眠る猫のようだ。
「あのね……あの、ね」
眠りかけなのかと思えば案外しっかりした声が膝の上から障子に向かって響いてくる。障子の手のひらを導いて頬に当ててすりすりと擦りつく。
その仕草に煩くなり始めた心臓を感じつつ、黙って続きの言葉を待った。
ふわふわと浮かび上がってしまいそうな柔らかな声が言葉を紡ぐ。
「しょうじくんが本読んでる時、すごく好き」
ひどく甘い響きだった。
それは、例えば柔らかなクッションが好きだとか、ホワイトチョコが好きだとか、動物モノの映画が好きだとかそういったものとは一線を画す。
この"好き"は"どうぞ食べてください"と同義語だ。
「でも、ちゅうしたくなって……大変」
その上でこんなことを言い放つ。一体どこで覚えてくるのか。
目を細めて、頬に添えた手の親指で唇をなぞる。まださらさら乾いている唇の弾力を確かめるように少し押して、指を離した。
そして、意識を読書に戻す。
西岐はつい今、障子が本を読んでいる時が好きだと言った。ならば好きなことを叶えてやろうという話。
痛いほど刺さる視線を丸っきり無視して活字を追うと、しばらく何か言いたそうにしていたが落ちた本を拾い上げてまた読み始めた。知っている、西岐はかなり諦めがいい。放置されればそれはそれで構わないと自分の世界に戻っていく。
微かな振動音の後、ポケットをまさぐる気配。本が床に置かれて小さな電子機器を操作しているのが分かる。いつもならすぐに終えて放り投げてしまう電子機器をどういうわけか弄っては眺め、眺めては弄り、いつまでもポケットに戻そうとする様子がない。膝に触れている肩が微かに弾んで吐息だけの笑いが漏れ聞こえる。
障子の完全敗北だった。読みかけのページにしおりを挟むのも忘れて、西岐の手から奪った電子機器と一緒に背後に放り投げる。
何事かと見上げてきた西岐の首を手のひらで掬って持ち上げると、乾いたままの唇に自分のそれを押し付けた。他人より横に裂けている口が西岐の小さい口を覆い、他人より長い舌がぬるぬると這って西岐の口の中へと入っていく。薄く小さな舌を捕まえて唾液を擦り付け、じゅっじゅっと啜り上げる。
西岐の言う"ちゅう"よりずっとディープな"キス"を堪能し、しっとりと唇が濡れ、触れる息が熱くなった頃に解放した。
「……はあ……ずるい」
ぐったり身を預けて恨めしそうに言う。負けを喫した溜飲がいくらか下がる。
「本は?……読むから我慢じゃなかったの?」
「もう読んだ」
「ほんと?」
嘘だ。西岐の手から本が落ちたあたりから一ページも進んでいない。嘘をついたり、意地悪をしたり、ズルをしたり、嫉妬深かったり、どれも西岐を好きになるまで知らなかった自分だ。割とそんな自分が嫌ではないのは西岐が手元にいてくれているからだろう。
障子の首に腕を引っ掛けて膝によじ登る。
「じゃあ、今度は俺の番、ね」
本当に嬉しそうに、にっこりと両目を弓なりにして笑う。そうして自分から障子の唇を啄みにくる。
諦めが早い割に構われたがりで、キス魔。付き合うようになって知った西岐の一面だ。悪くないどころか最高に愛しい。
口付けは西岐に思うまま任せて、障子は六本の腕で西岐の身体をまさぐる。耳や、背中や、胸元、腰、腿の内側、足の付け根、知り尽くしている西岐の弱いところを余すところなく、すりすりと撫でてやれば、もう物足りなさそうな顔でフーフーと荒い息を吐いた。
「ッ……、しょうじくん……」
「ああ、俺ももう我慢は効きそうにない」
お互いの声に余裕がなくなって積み上げた布団を崩して傾れ込む。
結局いつもこうなる。一緒にいれば触れたくなって口付けしてもっとと欲張って情が煽られて、熱が暴走してしまう。
だから、なかなか今日も読書が進まない。
1日1アンケの結果により『障子くんとラブラブ』なお話を書きました。
部屋でまったり。我慢比べ。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
身体の側面の重みがなくなって、また戻ってくる。寄り掛かっていた肩が背中に変わって本格的に体重を預けてきた。文字を追っているとは思えないぼんやりした目で手に持った本を見ている。手にしている本のタイトルは『中3から始める未来設計――まだ迷っている君に伝えたい大事なこと――』。高校一年の冬に読む本ではないことだけは確かだ。
「西岐、退屈してるのか?」
「んーん」
このやり取りも三往復目になる。
はじめは体育座りをして宙をぼんやり見ながらぐらぐら揺れ始めた時。その次は障子に寄り掛かってきた時で、三回目が今し方。
無駄どころか必要なものまで削ぎ落としたような障子の部屋には西岐の退屈を埋められるようなものはない。しかも今日の障子は読みたい本があって読書に勤しんでいたりする。西岐が退屈だというのなら別に読書などやめてしまって構わないのだが、そう言うと決まって「本を読んでて」と返ってきた。
ぺら、ぺら、とページを捲っているから読んではいるのだろう。
障子も自分の読書へと戻っていく。活字が一文字ずつ頭に吸い込まれていくに従って、本の中身へとどんどん集中力が飲み込まれていく。
微かな呼吸の音と、ページを捲る音。伝わってくる体温と、微かな鼓動。
本にのめり込んでいた意識は、しおりから何十ページと進んだあたりでバサッという音で引き戻された。
見れば、西岐が手にしていた本が床に転がっている。そしていつの間にか西岐の頭は障子の膝の上にあって、完全に閉じかけた目蓋が障子の視線を受けてギリギリで留まった。薄く開いた目が障子を見上げる。
「やっぱり、退屈させたな」
今更気を遣いあう間柄でもないしお互いが好きなように過ごしている時間をいちいち申し訳なく思うことはないが、一緒にいるのが退屈だと感じられてしまうのは不本意だった。眠ってしまほどであればなおさらに。
西岐は障子が額に手を置いて撫でると心地よさそうな表情になって手のひらに擦りついた。撫でるたびに長い前髪が揺れて鼻や頬を擽るが、構わない様子で髪の隙間から障子を見つめては口元を綻ばせている。まるで膝で眠る猫のようだ。
「あのね……あの、ね」
眠りかけなのかと思えば案外しっかりした声が膝の上から障子に向かって響いてくる。障子の手のひらを導いて頬に当ててすりすりと擦りつく。
その仕草に煩くなり始めた心臓を感じつつ、黙って続きの言葉を待った。
ふわふわと浮かび上がってしまいそうな柔らかな声が言葉を紡ぐ。
「しょうじくんが本読んでる時、すごく好き」
ひどく甘い響きだった。
それは、例えば柔らかなクッションが好きだとか、ホワイトチョコが好きだとか、動物モノの映画が好きだとかそういったものとは一線を画す。
この"好き"は"どうぞ食べてください"と同義語だ。
「でも、ちゅうしたくなって……大変」
その上でこんなことを言い放つ。一体どこで覚えてくるのか。
目を細めて、頬に添えた手の親指で唇をなぞる。まださらさら乾いている唇の弾力を確かめるように少し押して、指を離した。
そして、意識を読書に戻す。
西岐はつい今、障子が本を読んでいる時が好きだと言った。ならば好きなことを叶えてやろうという話。
痛いほど刺さる視線を丸っきり無視して活字を追うと、しばらく何か言いたそうにしていたが落ちた本を拾い上げてまた読み始めた。知っている、西岐はかなり諦めがいい。放置されればそれはそれで構わないと自分の世界に戻っていく。
微かな振動音の後、ポケットをまさぐる気配。本が床に置かれて小さな電子機器を操作しているのが分かる。いつもならすぐに終えて放り投げてしまう電子機器をどういうわけか弄っては眺め、眺めては弄り、いつまでもポケットに戻そうとする様子がない。膝に触れている肩が微かに弾んで吐息だけの笑いが漏れ聞こえる。
障子の完全敗北だった。読みかけのページにしおりを挟むのも忘れて、西岐の手から奪った電子機器と一緒に背後に放り投げる。
何事かと見上げてきた西岐の首を手のひらで掬って持ち上げると、乾いたままの唇に自分のそれを押し付けた。他人より横に裂けている口が西岐の小さい口を覆い、他人より長い舌がぬるぬると這って西岐の口の中へと入っていく。薄く小さな舌を捕まえて唾液を擦り付け、じゅっじゅっと啜り上げる。
西岐の言う"ちゅう"よりずっとディープな"キス"を堪能し、しっとりと唇が濡れ、触れる息が熱くなった頃に解放した。
「……はあ……ずるい」
ぐったり身を預けて恨めしそうに言う。負けを喫した溜飲がいくらか下がる。
「本は?……読むから我慢じゃなかったの?」
「もう読んだ」
「ほんと?」
嘘だ。西岐の手から本が落ちたあたりから一ページも進んでいない。嘘をついたり、意地悪をしたり、ズルをしたり、嫉妬深かったり、どれも西岐を好きになるまで知らなかった自分だ。割とそんな自分が嫌ではないのは西岐が手元にいてくれているからだろう。
障子の首に腕を引っ掛けて膝によじ登る。
「じゃあ、今度は俺の番、ね」
本当に嬉しそうに、にっこりと両目を弓なりにして笑う。そうして自分から障子の唇を啄みにくる。
諦めが早い割に構われたがりで、キス魔。付き合うようになって知った西岐の一面だ。悪くないどころか最高に愛しい。
口付けは西岐に思うまま任せて、障子は六本の腕で西岐の身体をまさぐる。耳や、背中や、胸元、腰、腿の内側、足の付け根、知り尽くしている西岐の弱いところを余すところなく、すりすりと撫でてやれば、もう物足りなさそうな顔でフーフーと荒い息を吐いた。
「ッ……、しょうじくん……」
「ああ、俺ももう我慢は効きそうにない」
お互いの声に余裕がなくなって積み上げた布団を崩して傾れ込む。
結局いつもこうなる。一緒にいれば触れたくなって口付けしてもっとと欲張って情が煽られて、熱が暴走してしまう。
だから、なかなか今日も読書が進まない。
create 2018/01/21
update 2018/01/21
update 2018/01/21