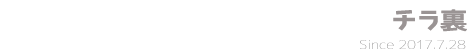1-A+α
Happy Valentine's Day
Happy Valentine's Day
アンケの結果により『ハーレムなバレンタイン』のお話を書きました。
ハーレムというより、いつも通りの『みんなでちやほや』な感じになっております。ご了承ください。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
「外泊許可……?」
訝しげな顔で相澤が振り返った。
「いつ?」
「えっと……今日の夜から」
「から?」
「……あ、の……三連休の間です」
「どこに」
「俺の家です、けど……」
鋭く目を細めて端的な言葉で問いかけてくる相澤の態度は、あからさまに不機嫌で、そんなに悪いことを申し出ただろうかと西岐を怯えさせた。
長い連休があれば時折自分のマンションに戻って過ごすなんてことは度々あったと思うのだが。
「誰と?」
「え……俺一人です」
一つ質問に答えるたびにどういう訳か周囲の空気が重くなっている気がする。
「連休三日間、家に一人で?」
「……はい」
まるで嘘を言っているかのような心境に陥る。それほどまでに相澤の探ってくる眼が鋭い。
目線を合わせているのが辛くて、ついブレザーの裾をいじる指先に目線を落とした。こうやって目を合わせないことがより一層、相澤の機嫌を損ねていることはなんとなく分かっているのだが、怒りを孕んでいる時の相澤は苦手だったりするからどうしようもない。
こんなことで躓くと思っていなかったから予想外の出来事に頭が混乱していた。
「俺が家に行ってもいいな?」
「……え」
追い打ちをかけるような問いかけに西岐は一瞬、頷きかけてから、遅すぎるくらいの動きで顔を上げた。
「だ、だめ」
「西岐、だったら許可は出せない」
こういうときの切り返しは自分でも嫌になるほど下手だ。動揺が声に出すぎて相澤の不信感を煽ってしまう。
それにしたって相澤の心象一つで外泊許可が下りないのは職権乱用ではないのかと思うが、ここは雄英、自由な校風が売りというのは教師の方針まで含まれる。どう訴えたところで相澤が許可できないと言えば外泊は無理だ。
全寮制の形となった今、無断外泊は除籍処分になりうる違反行為。
「…………来ていいです」
西岐には頷くという選択肢しかなかった。
それから短針と長針がぐるぐる回って普段の就寝時間を過ぎた頃、マンションのインターホンが鳴り響いた。あんまり遅いから仕事が忙しくて来られなくなったのかと淡い期待を抱いていたのだが、さすがは相澤、言った通りきっちり姿を見せた。
リビングに入るなりスンと鼻を鳴らし、キッチンに目を向ける。
充満している甘ったるい匂いと、所狭しと置かれている材料や調理器具やラッピング用品が、西岐が何をしているのか物語っている。
「……これは」
いったいどういうことを想像していたのか、相澤は拍子抜けして呟き、特に返事をせず作業に戻る西岐を眺めながら上着を着たままキッチンの端に置いてあるスツールに腰かける。
丸めたチョコクランチにアラザンやカラーシュガーを乗せてカラフルにしたものを小さなお皿に乗せて冷蔵庫へ、入れ替わりに冷やしておいたチョコ入りのシリコン型を出した。酸味の強いベリーソースを固まったチョコの窪みに流しいれてからさらに湯煎したチョコで蓋をして冷蔵庫へ戻し、今度は鍋で温めていた牛乳にオレンジピュレと刻んだチョコを順に入れて混ぜていく。それをこして、冷やしながらまんべんなく混ぜ、容器に入れて冷蔵庫へ入れていると、相澤が『ああ』と納得の声を出した。
「お前……全員分、それも一個ずつ違うのを作ってんのか?」
チョコに生クリームを混ぜ込む手を止めて西岐は相澤の言葉に一度頷く。
クラスのみんなと雄英の先生達、全員分を用意しようと思っての場所と時間、そこには勿論、相澤へのものも含まれていて、出来れば内緒にしておきたかったのだ。サプライズという意味もあるし、せっせと手作りしているのを知られるのが恥ずかしいという意味もあった。
頬に熱が集まった気がして俯いて手元に集中する。
今まで意識をしたこともなかったバレンタインデーという冬のイベント。どうしてか今年はテレビの特集から目が離せなくなっていた。大切な人にチョコレートを贈るということがキラキラした素敵なものに思えた。
西岐にとって大切な人といえば日々を共にする雄英のみんなだ。折角あげるなら全員が喜ぶものがいい。個性豊かな人達だから好きなものもみんな違う。それなら一つずつ作ろう。
……と、なったわけだ。
寮で作ればすぐに知られてしまうし全員分となれば長時間キッチンを占領してしまうことになる。だからバレンタイン前の連休を利用して自宅のマンションで、と思ったのだが、外泊許可でまさか相澤の機嫌を損ねることになるとは思っていなかったわけで。
サプライズに失敗した贈る予定の一人に溜息をつくと相澤は小指で頬を掻いた。
「タイミングがタイミングだから深読みした……」
「どんな?」
「そもそもお前が隠し事しようとしてあからさまに怪しいから悪い」
「う……、そうだけど」
確かに、手作りチョコのことを内緒にしようと思って挙動が怪しくなっていた自覚はある。聞き返した言葉をまるきり無視されて釈然としないものの、そこを突かれると言い返せない。
「チョコ、買うんじゃダメなのか?」
「みんなが気に入りそうなのを探すのが大変なの」
「全部同じで良いだろ、合理的に」
「……言うと思った」
相澤の物言いに苦笑を浮かべ、湯煎のチョコをゴムベラで混ぜる手を動かしつつ、目を細めた。
「バレンタイン、ってさ」
牛乳を混ぜたチョコの容器を冷蔵庫に入れて、使い終わった道具を洗い始める。目線は手元に置いたまま口を開く西岐の横顔に、相澤の視線が当てられていた。
「想像だけどさあ……、最初にもらうのはお母さんからで、最初にあげるのがお父さん。兄弟がいたら兄弟ってこともあるよね」
静かな部屋に響く水音。キッチンとリビングに最小限に灯された明かり。広すぎる空間に漂うヒヤリとした空気。もう慣れきったと思っていたけれど、寮から戻ってきてこんなにも自分の声が反響しただろうかと戸惑った。
あの賑やかな場所に馴染んで、この寂しさには戻れなくなっていることに気付いてしまう。
西岐にとって雄英のみんなは家族とは呼べないまでも、特別な存在なのは確かだ。
「……重い義理チョコだな」
全てを言わずとも察したらしい相澤がにべもなく言い捨てる。
「いいの」
重いという言葉に少々不安を感じつつも気にしないようにやや強く言い切って、洗い終えた道具をもう一度使えるように材料と一緒に調理台に並べ、一息ついた。
時間的に余裕があるとはいえまだ作りたいものは沢山ある。お菓子作りなどほとんどしたことのない西岐には難しい作業も多分ある。普段ならとっくに夢の国へ旅立っている時間だが、眠気を振り払って材料へ手を伸ばした。
そうして火曜日の朝。
ラッピングも済ませた全員分のチョコを見て西岐はほくほくと笑みを浮かべていた。クラスメイトの分と先生達の分と、その他のいくつかを紙袋に分けて入れて、急いで寮に向かう。
バレンタインデーにはまだ一日早いが、手作りなので日持ちしない。だからすぐにでも渡してしまいたかった。
「お、れぇ、おっはよ」
「れぇちゃん、おっはよー」
「おっはよー!」
寮の玄関先で真っ先に声をかけてきたのは爆豪組の三人。切島と上鳴と瀬呂。それと目はあったものの挨拶は特にない爆豪もいる。揃って朝のトレーニング帰りらしい。
「えっと、あの、これ、チョコ」
いざ渡そうとなって何と言えばいいのか言葉がうまく出てこなくて、もごもごと口ごもりながらラッピングされた小さな箱を四つ差し出した。
よくよく考えたらただのクラスメイトの男が男にチョコを渡すのは可笑しいような気がして今更不安になる。しかも手作りだ。相澤が言っていた通り重いかもしれない。今引っ込めてしまえば何事もなかったように出来るかもしれない。
そう思って引っ込みかけた手首を爆豪が掴んだ。
「俺の、どれだ」
「あ……あ、の……これ」
ブラウンの包装紙に包まれたものを指先で揺らすと手首の代わりに包みを掴んで持っていく。
「俺のは?」
他の三人がほぼ同時に聞いてくる。
「え、と、これがえいじろうくんで、これがはんたくんで、これがでんきくんの」
「やった! 手作り?」
「あ、うん」
「すげえ、まじか」
「やべえ……初バレンタインチョコなんですけど」
テンション高く喜ぶ上鳴と、しみじみと手元の包みを見下ろす切島と瀬呂。その嬉しそうな様子に少し前に抱いた不安が霧散していく。
一番要らないと言いそうな爆豪があっさり受け取ってくれたことで自信を取り戻し、ダイニングにいるメンバーへと紙袋を揺らしながら向き直った。
「みんなの分もあるの」
朝食の支度をしたり食べ始めていたりするクラスメイト達一人一人にチョコの包みを手渡していく。連休明けの朝っぱらから始まったいきなりのチョコ攻撃をそれぞれが戸惑った顔で受け取り、じわじわと照れたような笑みを浮かべている。
「私らのも?」
「あるよぉ」
勿論、女の子たちのも用意している。
同じテーブルに座っている女子全員に手渡すと、朝食の途中でありながら早速ラッピングを開いて中を覗いた。
「おいしそおおおお!」
「いやいや、実際おいしいよ! キャラメル入ってるー好きー!」
「音符書いてある……すごい……」
「私のはムースだわ」
「チョコ大福ううう!」
「りんご、知恵の実ですわね」
見た目でキャーキャーと盛り上がり、一口食べてはまたキャーキャー盛り上がる。女子のテンションは朝といえど高い。スイーツを前にすれば尚更なのだろう。
「りんご?」
背後で過剰に反応したのは常闇だ。
「ふふ、とこやみくんのもチョコとりんごのパイだよぉ」
常闇にも包みを差し出すと、おおっと感嘆の声と共にラッピングを解く。普段は落ち着いた物腰の常闇がいそいそと中身を確かめている様は微笑ましい。
隣に座っている障子にも同じように手渡す。障子はすぐには開けるつもりがなかったみたいだが、西岐が反応を期待してジッと見つめていることに気付いたのか、静かにラッピングの袋を開けてボックスを取り出した。
「…………たこ焼き?」
「そうなの、たこ焼き風のプチケーキなの」
ぱっと見、本物のたこ焼きにしか見えない丸いケーキが四つ並んでいるそれは、我ながら渾身の出来で、手で口元を抑えていても得意げな笑みが漏れてしまう。
手の中ににやにやした笑いを押し込めて、エレベーターから降りてきた緑谷と飯田と轟へ小走りに駆け寄って包みを差し出す。
「バレンタインッッ!!?」
「バレンタインか!!!」
「……」
顔を真っ赤にして過剰なほどの反応を見せる緑谷と飯田とは相反して、轟は手に持った包みを真顔で見下ろした。ちらっと二人を見てまた無言で視線を戻す。何か気に入らなかったのかと様子を伺いつつ轟にもう一つの包みを差し出した。最初に渡したものより幾らか落ち着いたラッピングを施してあるそれを見て轟の目に困惑が映る。
「これね、エンデヴァーさんの分」
「……俺が渡すのかよ」
「あ……自分で渡したほうがいいかな?」
「いや、俺が渡す」
あからさまに嫌そうな顔になる轟に手を引っ込みかけるが、一瞬で考えが変わったらしく奪うように包みを受け取った。
これでクラスメイト全員には手渡し終えた。
と、瞬間移動で部屋に戻る。
まだまだ渡す相手が残っている。
急いで制服に着替えて慌ただしく学校へと向かった。
職員室を前にして西岐は二の足を踏んでいた。
勢い勇んでここまで来たのはいいが、まず職員室という独特の雰囲気が入りにくくて怖気づく。
「れぇーちゃん、なーに突っ立ってんの?」
「ひっあああ」
入ろうか入るまいかとまごついていたところへ急に声が降ってきたと思うなり、肩に重みがかかって情けない声が喉から滑り落ちる。
「ビビりすぎだゼ、イレイザーに見られたらコロされる、落ち着け」
「ま、マイクせんせ」
声のトーンを落として耳に囁いてくるプレゼントマイクに、西岐は跳ね上がった心臓を落ち着かせようとフーフーと息を吐く。強く握りすぎたせいで皺が寄った紙袋をプレゼントマイクへと押し付けた。
「あの、チョコです」
いつもながら日本語の不自由さは自分でも呆れる。
「俺に?」
「みなさんに」
「へえ」
頬を紅潮させてパッと顔を輝かせたプレゼントマイクが返事を聞くなりシュンと萎れる。そのコロコロ変わる表情を見て緊張やさっきの驚きが消えて西岐の口元が緩む。
「マイクせんせのも入ってます」
渡した紙袋を横から広げて名前のカードが添えられた包みの一つを取り出す。
ちゃんと個別で用意されていると分かったからか再び晴れやかな表情となったプレゼントマイクは、目の前の扉をスパンと勢いよく開いた。
「ヘイオー!! チョコの差し入れだぜイエイ!!!」
喧しく登場したプレゼントマイクに職員室中の視線が集まって、背後にいる西岐も当然注目されることとなる。教員全員のチョコを用意したわけではないのでどうしようと焦るが、運よく見知った教師たちばかりが居合わせたようだ。
チョコという単語とプレゼントマイクが掲げている紙袋が繋がったのか、わらわらと集まってきた。
「私のもあるじゃない! 西岐くんったらいい子ね」
「わああ、僕のラッピングがコスモ柄!」
「なるほど、このぬりかべのような箱が私のですね」
「白イふわふわノ袋ガ我ノカ……」
「あの、スナイプせんせと、パワーローダーせんせと、校長せんせに」
「オッケオッケ、渡しとく!」
各々、自分の名前を見つけては声を高揚させていく教師達をしばし眺めているが、このままでは始業に間に合わなくなってしまうので、紙袋の中の残りをプレゼントマイクに任せて職員室を後にした。
遠目で校舎の壁を透かしていった先に目的の人物を見つけると迷わず瞬間移動した。普段は特別な理由がない限り使わないようにしているのだが、まあ、今は特別な理由に入るだろう。
突如姿を現した西岐を見るなり、紫の髪を揺らして心操は目を見開いた。
「……それ、何度見ても驚くからな」
踏み出しかけた右足が止まれずに地面に置かれて互いの距離が思ったより近付く。
「ごめんね、あの、これ、渡したくって」
紙袋から取り出したラッピングされた箱をそっと差し出す。すぐにはそれが何か理解できなかったのか箱と西岐の顔を視線が何度も往復して、最終的に箱へとジーッと視線が当てられた。
「あ……チョコです」
「俺に?」
「う、うん」
西岐が頷くとやっと受け取った。それでもまだまじまじと箱を見て、赤くなり始めた頬を擦っている。
ピューッと口笛が聞こえてそちらを向くと、普通科の教室の入り口から友人らしき二人がニヤニヤしながらこちらを見ては何か囁き合っている。
「ありがとう」
「あ、うん、じゃ……あの、俺いくね」
妙な空気になってしまったことに戸惑って首を傾げつつ、次へと向かうために別の場所に視線を投げて再度、瞬間移動をするのだった。
移動した先は仮眠室。
いつもどおり、部屋の中央に置かれたソファーに腰かけたオールマイトは、突然現れた西岐に驚くでもなく口角を緩めた。
「私の番かな」
「はい」
手のひらサイズの透明な筒。細いリボンが巻かれたそれを差し出す。
手作りをしているさなかから心が伝わってしまっていたので西岐がプレゼントすることも分かっていたと思うが、オールマイトは筒を掲げて内側のカップケーキを嬉しそうに目を細めて眺める。てっぺんに刺したクッキーでオールマイトの前髪を模してあって、同じものを緑谷にもプレゼントしていたりする。
「人生で一番嬉しいバレンタインだ」
「俺もです」
そんなふうに喜ばれると作った甲斐があるというもの。西岐まで嬉しさでいっぱいになって自然と頬が緩む。
「さ、次があるだろう? いってらっしゃい」
「はい」
優しく促され、西岐は頷き、すぐさま次へと移動した。
滅多に訪れることのない三年生の教室エリア。
その廊下で顔見知りの三人を見つけて姿を現すと、通形・波動・天喰それぞれが驚いたのかどうかわからない表情で目の前の西岐を見つめて動きを止めた。
一番最初に口を開いたのはやはり波動だった。
「瞬間移動! はじめて近くで見た、不思議! ねぇ、どうやってるの? 前髪が長いのと関係ある?」
「え、あ……」
「どうしたの? 私に会いに来たの? その紙袋はなあに?」
「あの」
「波動さん、畳みかけるとこの人喋れなくなるから」
波動の質問攻めによって処理能力に支障をきたした西岐に、天喰が助け船を出してくれて、隣に立つ通形にもニコッと効果音が付きそうな笑顔が浮かんだ。
「ほんとに、どうした? 会いに来た?」
「うん、あの、これをね」
手渡そうとする気配を感じ取ったのか差し出してくれる三人の手に、包みを一つずつ乗せる。
今度は天喰の反応が一番早かった。
鋭利な目がそれと分からなくなるほど見開かれ、ボッと火を噴いたように赤くなった。
「これ……ばれん……」
「タイン!」
「チョコ!」
震えて途切れた天喰の言葉を波動が引き継ぎ、続いて通形もはっと気づいて声を張り上げる。相変わらずの仲の良さだ。
「はい、よかったら食べてください、では」
三人に向かって軽くお辞儀をしてから、最後の場所、1-Aの教室へと向かった。
西岐が教室に瞬間移動したのと、予鈴が鳴ったのと、相澤がドアを開けたのはほぼ同時だった。あと数秒遅れていれば遅刻扱いになっていたかもしれない。ふうと安堵の息を吐く暇もなく相澤が席につけと促しながら教卓へと近づいてくる。
「……あいざわせんせ、お約束の品です」
バッと両手で包みを持って相澤に差し出す。
チョコを作ることも渡すこともバレてしまっているが、何を作るのかまでは死守して見せていない。当然ラッピングも。
落ち着いた色合いでありながらも猫の足跡が散らばったラッピングペーパーに包んだ箱と西岐を見下ろして相澤の口がへの字に引き結ばれている。
教室がシンと静まり返った。
あれ、何か間違っただろうかと不安が過る。
すでにクラス全員に配っているからチョコについては今更だし、相澤は猫が好きだったはずだしと考えを巡らせている西岐の頭の上に、聞かせるためにわざと大きくしたような溜息が降ってきた。
「……今かよ」
低いボソッとした声が耳に滑り込む。
なるほど、問題はタイミングだったらしい。
「あ、じゃあ……あとで」
確かにもうHRの時間だ。今渡すのは不味いかと納得して席につくべく回れ右をするや、長い腕が行く手を遮るように伸びて箱を掴んだ。
「さっさと席につけ」
着席を促す相澤に、呆気にとられたまま素直に従えば何事もなかったかのようにHRが開始される。
近付いてきた期末テストの話題になって教室の空気が切り替わり、チョコを渡し終えた達成感で胸がいっぱいになっていた西岐もまた、無理やり表情を引き締めた。
大人数へのチョコを作り、それをしっかり全員に配り終えたという達成感からすっかり終えた気でいたバレンタイン当日。
ヒーロー基礎学を終えた直後、オールマイトに肩を叩かれて西岐一人だけが演習場に取り残された。
「……居残り?」
「少年、今日の授業、全ッ然できてなかったからね、私ともう一度勉強しよう!」
無情に告げられた居残り宣告に西岐は切なげな眼をオールマイトに向けた。
多少それでたじろぐものの肩に置かれた手は緩まない。
確かに今日のヒーロー基礎学は酷かった。西岐の苦手な『動かしたら駄目な爆弾の処理』が課題なうえ、チームアップもなく単独で処理しなくてはならず、呆気なく爆弾が粉砕した。一学年を終えようというのに未だに上達しない爆弾処理、居残りをしろと言われても仕方ない状態だ。肩を落とし頷く。
一度教室に戻ってHRを終えてから再び演習場にて爆弾処理の勉強に励んだ。動かせる爆弾ならば人のいないところまで持って行って爆破すればいいので余裕なのだが、こういう動かしてはいけないという条件が付いてしまうと集中力と頭脳と冷静さが必要な作業となって、途端に苦手意識が働く。オールマイトに付きっきりで爆弾の構造を説明してもらい、一生懸命こなしていくが、何度も爆発してはやり直し、やり直しては爆発して、特に成果も出ぬまま遠くの空に太陽が沈んだ。
着替えて寮に向かう西岐をオールマイトが追いかけてきて隣を並び歩く。
「二年生になれなかったらどうしよう……」
「大丈夫、私も実のところ爆弾処理は大の苦手なんだ。宇宙にでも捨ててきた方が早い! って思っちゃうよな」
暗くなるまで居残りをしたというのに全く進歩しなかった自分にズンと暗く沈む西岐に、オールマイトは慌ててフォローを入れる。
「でも……いつもは居残りなんてしない、ですよね」
余程自分が駄目だったのかと更に沈み込めば、隣でブンブンと両手を振る。
「あああ、あんまり落ち込まないでくれ、良心が痛む」
「良心?」
「ほ、ほら、寮についた!」
あっという間に到着した1-Aの寮。玄関前の階段をのぼりながら未だに隣をついてきているオールマイトに首を傾げて、扉に手をかけた状態で振り向いた。
「あれ、中に入るんですか?」
「入るとも! 私も参加したいからね!」
「参加?」
どうもオールマイトの態度は怪しいのだが西岐の手が置かれたノブに細長い手が被さって扉が開くと、温かな空気と独特の甘い匂いがふわりと広がり、意識が寮の中へと持っていかれてしまった。そっと背中を押されて中に入り、ルームシューズに履き替えてリビングへと動線を辿る。
「私と西岐少年が、きた!」
玄関からL字に曲がった先に広がる光景に、前髪で隠れた西岐の両目が丸く見開く。
「おかえりー!」
クラスメイト全員が勢揃いで西岐を出迎える。
何よりも西岐の視線を釘付けにしたのは、ダイニングテーブルに置かれた装置、所謂チョコレートファウンテン。チョコレートが噴水状に流れていて、玄関まで漂っていた甘い匂いはここからしていたようだ。そして装置の周りには所狭しとフルーツやクッキー、プチシューやマシュマロなど様々な具材が並べられている。
「オールマイト、おっそい」
「補習、本気でやりすぎ」
「すまんすまん、一生懸命やってくれるから楽しくなっちゃってさ」
数人から不満の声が飛んできてオールマイトが苦笑する。どうやらオールマイトもこの状況に一枚噛んでいるらしい。
ぽかんとしたまま突っ立っている西岐を覗き込んで、申し訳なさそうに頬を掻いた。
「彼らがこれを用意している間、足止めをするってことになっててね。居残りなんてさせてしまってすまなかった」
「……え」
種明かしをされて西岐は一層混乱する。
「なんで? 足止め?」
「そんなんサプライズだからに決まってるでしょ!」
「俺らから、れぇちゃんに、だぜ」
ソファースペースの手前で佇んでいた西岐を上鳴と瀬呂が迎えにくる。両側から手を取ってダイニングの方へと導いた。
「これは教師一同からな」
奥のキッチンから姿を見せた相澤。まさか相澤まで居合わせているとは思っていなかった西岐が、見開いた目を動揺で揺らしているのをよそに、山盛りにされたいちごの器をテーブルへと置く。大粒で真っ赤でつやつやしたいちごは、きっと恐らく生徒たちだけで用意するには少々手が届きづらい品に違いない。
「ああぁぁぁ……いちご……」
「好きだろ」
「だいすき……!」
外気と室温の温度差で赤くなっていた頬により赤みがさして、沸き上がった熱が抑えきれないとばかりに手で覆う。
「れぇちゃん、コート」
「あ、うん」
緑谷に促されてコートを脱ぐと緑谷の手が受け取ってソファーの背に掛けた。
「……俺が食べてもいいの?」
「当たり前だろ。手作りチョコのお礼、な」
ほらほら、と切島がフォンデュフォークを差し出してくる。受け取って細長いフォークの先にいちごを刺して持ち上げると胸がドキドキと高鳴った。
こういうのを一度やってみたかったのだ。
憧れていたと言ってもいい。
もしかしたら相澤が知っていてみんなに助言したのかもしれない。
チョコレートの滝にいちごを当てるとあっという間にコーティングされて、魅惑的な赤とチョコブラウンの色どりが西岐の乏しい食欲を刺激する。
思いのほか熱くないことを確かめてから口を開き、齧り付いた。
一口では食べきれない大きさのいちごからトロッとチョコが垂れて唇にも貼りつく。
「んん……」
口の中に広がる絶妙な甘みと酸味に、とろけた声が鼻から抜ける。
唇についたチョコをぺろっと舐めとると西岐に集まっていた視線が何やら熱を帯びたような気配がして、何人かがごくっと唾を飲む。
「みんなも食べよ」
「そ、そだね!」
「たーべよー!」
歯型のついたいちごをフォークに刺した状態で軽く上下に振りみんなにも促すと、まず女子がわらわらとファウンテンに群がった。思い思いの物をフォークに刺してチョコを纏わせていく。
それに続いて男子も次々とフォークを手に取る。
「爆豪は?」
「いらねーよ」
「まーそうだよなー非甘党だもんな」
奥の方で少し離れて立つ爆豪へ切島が声をかけるが、興味なさそうな声が返ってくる。
「じゃあさ、れぇちゃんのチョコどうしたん? 食べてないの?」
頬張ったバナナをもごもごさせつつ上鳴が口を挟む。つられて西岐と何人かの視線が爆豪に向いた。
「……チョコじゃなかった。なんかチップスみてーな甘くないやつ」
爆豪がぼそっと吐き捨てるのを聞いて、爆豪に向けられていた視線が一気に西岐へと移動する。
「チップスも作ったの?」
「あ、うん」
「マメ! 彼女でもなかなかそこまでしないぜ。彼女いないから知らねえけど」
「知らねえのに言い切るってすげえな」
最早コントのような上鳴と切島のやり取りを横目に西岐は爆豪の方へと近づいた。ちらっと伺いの目を向けた先で爆豪もなんだとばかりに見返してくる。
「からくなかった?」
「全然」
「そっか」
爆豪の返事にホッと息を吐く。辛味に弱いせいで味見をしてもどの程度がちょうどいいのか分からず、爆豪に贈ったものが一番自信がなかったのだ。辛くなかったならよかった。食べてくれたのもよかった。そう思って嬉しさに口元を緩めていると爆豪の目がふっと僅かに細められる。
「別に……お前からならチョコでも食う」
「え?」
聞き取りにくいトーンで発せられた言葉を聞き返している間に西岐の手首を掴んで引き寄せ、食べかけのいちごを爆豪が頬張った。いちごの酸味があるとはいえミルクが多く含まれるチョコレートでコーティングされている。爆豪には甘すぎたのだろう。眉間の皺を深くして咀嚼し、早々と飲み込んだ。そして先程、西岐がしたのと同じように口元についたチョコを舌で拭う。
覗き込んでくる眼がいつものトゲトゲしたものではなく、甘さを纏って西岐を絡めとった。
「西岐くん、もう食べないのか?」
「んん、たべる……!」
飯田に声をかけられて爆豪の視線と手が剥がれていく。自由になった西岐の意識はファウンテンに引き戻されて、何を食べようかと考えを巡らせる。
「マシュマロは?」
「すき……」
頭上で障子の声がして反射的に言葉を返すなり、西岐を覆うように大きな体が背中に触れ、高い位置から腕が伸びて少し遠くにあるマシュマロをフォークの先で突き刺した。右腕を伸ばし、左手がテーブルの縁についているものだから西岐は囲われているような状態だ。そのまま障子の手がマシュマロをチョコに浸して西岐の口元に差し出した。
首を捻って見上げても目元しか見えない障子の心境は読めなくて、素直に口を開いてマシュマロを押し込まれる。
口の中の温度で溶け出すマシュマロとトロトロのチョコが混ざり合った甘さに、ほうと息が漏れる。
「おいしいぃ」
うっとりと頬に手を当てていると障子の手が頭を一撫でして離れていく。
それを待っていたとばかりに、西岐に向かって次々とフォークの先が向けられた。甘酸っぱいフルーツから甘ったるいお菓子まで、チョコでコーティングされたものを押し付けられるままに片っ端から食べる。甘いものは別腹という言葉があるが、普段の食欲から考えると信じられない量が胃袋に消えていくのであながち間違いではなさそうだ。
美味しそうに食べる西岐につられてクラスメイト達も自分が食べるほうに気持ちがシフトしていく。
その中で一人、轟だけが美味しくなさそうにもそもそ口を動かしている。彼もまたこういうものがあまり好きではないので仕方がないが、それにしてもいつになく静かだ。
「どうしたの、大丈夫?」
心配になって身を寄せると色違いの二つの眼が西岐に当てられた。
「釈然としなくて」
轟の言葉はいつも少しわかりにくい。首を傾げる西岐に構わず轟は持っていたフォークをテーブルに置き西岐との距離を詰める。
「バレンタインって……好きなやつにチョコをあげるんじゃないのか」
唐突に投げられた正論に西岐はぱちぱちと瞬きした。
「俺、しょうとくん好きだよ」
思ったままを声にしてみるが轟の顔はまさに釈然としないという風に複雑に歪む。くっきり刻まれた眉間の皺と僅か逸らされた視線が拗ねているようにさえ見える。
「……俺は西岐から俺だけの特別なチョコが欲しい」
「特別? どういうの?」
「…………これでいい」
これと言うのと同時に顎を掬われ、れろっと口の端を舐めた。
「っ……!」
触れていたのは僅かな時間。だが感触が残っていて、西岐は茫然と間近にある顔を見つめる。
ガシャンとかバキとかボンとかバサッとかいろんな音があちこちから聞こえた。
もう一度、轟との距離が詰められて息がかかりそうなほど近付くと、細長い手が西岐の口元を覆って後ろに引き寄せた。
「口元を拭うならペーパーナプキンを使った方がいいな」
「……オールマイト」
西岐の背後の人物を認めるなり、轟は気まずそうに顔を背け行き場を失った手を首に当てている。
「西岐少年は無防備すぎていけない」
「ん……」
親指でグイッと唇を拭ってからオールマイトの手が剥がれる。跳ね上がってしまった心臓が苦しくて無言で頷く西岐を見下ろして困ったように笑う。
上がった体温を落ち着かせようと静かに息を吐くが、暖房と噎せ返るほどの甘い匂いでくらくらしてきて、浴びている注目を振り払いたいというのもあって西岐は洗面所へと逃げた。ダイニングと違って暖房が行き届かず冷たい空気が淀む洗面所で、明かりもつけず洗面台に手をつく。全身が冷やされていく感覚に目を閉じる。
「茶番は楽しくなかったか」
背後からの声にビクッと肩が跳ねた。
洗面所の入り口を背の高い相澤が塞いで廊下からの光を遮っている。逆光になって見えないが恐らく冷やかすような笑みを浮かべているのだろう。そんな感じの声だったから。
「楽しいよ。……でも」
「時々調子が狂う」
「……そう」
的確に当てられて項垂れた。自分が動揺しているのが可笑しいのだろうけど、それにしたって今日は変に調子が狂う。
「それはそうだろ。バレンタインってのは"そういう日"だ」
「……わかんない」
「ガキだな」
相澤が近づくたびに西岐の上に落とされた影が濃くなる。追いつめられているような感覚に後ずさりしたい気持ちが湧くのだが、逃げるためのスペースなどなく、洗面台に腰を押し付けて仰け反った。相澤の両手が西岐を挟むように洗面台に置かれて、上から覆い被さる。
「俺も家族ごっごは御免だって話だ」
「わかんない」
「分かれよ」
囁くようなトーンになって唇の動きが感じ取れそうなほど近付いた相澤に、西岐は息を詰める。洗面台の上で上半身が反った不安定な体勢のせいで身体が震えてしまい、それだけで唇が触れそうで相澤の胸に手を置いた。大した抵抗にはならなくて、寧ろ胸元が手のひらを押し返してもっと寄せてくる。
相澤の顔が角度を変えて頬を摺り寄せるような形でずれていく。片手が腰を抱き支えた。
「次はチョコを一つだけにするんだな」
耳に声を注いでからさっさと洗面所を出ていく。玄関の扉が開く音が聞こえて冷たい風が吹き込む。あのまま寮を出て行ったのだろう。
取り残された西岐は暗がりの中でずるずると床に座り込んでいた。
心臓がうるさいし顔が熱い。
なんだったのだ、今のは。
相澤が放った言葉は一つとして意味が飲み込めず、吹きかけられた息の熱さが蘇って、余計に考えられなくなる。
チョコを一つだけ。それはとてつもない難題に思えた。
ただ単に、大切に思っている人たちに大切に思っているという気持ちを込めてチョコを贈る、それだけではダメなのだろうか。
賑やかなダイニングから西岐を呼ぶ声が響く。
纏わりついていた理解できない熱い感覚を振り払って、声を返しながらダイニングへと戻る。
特別な想いを込めた一つだけのチョコレート。それを誰かに手渡すようなとびきりのバレンタインデーが訪れるのはまだまだ、ずっと先の話。
ひとまず今は、笑顔で迎え入れてくれるクラスメイト達の輪の中で甘やかな時間を過ごすのだった。
ハーレムというより、いつも通りの『みんなでちやほや』な感じになっております。ご了承ください。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
「外泊許可……?」
訝しげな顔で相澤が振り返った。
「いつ?」
「えっと……今日の夜から」
「から?」
「……あ、の……三連休の間です」
「どこに」
「俺の家です、けど……」
鋭く目を細めて端的な言葉で問いかけてくる相澤の態度は、あからさまに不機嫌で、そんなに悪いことを申し出ただろうかと西岐を怯えさせた。
長い連休があれば時折自分のマンションに戻って過ごすなんてことは度々あったと思うのだが。
「誰と?」
「え……俺一人です」
一つ質問に答えるたびにどういう訳か周囲の空気が重くなっている気がする。
「連休三日間、家に一人で?」
「……はい」
まるで嘘を言っているかのような心境に陥る。それほどまでに相澤の探ってくる眼が鋭い。
目線を合わせているのが辛くて、ついブレザーの裾をいじる指先に目線を落とした。こうやって目を合わせないことがより一層、相澤の機嫌を損ねていることはなんとなく分かっているのだが、怒りを孕んでいる時の相澤は苦手だったりするからどうしようもない。
こんなことで躓くと思っていなかったから予想外の出来事に頭が混乱していた。
「俺が家に行ってもいいな?」
「……え」
追い打ちをかけるような問いかけに西岐は一瞬、頷きかけてから、遅すぎるくらいの動きで顔を上げた。
「だ、だめ」
「西岐、だったら許可は出せない」
こういうときの切り返しは自分でも嫌になるほど下手だ。動揺が声に出すぎて相澤の不信感を煽ってしまう。
それにしたって相澤の心象一つで外泊許可が下りないのは職権乱用ではないのかと思うが、ここは雄英、自由な校風が売りというのは教師の方針まで含まれる。どう訴えたところで相澤が許可できないと言えば外泊は無理だ。
全寮制の形となった今、無断外泊は除籍処分になりうる違反行為。
「…………来ていいです」
西岐には頷くという選択肢しかなかった。
それから短針と長針がぐるぐる回って普段の就寝時間を過ぎた頃、マンションのインターホンが鳴り響いた。あんまり遅いから仕事が忙しくて来られなくなったのかと淡い期待を抱いていたのだが、さすがは相澤、言った通りきっちり姿を見せた。
リビングに入るなりスンと鼻を鳴らし、キッチンに目を向ける。
充満している甘ったるい匂いと、所狭しと置かれている材料や調理器具やラッピング用品が、西岐が何をしているのか物語っている。
「……これは」
いったいどういうことを想像していたのか、相澤は拍子抜けして呟き、特に返事をせず作業に戻る西岐を眺めながら上着を着たままキッチンの端に置いてあるスツールに腰かける。
丸めたチョコクランチにアラザンやカラーシュガーを乗せてカラフルにしたものを小さなお皿に乗せて冷蔵庫へ、入れ替わりに冷やしておいたチョコ入りのシリコン型を出した。酸味の強いベリーソースを固まったチョコの窪みに流しいれてからさらに湯煎したチョコで蓋をして冷蔵庫へ戻し、今度は鍋で温めていた牛乳にオレンジピュレと刻んだチョコを順に入れて混ぜていく。それをこして、冷やしながらまんべんなく混ぜ、容器に入れて冷蔵庫へ入れていると、相澤が『ああ』と納得の声を出した。
「お前……全員分、それも一個ずつ違うのを作ってんのか?」
チョコに生クリームを混ぜ込む手を止めて西岐は相澤の言葉に一度頷く。
クラスのみんなと雄英の先生達、全員分を用意しようと思っての場所と時間、そこには勿論、相澤へのものも含まれていて、出来れば内緒にしておきたかったのだ。サプライズという意味もあるし、せっせと手作りしているのを知られるのが恥ずかしいという意味もあった。
頬に熱が集まった気がして俯いて手元に集中する。
今まで意識をしたこともなかったバレンタインデーという冬のイベント。どうしてか今年はテレビの特集から目が離せなくなっていた。大切な人にチョコレートを贈るということがキラキラした素敵なものに思えた。
西岐にとって大切な人といえば日々を共にする雄英のみんなだ。折角あげるなら全員が喜ぶものがいい。個性豊かな人達だから好きなものもみんな違う。それなら一つずつ作ろう。
……と、なったわけだ。
寮で作ればすぐに知られてしまうし全員分となれば長時間キッチンを占領してしまうことになる。だからバレンタイン前の連休を利用して自宅のマンションで、と思ったのだが、外泊許可でまさか相澤の機嫌を損ねることになるとは思っていなかったわけで。
サプライズに失敗した贈る予定の一人に溜息をつくと相澤は小指で頬を掻いた。
「タイミングがタイミングだから深読みした……」
「どんな?」
「そもそもお前が隠し事しようとしてあからさまに怪しいから悪い」
「う……、そうだけど」
確かに、手作りチョコのことを内緒にしようと思って挙動が怪しくなっていた自覚はある。聞き返した言葉をまるきり無視されて釈然としないものの、そこを突かれると言い返せない。
「チョコ、買うんじゃダメなのか?」
「みんなが気に入りそうなのを探すのが大変なの」
「全部同じで良いだろ、合理的に」
「……言うと思った」
相澤の物言いに苦笑を浮かべ、湯煎のチョコをゴムベラで混ぜる手を動かしつつ、目を細めた。
「バレンタイン、ってさ」
牛乳を混ぜたチョコの容器を冷蔵庫に入れて、使い終わった道具を洗い始める。目線は手元に置いたまま口を開く西岐の横顔に、相澤の視線が当てられていた。
「想像だけどさあ……、最初にもらうのはお母さんからで、最初にあげるのがお父さん。兄弟がいたら兄弟ってこともあるよね」
静かな部屋に響く水音。キッチンとリビングに最小限に灯された明かり。広すぎる空間に漂うヒヤリとした空気。もう慣れきったと思っていたけれど、寮から戻ってきてこんなにも自分の声が反響しただろうかと戸惑った。
あの賑やかな場所に馴染んで、この寂しさには戻れなくなっていることに気付いてしまう。
西岐にとって雄英のみんなは家族とは呼べないまでも、特別な存在なのは確かだ。
「……重い義理チョコだな」
全てを言わずとも察したらしい相澤がにべもなく言い捨てる。
「いいの」
重いという言葉に少々不安を感じつつも気にしないようにやや強く言い切って、洗い終えた道具をもう一度使えるように材料と一緒に調理台に並べ、一息ついた。
時間的に余裕があるとはいえまだ作りたいものは沢山ある。お菓子作りなどほとんどしたことのない西岐には難しい作業も多分ある。普段ならとっくに夢の国へ旅立っている時間だが、眠気を振り払って材料へ手を伸ばした。
そうして火曜日の朝。
ラッピングも済ませた全員分のチョコを見て西岐はほくほくと笑みを浮かべていた。クラスメイトの分と先生達の分と、その他のいくつかを紙袋に分けて入れて、急いで寮に向かう。
バレンタインデーにはまだ一日早いが、手作りなので日持ちしない。だからすぐにでも渡してしまいたかった。
「お、れぇ、おっはよ」
「れぇちゃん、おっはよー」
「おっはよー!」
寮の玄関先で真っ先に声をかけてきたのは爆豪組の三人。切島と上鳴と瀬呂。それと目はあったものの挨拶は特にない爆豪もいる。揃って朝のトレーニング帰りらしい。
「えっと、あの、これ、チョコ」
いざ渡そうとなって何と言えばいいのか言葉がうまく出てこなくて、もごもごと口ごもりながらラッピングされた小さな箱を四つ差し出した。
よくよく考えたらただのクラスメイトの男が男にチョコを渡すのは可笑しいような気がして今更不安になる。しかも手作りだ。相澤が言っていた通り重いかもしれない。今引っ込めてしまえば何事もなかったように出来るかもしれない。
そう思って引っ込みかけた手首を爆豪が掴んだ。
「俺の、どれだ」
「あ……あ、の……これ」
ブラウンの包装紙に包まれたものを指先で揺らすと手首の代わりに包みを掴んで持っていく。
「俺のは?」
他の三人がほぼ同時に聞いてくる。
「え、と、これがえいじろうくんで、これがはんたくんで、これがでんきくんの」
「やった! 手作り?」
「あ、うん」
「すげえ、まじか」
「やべえ……初バレンタインチョコなんですけど」
テンション高く喜ぶ上鳴と、しみじみと手元の包みを見下ろす切島と瀬呂。その嬉しそうな様子に少し前に抱いた不安が霧散していく。
一番要らないと言いそうな爆豪があっさり受け取ってくれたことで自信を取り戻し、ダイニングにいるメンバーへと紙袋を揺らしながら向き直った。
「みんなの分もあるの」
朝食の支度をしたり食べ始めていたりするクラスメイト達一人一人にチョコの包みを手渡していく。連休明けの朝っぱらから始まったいきなりのチョコ攻撃をそれぞれが戸惑った顔で受け取り、じわじわと照れたような笑みを浮かべている。
「私らのも?」
「あるよぉ」
勿論、女の子たちのも用意している。
同じテーブルに座っている女子全員に手渡すと、朝食の途中でありながら早速ラッピングを開いて中を覗いた。
「おいしそおおおお!」
「いやいや、実際おいしいよ! キャラメル入ってるー好きー!」
「音符書いてある……すごい……」
「私のはムースだわ」
「チョコ大福ううう!」
「りんご、知恵の実ですわね」
見た目でキャーキャーと盛り上がり、一口食べてはまたキャーキャー盛り上がる。女子のテンションは朝といえど高い。スイーツを前にすれば尚更なのだろう。
「りんご?」
背後で過剰に反応したのは常闇だ。
「ふふ、とこやみくんのもチョコとりんごのパイだよぉ」
常闇にも包みを差し出すと、おおっと感嘆の声と共にラッピングを解く。普段は落ち着いた物腰の常闇がいそいそと中身を確かめている様は微笑ましい。
隣に座っている障子にも同じように手渡す。障子はすぐには開けるつもりがなかったみたいだが、西岐が反応を期待してジッと見つめていることに気付いたのか、静かにラッピングの袋を開けてボックスを取り出した。
「…………たこ焼き?」
「そうなの、たこ焼き風のプチケーキなの」
ぱっと見、本物のたこ焼きにしか見えない丸いケーキが四つ並んでいるそれは、我ながら渾身の出来で、手で口元を抑えていても得意げな笑みが漏れてしまう。
手の中ににやにやした笑いを押し込めて、エレベーターから降りてきた緑谷と飯田と轟へ小走りに駆け寄って包みを差し出す。
「バレンタインッッ!!?」
「バレンタインか!!!」
「……」
顔を真っ赤にして過剰なほどの反応を見せる緑谷と飯田とは相反して、轟は手に持った包みを真顔で見下ろした。ちらっと二人を見てまた無言で視線を戻す。何か気に入らなかったのかと様子を伺いつつ轟にもう一つの包みを差し出した。最初に渡したものより幾らか落ち着いたラッピングを施してあるそれを見て轟の目に困惑が映る。
「これね、エンデヴァーさんの分」
「……俺が渡すのかよ」
「あ……自分で渡したほうがいいかな?」
「いや、俺が渡す」
あからさまに嫌そうな顔になる轟に手を引っ込みかけるが、一瞬で考えが変わったらしく奪うように包みを受け取った。
これでクラスメイト全員には手渡し終えた。
と、瞬間移動で部屋に戻る。
まだまだ渡す相手が残っている。
急いで制服に着替えて慌ただしく学校へと向かった。
職員室を前にして西岐は二の足を踏んでいた。
勢い勇んでここまで来たのはいいが、まず職員室という独特の雰囲気が入りにくくて怖気づく。
「れぇーちゃん、なーに突っ立ってんの?」
「ひっあああ」
入ろうか入るまいかとまごついていたところへ急に声が降ってきたと思うなり、肩に重みがかかって情けない声が喉から滑り落ちる。
「ビビりすぎだゼ、イレイザーに見られたらコロされる、落ち着け」
「ま、マイクせんせ」
声のトーンを落として耳に囁いてくるプレゼントマイクに、西岐は跳ね上がった心臓を落ち着かせようとフーフーと息を吐く。強く握りすぎたせいで皺が寄った紙袋をプレゼントマイクへと押し付けた。
「あの、チョコです」
いつもながら日本語の不自由さは自分でも呆れる。
「俺に?」
「みなさんに」
「へえ」
頬を紅潮させてパッと顔を輝かせたプレゼントマイクが返事を聞くなりシュンと萎れる。そのコロコロ変わる表情を見て緊張やさっきの驚きが消えて西岐の口元が緩む。
「マイクせんせのも入ってます」
渡した紙袋を横から広げて名前のカードが添えられた包みの一つを取り出す。
ちゃんと個別で用意されていると分かったからか再び晴れやかな表情となったプレゼントマイクは、目の前の扉をスパンと勢いよく開いた。
「ヘイオー!! チョコの差し入れだぜイエイ!!!」
喧しく登場したプレゼントマイクに職員室中の視線が集まって、背後にいる西岐も当然注目されることとなる。教員全員のチョコを用意したわけではないのでどうしようと焦るが、運よく見知った教師たちばかりが居合わせたようだ。
チョコという単語とプレゼントマイクが掲げている紙袋が繋がったのか、わらわらと集まってきた。
「私のもあるじゃない! 西岐くんったらいい子ね」
「わああ、僕のラッピングがコスモ柄!」
「なるほど、このぬりかべのような箱が私のですね」
「白イふわふわノ袋ガ我ノカ……」
「あの、スナイプせんせと、パワーローダーせんせと、校長せんせに」
「オッケオッケ、渡しとく!」
各々、自分の名前を見つけては声を高揚させていく教師達をしばし眺めているが、このままでは始業に間に合わなくなってしまうので、紙袋の中の残りをプレゼントマイクに任せて職員室を後にした。
遠目で校舎の壁を透かしていった先に目的の人物を見つけると迷わず瞬間移動した。普段は特別な理由がない限り使わないようにしているのだが、まあ、今は特別な理由に入るだろう。
突如姿を現した西岐を見るなり、紫の髪を揺らして心操は目を見開いた。
「……それ、何度見ても驚くからな」
踏み出しかけた右足が止まれずに地面に置かれて互いの距離が思ったより近付く。
「ごめんね、あの、これ、渡したくって」
紙袋から取り出したラッピングされた箱をそっと差し出す。すぐにはそれが何か理解できなかったのか箱と西岐の顔を視線が何度も往復して、最終的に箱へとジーッと視線が当てられた。
「あ……チョコです」
「俺に?」
「う、うん」
西岐が頷くとやっと受け取った。それでもまだまじまじと箱を見て、赤くなり始めた頬を擦っている。
ピューッと口笛が聞こえてそちらを向くと、普通科の教室の入り口から友人らしき二人がニヤニヤしながらこちらを見ては何か囁き合っている。
「ありがとう」
「あ、うん、じゃ……あの、俺いくね」
妙な空気になってしまったことに戸惑って首を傾げつつ、次へと向かうために別の場所に視線を投げて再度、瞬間移動をするのだった。
移動した先は仮眠室。
いつもどおり、部屋の中央に置かれたソファーに腰かけたオールマイトは、突然現れた西岐に驚くでもなく口角を緩めた。
「私の番かな」
「はい」
手のひらサイズの透明な筒。細いリボンが巻かれたそれを差し出す。
手作りをしているさなかから心が伝わってしまっていたので西岐がプレゼントすることも分かっていたと思うが、オールマイトは筒を掲げて内側のカップケーキを嬉しそうに目を細めて眺める。てっぺんに刺したクッキーでオールマイトの前髪を模してあって、同じものを緑谷にもプレゼントしていたりする。
「人生で一番嬉しいバレンタインだ」
「俺もです」
そんなふうに喜ばれると作った甲斐があるというもの。西岐まで嬉しさでいっぱいになって自然と頬が緩む。
「さ、次があるだろう? いってらっしゃい」
「はい」
優しく促され、西岐は頷き、すぐさま次へと移動した。
滅多に訪れることのない三年生の教室エリア。
その廊下で顔見知りの三人を見つけて姿を現すと、通形・波動・天喰それぞれが驚いたのかどうかわからない表情で目の前の西岐を見つめて動きを止めた。
一番最初に口を開いたのはやはり波動だった。
「瞬間移動! はじめて近くで見た、不思議! ねぇ、どうやってるの? 前髪が長いのと関係ある?」
「え、あ……」
「どうしたの? 私に会いに来たの? その紙袋はなあに?」
「あの」
「波動さん、畳みかけるとこの人喋れなくなるから」
波動の質問攻めによって処理能力に支障をきたした西岐に、天喰が助け船を出してくれて、隣に立つ通形にもニコッと効果音が付きそうな笑顔が浮かんだ。
「ほんとに、どうした? 会いに来た?」
「うん、あの、これをね」
手渡そうとする気配を感じ取ったのか差し出してくれる三人の手に、包みを一つずつ乗せる。
今度は天喰の反応が一番早かった。
鋭利な目がそれと分からなくなるほど見開かれ、ボッと火を噴いたように赤くなった。
「これ……ばれん……」
「タイン!」
「チョコ!」
震えて途切れた天喰の言葉を波動が引き継ぎ、続いて通形もはっと気づいて声を張り上げる。相変わらずの仲の良さだ。
「はい、よかったら食べてください、では」
三人に向かって軽くお辞儀をしてから、最後の場所、1-Aの教室へと向かった。
西岐が教室に瞬間移動したのと、予鈴が鳴ったのと、相澤がドアを開けたのはほぼ同時だった。あと数秒遅れていれば遅刻扱いになっていたかもしれない。ふうと安堵の息を吐く暇もなく相澤が席につけと促しながら教卓へと近づいてくる。
「……あいざわせんせ、お約束の品です」
バッと両手で包みを持って相澤に差し出す。
チョコを作ることも渡すこともバレてしまっているが、何を作るのかまでは死守して見せていない。当然ラッピングも。
落ち着いた色合いでありながらも猫の足跡が散らばったラッピングペーパーに包んだ箱と西岐を見下ろして相澤の口がへの字に引き結ばれている。
教室がシンと静まり返った。
あれ、何か間違っただろうかと不安が過る。
すでにクラス全員に配っているからチョコについては今更だし、相澤は猫が好きだったはずだしと考えを巡らせている西岐の頭の上に、聞かせるためにわざと大きくしたような溜息が降ってきた。
「……今かよ」
低いボソッとした声が耳に滑り込む。
なるほど、問題はタイミングだったらしい。
「あ、じゃあ……あとで」
確かにもうHRの時間だ。今渡すのは不味いかと納得して席につくべく回れ右をするや、長い腕が行く手を遮るように伸びて箱を掴んだ。
「さっさと席につけ」
着席を促す相澤に、呆気にとられたまま素直に従えば何事もなかったかのようにHRが開始される。
近付いてきた期末テストの話題になって教室の空気が切り替わり、チョコを渡し終えた達成感で胸がいっぱいになっていた西岐もまた、無理やり表情を引き締めた。
大人数へのチョコを作り、それをしっかり全員に配り終えたという達成感からすっかり終えた気でいたバレンタイン当日。
ヒーロー基礎学を終えた直後、オールマイトに肩を叩かれて西岐一人だけが演習場に取り残された。
「……居残り?」
「少年、今日の授業、全ッ然できてなかったからね、私ともう一度勉強しよう!」
無情に告げられた居残り宣告に西岐は切なげな眼をオールマイトに向けた。
多少それでたじろぐものの肩に置かれた手は緩まない。
確かに今日のヒーロー基礎学は酷かった。西岐の苦手な『動かしたら駄目な爆弾の処理』が課題なうえ、チームアップもなく単独で処理しなくてはならず、呆気なく爆弾が粉砕した。一学年を終えようというのに未だに上達しない爆弾処理、居残りをしろと言われても仕方ない状態だ。肩を落とし頷く。
一度教室に戻ってHRを終えてから再び演習場にて爆弾処理の勉強に励んだ。動かせる爆弾ならば人のいないところまで持って行って爆破すればいいので余裕なのだが、こういう動かしてはいけないという条件が付いてしまうと集中力と頭脳と冷静さが必要な作業となって、途端に苦手意識が働く。オールマイトに付きっきりで爆弾の構造を説明してもらい、一生懸命こなしていくが、何度も爆発してはやり直し、やり直しては爆発して、特に成果も出ぬまま遠くの空に太陽が沈んだ。
着替えて寮に向かう西岐をオールマイトが追いかけてきて隣を並び歩く。
「二年生になれなかったらどうしよう……」
「大丈夫、私も実のところ爆弾処理は大の苦手なんだ。宇宙にでも捨ててきた方が早い! って思っちゃうよな」
暗くなるまで居残りをしたというのに全く進歩しなかった自分にズンと暗く沈む西岐に、オールマイトは慌ててフォローを入れる。
「でも……いつもは居残りなんてしない、ですよね」
余程自分が駄目だったのかと更に沈み込めば、隣でブンブンと両手を振る。
「あああ、あんまり落ち込まないでくれ、良心が痛む」
「良心?」
「ほ、ほら、寮についた!」
あっという間に到着した1-Aの寮。玄関前の階段をのぼりながら未だに隣をついてきているオールマイトに首を傾げて、扉に手をかけた状態で振り向いた。
「あれ、中に入るんですか?」
「入るとも! 私も参加したいからね!」
「参加?」
どうもオールマイトの態度は怪しいのだが西岐の手が置かれたノブに細長い手が被さって扉が開くと、温かな空気と独特の甘い匂いがふわりと広がり、意識が寮の中へと持っていかれてしまった。そっと背中を押されて中に入り、ルームシューズに履き替えてリビングへと動線を辿る。
「私と西岐少年が、きた!」
玄関からL字に曲がった先に広がる光景に、前髪で隠れた西岐の両目が丸く見開く。
「おかえりー!」
クラスメイト全員が勢揃いで西岐を出迎える。
何よりも西岐の視線を釘付けにしたのは、ダイニングテーブルに置かれた装置、所謂チョコレートファウンテン。チョコレートが噴水状に流れていて、玄関まで漂っていた甘い匂いはここからしていたようだ。そして装置の周りには所狭しとフルーツやクッキー、プチシューやマシュマロなど様々な具材が並べられている。
「オールマイト、おっそい」
「補習、本気でやりすぎ」
「すまんすまん、一生懸命やってくれるから楽しくなっちゃってさ」
数人から不満の声が飛んできてオールマイトが苦笑する。どうやらオールマイトもこの状況に一枚噛んでいるらしい。
ぽかんとしたまま突っ立っている西岐を覗き込んで、申し訳なさそうに頬を掻いた。
「彼らがこれを用意している間、足止めをするってことになっててね。居残りなんてさせてしまってすまなかった」
「……え」
種明かしをされて西岐は一層混乱する。
「なんで? 足止め?」
「そんなんサプライズだからに決まってるでしょ!」
「俺らから、れぇちゃんに、だぜ」
ソファースペースの手前で佇んでいた西岐を上鳴と瀬呂が迎えにくる。両側から手を取ってダイニングの方へと導いた。
「これは教師一同からな」
奥のキッチンから姿を見せた相澤。まさか相澤まで居合わせているとは思っていなかった西岐が、見開いた目を動揺で揺らしているのをよそに、山盛りにされたいちごの器をテーブルへと置く。大粒で真っ赤でつやつやしたいちごは、きっと恐らく生徒たちだけで用意するには少々手が届きづらい品に違いない。
「ああぁぁぁ……いちご……」
「好きだろ」
「だいすき……!」
外気と室温の温度差で赤くなっていた頬により赤みがさして、沸き上がった熱が抑えきれないとばかりに手で覆う。
「れぇちゃん、コート」
「あ、うん」
緑谷に促されてコートを脱ぐと緑谷の手が受け取ってソファーの背に掛けた。
「……俺が食べてもいいの?」
「当たり前だろ。手作りチョコのお礼、な」
ほらほら、と切島がフォンデュフォークを差し出してくる。受け取って細長いフォークの先にいちごを刺して持ち上げると胸がドキドキと高鳴った。
こういうのを一度やってみたかったのだ。
憧れていたと言ってもいい。
もしかしたら相澤が知っていてみんなに助言したのかもしれない。
チョコレートの滝にいちごを当てるとあっという間にコーティングされて、魅惑的な赤とチョコブラウンの色どりが西岐の乏しい食欲を刺激する。
思いのほか熱くないことを確かめてから口を開き、齧り付いた。
一口では食べきれない大きさのいちごからトロッとチョコが垂れて唇にも貼りつく。
「んん……」
口の中に広がる絶妙な甘みと酸味に、とろけた声が鼻から抜ける。
唇についたチョコをぺろっと舐めとると西岐に集まっていた視線が何やら熱を帯びたような気配がして、何人かがごくっと唾を飲む。
「みんなも食べよ」
「そ、そだね!」
「たーべよー!」
歯型のついたいちごをフォークに刺した状態で軽く上下に振りみんなにも促すと、まず女子がわらわらとファウンテンに群がった。思い思いの物をフォークに刺してチョコを纏わせていく。
それに続いて男子も次々とフォークを手に取る。
「爆豪は?」
「いらねーよ」
「まーそうだよなー非甘党だもんな」
奥の方で少し離れて立つ爆豪へ切島が声をかけるが、興味なさそうな声が返ってくる。
「じゃあさ、れぇちゃんのチョコどうしたん? 食べてないの?」
頬張ったバナナをもごもごさせつつ上鳴が口を挟む。つられて西岐と何人かの視線が爆豪に向いた。
「……チョコじゃなかった。なんかチップスみてーな甘くないやつ」
爆豪がぼそっと吐き捨てるのを聞いて、爆豪に向けられていた視線が一気に西岐へと移動する。
「チップスも作ったの?」
「あ、うん」
「マメ! 彼女でもなかなかそこまでしないぜ。彼女いないから知らねえけど」
「知らねえのに言い切るってすげえな」
最早コントのような上鳴と切島のやり取りを横目に西岐は爆豪の方へと近づいた。ちらっと伺いの目を向けた先で爆豪もなんだとばかりに見返してくる。
「からくなかった?」
「全然」
「そっか」
爆豪の返事にホッと息を吐く。辛味に弱いせいで味見をしてもどの程度がちょうどいいのか分からず、爆豪に贈ったものが一番自信がなかったのだ。辛くなかったならよかった。食べてくれたのもよかった。そう思って嬉しさに口元を緩めていると爆豪の目がふっと僅かに細められる。
「別に……お前からならチョコでも食う」
「え?」
聞き取りにくいトーンで発せられた言葉を聞き返している間に西岐の手首を掴んで引き寄せ、食べかけのいちごを爆豪が頬張った。いちごの酸味があるとはいえミルクが多く含まれるチョコレートでコーティングされている。爆豪には甘すぎたのだろう。眉間の皺を深くして咀嚼し、早々と飲み込んだ。そして先程、西岐がしたのと同じように口元についたチョコを舌で拭う。
覗き込んでくる眼がいつものトゲトゲしたものではなく、甘さを纏って西岐を絡めとった。
「西岐くん、もう食べないのか?」
「んん、たべる……!」
飯田に声をかけられて爆豪の視線と手が剥がれていく。自由になった西岐の意識はファウンテンに引き戻されて、何を食べようかと考えを巡らせる。
「マシュマロは?」
「すき……」
頭上で障子の声がして反射的に言葉を返すなり、西岐を覆うように大きな体が背中に触れ、高い位置から腕が伸びて少し遠くにあるマシュマロをフォークの先で突き刺した。右腕を伸ばし、左手がテーブルの縁についているものだから西岐は囲われているような状態だ。そのまま障子の手がマシュマロをチョコに浸して西岐の口元に差し出した。
首を捻って見上げても目元しか見えない障子の心境は読めなくて、素直に口を開いてマシュマロを押し込まれる。
口の中の温度で溶け出すマシュマロとトロトロのチョコが混ざり合った甘さに、ほうと息が漏れる。
「おいしいぃ」
うっとりと頬に手を当てていると障子の手が頭を一撫でして離れていく。
それを待っていたとばかりに、西岐に向かって次々とフォークの先が向けられた。甘酸っぱいフルーツから甘ったるいお菓子まで、チョコでコーティングされたものを押し付けられるままに片っ端から食べる。甘いものは別腹という言葉があるが、普段の食欲から考えると信じられない量が胃袋に消えていくのであながち間違いではなさそうだ。
美味しそうに食べる西岐につられてクラスメイト達も自分が食べるほうに気持ちがシフトしていく。
その中で一人、轟だけが美味しくなさそうにもそもそ口を動かしている。彼もまたこういうものがあまり好きではないので仕方がないが、それにしてもいつになく静かだ。
「どうしたの、大丈夫?」
心配になって身を寄せると色違いの二つの眼が西岐に当てられた。
「釈然としなくて」
轟の言葉はいつも少しわかりにくい。首を傾げる西岐に構わず轟は持っていたフォークをテーブルに置き西岐との距離を詰める。
「バレンタインって……好きなやつにチョコをあげるんじゃないのか」
唐突に投げられた正論に西岐はぱちぱちと瞬きした。
「俺、しょうとくん好きだよ」
思ったままを声にしてみるが轟の顔はまさに釈然としないという風に複雑に歪む。くっきり刻まれた眉間の皺と僅か逸らされた視線が拗ねているようにさえ見える。
「……俺は西岐から俺だけの特別なチョコが欲しい」
「特別? どういうの?」
「…………これでいい」
これと言うのと同時に顎を掬われ、れろっと口の端を舐めた。
「っ……!」
触れていたのは僅かな時間。だが感触が残っていて、西岐は茫然と間近にある顔を見つめる。
ガシャンとかバキとかボンとかバサッとかいろんな音があちこちから聞こえた。
もう一度、轟との距離が詰められて息がかかりそうなほど近付くと、細長い手が西岐の口元を覆って後ろに引き寄せた。
「口元を拭うならペーパーナプキンを使った方がいいな」
「……オールマイト」
西岐の背後の人物を認めるなり、轟は気まずそうに顔を背け行き場を失った手を首に当てている。
「西岐少年は無防備すぎていけない」
「ん……」
親指でグイッと唇を拭ってからオールマイトの手が剥がれる。跳ね上がってしまった心臓が苦しくて無言で頷く西岐を見下ろして困ったように笑う。
上がった体温を落ち着かせようと静かに息を吐くが、暖房と噎せ返るほどの甘い匂いでくらくらしてきて、浴びている注目を振り払いたいというのもあって西岐は洗面所へと逃げた。ダイニングと違って暖房が行き届かず冷たい空気が淀む洗面所で、明かりもつけず洗面台に手をつく。全身が冷やされていく感覚に目を閉じる。
「茶番は楽しくなかったか」
背後からの声にビクッと肩が跳ねた。
洗面所の入り口を背の高い相澤が塞いで廊下からの光を遮っている。逆光になって見えないが恐らく冷やかすような笑みを浮かべているのだろう。そんな感じの声だったから。
「楽しいよ。……でも」
「時々調子が狂う」
「……そう」
的確に当てられて項垂れた。自分が動揺しているのが可笑しいのだろうけど、それにしたって今日は変に調子が狂う。
「それはそうだろ。バレンタインってのは"そういう日"だ」
「……わかんない」
「ガキだな」
相澤が近づくたびに西岐の上に落とされた影が濃くなる。追いつめられているような感覚に後ずさりしたい気持ちが湧くのだが、逃げるためのスペースなどなく、洗面台に腰を押し付けて仰け反った。相澤の両手が西岐を挟むように洗面台に置かれて、上から覆い被さる。
「俺も家族ごっごは御免だって話だ」
「わかんない」
「分かれよ」
囁くようなトーンになって唇の動きが感じ取れそうなほど近付いた相澤に、西岐は息を詰める。洗面台の上で上半身が反った不安定な体勢のせいで身体が震えてしまい、それだけで唇が触れそうで相澤の胸に手を置いた。大した抵抗にはならなくて、寧ろ胸元が手のひらを押し返してもっと寄せてくる。
相澤の顔が角度を変えて頬を摺り寄せるような形でずれていく。片手が腰を抱き支えた。
「次はチョコを一つだけにするんだな」
耳に声を注いでからさっさと洗面所を出ていく。玄関の扉が開く音が聞こえて冷たい風が吹き込む。あのまま寮を出て行ったのだろう。
取り残された西岐は暗がりの中でずるずると床に座り込んでいた。
心臓がうるさいし顔が熱い。
なんだったのだ、今のは。
相澤が放った言葉は一つとして意味が飲み込めず、吹きかけられた息の熱さが蘇って、余計に考えられなくなる。
チョコを一つだけ。それはとてつもない難題に思えた。
ただ単に、大切に思っている人たちに大切に思っているという気持ちを込めてチョコを贈る、それだけではダメなのだろうか。
賑やかなダイニングから西岐を呼ぶ声が響く。
纏わりついていた理解できない熱い感覚を振り払って、声を返しながらダイニングへと戻る。
特別な想いを込めた一つだけのチョコレート。それを誰かに手渡すようなとびきりのバレンタインデーが訪れるのはまだまだ、ずっと先の話。
ひとまず今は、笑顔で迎え入れてくれるクラスメイト達の輪の中で甘やかな時間を過ごすのだった。
create 2018/02/06
update 2018/02/06
update 2018/02/06